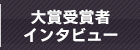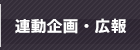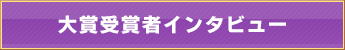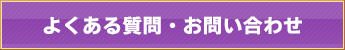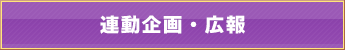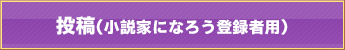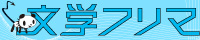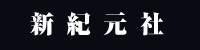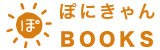- タイトル
- 『がんばれアンバレンスさん! 仮想死後世界アガルタ日本サーバー第二十七管区の舞台裏!』
- 原案
- 高山理図
- 執筆
- アマラ
-
日本を離れた赤鞘が、まだ「海原と中原」の天界にいたころの話である。
新天地の言語を覚えようと、必死でがんばっている赤鞘を、アンバレンスはいろいろなところに連れ出していた。
居酒屋やカラオケ、そのほかにも何かこう、神事っぽいなにかとか。
赤鞘が学習で煮詰まった様子になっているのを見かけるたびに、息抜きと称してそういったところに連れて行っていたのである。
異世界というなれないところに連れて来た、という負い目もあったのだろう。
まあ、もちろん、単に二柱で遊びに行きたかっただけというのも、否めないわけだが。
最高神であるアンバレンスは、同じ世界では友達と呼べるような存在がいなかった。
赤鞘はアンバレンスにとって初めて出来た、気軽に遊べるお友達だったのだ。
その日、アンバレンスは知り合いの神から新しい遊び、ではなく、息抜きの仕方を仕入れ、赤鞘の元へスキップでやってきていた。
二柱でそれを試してみよう、というのだ。
赤鞘もちょうど単語が覚えられなくてうなっていた所であったため、ちょうどよい息抜きにすぐに飛びついた。
だが、その息抜きというのは、思いのほか大掛かりなものだったのである。
「えー。異世界に遊びに行くん、ですか?」
「そうそう! 知り合いに面白そうなところ教わりましてね? なかなかこう、エキサイティングなアミューズメントなんですよ!」
ハイテンションで語るアンバレンスのペースに乗せられ、赤鞘もわくわくとした表情になる。
「でも、ほかの世界に行くときっていろいろ制約ありますよね? あれしちゃだめ、これしちゃだめって」
赤鞘の言うように、別の世界にいく場合、神様の行動にはかなりの規制がかけられる。
お邪魔する方の神からすれば窮屈だが、お邪魔されるほうの神からすれば当然のことと言えるだろう。
よそから来て勝手にいろいろ引っ掻き回されるのは、この上なく迷惑なのだ。
アンバレンスも、よその世界に行くときはとても気を使っていた。
気を使いすぎて力を使わず、迷子になったりするほどである。
赤鞘に自分の世界に来ないか、という話をしに行ったときが、まさにその状態だったのだ。
別にアンバレンスがうっかりなだけではなかったのである。
もちろん、うっかりな点も多々あるということも、否定できないわけだが。
赤鞘の質問に、アンバレンスはにやりと笑顔を作る。
待ってましたと言わんばかりのその笑顔は、なんとなく通販番組っぽい。
「と、思うでしょう? じつはかなりすき放題やっても平気な場所、あったんですよっ!」
「えー? 本当ですかぁー?」
「それが、本当なんですっ! その場所というのが、こちらっ!」
アンバレンスはどこからともなくフリップを取り出すと、ドーンという効果音付きで掲げた。
そこにはやたらカラフルな配色で、こんな文字が書かれている。
全記憶投入型仮想空間 仮想死後世界「アガルタ」
見覚えも聞き覚えも無いそれに、赤鞘は首を傾げた。
「どこの世界なんです? それ」
「いやいや、実はですね。ここは正確には世界であって、世界では無いんですよ」
「と、いいますと?」
仮想死後世界「アガルタ」。
それは、電子的に作られた、コンピュータの中にだけ存在する世界だ。
科学技術の発達により作り出されたそれによって、その世界の人類は死を克服したのである。
「まあ、ぶっちゃけた話? 技術が進歩しすぎて人が死ににくくなったから、さっさと現実引退して夢の楽園で余生を過ごしてください、っていうね。すっごくSFなアレなんですよね」
「ぶっちゃけましたねぇー」
なかなかメタな発言だが、二人は神様なのでそういった事情はお構い無しなのだ。
「まあ、更にいうとですね? コレ場所、日本なんですよね」
「ええ!? 私がいない数週間の間にそんなに技術発達したんですか!? 日本!!」
「そんなわけないじゃないですかぁーもぉー。いやいや、赤鞘さんがいた世界の、未来かもしれない世界ですよ」
「未来? ですか?」
「そう! このアガルタっていうのがあるのは、西暦2133年の日本なんですよ!」
赤鞘がいた日本から見れば、それはずいぶん未来の年代だ。
アガルタがあるという世界は、赤鞘の世界とはパラレルワールドの関係になるのだという。
「そうなるかもしれないし、ならないかもしれない。あるかも知れないし無いかもしれない未来ってところですかねぇー。わかります?」
「いえ、全然」
「あー。まあ、似たような異世界ってことで一つ」
「はぁー?」
いまいち赤鞘は理解していないっぽいのだが、赤鞘は基本的に理解力に乏しい神様だ。
実際に行ってみれば分かるだろうという事で、アンバレンスはとりあえず放置する事にした。
「でも、そこだとどうして向こうの神様にご迷惑かけないんです?」
「それはですね。アガルタがあくまでネットワークサーバー上に存在するバーチャルリアリティだから、なんですよ。現実世界と違って、巻き戻そうが何しようが表の神様陣には影響が無いわけなんです!」
プログラムであるアガルタは、人工的に作り出されたデータの中の存在だ。
そこに携わり、管理している人さえごまかせば、その世界自体に与える影響はほぼゼロなのだという。
「へぇー。すごいですねぇー、バーチャルリアリティって」
「ねー、すごいですよねー、バーチャルリアリティって。まあ、そんな訳で。仮想死後世界アガルタ第二十七管区へ、いってみよぉー!」
「おー!」
こうして、赤鞘とアンバレンスは、一路、西暦2133年の日本へと向うのであった。
「はい、というわけで御座いまして、ねっ! 厚生労働省日本アガルタゲートウェイ、第27管区へ来たわけなんですけれども!」
「あっというまですねぇー」
忘れられがちだが、アンバレンスは太陽神であり、一つの世界の最高神だ。
その気になれば、割と何でも出来ちゃったりする。
別の世界のコンピュータで作られた空間にワープするのだって、あっという間なのだ。
「ちなみに、帰るときにこの世界の時間を巻き戻して、俺等がきたこと事態なかったことにするので。基本、どんな影響与えても大丈夫です」
「えー。じゃあ、イロイロ見て回っても平気なんですねぇー」
「ちなみに、ここをモニタリングしてる西園さんって担当の役所の方がいるんですけど。その方の記憶はこう、後で神様パワーでなんやかんやするので気にしないでオッケーです」
「あー。そうなんですかぁー」
「赤鞘さん、意味分かってます?」
「いえ。全然」
いつも通り真顔で答える赤鞘に、アンバレンスはなんとなく安心感を覚えた。
赤鞘という神は、基本的にこういう神なのだ。
「まあ、その辺は分からなくても何とかなりますからね! 神様パワーで!」
「いやぁー、やっぱり最高神様は違いますねぇー」
「あっはっはっは! もっと褒めてもいいのよっ!」
「所でアンバレンスさん。私達の体、透けてませんか?」
赤鞘の身体は元々透けているのだが、アンバレンスの身体もスケスケ状態になっていた。
アンバレンスはにやりと笑うと、いい質問だというように指を立てる。
「まずはこの世界を観察しよう! というわけでございまして、ね! 現在、俺達は透明人間仕様になっておりまーす!」
「透明人間仕様? ってことは、目に見えないんですか?」
「察しがいいですねぇーい! そう! 俺達の姿は、この世界の動植物からは見えない状態になっています! そうすることで、この世界を安全に見学する事ができるのです!」
「おー!」
赤鞘は感心した様子で、アンバレンスの身体を見回す。
最高神様をじろじろ観察するというのか中々不敬なことなのだが、二柱は既にマブダチになっているから大丈夫なのだ。
ちなみに自分の体を観察しないのは、赤鞘自身の体が普段から半透け状態だからである。
アンバレンスもその辺は了解しているらしく、妙なポーズをとっていた。
「あ、でも、赤鞘さんもアレですよ。本体、透けてますよ」
「え? 鞘ですか?」
赤鞘は、鞘を本体とする神様だ。
体の中で、そこだけは唯一実体なのである。
そういわれて、赤鞘は腰に差している鞘に目を向けた。
アンバレンスの言うとおり、半透明に透けて見えている。
「うわぁー! なんか落ち着かないっ! 唯一の本体なのにコレなんかすごい落ち着かないですよ! 地に足が着いて無いみたいな!」
「まぁまぁまぁ、鞘もね! 透けて無いと見つかっちゃいますんでね! 今日はとりあえず、この状態で! イロイロ見学していきたいんですけれども!」
知らない世界というのは、見学するだけでも楽しかったりする。
ましてこの場所は、神の介在無しで作られた場所だ。
世界作りの専門家である神様的には、見ているだけでも面白い、非常に興味深い場所なのである。
「あれ? でも、この世界って私達が干渉しても平気なんですよね? 何でわざわざ姿隠すんです?」
「人間とかね、その辺なら直接お話するのもね、楽しみがあるんですけれども。野生動物の観察とかは、ほら、やっぱり自然の姿をね。見たほうが面白いですから」
「あー、野生動物怖いですもんねぇー。私も熊に齧られたりしたもんですよぉー。社に侵入されましてねぇー」
「なにそれ超怖い」
なにやら思い出すように頷く赤鞘に、ドン引きするアンバレンス。
アンバレンス的に姿を隠す理由は、神としての存在感で動物達を驚かしたりひれ伏してしまうのを避けるためだった。
だが、赤鞘的には齧られたり、弄ばれたりするのを防ぐ意味があるようだ。
生まれながらに太陽神という高貴すぎる神であるアンバレンスと、元人間で現在鞘が本体であるがザコ神赤鞘の違いだろう。
「まあ、とにかくですよ! 今、俺達は草原にいるわけなんですけれども! ここからですね、植物とか野生動物を観察しながら! 人里を目指そうと思うんですけれどもね!」
「おー、ホントに草原ですねぇー」
説明的な台詞に促され、赤鞘は周囲を見渡した。
一帯は緑の草に、まばらに木が生えた、正に草原という言葉がしっくり来る景色だ。
「まあ、元々このアガルタはですね! 死んだ後の楽園というのがコンセプトな訳ですからね! 当然人間が居るわけなんですよね!」
「楽園ですかぁー。なんかいい場所っぽいですねぇー」
「何がすごいってですね! この世界の住民は基本ノンプレイヤーキャラクターってヤツなんですけれども。それをですね、神様に扮した公務員の人が、なんと千年間も導いて文明を作っていくっていう気の長い事をして作ってるんですよ!」
「おー! 大変なお仕事なんですねぇー」
「この二十七管区はまだまだ初めて百年経ってないみたいなんですけれどもね! いや、頭が下がる思いですよホント!」
千年どころか、数億年単位で神様をやってるアンバレンスではあるが、それでも千年という時間は長く感じるらしい。
アガルタという場所は、アンバレンスの言葉通り、人間が神に扮して文明を作り上げる場所だ。
そして、その出来上がった場所に、現実人間を移住させるのである。
わざわざ現実から移住してもらう場所なのだから、魅力的な場所にしなくてはならない。
神様役をする公務員の人には、凄まじいプレッシャーが圧し掛かるだろう。
千年間閉じ込められて神様役をやるというのも、尋常でないストレスになるはずだ。
普通の人間ならば耐えられないようなことなのだろうが、ここではそういった問題を擬似的な脳を作ることで解消しているのだとか。
要するに、バーチャルリアリティで軽く人格的なものを作り変えて神様役になるのである。
勿論それはコンピュータの中での話しで、別に人体を作り変えるわけではない。
倫理的にも安心なのだ。
「じゃ、まあ、そんな感じで。早速行きましょうか! 徒歩で!」
「徒歩なんですねぇー」
元気良く歩き出すアンバレンスの後ろに続き、赤鞘もぼちぼちと歩き始める。
基本的に方向音痴なアンバレンスだが、今回は迷う心配は無い。
「この世界、コンピュータの中の世界ですからね。こう、空中に浮かぶ半透明なタブレット的なものがあるんですよ」
アンバレンスの手元には、言葉通りのものが浮かんでいた。
かなりSFチックな光景に、赤鞘は感心の声を上げる。
映し出されているのは、上空から見下ろしたような地図と、アンバレンスを示しているらしい太陽のマークだ。
「便利なんですねぇー」
「ホントにねー。でもホントの世界でこういうのやると、勘違いしたヤツが転生してきて無双とかしたりハーレム作ったりするんですよねー」
「どういう状況なんですかそれー」
「いやいや、マジなんですって。この間も俺の知り合いの最高神が、なんか押し付けられた魂を記憶保存したまま転生させたら……。あ、いたいた!」
半透明の画面を見ながら歩いていたアンバレンスが、突然顔を上る。
あたりをきょろきょろと見回すと、何かを見つけたらしく少し離れた場所を指差した。
赤鞘がそこに目を向けると、なにやら草むらがごそごそと動いているのが見える。
「うわ、なんですかアレ!」
「このタブレットっぽいのに、動物の反応があったんですよ! たぶんこの世界の野生動物ですね! っつっても、人間のデザイナーが作ったやつですけど!」
人間の手で作られた世界であるだけに、ここにいる生物はデザイナーが作ったものであった。
自然淘汰などによる進化とは、無縁の存在なのだ。
がさがさと音がする草むらに、赤鞘とアンバレンスは期待のこもった視線を向ける。
飛び出してきたのは、なにやら丸っこい生物であった。
ふわふわもこもこで、くるんと丸みを帯びた生物。
では、ない。
球体のようなボディーに、直接顔と口がくっついたようなフォルム。
その下に、適当に四本の足をくっつけた。
ボールに顔を書いて、木の棒を四本突き刺して自立するようにすれば似たような物体が出来上がるだろう。
これでふさふさの毛でも生えていれば可愛げもあるのだろうが、残念ながらその生物には一本の体毛もなかった。
なんとなくうすピンク色の肌色っぽい、毛皮のない生物独特の皮膚をした球状の生物なのだ。
程よく動きやすくするためか間接部には適度に皺も寄っており、非常にすばしっこそうな外見をしていた。
そして。
毛のない動物特有の、なんというか。
ストレートな言い方をすると。
「キモイ」
「キモイですねこれは」
そう、キモかった。
球体の肉の塊に手足をつけたような体に、ねずみの顔を平らにしたような面構えのそれは、果てしなくどこまでもキモかったのだ。
無色透明で感知できない存在になっている赤鞘とアンバレンスにまったく気がつく様子もなく、そのキモイ生物は近くに生えている草をかじり始めた。
どうやら、草食動物のようだ。
若干引いた顔で、赤鞘はゆっくりとその生物に近づいた。
「え、なんですかこれ。ここって仮想空間の世界ですよね。デザイナーさんが生物デザインしてるんですよね」
「そうよ。ちなみにここにくるときに二十七管区っていったけど、それ二十七番目ってことだから。スタッフさん相当なれてるはずなんだけどね」
「まあ、さすがにいろいろな方がいるでしょうけど。だからってこれは……」
赤鞘とアンバレンスは表情を引きつらせながら、その丸っこい生物に視線を向けた。
くっちゃくっちゃと草を噛んでいる生物は、そこはかとなく幸せそうに見える。
限りなく気持ち悪くはあるのだが。
「えーと。なんか手元の情報によりますとですね。メインで担当してるデザイナーの人が、最初のところは無毛の動物だらけにする。とかいったとかで」
「最初のところ、ですか?」
「ええ。なんか、メインになる主神さんがいて、その人が民を導いて世界を安定させるんだとか。千年かけて。最初は村、そこから徐々に範囲を広げていくんですって。なもんで、文明とか人口とかでいける範囲を段階的に開放していく、とかなんとか。わかります?」
「全然」
「ですよねぇー……」
赤鞘の理解力は、基本的にものすごく低いのだ。
半笑いで疲れたように笑うアンバレンスだったが、すぐに気を取り直し姿勢を正した。
「さ! とりあえずこのナマモノで俺達の姿が見えてないことは確認できましたし! 行きましょうか。徒歩で」
「そうですねぇー」
いまだに草をもぐもぐし続けている丸っこい生物を放置して、赤鞘とアンバレンスは地図が示す目的地へと向かった。
しかし。
二柱の神を待っていたのは、予想外の恐怖であった。
植物はいい。
ごく普通の、よくある感じの植物だ。
草とかは緑色で、木は茶色い幹がある。
だが、問題なのは動物のほうだ。
皆、毛がない。
毛がないのだ。
たかがそれぐらいで、と思うかもしれない。
しかし、そうではないのだ。
元来、毛があるだろうデザインの生物に毛がないというのは、恐ろしい事態を招くものなのである。
たとえば、ふわもこであったかそうな毛皮のわんちゃんがいたとしよう。
それに水をぶっ掛けると、それはそれは貧相な外見になる。
種類によっては、すごくおっかない外見になるのだ。
ふわもこがぴったり体に張り付いただけでそうなのに、それらがつるっとした肌で現れたらどうなるのか。
ためしに「ハダカデバネズミ」という動物を検索してみるといいだろう。
名前のとおり、毛皮のないねずみなのだが、これが結構スリリングな外見をしている。
草原は、ソレ系の動物の宝庫なのだ。
赤鞘もアンバレンスも、基本的にキモイ生き物が苦手だった。
ド田舎とはいえ、基本的に人里近くで長年神様をやっていた赤鞘。
最高神なのに、自分の世界の動物はキモイからほかの世界がうらやましいとか言っちゃうアンバレンス。
キワモノっぽい動物を大量に目撃したことによって、二柱の心のエネルギーはがりがりと削られていたのだ。
そして、目的の村についた頃には。
二柱ともげっそりとした、すこぶる悪い顔色でぷるぷると膝とかを震わせていた。
「……やべぇ……キモイ生き物まじやべぇ……」
「なんかこう、ハートに来ますね……」
「あいつらこっちが見えないからって突然出てくるんだもん。心構えができてないところに。なんだよあのにゃんこ系統の口元。あれ絶対毛皮があるから可愛いんだよ」
「毛がなくて皮膚がダイレクトだとグロイですね。キモイを通り越して」
「ね。ホントね。違う世界を見てるって感じで気分転換にはなるけど、精神的な防壁をごっそり削られてる思いだわ」
深呼吸で心の平穏を取り戻すと、赤鞘とアンバレンスは村のほうへと目を向けた。
高床式で、三角形の建築物。
住んでいる人々の服装は、紫と黄色の縞模様。
ソレが、その村の外観だった。
農業が行われているのか、近くには畑のようなものもある。
地球で言うところの、ぺんぺん草に似ている植物だ。
ソレをじっくりと確認すると、赤鞘はぱっと表情を明るくした。
「おー! いやぁー、よく育ってますねぇー!」
「おう? 赤鞘さんはテンション回復ですか? サスガ、豊作の神様」
「いやぁー、土地神になってからこっち、ずっと農業を見てきましたからねぇー」
農業国である日本に生きる赤鞘にとって、神であるということは、住民と農地を支えることだった。
神にしかあずかり知らないものを治め、土地そのものを守る。
そして、そこに暮らす生き物を、生き易くする。
そのことだけに、何百年も注力してきたのだ。
だから、農業を見ればそれだけで心が躍る。
「あれ?」
表情を輝かせていた赤鞘が、ふと眉根を寄せた。
目を見開いたり細めたりしながら、空や地面を見回す。
一見おかしな行動にしか見えないが、神的にはソレはおかしいことではないらしい。
アンバレンスはそんな赤鞘を見て、納得したように苦笑する。
「作物見て気がつくあたり、やっぱ赤鞘さん土地神ですわー」
「あー、いや。不自然だなぁーとは思ってたんですけどねぇー?」
赤鞘が見ていた。
正確には、見ようとしていたもの。
それは、世界を構成する「力の流れ」だ。
神々が世界を創り、運営する際に使うそれらが、この土地では一切感じることができなかったのである。
普通ならば真っ先に気がつきそうなものだが、赤鞘も珍しい土地に来て舞いあがっていたのだろう。
単にキモイ生物に翻弄されていただけ、という恐れもあるのだが。
「もうちょい文明が進めばその辺の解析もされるかもしれませんから。アガルタにも反映されるかもしれませんけどねぇー」
そういいながらも、アンバレンスはその可能性は低いだろう、と思っていた。
何しろ「力の流れ」というのは複雑怪奇で制御困難なくせに、物質的なものだけをとってみれば、ほとんど現実世界に影響を及ぼさない。
言ってみれば、世界を作り出す理そのものなのだ。
プログラムがすべてを滞りなく「設定された通りに」こなしてくれるこの世界では、赤鞘のような神は不要なのである。
「いやぁー。便利ですねぇー」
「まあ、赤鞘さんとしては存在理由を否定された感じで、アレでしょうけど」
「いいんじゃありませんかねぇー? 私みたいなのが下手クソが管理しなくても土地が回るなら、それに越したことはありませんよ」
にへらっとした笑顔でそういう赤鞘に、アンバレンスは苦笑とため息を漏らす。
確かに神々がそれをしなくて済むのであれば、話はずいぶん簡単だろう。
だが、その「管理」がすさまじく難しいことだから、赤鞘は「海原と中原」に呼ばれたのだ。
「その下手クソなことが出来る神が、ウチにはほとんどいないんですけどねー」
アンバレンスの目から見て、このアガルタという世界はとてもとても管理のしやすい、うらやましいものに映っていた。
もちろんいろいろ大変なことはあるのだろうが、アンバレンスの抱えている問題は大体一歩間違うと宇宙規模で世界が崩壊するようなことばかりだ。
「最高神にしかわからない悩みってつらいわぁ……」
「あの、だいじょうぶですか?」
アンバレンスに、赤鞘は心配そうに声をかける。
それに答えるように、アンバレンスは元気よく顔を上げた。
「さっ! じゃあ、早速、この世界の主神様のところに行って見ましょうかっ!」
「えー、いきなりですかぁー?」
「一応ご挨拶してからね、村の見学をしようと思います!」
「この状態で見学するんじゃないんですか?」
自分の体を見回して、赤鞘は首をかしげた。
半透明で誰にも感知されないこの状態のほうが、観察にはいろいろ都合がいいだろう。
だが、アンバレンスはにやりと笑うと、指を立てて左右に振って見せた。
「確かに観察するだけならそれがいいでしょう! でも、この世界のいいところは、比較的簡単に時間が巻き戻せることですよ? 俺たちが来ていたこともなかったことにするから、住民とくっちゃべっても平気なんです!」
「あー、なるほどぉー!」
「でも、いきなり声掛けすると不審神物ですからねっ! この世界の主神様に話を通して、円滑に住民と遊ぼうというわけですよ!!」
「おー!」
ぱちぱちと手を叩く赤鞘に、アンバレンスはドヤ顔で手を上げる。
「でも、主神さんどちらにいらっしゃるんです?」
「なんか今は洞窟で暮らしてるらしいですよ。物理結界とかはって」
「うわぁー。なんかむやみに体当たりする人とかいそうですねぇー、物理結界ってー」
「あっはっはっは! そんなやついないでしょぉ!」
このときはまだ二柱とも知る由もないのだが、後に結界と見るやいきなりタックルをかます連中と出会うことになる。
赤鞘にいたってはそんな連中が自分が管理する土地の住民になったりするのだが、まあ、今は関係ないことだろう。
「まあ、神的な人がいるのにいきなり来てなんやかんやするのもよろしくないですからね! ご挨拶をして住民と戯れましょう!」
住民と戯れる、というあたりで、アンバレンスは妙にアッパーなテンションになっていた。
太陽神であり最高神である彼には、そういうことが出来る場所などほとんどないからだ。
「ところで、その主神の人に私達のことはなんて説明してあるんです?」
「それはですね、なんかこう、西園さんにいい感じにごまかしといてって伝えてあります」
「なんか適当ですねぇー」
「まあ、そのへんはね。ほら。俺がなんか設定考えるより、現場の人に任せたほうがそれっぽい感じのことでっち上げてくれるっぽいじゃないですか」
餅は餅屋ということだろう。
専門ごとは専門家に任せるに限るのだ。
「じゃあ、いってみましょー!」
「おー!」
元気よく拳を振り上げると、赤鞘とアンバレンスは件の洞窟へと向かうのであった。
アンバレンスの情報では、この世界の主神は赤井という名前なのだという。
イメージカラーが赤いので、赤井なのだとか。
安直だなぁ、と思った赤鞘だったが、言葉には出さなかった。
自分のほうが億倍安直な名前だからである。
まあ、それはいいとして。
そんなアガルタ二十七管区の主神、赤井は、現在。
赤鞘達の前でムチャクチャキョドっていた。
「あ、あの! 私何かしましたかねっ! やばいミスとか!? やばいミスとかしました!?」
文字通りの右往左往具合に、赤鞘とアンバレンスは逆に冷静になっていた。
ものすごくビジュアルの整った神様ルックの人がキョドってるのって、なんかすごい不安をあおるな。
そんなどうでもいいことを考えながら、赤鞘は頬を伝う汗をぬぐった。
赤鞘とアンバレンスは、すでに透明人間化を解いている。
もうすけすけボディーではなくなっているのだ。
ついでに言うと、赤鞘の体もきちんとした実体を伴うものになっていた。
本来赤鞘の体はすけすけなのだが、それだといろいろ問題がありそうだったので、アンバレンスの神様パワーで一時的にはっきりした体にしているのだ。
「西園さん、私達のことなんて説明したんですかね?」
「さぁ。なんか、査察官とかいったらしいですよ?」
「あー……」
何かやらかして、査察が来た。
どうやら赤井はそう思っているらしい。
おそらく普段は超然とした神の演技をしているのだろうが、幸か不幸かここには彼が導くべき民の目はなかった。
「あー、いや、とりあえず落ち着いて! 別に俺等、赤井さんをどうこうしに来たわけじゃありませんから! こう、なんていうか、見学? 的な?」
「見学!? 見学ですか!? え、普通の見学ですか!?」
アンバレンスに声を掛けられ、赤井の混乱は増すばかりだ。
「アンバレンスさん! アンバレンスさん、余計に混乱しますからっ! ここは私に……!」
赤鞘はアンバレンスをとりあえず横に押しやると、にっこりとした笑顔を作った。
「突然の訪問で驚かれているでしょう。私達は、別に処罰を決定するとか、そういうことのためにきた訳ではありません。ただ、二十七管区が円滑に運営されているか、本当に見学をしに来ただけなんですよ」
「え、あ、そうなんですか?」
「はい。一応私達もモニタ越しに状況確認はしているのですが、直接触れ合うことで肌で感じる部分もありますから。数値ではわからない部分、というと、場所柄似つかわしくないかも知れませんけれど。将来ここへいらっしゃる国民の方々のために、直接眼で見て確認をしに来ているんですよ」
「あ、なるほど、え、そうなんですか! あれ、でもそういうお話って初耳なんですが……?」
不思議そうに首をかしげる赤井に、赤鞘は再びにっこりと微笑んだ。
そして、人差し指を立てると、口元にそれを持ってくる。
「先にお話してしまうと、抜き打ちの査察にならないでしょう? こういうのは突然くるから、本来の姿が見えるんですよ」
「あー、あー! なるほどー! そうですよねー! いやぁー、国民の皆さんの視点ですかー! なるほどねー!」
「そうそう、ご挨拶が遅れました。本名は事情が事情なので明かせませんが、今回査察を勤めさせていただきます、赤鞘といいます。こちらは私の上司で、アンバレンスといいます」
「あ、どうもー、よろしくおねがいしますぅー」
突然話を振られ、アンバレンスは若干あわてながらもぺこぺこと頭を下げた。
それを見た赤井も、あわてたように頭を下げる。
「あ、いえいえい! すみませんなんか取り乱しちゃいまして! ちょーっと、前にやからし、いえ! 全然なんでもないんですけどねっ! ちょーっと勘違いしちゃって! あはははは!」
どうやら、何か査察を受けそうな覚えが合ったらしい。
笑ってごまかそうとする赤井に半笑いであわせながら、アンバレンスはそっと赤鞘に耳打ちをする。
「よくとっさにそんなの思いつきましたね」
「いや、昔私もやられたことあるんですよ」
「わーお。日本神って怖い」
日本人の勤勉さは、日本神の影響を受けているのかもしれない。
そんなことを考えて、アンバレンスは引きつった笑いを浮かべた。
ようやく落ち着いたところで、赤鞘とアンバレンスはこの世界について、赤井にいろいろと話を聞くこととなった。
名目上は「聞き取り調査」なのだが、落ち着きを取り戻した赤井は、冷静に受け答えをしている。
「あー、見たんですかー、毛のない生物! あれなんていうか、もうちょっとどうにかならないんですかねぇー?」
赤井は腕を組むと、うんうんとうなずきながらそう口にする。
毛のない生物を見た衝撃をアンバレンスが口にしたのだが、どうやら赤井も同じような感想を持っていたらしい。
「ほら、もふもふって癒し効果があるじゃないですかぁ。猫とは言いませんけど、こう、毛皮的なものがあるだけで全然違うと思うんですよ! こう、心癒すっていうか!」
「あー、わかりますわー! 結構、ふわふわなだけで心休まりそうな生物居ましたよねー」
「そうなんですよ! やっぱり至上は犬猫だと思うんですけど、ふわふわな動物をもっふる出来ないってほら、精神衛生上よくないじゃないですか! ちょっとあるだけで違うと思うんですよね!」
どうやら赤井的にも、ふわふわもこもこの動物は欲しいところなようだ。
そういった動物が好きな人間にとっては、このあたりに生息している生物群は悪夢そのものなのかもしれない。
赤鞘もこくこくとうなずきながら、顔色悪く体をぶるりと振るわせる。
「不満を言うつもりはないんですけどね? ほら、直接その場所にいるものとしてはもーちょっとだけこう、ふわもこがほしいかなぁーっていう! そのほうが絶対国民の方々も喜ぶと思うんですよ! ええ!」
「ですよねー! 絶対そうですよねー! ちょっと後で言ってやりますよー、デザイナーに!」
「マジですかー!? いやぁー、アンバレンスさん頼りになりますぅー!」
どうやら赤井もアンバレンスも、コミュニケーション能力は高い部類であるらしい。
わずかの間に、かなり打ち解け合っていた。
赤鞘は二柱の会話を横でニコニコと聞きつつ、相槌を打ったり、フォローを入れたりしている。
「あ、そうそう、デザインといえば!」
ぱちんと手をたたくと、赤井は自分のまとっている衣を持ち上げた。
「この衣装って、もう少しどうにかなりませんかね?」
「衣装?」
赤鞘とアンバレンスは、そろって首をかしげた。
衣装という言葉に、ぴんと来なかったのだ。
それにかまわず、赤井は言葉を続ける。
「ほら。用意された衣装って変えられないじゃないですか! 着てもぼろぼろになっちゃいますし!」
アンバレンスはそっと赤鞘に顔を寄せると、ぼそぼそと小声でつぶやく。
「そうなの?」
「そうなんじゃありません?」
そんな二人のやり取りには気がつかず、赤井は難しい顔で腕組みをする。
真剣なその様子に、赤鞘とアンバレンスは顔を見合わせた。
「確かに衣装って大事だと思うんですよ。らしさってありますし、外見イメージもありますし! お二人とか、すっごく神様っぽいですしね!」
アンバレンスは、赤井と同じく白い衣のような衣服に身を包んでいた。
普段ジャージだったりスエットだったりする太陽神様なのだが、流石によそへ行くときは正装をしているのだ。
赤鞘はといえば、黒い和服に袴。
真っ赤な衣という、少し派手目ではあるものの、よくある和服姿だった。
もっとも、だからこそ「日本の神様」っぽさは出ているのだが。
「時にお聞きしたいんですが」
「はいはい?」
「お二人の衣装って、その、パンツとかついてるんですか?」
「はい?」
思わず、アンバレンスは表情を引きつらせて聞き返す。
ふざけているのか、セクハラか、と思ったが、赤井の表情はどこまでも真剣だ。
その真意を測りかねる赤鞘とアンバレンスに、赤井は等々と語り始めた。
「ご存知とは思うんですが、私の衣装ってないんですよ。パンツ」
「え、なにそれ怖い。マジですか?」
「マジですよ、マジ! 主神のアバターって性別が無いでしょう? 男でも女でもないから股間つるっとしてるんですけど、だからってノーパンはないと思うんですよ!」
「え、性別ないの?」
「いや、私も知りませんけど」
思わず小声で赤鞘に確認してしまうアンバレンスだが、やはり赤井には聞こえていない様子だ。
そんなことよりも、パンツのことで頭がいっぱいなのだろう。
「西園さんにもお願いしたんですけど、聞いてくれないんですよねぇー……。神様だから、って! でも、神様でもいいと思うんですよ、パンツ穿いても。むしろ素民の皆に広めるためにも、穿くべきだと思うんですよ、パンツ! 見えないからってグラフィック削らないでほしいですよね! データ容量削減ならほかでやってほしいですよ、スカートめくりとかされると慌てますし!」
素民というのは、この世界に生活する人々のことだ。
プログラムによって作られた、いわゆるノンプレイヤーキャラクター達のことである。
素になる民だから、素民。
赤井や赤鞘と同じ類のセンスを感じる、ド直球なネーミングだ。
「あー。まあ、パンツは大事ですよねー。こう、スースーするって言うか」
「そうなんですよ! ものすごくこう、不安っていうか!」
同意が得られたのがうれしかったのか、赤井はぱっと表情を輝かせた。
ちなみに、赤井はとてもきれいな外見をしている。
アガルタは理想の楽園を目指しているわけだから、別に外見を悪くする理由はない。
むしろ積極的に、美形ぞろいになるように設定されていた。
なので、赤井が治める集落も、美人美形ばかりであったりする。
主神である赤井は、それらの中でも飛びぬけた美形であった。
その美形が「パンツパンツ」とパンツを連呼する姿は、なかなかにシュールである。
「で、あの、アンバレンスさんはパンツは……?」
「はいてますよ? ボクサーパンツ」
「マジですかー!? いいなー! あこがれちゃうなぁー!」
「いやー! ごく普通のやつなんですけどねぇー! ダーク系のやつ!」
「シックな大人の雰囲気ってやつですね!? ちょっと見せて、って、あ! これセクハラですかね!? セクハラですかね!?」
「まぁまぁ、どうせ男だけですしー!」
なにやらテンションが上がっている様子の赤井とアンバレンスを、赤鞘はにこにこと見守っている。
それを見たアンバレンスは、にやりと笑い話を赤鞘へと振った。
「ちなみに、赤鞘さんってどんなんなんすか! そんなんなんすか! パンツ!」
「え? はいてないですよ? パンツ」
「えええ!? 本当ですか!?」
「ここに来てまさかの赤井さんとのおそろい!?」
赤鞘はにやりと笑うと、静かに口を開いた。
「私、ふんどしなんで」
「でたー! 和装のお約束ネタでたー!」
「いいますわー! 赤鞘さんそれ絶対待ち構えてたやつじゃないですー!」
もはや神様というか、男子高校生のノリである。
普段からすこぶる軽いアンバレンスや、限られた地域の土地神であった赤鞘はともかく、この世界の主神である赤井がそんな感じなのは、なんとなく問題がある気がしないでもない。
だが、赤井は元々人間であり、人間には息抜きも必要だ。
まして彼は、ずっと一人で「神」という役を演じてきたのである。
このぐらいの気晴らしは、必要だろう。
もっとも、そうなると本物の神である二柱のほうに問題がある感じになるわけだが。
三柱はハイテンションのまま、長々とくっちゃべっていた。
アンバレンスや赤鞘にとって。
そして、赤井にとっても、実に貴重な息抜きとなった。
村の視察へと向かうことになったのは、結局数時間しゃべり倒した後であった。
アンバレンスと赤鞘は、透明人間モードで付いて行くことにする。
赤井がどんな風に民と接しているのか、興味を持ったからだ。
自分達が素民と話すよりも、そのほうが楽しそうだと思ったのである。
「いやいや、なかなかどうして。堂に入ってますね」
実際に民と触れあう赤井をみて、アンバレンスは感心した様子で、そうつぶやいた。
さまざまな世界の様子を知るアンバレンスは、神が直接民を導いている世界も見知ってる。
赤井の態度や様子は、そういったものと遠からぬものであった。
「私よりも神様っぽいですかねぇー?」
「うーん。それはどうでしょう。なんだかんだ、赤鞘さんもベテランですからね」
「えー? ベテランっていうのはやっぱり、千年ぐらいやらないとですよぉー」
「基準厳しいなー。ってことは赤井さんはぺーぺーってことです?」
「ですかねぇー?」
民に祝福を与える赤井を眺めながら、二柱の神は妙に楽しそうな様子で笑いあうのであった。
赤井の祝福が終わるのを見届けると、赤鞘とアンバレンスは「海原と中原」へと戻っていった。
アガルタの時間は巻き戻され、西園の記憶は改ざんされ。
二柱がやってきたことは、完全に「なかったこと」になった。
その後。
西園の脳裏に一瞬だけ「あれ、赤井のアバターにパンツ追加してもいいかな?」という思考がよぎる事になるのだが、それはどこかの太陽神の、粋な計らいであったりする。
もっとも、すぐに却下されてしまうのではあるのだが。
「神様は異世界にお引越ししました 」:アマラ
あらすじ
守っていた村が廃村に成ってしまった神様、「赤鞘」。
そんな彼の元に、異世界の主神が突然たずねてくる。
事情を聴けば、異世界は諸々あって神様不足。
是非こちらの世界に来て欲しいとのこと。
豊穣と繁栄の神である彼に、是非力に成ってほしいということなのだが……。
申し入れを受け入れ、赤鞘は異世界にやってくる。
目の前に広がっていたのは、生物の気配が薄い荒野であった。
赤鞘は助手である天使と共に、土地を復活させる為の仕事に取り掛かる。
ゆるい感じで土地運営をしたいと望む赤鞘。
だが、世界情勢はそれを許してくれそうにもなく……。
特に可もなく不可もない元人間の神様が、異世界で涙と感動の冒険活劇を繰り広げません。
異世界で四苦八苦しながら、土地を開拓していく。
そんなお話に成る予定ですたぶん。
「ヘヴンズ・コンストラクター」:高山理図
あらすじ
西暦2133年。人々は仮想現実によって死後の楽園を造り出し、死を克服し永遠を生きていた。そんな近未来日本で、厚生労働省の新米技官が仮想世界管理者・構築士として新規開設する管区の構築を手がけることに。
自然科学をこよなく愛するスーパー公務員である彼は現実世界で十年間、仮想世界で千年間の任期と四十億円の巨額報酬と引き換えに、仮想世界で神様役を演じ住民との絆を深めつつ、その一方で現実世界の国民利用者に向けた独創的ヴァーチャルユートピアの構築を目指してゆく。
科学技術と人類社会の発展可能性、人間の心と自我、技術的特異点の先に焦点を当て、近未来の現実世界と仮想世界を両面から描くサイバーパンク小説です。