|
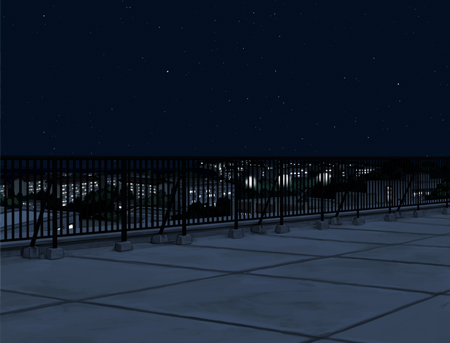 |
みんなの思い出
オープニング
●
雪が降り続ける公園
ブランコで寂しそうに笑っていた
凍えるような白い吐息
俺は何故か悲しい気持ちに襲われた
白い雪を一歩ずつ踏みしめて
うつむいた少女の頭に傘を差し出す
まるで何かから身を守るように
不意に「彼女」が気付いて俺に顔を向ける
「ありがとう、浅川きゅ〜ん」
分厚い唇を突き出してきたのはごつい男の娘
ギャアアアアアアアアアアアアアアアアアアああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ――――
「はぁ……はぁ……はぁ……またうなされていたか……」
俺はベッドから飛び起きた。
時計を見ると夜中の四時過ぎだった。
怖ろしい夢だった。
だが、それは現実だった。
できることならば全て夢であってほしかった。
最愛の初恋の相手が――まさか「男の娘」だったなんて。
「俊一くん、今何かあったの!? おねがいだから出てきて……」
階段を上ってくる音がして不意にドアが叩かれた。
夜中に突然唸り声を上げた俺を心配して沙織さんがやってきた。だが、当然の如く中から鍵をかけているために入ることはできない。
しばらしくて沙織さんは諦めて階段を下りて行った。
俺はあれから学校が怖くなって引きこもりになっていた。いつの間にか新年があけて新学期が始まっていた。すでに一週間以上が経過している。
学校から連絡が入っていたが全て無視していた。
もちろん、神社の見回りの当番もずっとサボったまま。
絶望。世の中が真っ暗になった。
生きていく気力もなくて、この世からいなくなることも考えたが、さすがにその勇気もなくてずっと部屋を真っ暗にして布団に籠っていた。
「――もうダメだ、俺はもう生きている価値もない」
ずっと男の娘に恋してたんなんて惨めだった。自分が情けなかった。
誰も信用できなかった。誰にも、もう会いたくなかった。
●
「美少女ゲーム『久遠〜遥かなる季節〜』の第三弾、告白編です。今回はシリーズの中でもっとも重要なイベントになる告白をしてもらいます。今回の主要な目的は、互いに意識し合った主人公に対してヒロインが重要な想いを打ち明けることです」
ゲームのスタッフが資料を片手に説明を始める。
これまでの流れとしては、転校してきた主人公とヒロイン&悪友が交流を通して、互いに意識し合った状況になっていた。
しかし、前回の思わぬ展開によって主人公は現在引きこもりになってしまっている。
主人公は告白以前にメンタルが崩壊していた。
「告白をする前に、まずは引きこもっている主人公をどうやって立ち直らせるかがキモになるでしょう。ここで上手くいかなかったり、こじらせてしまったら、次のエンディングはバッドエンドまっしぐらになってしまうかもしれませんので注意が必要です。ちなみに告白の結果は次回の完結編で主人公がしてくれる予定ですのでよろしくお願いします」
前回のシナリオを見る
雪が降り続ける公園
ブランコで寂しそうに笑っていた
凍えるような白い吐息
俺は何故か悲しい気持ちに襲われた
白い雪を一歩ずつ踏みしめて
うつむいた少女の頭に傘を差し出す
まるで何かから身を守るように
不意に「彼女」が気付いて俺に顔を向ける
「ありがとう、浅川きゅ〜ん」
分厚い唇を突き出してきたのはごつい男の娘
ギャアアアアアアアアアアアアアアアアアアああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ――――
「はぁ……はぁ……はぁ……またうなされていたか……」
俺はベッドから飛び起きた。
時計を見ると夜中の四時過ぎだった。
怖ろしい夢だった。
だが、それは現実だった。
できることならば全て夢であってほしかった。
最愛の初恋の相手が――まさか「男の娘」だったなんて。
「俊一くん、今何かあったの!? おねがいだから出てきて……」
階段を上ってくる音がして不意にドアが叩かれた。
夜中に突然唸り声を上げた俺を心配して沙織さんがやってきた。だが、当然の如く中から鍵をかけているために入ることはできない。
しばらしくて沙織さんは諦めて階段を下りて行った。
俺はあれから学校が怖くなって引きこもりになっていた。いつの間にか新年があけて新学期が始まっていた。すでに一週間以上が経過している。
学校から連絡が入っていたが全て無視していた。
もちろん、神社の見回りの当番もずっとサボったまま。
絶望。世の中が真っ暗になった。
生きていく気力もなくて、この世からいなくなることも考えたが、さすがにその勇気もなくてずっと部屋を真っ暗にして布団に籠っていた。
「――もうダメだ、俺はもう生きている価値もない」
ずっと男の娘に恋してたんなんて惨めだった。自分が情けなかった。
誰も信用できなかった。誰にも、もう会いたくなかった。
●
「美少女ゲーム『久遠〜遥かなる季節〜』の第三弾、告白編です。今回はシリーズの中でもっとも重要なイベントになる告白をしてもらいます。今回の主要な目的は、互いに意識し合った主人公に対してヒロインが重要な想いを打ち明けることです」
ゲームのスタッフが資料を片手に説明を始める。
これまでの流れとしては、転校してきた主人公とヒロイン&悪友が交流を通して、互いに意識し合った状況になっていた。
しかし、前回の思わぬ展開によって主人公は現在引きこもりになってしまっている。
主人公は告白以前にメンタルが崩壊していた。
「告白をする前に、まずは引きこもっている主人公をどうやって立ち直らせるかがキモになるでしょう。ここで上手くいかなかったり、こじらせてしまったら、次のエンディングはバッドエンドまっしぐらになってしまうかもしれませんので注意が必要です。ちなみに告白の結果は次回の完結編で主人公がしてくれる予定ですのでよろしくお願いします」
前回のシナリオを見る
リプレイ本文
●
「あ、あー、マイクテストマイクテスト。
本日も引きこもりなり、本日も引きこもりなり!」
窓の外から爆音が聞こえてきた。
夜中の二時である。もういちど繰り返すが夜中のニ時である。
こんな時間にこんな馬鹿なことをする奴はあいつしかいない。
――霧谷 温(jb9158)が拡声器を使って外で叫んでいた。
「初恋が実は男の娘で玉砕ブロークンハートの少年! 聞こえているか!
辛いのわかる! 騙されたと思うのも仕方ない!
だからこそ、あえて俺はこう言おう!『黒歴史乙』!!」
奴は毎晩お構いなしに俺の家へと訪れて怒鳴り声を上げていた。
近所迷惑なんて一切気にしていない。
俺は毎晩うなされていた――原因は言うまでもない。
すでに今が夜なのか昼間なのかさえわからなくなっていた。頭がすでにオカシクなってしまったようだ。視界に靄がかかったように朦朧としている。
「まあ、ほら、あれだ! 昔の女……いや、この場合男?のことなんて忘れて、次の新しい恋とやらを探そうじゃないか! 何、ネタは一杯ある! このままズルズル年取って、大学や社会に出て彼女が出来るなんて考えてんじゃねえぞこの少年! いつ彼女作るの? 今でしょ!」
励ましているつもりなのだろうが、一層俺は自分がみじめに思えてきた。
奴の行為は完全に逆効果だった。そもそもあいつに俺を慰めようと言う気はさらさらないのかもしれないが――。
毎晩の近所迷惑のせいで俺はさらに頭がおかしくなった。もう目の前に幻覚さえみえてきていた。 だって引きこもりの俺の部屋に他に人がいるのが見えるのだから。
「――よぉ引篭り気分はどうだ?」
上半身裸のフードを頭に被った男が天上から現れた。
一瞬、俺は目を疑った。そいつは天上から俺のベッドの上に落ちてきた。
「うわああああああああああああああああああああああああああ」
俺は押しつぶされて発狂した。
ついに幻覚が本物になってしまったのかと恐怖で頭を抱えて叫ぶ。
「おい、なにうなされているんだ? 俺だよ、千代だ」
俺はもう一度そいつの顔を正面から見た。
そこにいたのは紛れもない彪姫 千代(jb0742)だった。
「この辺の抜け道は猫が教えてくれんだ」
聞いてもいないのに千代は語る。何やらいつもよりも若干テンションが高い。引きこもりのくせに余計な御世話だと追い払おうしたが、不意に考える。
俺もこいつと同じ引きこもりだった……。
あまりのブーメランに自分がさらに惨めに思えてくる。俺が考え込んでいる間に当の本人は無邪気に俺の部屋を食料を求めて荒らしまくっていた。
どうやらお腹がすいたらしい。こうやって見ていると千代はあどけない表情をしていた。まるで猫のようである。俺は不意に疑問に思った。
どうしてこいつは引きこもりになったのだろう?
俺は千代のあどけない表情を見て考えた。もしかしたら――俺と同じようにつらい過去があったのかもれしない。俺はこいつのことをもっと知りたくなった。
何か立ち直るきっかけがつかめるかもしれない。
だが、この日俺は結局聞けなかった。
こいつにも誰にも知られたくない過去がある。
それをほじくり返すわけにはいかない。
それから毎晩千代は俺の部屋に来るようになった。夜中二時を過ぎて天上から千代はいつものルートを使ってやってきた。とくにお互いに示し合わせたわけではない。
一緒に何かをするわけでもなかった。
だけど、なぜかお互いに一緒にいると落ち付いた。
心の安らぎを感じた。
思えば、一緒の境遇だった。
「――なあ、おまえはどうして引きこもりになったんだ?」
俺が尋ねると、千代は恥ずかしそうに一呼吸置いて語った。
入学当初から千代がかなり懐いていた教師がいた。
ある日教師に呼ばれ会いに行くと知らない大人数名に暴行された。
この後事件が発覚し教師は学校を去ったが、未だに男性に触られたり学校へ行こうとすると当時の記憶が蘇り震えが止まらず怖くなった。俊一であっても2人でいる状況が本当は怖く脂汗が滲み出るとのことだった。
俺は千代の話を聞いてぐっと拳を握りしめた。
やっぱりだ。俺はこいつと似ている。
信じていた者に裏切られ、人間不信に陥った。
それでも――生きて行くために。
「……もし……俺がもう一度学校に行けたら、その時は本当の友達になってくれるか?」
千代は俺の目を見つめて言った。返事は言うまでもなかった。
その日から俺達は「引きこもりーズ」を結成し、一緒に学校へ行くリハビリのためのロードワークを開始した。早朝の四時頃誰もいない時を見計って寒空の中を走る。
もちろん、上半身は裸でフード付きだ。
万が一誰にも見られるわけにはいかない。ロードワークの後は一緒に部屋に入って沙織さんがドアの前に置いてくれていた食事を一緒に猫のように貪った。
まるで猫のように二人で仲良く食べながら――満腹になった後は一緒にベッドの布団で一糸纏わぬ姿で寝た。千代といると肌の温もりを感じた。
いつしかずっとこのまま一緒にいられたらと願うようになった。
そうやって瞬く間に一週間が過ぎていった。
●
一文字 紅蓮(jb6616)は部屋で一人考える。
俊一にとって、思い出のあの子は特別だった。
記憶の中で更に美化されて、信仰にも近かったのだろう。
それが砕かれた。だから、引き篭もった。
何一つ信じるものなどないように。
だけど、逃避してどうなる。死ぬまでそこにいるのか。
初めから、思い出の『女の子』なんていなかったのだから、 それを認めて次の女の子に恋でもすればいい。そうでなければ、あまりに自分が滑稽だ。
この想いは何なのだろう。恋をした覚えもない俺には分からない。
――ただ、慕って集まった全ての縁にも、俊一自身にさえ向き合おうとしない事に対して、 どうしようもなく苛立った。
紅蓮は決心した。今の自分にできることは何か考える。
あいつを、俊一を助けたかった。
彼を暗闇から引きずり出すために。
一枚の古い写真を握り締める。
そこには溌剌とした超絶美少女がいた。
幼い頃の「自分自身」が笑顔で映っていた――。
●
「俊一くん、お友達が来てるわよ」
朝早く沙織さんがドアを叩く音がした。
目が覚めたが俺は部屋を出る気は全くなかった。
またクラスの誰かもしくは担任だろう。俺に説教しても無駄だ。
もう誰も信用しないと決めたんだ。
そうやって無視を決めこもうとした時だった。
「この間は、本当に失礼しました。言い訳にもなりませんが、貴方が他の女性と楽しそうにしているのに我慢できなくって……」
雫(ja1894)の声が突然ドアの向こうから聞こえてきた。
有り得ない出来事に俺は一瞬パニックになる。こないだ喧嘩別れして以来だった。気の強そうなプライドの高い雫が自分から謝りにくるなんて。
「私を許せないと言うのなら今後、会わない様にしますが、家族の方が心配していますから顔だけでも見せてあげてくれませんか?」
懇願するような声音に俺の心がぐらぐらと揺らいだのがわかった。雫は俺のことを心から心配しているのがわかった。
表面上はツンツンしているが、本当は心の優しい少女なのだ。
俺は雫のことを誤解していた。
だが、俺はもう引きこもりになってしまったのだ。
それに今の俺には――
ベッドには、一緒に寝ていた千代の姿。
幸せそうに目を瞑って寝ている。
「すまんが、帰ってくれないか? 俺はもうこの部屋から出られない」
俺は絞り出すように言った。このままここで怒鳴り合いの問答をしていると、千代が起きてしまう可能性があった。それだけはなんとしても避けたい。
状況がより複雑になる可能性がある……。
穏便に雫を返そうと思った時だった。
雫は何かに気が付いた。地面に写真が落ちていた。千代が連日お菓子を求めて猫のように部屋を荒らしていた。部屋や廊下は物が散乱していた。
それを見て一瞬で雫は凍った。
「もしかして、あの時の初恋の相手って……もしかして、貴方ですか!?」
「はっ……いきなり何を言うんだ?」
事情がまだわからない俺はわけがわからずに聞き返す。
「いっ、今のは無しで、今言った事は忘れて下さい!」
「なんかあったのか?」
「いい加減に子供じみた真似は止めなさい!
――私が気に入らないならはっきりと言いなさい」
雫は突然、ブチ切れて、壁をドンドンと叩き壊そうとしてきた。俺は必死になってドアノブに体重をかけて壊れないように必死に抵抗した。
やばい、やばすぎる!
このまま雫が入ってきたら大変なことになる!
「うん……やけにうるさいな、なんか」
やばいっ、千代が目を擦りながらベッドから顔を出した。
もちろん、一糸纏わぬ姿である……。
「おい、ちょ、雫やめろ! ドアが壊れる!」
「――はっきりしてくれるまで私逃げませんから!」
雫は最後通牒を発してきた。
このままでは修羅場になるのが見えている!
この最悪の状態で千代と雫を鉢合わせるのだけは何としても避けたかった。
「はぁ……人が人を好きになるのに間違いは無いと思いますよ。貴方が抱いたのは友愛、それを親愛と思い違いしてしまっただけでしょ?」
「そうじゃない、違うんだ!」
俺は必死に弁明した。もうこうなったらやけくそだ!
「好きだよ、雫! 俺お前のこと前から好きだったんだ。文句あるか!」
俺は言葉を振り絞って告白した。
その瞬間、「えっ……」と驚いて雫が声を失ったのがわかった。
もうこの修羅場を潜り抜けるのはこの方法しかなかった。
もちろん、雫のことは好きだ。
少なくとも好意は持っている。それは間違いない。
だけど、このタイミングでこんな風に言うのは流石にどうかと思った。
雫の方はどうやら放心したようだった。無理もない。突然こんなことを言われて戸惑っているのが目に浮かぶ。だが俺は逆に安心していた。
これで修羅場が回避――と思った時。
「なあ、俺ちょっとトイレ」
千代がベッドから起きてきてドアに向かってきた。
俺は真っ青になった。今はマズイすぎる。
ドアの向こうには雫が!
俺と千代は互いにドアを取り合った。
「なにするんだ、もれてしまうじゃないかあああ」
千代はすでに臨戦態勢になっていた。朝の状態がものすごいことになっている。これはやばい。いくらなんでもやばい。雫が見たら――って雫さん?
「浅川さん、その人誰ですか?」
その瞬間、背中ら冷たい声が聞こえてきた。
俺はぞっと寒気が走った。
なぜかドアが開いていて雫と千代が対峙していた。
お互いになぜか無表情である。傍目には冷静に見えなくもない。
「雫これは違うんだ! っていうか何かの間違いだ! そうだ、このあと一緒にみんなでデートしようぜ。どこがいい? 自転車の後ろにこいつ乗っけてさ、丘の上まで――」
その週間、俺はなぜか雫にひざ蹴りを食らった。
鳩尾に鋭い痛みを食らってその場に崩れ墜ちる。
「ヘンタイ」
気が付いた時には雫はいなかった。
床に残されていたのは一枚の古い写真だった。神社で親父さんにとってもらったのだろう――幼い雫が映っている。さらにその脇には俺が映っていた。
子供の頃の俺だった。
俺はその昔、雫に会っていた。その頃から雫は俺のことを――。
さっきいきなり様子が変貌したのはこのことだったのだ。
俺はようやく雫の気持ちに気が付いた。
慌てて外に出たがどこにも見当たらない。
そこにいたのは拡声器を持ったアロハシャツ男。
塀の上に乗って絶叫していた。
「俺は肝要だから! 君が引きこもりになろうが! 男の娘の道に行こうが! 彼女を作ろうが! 気にしない! むしろ、そのまま引きこもって留年仲間として大歓迎だ! なんならそのままヒッキーしてくれていいぞ! 俺が楽しい留年ライフを教えてやろう!」
●
「はぁ……はぁ……はぁ……はぁ……」
俺は早朝のロードワークをしていた。当然のように横に居るのは千代。あの雫の出来事からさらに闇の絶望に陥ってしまう所を千代は慰めてくれた。
もうこいつなしに俺の人生はない。
もしかして――これは恋なのだろうか?
俺は気が付いてしまった。男の娘に恋をしてしまったのも。
これまでずっと恋人を作らなかったのも。
重大な真実に気が付いてしまった。どうやら連日のあの馬鹿の拡声器のせいで身も心もおかしくなったようだ。全ては全部あいつのせいである。
俺はそう思わないとやっていられなかった。
雫は俺のことを完全に嫌ってしまっただろう。
俺はまだ雫のことは好きだったが、おそらく許してくれるはずはない。俺はもう千代と生きて行くしかなすすべはなかった。
当の本人はどう思っているのだろうか?
千代は俺のことを好きなのか? 考えただけでも恐ろしかった。
そういえば――と考える。
あの不良野郎と千代は仲がよかった。
もしかして千代はあいつのことが好きなのではないか?
許せなかった。あいつだけは絶対に許せない。
初恋を奪ったあの恐ろしい男の娘。
俺の嫁を奪うならやってみろ。俺の方が千代を深く愛しているはずだ。
「さっきから何を黙っているんだ?」
千代が話しかけてきたが、俺は心の内を言えるわけなかった。
お前のことが好きだなんてそんなことは――。
「おい、家の前にだれかいるぞ」
突然、千代が小刻みに震えだした。見ると、確かに家の前の鳥居に人影がある。怯えている千代を先に家に入れると俺は恐る恐る近づいて行った。
「俊一くん、ひさしぶり!!」
「――その声はシノンか?」
マフラーを巻いて寒そうに木陰に佇んでいたのはシノン=ルーセントハート(jb7062)。彼女を見た瞬間に俺の振動が速く鼓動を打つのがわかった。
可愛らしい容姿は紛れもなく学園一の美少女。
俺はこんな可愛い子になんでもっと早く気がつかなかったと悔やまれる。
「俊一くんにまた声掛けて貰えたら嬉しいな……。
初めて会った時、声を掛けて貰えて、助けて貰って……。
わたし、のろまだから……、みんな、速くて……、一人、置いて行かれるから……。
オーストリアのコンクールでもわたし、何も出来なくて……。
でも、音楽が大好きだから……諦め切れなくて……」
シノンは溢れる想いを俺にぶつけてきた。ずっと俺に言いたいことが溜まっていたのだろう。俺を引きこもりから救うために一生懸命に考えてくれていたんだ。
俺は話を聞いていて泣きそうになった。
こんなに自分を思ってくれる娘は他にはいないだろう。
「……あ、今度、文化ホールで、吹奏楽部の演奏会があるんだ!
其処で、コントラバスを頑張って弾くんだ!
……ブラックバスじゃないよ?」
「わかってる」
俺は思わず苦笑した。
もう俺はシノンに釣られた魚だ。
「俊一くんも良かったら、……来てくれると、嬉しいな……。
音と共に伝えたい事があるんだ。
じゃあ、これから帰って、また頑張って練習するよ。
文化ホールで待ってるから……」
シノンは俺の目を真っ直ぐに見詰めて券を渡した。
手渡してすぐに背を向けて去って行く。
俺は嬉しかった。これが神様が与えてくれた最後のチャンスだ。
俺の人生がハッピーエンドになるか、バッドエンドになるか。
きちんとけじめをつけないといけない。
幸せになるためには、自分の力でつかまなきゃいけないんだ。
●
男は、先ほどから悩んでいた。
女装させられていた昔の自分の写真を引っ張り出し見つめる。
酷く胸が苦しい。
過去のトラウマを思い出していた。
しかたがない。もう時間がなかった。
意を決して衣装ダンスに向かった。
遠い昔に封印した過去。
開けると、甘酸っぱい記憶が漂ってきた。
だがやるしかない。
その写真と近い服とウィッグを揃えて女装する。
鏡に映った自分を眺めた。
なんて格好だ。悲しくなってきた。
――だが、必要な事だ。
●
俺はどうすればいいのだろう?
わからなかった。
これから何処に向かうべきか。
自分が何をすべきなのか。
俺はまず雫の居場所を探した。神社の見回り当番に来ている筈だと思って、近所の神社を回ってみたが彼女は来ていなかった。
どうやら雫もあれ以来サボっているようだった。
――無理もない。あんな状況では誰もが誤解するだろう。
きちんと向き合ってもう一度話したかった。
しかし、おそらく雫も俺と同じように今引きこもっているのかもしれない……。
最低な男だった。俺のせいであいつを苦しめた。
「もうこんな時間か……どうする?」
俺は自問自答した。
今日はシノンのコンサートの当日だった。
朝からずっと雫を探していてもう時間がなくなっていた。今からもう間にあわないかもしれない。それでも俺はシノンに貰った券を持って必死になって走った。
普通ならバスか電車で行く場所だ。
出発時刻を考えると、俺は自分の足で走ることを選択した。
これ以上、女の子を不幸にするわけにはいかない。
俺が引きこもっている間、一生懸命心配してくれたのは他ならぬ彼女達なのだから。
「はぁ……はぁ……はぁ……」
町はずれのコンサートホールに到着した。
すでに終了直前だった。
間にあった。俺はすぐにコンサートホールの扉を開けた。
大勢の観客が吹奏楽部の演奏に聞き入っていた。すばらしい音色だった。シノンを探すと大きなコントラバスを弾いている姿が目に飛び込んできた。
一生懸命に何かを伝えようとしていた。
「あっ……」
不意にシノンと目があった。
ガタアアアアアアアアアアアアアン!
動揺したシノンが思いっきりコントラバスを床に倒した。
盛大な音がして演奏がストップした。
何やってるんだ! あの馬鹿!
俺は居ても経っても居られずにホールを掛け降りた。
「――シノン!」
「俊一くん!」
俺は舞台の下までやってきて叫んだ。
対するシノンは突然の出来事にすでに涙を浮かべている。
「ううっ……ごめん、わたし……演奏……」
演奏を中断させてしまって軽いパニックなっているようだった。
周りの観客達も突然のことにどうしていいかわからない様子だった。演奏していた他の部員達も今はただ手を止めて俺とシノンの成り行きを見守るばかりだ。
「大丈夫だ、シノン! 俺がいるからもう安心するんだ」
俺は叫んだ。不意に周囲の視線が気になる。
大勢の観客が集まったコンサートホール。当然のように周りには詰めかけた観客が俺達のことを興味深そうに見つめていたのだ。
俺は急に恥ずかしくなってしまった。
こんな衆人環視の舞台で俺は何やっているんだ!
猛烈な恥ずかしさに襲われてすぐに背を向けて立ち去ろうとした時だ。
「待って、俊一くん。わたし伝えたいことがあるの!」
踵を返そうとして立ち止まる。
振り返ると、シノンが俺に向かって叫んでいた。
シノンの顔は真っ赤に上気していた。
いやな予感がした。
ちょっと、まてまて。
わかったから落ち付いてくれ!
だが、逆に感極まって胸に溜まった言葉を一斉に吐き出す。
「……わたし、音楽が凄く好きで、日本も同じ位に好き。
でも、日本よりも、音楽よりも好きになれそうなものを見つけたと思うよ」
シノン、ちょっと待て!
心の叫びも空しく彼女は大声で絶叫した。
「――好きだよ、俊一くん」
コンサートホールに全体に響くような叫びだった。
俺はその瞬間、身体が震えていた。
人生でもしかして一番だったかもしれない。
頭が真っ白になった。
何も考えられなくなった。
気が付くと、俺は舞台上に駆け上がっていた。
「俊一くん!」
シノンは俺の胸に抱きついてきた。
俺はそっと彼女の頭に手をやって慰めた。
緊張しすぎて泣きだしていた。
なんかもうどうでもよくなっていた。これまでの引きこもり騒動とか、俺の失恋のこととかすべてのことが吹き飛んでしまっていた。
だが、俺も彼女に言わなければならないことがあった。
俺の全てを受け入れてくれるのか。
それが唯一の不安だった。俺は自分の本性に気が付いてしまっていた。
もう俺は君の知っている俺ではないということを。
「シノン――実は、俺、ホモなんだ」
「……えっ?」
俺は彼女の目に真っ直ぐに向かって、「告白」した。
重大な事実だった。
俺は自分の本性に気が付いてしまった。
昔知らず知らずのうちに男の娘を好きになっていたのも。
それから千代にあんなに親近感を抱くのも。
全ては俺が「ホモ」だからではないか――?
その事実を言わずにしてこれからシノンやもしくは雫と付き合っていくわけにはいかなかった。
その瞬間、シノンの目が大きく見開かれる。
彼女が何かを口にしようとした瞬間。
「あさかわああああああああああああああああああああああああ!」
コンサートホールの上段の扉がバアアアンと開かれた。
俺は振り返った。
眩しい光と共に現れたのは――紅蓮だった。
なぜあいつが、ここに?
最悪のタイミングで最悪の人物がやってきた。
お願いだから、邪魔しないでくれ!
心の叫びを無視して紅蓮は睨みを利かせて俺を探す。
一瞬、明りが侵入者の紅蓮を照らした。
というか、なんだ、その格好は!?
俺は見てはいけないモノを見てしまった。
ごついすね毛の太股にピチピチのピンクのフリルのミニスカート。
頭は栗色のツインテールのウィッグを被っている。
頬には薄紅色をつけて、真っ赤なルージュを塗っていた。
「さがしたぞあさかわあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ!!」
女装した紅蓮は俺に向かって突進してきた。
鬼のような形相だった。
短いスカートの中身が翻って中身がモロ見えになったが、そんなことはどうでもよかった。俺はあまりの恐怖で一歩も動けなかった。
次の瞬間、俺は頬に強烈なパンチを食らう。
気が付いた時は宙に放り出されて舞台裏に落下していた。
「目を覚ますんだ、浅川あああ!
どうじゃ想い出は蘇ったかの。
なんじゃあ……お前さんの恋心なんてのは程度の低い想いじゃったか、下らんのぅ」
紅蓮は俺が伸びてしまったのをみて急にしおらしくなった。
どうやら殴り合いのケンカを想定していたようだ。
しかし、強力すぎる一発目の衝撃に俺はノックダウンしてしまった。
「おい、大丈夫か浅川……?」
「おええええ」
俺は紅蓮に起された。
あまりの気持ち悪い顔をドアップで見て吐いてしまう。
それを見たシノンがついに叫んだ。
「いやああああああああああああああああああああ!」
シノンは顔を押さえて舞台袖へと消えた。
「まってくれ……誤解だ、俺はこいつじゃなくて……」
言い訳しようとしたが、声は届かなかった。意識が朦朧としてきていた。
皆が見ている前でホモかもしれないと告白した。
次の瞬間にこいつが現れたら誰だって誤解する。
人生が終わった瞬間だった。
俺はただありのままの自分を受け入れてほしかった。
ただそれだけなのに――どうしてこうなった?
昏倒した俺は女装男にお姫様抱っこされてしまった。
「それが悔しければ、彼女たちの声にでも耳を傾けるんだな! HAHAHA、喜べBOY! あれだけ嫌がってた俺のフレンドまでリトルモア(意味不明)だ!」
なぜかそこの観客席に居た温がよっぱらいながら絶叫していた。
もうなにがなんだかわからなかった。
俺はいったいどうなってしまうのだろう。
全部夢であればいいのに。
できることなら最初からやり直したかった。
「浅川、死ぬなああしっかりしろおおおおおおおおおおおおおお!」
――俺はついに、ブラックアウトした。
「あ、あー、マイクテストマイクテスト。
本日も引きこもりなり、本日も引きこもりなり!」
窓の外から爆音が聞こえてきた。
夜中の二時である。もういちど繰り返すが夜中のニ時である。
こんな時間にこんな馬鹿なことをする奴はあいつしかいない。
――霧谷 温(jb9158)が拡声器を使って外で叫んでいた。
「初恋が実は男の娘で玉砕ブロークンハートの少年! 聞こえているか!
辛いのわかる! 騙されたと思うのも仕方ない!
だからこそ、あえて俺はこう言おう!『黒歴史乙』!!」
奴は毎晩お構いなしに俺の家へと訪れて怒鳴り声を上げていた。
近所迷惑なんて一切気にしていない。
俺は毎晩うなされていた――原因は言うまでもない。
すでに今が夜なのか昼間なのかさえわからなくなっていた。頭がすでにオカシクなってしまったようだ。視界に靄がかかったように朦朧としている。
「まあ、ほら、あれだ! 昔の女……いや、この場合男?のことなんて忘れて、次の新しい恋とやらを探そうじゃないか! 何、ネタは一杯ある! このままズルズル年取って、大学や社会に出て彼女が出来るなんて考えてんじゃねえぞこの少年! いつ彼女作るの? 今でしょ!」
励ましているつもりなのだろうが、一層俺は自分がみじめに思えてきた。
奴の行為は完全に逆効果だった。そもそもあいつに俺を慰めようと言う気はさらさらないのかもしれないが――。
毎晩の近所迷惑のせいで俺はさらに頭がおかしくなった。もう目の前に幻覚さえみえてきていた。 だって引きこもりの俺の部屋に他に人がいるのが見えるのだから。
「――よぉ引篭り気分はどうだ?」
上半身裸のフードを頭に被った男が天上から現れた。
一瞬、俺は目を疑った。そいつは天上から俺のベッドの上に落ちてきた。
「うわああああああああああああああああああああああああああ」
俺は押しつぶされて発狂した。
ついに幻覚が本物になってしまったのかと恐怖で頭を抱えて叫ぶ。
「おい、なにうなされているんだ? 俺だよ、千代だ」
俺はもう一度そいつの顔を正面から見た。
そこにいたのは紛れもない彪姫 千代(jb0742)だった。
「この辺の抜け道は猫が教えてくれんだ」
聞いてもいないのに千代は語る。何やらいつもよりも若干テンションが高い。引きこもりのくせに余計な御世話だと追い払おうしたが、不意に考える。
俺もこいつと同じ引きこもりだった……。
あまりのブーメランに自分がさらに惨めに思えてくる。俺が考え込んでいる間に当の本人は無邪気に俺の部屋を食料を求めて荒らしまくっていた。
どうやらお腹がすいたらしい。こうやって見ていると千代はあどけない表情をしていた。まるで猫のようである。俺は不意に疑問に思った。
どうしてこいつは引きこもりになったのだろう?
俺は千代のあどけない表情を見て考えた。もしかしたら――俺と同じようにつらい過去があったのかもれしない。俺はこいつのことをもっと知りたくなった。
何か立ち直るきっかけがつかめるかもしれない。
だが、この日俺は結局聞けなかった。
こいつにも誰にも知られたくない過去がある。
それをほじくり返すわけにはいかない。
それから毎晩千代は俺の部屋に来るようになった。夜中二時を過ぎて天上から千代はいつものルートを使ってやってきた。とくにお互いに示し合わせたわけではない。
一緒に何かをするわけでもなかった。
だけど、なぜかお互いに一緒にいると落ち付いた。
心の安らぎを感じた。
思えば、一緒の境遇だった。
「――なあ、おまえはどうして引きこもりになったんだ?」
俺が尋ねると、千代は恥ずかしそうに一呼吸置いて語った。
入学当初から千代がかなり懐いていた教師がいた。
ある日教師に呼ばれ会いに行くと知らない大人数名に暴行された。
この後事件が発覚し教師は学校を去ったが、未だに男性に触られたり学校へ行こうとすると当時の記憶が蘇り震えが止まらず怖くなった。俊一であっても2人でいる状況が本当は怖く脂汗が滲み出るとのことだった。
俺は千代の話を聞いてぐっと拳を握りしめた。
やっぱりだ。俺はこいつと似ている。
信じていた者に裏切られ、人間不信に陥った。
それでも――生きて行くために。
「……もし……俺がもう一度学校に行けたら、その時は本当の友達になってくれるか?」
千代は俺の目を見つめて言った。返事は言うまでもなかった。
その日から俺達は「引きこもりーズ」を結成し、一緒に学校へ行くリハビリのためのロードワークを開始した。早朝の四時頃誰もいない時を見計って寒空の中を走る。
もちろん、上半身は裸でフード付きだ。
万が一誰にも見られるわけにはいかない。ロードワークの後は一緒に部屋に入って沙織さんがドアの前に置いてくれていた食事を一緒に猫のように貪った。
まるで猫のように二人で仲良く食べながら――満腹になった後は一緒にベッドの布団で一糸纏わぬ姿で寝た。千代といると肌の温もりを感じた。
いつしかずっとこのまま一緒にいられたらと願うようになった。
そうやって瞬く間に一週間が過ぎていった。
●
一文字 紅蓮(jb6616)は部屋で一人考える。
俊一にとって、思い出のあの子は特別だった。
記憶の中で更に美化されて、信仰にも近かったのだろう。
それが砕かれた。だから、引き篭もった。
何一つ信じるものなどないように。
だけど、逃避してどうなる。死ぬまでそこにいるのか。
初めから、思い出の『女の子』なんていなかったのだから、 それを認めて次の女の子に恋でもすればいい。そうでなければ、あまりに自分が滑稽だ。
この想いは何なのだろう。恋をした覚えもない俺には分からない。
――ただ、慕って集まった全ての縁にも、俊一自身にさえ向き合おうとしない事に対して、 どうしようもなく苛立った。
紅蓮は決心した。今の自分にできることは何か考える。
あいつを、俊一を助けたかった。
彼を暗闇から引きずり出すために。
一枚の古い写真を握り締める。
そこには溌剌とした超絶美少女がいた。
幼い頃の「自分自身」が笑顔で映っていた――。
●
「俊一くん、お友達が来てるわよ」
朝早く沙織さんがドアを叩く音がした。
目が覚めたが俺は部屋を出る気は全くなかった。
またクラスの誰かもしくは担任だろう。俺に説教しても無駄だ。
もう誰も信用しないと決めたんだ。
そうやって無視を決めこもうとした時だった。
「この間は、本当に失礼しました。言い訳にもなりませんが、貴方が他の女性と楽しそうにしているのに我慢できなくって……」
雫(ja1894)の声が突然ドアの向こうから聞こえてきた。
有り得ない出来事に俺は一瞬パニックになる。こないだ喧嘩別れして以来だった。気の強そうなプライドの高い雫が自分から謝りにくるなんて。
「私を許せないと言うのなら今後、会わない様にしますが、家族の方が心配していますから顔だけでも見せてあげてくれませんか?」
懇願するような声音に俺の心がぐらぐらと揺らいだのがわかった。雫は俺のことを心から心配しているのがわかった。
表面上はツンツンしているが、本当は心の優しい少女なのだ。
俺は雫のことを誤解していた。
だが、俺はもう引きこもりになってしまったのだ。
それに今の俺には――
ベッドには、一緒に寝ていた千代の姿。
幸せそうに目を瞑って寝ている。
「すまんが、帰ってくれないか? 俺はもうこの部屋から出られない」
俺は絞り出すように言った。このままここで怒鳴り合いの問答をしていると、千代が起きてしまう可能性があった。それだけはなんとしても避けたい。
状況がより複雑になる可能性がある……。
穏便に雫を返そうと思った時だった。
雫は何かに気が付いた。地面に写真が落ちていた。千代が連日お菓子を求めて猫のように部屋を荒らしていた。部屋や廊下は物が散乱していた。
それを見て一瞬で雫は凍った。
「もしかして、あの時の初恋の相手って……もしかして、貴方ですか!?」
「はっ……いきなり何を言うんだ?」
事情がまだわからない俺はわけがわからずに聞き返す。
「いっ、今のは無しで、今言った事は忘れて下さい!」
「なんかあったのか?」
「いい加減に子供じみた真似は止めなさい!
――私が気に入らないならはっきりと言いなさい」
雫は突然、ブチ切れて、壁をドンドンと叩き壊そうとしてきた。俺は必死になってドアノブに体重をかけて壊れないように必死に抵抗した。
やばい、やばすぎる!
このまま雫が入ってきたら大変なことになる!
「うん……やけにうるさいな、なんか」
やばいっ、千代が目を擦りながらベッドから顔を出した。
もちろん、一糸纏わぬ姿である……。
「おい、ちょ、雫やめろ! ドアが壊れる!」
「――はっきりしてくれるまで私逃げませんから!」
雫は最後通牒を発してきた。
このままでは修羅場になるのが見えている!
この最悪の状態で千代と雫を鉢合わせるのだけは何としても避けたかった。
「はぁ……人が人を好きになるのに間違いは無いと思いますよ。貴方が抱いたのは友愛、それを親愛と思い違いしてしまっただけでしょ?」
「そうじゃない、違うんだ!」
俺は必死に弁明した。もうこうなったらやけくそだ!
「好きだよ、雫! 俺お前のこと前から好きだったんだ。文句あるか!」
俺は言葉を振り絞って告白した。
その瞬間、「えっ……」と驚いて雫が声を失ったのがわかった。
もうこの修羅場を潜り抜けるのはこの方法しかなかった。
もちろん、雫のことは好きだ。
少なくとも好意は持っている。それは間違いない。
だけど、このタイミングでこんな風に言うのは流石にどうかと思った。
雫の方はどうやら放心したようだった。無理もない。突然こんなことを言われて戸惑っているのが目に浮かぶ。だが俺は逆に安心していた。
これで修羅場が回避――と思った時。
「なあ、俺ちょっとトイレ」
千代がベッドから起きてきてドアに向かってきた。
俺は真っ青になった。今はマズイすぎる。
ドアの向こうには雫が!
俺と千代は互いにドアを取り合った。
「なにするんだ、もれてしまうじゃないかあああ」
千代はすでに臨戦態勢になっていた。朝の状態がものすごいことになっている。これはやばい。いくらなんでもやばい。雫が見たら――って雫さん?
「浅川さん、その人誰ですか?」
その瞬間、背中ら冷たい声が聞こえてきた。
俺はぞっと寒気が走った。
なぜかドアが開いていて雫と千代が対峙していた。
お互いになぜか無表情である。傍目には冷静に見えなくもない。
「雫これは違うんだ! っていうか何かの間違いだ! そうだ、このあと一緒にみんなでデートしようぜ。どこがいい? 自転車の後ろにこいつ乗っけてさ、丘の上まで――」
その週間、俺はなぜか雫にひざ蹴りを食らった。
鳩尾に鋭い痛みを食らってその場に崩れ墜ちる。
「ヘンタイ」
気が付いた時には雫はいなかった。
床に残されていたのは一枚の古い写真だった。神社で親父さんにとってもらったのだろう――幼い雫が映っている。さらにその脇には俺が映っていた。
子供の頃の俺だった。
俺はその昔、雫に会っていた。その頃から雫は俺のことを――。
さっきいきなり様子が変貌したのはこのことだったのだ。
俺はようやく雫の気持ちに気が付いた。
慌てて外に出たがどこにも見当たらない。
そこにいたのは拡声器を持ったアロハシャツ男。
塀の上に乗って絶叫していた。
「俺は肝要だから! 君が引きこもりになろうが! 男の娘の道に行こうが! 彼女を作ろうが! 気にしない! むしろ、そのまま引きこもって留年仲間として大歓迎だ! なんならそのままヒッキーしてくれていいぞ! 俺が楽しい留年ライフを教えてやろう!」
●
「はぁ……はぁ……はぁ……はぁ……」
俺は早朝のロードワークをしていた。当然のように横に居るのは千代。あの雫の出来事からさらに闇の絶望に陥ってしまう所を千代は慰めてくれた。
もうこいつなしに俺の人生はない。
もしかして――これは恋なのだろうか?
俺は気が付いてしまった。男の娘に恋をしてしまったのも。
これまでずっと恋人を作らなかったのも。
重大な真実に気が付いてしまった。どうやら連日のあの馬鹿の拡声器のせいで身も心もおかしくなったようだ。全ては全部あいつのせいである。
俺はそう思わないとやっていられなかった。
雫は俺のことを完全に嫌ってしまっただろう。
俺はまだ雫のことは好きだったが、おそらく許してくれるはずはない。俺はもう千代と生きて行くしかなすすべはなかった。
当の本人はどう思っているのだろうか?
千代は俺のことを好きなのか? 考えただけでも恐ろしかった。
そういえば――と考える。
あの不良野郎と千代は仲がよかった。
もしかして千代はあいつのことが好きなのではないか?
許せなかった。あいつだけは絶対に許せない。
初恋を奪ったあの恐ろしい男の娘。
俺の嫁を奪うならやってみろ。俺の方が千代を深く愛しているはずだ。
「さっきから何を黙っているんだ?」
千代が話しかけてきたが、俺は心の内を言えるわけなかった。
お前のことが好きだなんてそんなことは――。
「おい、家の前にだれかいるぞ」
突然、千代が小刻みに震えだした。見ると、確かに家の前の鳥居に人影がある。怯えている千代を先に家に入れると俺は恐る恐る近づいて行った。
「俊一くん、ひさしぶり!!」
「――その声はシノンか?」
マフラーを巻いて寒そうに木陰に佇んでいたのはシノン=ルーセントハート(jb7062)。彼女を見た瞬間に俺の振動が速く鼓動を打つのがわかった。
可愛らしい容姿は紛れもなく学園一の美少女。
俺はこんな可愛い子になんでもっと早く気がつかなかったと悔やまれる。
「俊一くんにまた声掛けて貰えたら嬉しいな……。
初めて会った時、声を掛けて貰えて、助けて貰って……。
わたし、のろまだから……、みんな、速くて……、一人、置いて行かれるから……。
オーストリアのコンクールでもわたし、何も出来なくて……。
でも、音楽が大好きだから……諦め切れなくて……」
シノンは溢れる想いを俺にぶつけてきた。ずっと俺に言いたいことが溜まっていたのだろう。俺を引きこもりから救うために一生懸命に考えてくれていたんだ。
俺は話を聞いていて泣きそうになった。
こんなに自分を思ってくれる娘は他にはいないだろう。
「……あ、今度、文化ホールで、吹奏楽部の演奏会があるんだ!
其処で、コントラバスを頑張って弾くんだ!
……ブラックバスじゃないよ?」
「わかってる」
俺は思わず苦笑した。
もう俺はシノンに釣られた魚だ。
「俊一くんも良かったら、……来てくれると、嬉しいな……。
音と共に伝えたい事があるんだ。
じゃあ、これから帰って、また頑張って練習するよ。
文化ホールで待ってるから……」
シノンは俺の目を真っ直ぐに見詰めて券を渡した。
手渡してすぐに背を向けて去って行く。
俺は嬉しかった。これが神様が与えてくれた最後のチャンスだ。
俺の人生がハッピーエンドになるか、バッドエンドになるか。
きちんとけじめをつけないといけない。
幸せになるためには、自分の力でつかまなきゃいけないんだ。
●
男は、先ほどから悩んでいた。
女装させられていた昔の自分の写真を引っ張り出し見つめる。
酷く胸が苦しい。
過去のトラウマを思い出していた。
しかたがない。もう時間がなかった。
意を決して衣装ダンスに向かった。
遠い昔に封印した過去。
開けると、甘酸っぱい記憶が漂ってきた。
だがやるしかない。
その写真と近い服とウィッグを揃えて女装する。
鏡に映った自分を眺めた。
なんて格好だ。悲しくなってきた。
――だが、必要な事だ。
●
俺はどうすればいいのだろう?
わからなかった。
これから何処に向かうべきか。
自分が何をすべきなのか。
俺はまず雫の居場所を探した。神社の見回り当番に来ている筈だと思って、近所の神社を回ってみたが彼女は来ていなかった。
どうやら雫もあれ以来サボっているようだった。
――無理もない。あんな状況では誰もが誤解するだろう。
きちんと向き合ってもう一度話したかった。
しかし、おそらく雫も俺と同じように今引きこもっているのかもしれない……。
最低な男だった。俺のせいであいつを苦しめた。
「もうこんな時間か……どうする?」
俺は自問自答した。
今日はシノンのコンサートの当日だった。
朝からずっと雫を探していてもう時間がなくなっていた。今からもう間にあわないかもしれない。それでも俺はシノンに貰った券を持って必死になって走った。
普通ならバスか電車で行く場所だ。
出発時刻を考えると、俺は自分の足で走ることを選択した。
これ以上、女の子を不幸にするわけにはいかない。
俺が引きこもっている間、一生懸命心配してくれたのは他ならぬ彼女達なのだから。
「はぁ……はぁ……はぁ……」
町はずれのコンサートホールに到着した。
すでに終了直前だった。
間にあった。俺はすぐにコンサートホールの扉を開けた。
大勢の観客が吹奏楽部の演奏に聞き入っていた。すばらしい音色だった。シノンを探すと大きなコントラバスを弾いている姿が目に飛び込んできた。
一生懸命に何かを伝えようとしていた。
「あっ……」
不意にシノンと目があった。
ガタアアアアアアアアアアアアアン!
動揺したシノンが思いっきりコントラバスを床に倒した。
盛大な音がして演奏がストップした。
何やってるんだ! あの馬鹿!
俺は居ても経っても居られずにホールを掛け降りた。
「――シノン!」
「俊一くん!」
俺は舞台の下までやってきて叫んだ。
対するシノンは突然の出来事にすでに涙を浮かべている。
「ううっ……ごめん、わたし……演奏……」
演奏を中断させてしまって軽いパニックなっているようだった。
周りの観客達も突然のことにどうしていいかわからない様子だった。演奏していた他の部員達も今はただ手を止めて俺とシノンの成り行きを見守るばかりだ。
「大丈夫だ、シノン! 俺がいるからもう安心するんだ」
俺は叫んだ。不意に周囲の視線が気になる。
大勢の観客が集まったコンサートホール。当然のように周りには詰めかけた観客が俺達のことを興味深そうに見つめていたのだ。
俺は急に恥ずかしくなってしまった。
こんな衆人環視の舞台で俺は何やっているんだ!
猛烈な恥ずかしさに襲われてすぐに背を向けて立ち去ろうとした時だ。
「待って、俊一くん。わたし伝えたいことがあるの!」
踵を返そうとして立ち止まる。
振り返ると、シノンが俺に向かって叫んでいた。
シノンの顔は真っ赤に上気していた。
いやな予感がした。
ちょっと、まてまて。
わかったから落ち付いてくれ!
だが、逆に感極まって胸に溜まった言葉を一斉に吐き出す。
「……わたし、音楽が凄く好きで、日本も同じ位に好き。
でも、日本よりも、音楽よりも好きになれそうなものを見つけたと思うよ」
シノン、ちょっと待て!
心の叫びも空しく彼女は大声で絶叫した。
「――好きだよ、俊一くん」
コンサートホールに全体に響くような叫びだった。
俺はその瞬間、身体が震えていた。
人生でもしかして一番だったかもしれない。
頭が真っ白になった。
何も考えられなくなった。
気が付くと、俺は舞台上に駆け上がっていた。
「俊一くん!」
シノンは俺の胸に抱きついてきた。
俺はそっと彼女の頭に手をやって慰めた。
緊張しすぎて泣きだしていた。
なんかもうどうでもよくなっていた。これまでの引きこもり騒動とか、俺の失恋のこととかすべてのことが吹き飛んでしまっていた。
だが、俺も彼女に言わなければならないことがあった。
俺の全てを受け入れてくれるのか。
それが唯一の不安だった。俺は自分の本性に気が付いてしまっていた。
もう俺は君の知っている俺ではないということを。
「シノン――実は、俺、ホモなんだ」
「……えっ?」
俺は彼女の目に真っ直ぐに向かって、「告白」した。
重大な事実だった。
俺は自分の本性に気が付いてしまった。
昔知らず知らずのうちに男の娘を好きになっていたのも。
それから千代にあんなに親近感を抱くのも。
全ては俺が「ホモ」だからではないか――?
その事実を言わずにしてこれからシノンやもしくは雫と付き合っていくわけにはいかなかった。
その瞬間、シノンの目が大きく見開かれる。
彼女が何かを口にしようとした瞬間。
「あさかわああああああああああああああああああああああああ!」
コンサートホールの上段の扉がバアアアンと開かれた。
俺は振り返った。
眩しい光と共に現れたのは――紅蓮だった。
なぜあいつが、ここに?
最悪のタイミングで最悪の人物がやってきた。
お願いだから、邪魔しないでくれ!
心の叫びを無視して紅蓮は睨みを利かせて俺を探す。
一瞬、明りが侵入者の紅蓮を照らした。
というか、なんだ、その格好は!?
俺は見てはいけないモノを見てしまった。
ごついすね毛の太股にピチピチのピンクのフリルのミニスカート。
頭は栗色のツインテールのウィッグを被っている。
頬には薄紅色をつけて、真っ赤なルージュを塗っていた。
「さがしたぞあさかわあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ!!」
女装した紅蓮は俺に向かって突進してきた。
鬼のような形相だった。
短いスカートの中身が翻って中身がモロ見えになったが、そんなことはどうでもよかった。俺はあまりの恐怖で一歩も動けなかった。
次の瞬間、俺は頬に強烈なパンチを食らう。
気が付いた時は宙に放り出されて舞台裏に落下していた。
「目を覚ますんだ、浅川あああ!
どうじゃ想い出は蘇ったかの。
なんじゃあ……お前さんの恋心なんてのは程度の低い想いじゃったか、下らんのぅ」
紅蓮は俺が伸びてしまったのをみて急にしおらしくなった。
どうやら殴り合いのケンカを想定していたようだ。
しかし、強力すぎる一発目の衝撃に俺はノックダウンしてしまった。
「おい、大丈夫か浅川……?」
「おええええ」
俺は紅蓮に起された。
あまりの気持ち悪い顔をドアップで見て吐いてしまう。
それを見たシノンがついに叫んだ。
「いやああああああああああああああああああああ!」
シノンは顔を押さえて舞台袖へと消えた。
「まってくれ……誤解だ、俺はこいつじゃなくて……」
言い訳しようとしたが、声は届かなかった。意識が朦朧としてきていた。
皆が見ている前でホモかもしれないと告白した。
次の瞬間にこいつが現れたら誰だって誤解する。
人生が終わった瞬間だった。
俺はただありのままの自分を受け入れてほしかった。
ただそれだけなのに――どうしてこうなった?
昏倒した俺は女装男にお姫様抱っこされてしまった。
「それが悔しければ、彼女たちの声にでも耳を傾けるんだな! HAHAHA、喜べBOY! あれだけ嫌がってた俺のフレンドまでリトルモア(意味不明)だ!」
なぜかそこの観客席に居た温がよっぱらいながら絶叫していた。
もうなにがなんだかわからなかった。
俺はいったいどうなってしまうのだろう。
全部夢であればいいのに。
できることなら最初からやり直したかった。
「浅川、死ぬなああしっかりしろおおおおおおおおおおおおおお!」
――俺はついに、ブラックアウトした。
依頼結果
| 依頼成功度:成功 |
| MVP: 撃退士・彪姫 千代(jb0742) |
| 重体: − |
| 面白かった!:3人 |
| 歴戦の戦姫・ 不破 雫(ja1894) 中等部2年1組 女 阿修羅 |
撃退士・ 彪姫 千代(jb0742) 高等部3年26組 男 ナイトウォーカー |
||
| 男の娘・ 一文字 紅蓮(jb6616) 大学部5年142組 男 阿修羅 |
恋する乙女(ヒロイン)・ シノン=ルーセントハート(jb7062) 高等部3年23組 女 アストラルヴァンガード |
||
| 黒い胸板に囲まれて・ 霧谷 温(jb9158) 大学部3年284組 男 アストラルヴァンガード |

