|
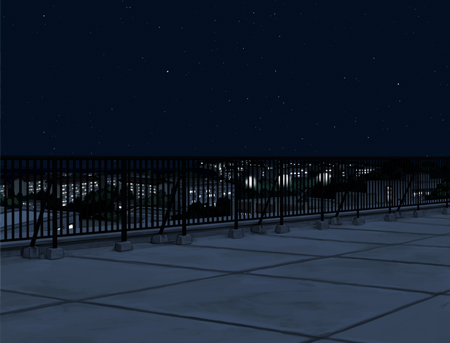 |
みんなの思い出
オープニング
●さよならの夏
二〇一七年八月三十一日、夜。
あと数時間もすれば、今日が終わる。
八月三十一日。きっと明日からも暑いけれど、夏が終わる。
ツクツクボウシの声も尽き。
早くもコオロギが鳴いている。
日没までの時間は、これからどんどん短くなるのだろう。
厭うほどの暑さも少しずつ弱くなっていくのだろう。
思えば、今年が終わるまであと三カ月ほど。
そう思うと益々、時の速さを思い知る。
思えば矢のような速さだった。
夏が終わる。
あのさんざめく季節が。
夏が終わる。
あの幻のようなひとときが。
夏が終わる。
八月三十一日が終わる。
君達は――
最後の数時間をどう過ごしているだろうか。
夏休みの宿題と壮絶な戦いを繰り広げているだろうか。
撃退士として任務に赴いているのだろうか。
友達の家で遊んでいるだろうか。
あるいは、変わらぬ日常を穏やかに過ごしているだろうか。
八月という夏の思い出を、ひそやかに回顧しているだろうか。
――夏が、八月三十一日が、今日、終わる。
二〇一七年八月三十一日、夜。
あと数時間もすれば、今日が終わる。
八月三十一日。きっと明日からも暑いけれど、夏が終わる。
ツクツクボウシの声も尽き。
早くもコオロギが鳴いている。
日没までの時間は、これからどんどん短くなるのだろう。
厭うほどの暑さも少しずつ弱くなっていくのだろう。
思えば、今年が終わるまであと三カ月ほど。
そう思うと益々、時の速さを思い知る。
思えば矢のような速さだった。
夏が終わる。
あのさんざめく季節が。
夏が終わる。
あの幻のようなひとときが。
夏が終わる。
八月三十一日が終わる。
君達は――
最後の数時間をどう過ごしているだろうか。
夏休みの宿題と壮絶な戦いを繰り広げているだろうか。
撃退士として任務に赴いているのだろうか。
友達の家で遊んでいるだろうか。
あるいは、変わらぬ日常を穏やかに過ごしているだろうか。
八月という夏の思い出を、ひそやかに回顧しているだろうか。
――夏が、八月三十一日が、今日、終わる。
リプレイ本文
●夜、久遠ヶ原学園01
(色々なことがあったなぁ)
八月三一日。それは蓮城 真緋呂(jb6120)にとって、久遠ヶ原学園で過ごす最後の日。
(学園に編入したのが、四年前の六月……)
見慣れてしまった景色とも、今日でお別れ……名残惜しさを噛み締めて、真緋呂は夜の学園の散策を始める。
「初めての教室がここ。……何だか必死だったわよね」
最初に訪れたのは高等部校舎の一年生教室。最初に座った座席――机をそっと指先で撫でた。
敵を討つ為に強くならなくては。そんな想いが強くあって、我武者羅に依頼を受け続けたっけ。
「手が届かなかったことも……あった」
羽根を残してくれた黄金の天使に、何もできなかったと涙したことを思い出す。
あれから強くなれただろうか。など、自問してみる。最初の席に、座ってみる。目を閉じれば鮮明に思い返せる、激闘の日々――。
「……ある意味、強者相手に戦い続けた凄い場所よね」
所変わって学食。ここもまた、真緋呂にとっては激闘の場所。顔を覗かせてみれば、厨房で職員達が明日の分の仕込みを行っている。
は、と彼等と目が合った。食欲魔人として名高い真緋呂の出現に「まだ準備中ですよ〜」と先制されるが、彼女は「食べに来たんじゃないんです」と苦笑を浮かべた。
「ご馳走様でした」
手を合わせ、深々とお辞儀。心が折れた時もお腹は空いた。そんな時、いつだって優しく迎えてくれたのがここだった……。
「久遠ヶ原から人が旅立つのは何度も見送ってきたが――今度は俺が旅立つ番、ってな」
今日で小田切ルビィ(ja0841)の学園生活が終わる。
(十年以上厄介になった学園からやっと解放……もとい、新たな一歩、か)
明日からの肩書は『卒業生』。彼は明日、ここから旅立つ。荷造りなどは既に終え、今はちょっとした『野暮用』、だ。手には花束、学園内を歩いて、足を止めたのはとある場所。
「よう」
見上げた先には、供養塔。敵味方問わず、今までの戦いで命を落とした者達の冥福を祈る場所。ルビィはそこに花を供え、線香に火をつける。
「人の血も、魔の血も抱えて――俺は生きるぜ、ゐのり……」
目を閉じれば思い出す、孤独な少女。ルビィと同じ半魔という、血の宿命を持っていた者。京臣ゐのりは、ルビィのありえた可能性……。
(できることなら、あんたを救ってやりたかった……)
立ち上る細い煙の中、手を合わせ。目を閉じて。少女と同じ名前の行為――『いのり』を捧げる。
「棄棄先生、お疲れさま」
職員室の戸が開いて、Robin redbreast(jb2203)が顔を覗かせた。
「パウンドケーキを作ってみたよ。食べてくれたら嬉しいな」
そう言って、棄棄のデスクまで来ると、差し出したのは可愛らしくラッピングされたパウンドケーキだ。書類に向かっていた教師だったが、差し入れに「ありがとさん!」と笑みを向ける。
「ロビンちゃん、宿題は終わったのかい?」
「うん、ばっちり」
ロビンはそう頷くと、次いで差し入れに視線をやった。味の感想が聞きたいな、という意思表示である。
――ロビンは去年から料理教室に通っている。
二年前に受けた、殺人的料理を作成する依頼からの成長は著しい。最近は乙女らしく、休みの日などにお菓子作りにもチャレンジしており、「寮のキッチンは狭いので」と学園の家庭科室を借りては勤しんでいるのである。
ただ、練習で大量に作りすぎてしまうので、こうして夏休みでも学園に来ている教師陣におすそ分けしているのだ。
「はい、めしあがれ」
お皿に盛って、紅茶も淹れて。食器も料理の一つと語らんばかりの行動は、『例の依頼』を受けた少女のものとは思えない。
「いただきます」
手を合わせ、パウンドケーキを頬張る棄棄。ロビンはそんな教師の様子をじーっと見ている。
「美味しい?」
「もちろん!」
「よかった」
にこ。その笑みは、かつてのような『人形的』ではない。少女が笑みたいと思って笑んだ笑顔。そんな表情のまま、ロビンは歌うように声を弾ませる。
「明日から大学生になるんだよ。大学の制服つくってみたんだ」
「作ったって、自作したのか!? そりゃ凄いな」
「明日、着てくるね」
「楽しみにしとくよ。進学、おめでとさん」
「ありがとう」
と、そこへ。
再び職員室の戸が開いて、今度はルビィが現れる。
「こんばんは、棄棄センセー」
「おうルビィくん、お前もパウンドケーキか?」
「へ?」
「ははは。で、どした?」
紅茶片手に教師が問う。実は、とルビィは表情を改めて――告げるのは、明日ここを発つこと。「そうか」と、教師は穏やかに微笑み、それを肯定してくれた。
「そういえば」
ルビィが問う。
「センセーは学園辞めた後はどうすんだ? 俺は世界をこの目で見る為に旅に出るぜ」
「いいねえ、俺もそんな感じの予定さ。じゃ、世界のどっかで会うかもな!」
「それじゃあ、どっかて会ったらよろしくな、センセー」
「こちらこそ」
また会おうぜ。それは男の約束ってやつだ。
●夜、久遠ヶ原島
「早かったような短かったような、学園生活でしたね……」
腰を下ろしたソファー。ファティナ・V・アイゼンブルク(ja0454)はそう呟き、隣の神月 熾弦(ja0358)にそっと身を預けていた。
「そうですね。でも、色んなことがありましたね……」
恋人の体温を感じつつ、熾弦が答える。二人の手は繋がれ、白い指が絡んでいる。
かち、こち、時計の針の音。
ここはファティナが経営する喫茶店「silver faery」の二階、その私室。
二人は沈黙に耳を傾け、長かったような短かったような、学園での日々を思い返していた。
「シヅルさん、話しておかないといけないことがあります」
「私からもですよ、ファティナさん」
おもむろな言葉。
ひとつずつ語る。
ファティナはこの喫茶店を閉め、一度故郷に戻る。
熾弦も同じく学園を離れ、将来のために家に戻る。
つまり、長いお別れになるのだ。
「……料理の勉強をし直したら、またここに必ず戻ってきます」
ファティナが告げる。熾弦はゆったり微笑み、恋人の手を優しく握り直した。
「迷いなく進む道ではありますが、先に待つ困難は男女の恋人とは大きく違います……家族の理解も。それを乗り越えるための期間だと、私は理解しています」
「そうですよね……。家族のこと、特に父とは疎遠でしたが流石に話をしないとですし。お姉様はともかく、お兄様はシスコンで説得が大変そうですし」
苦笑してみせる。顔を上げれば、ファティナを見守る熾弦と視線が合った。赤い瞳と、青い瞳――。
「ふふ」と、笑んだのは熾弦。
「待っていてください、と言うのも変ですね。楽しみにしていてください、と言いましょうか、お互いにそれぞれの道を乗り越えてまた寄り添える日を」
その言葉に、ファティナは笑みと共に頷きを返した。
「遠く離れても、私の一番はずっとシヅルさん。また寄り添える日を心待ちにしております」
性別という世間的な壁はあるけれど。
愛は勝つ、なんて乙女思考が過ぎるかもしれないけれど。
それでも、二人は愛し合っていた。二人の愛は本物で。
長いお別れになる。寂しくないと言えば嘘になる。
でも、二人は互いを信じている。
いつかきっと、また会える――。
「――……」
余分な言葉はもう蛇足だろうか。二人は寄り添い続けている。しばしの別れを惜しむように。一秒でも、恋人の体温を覚えていたいと言わんばかりに。
「あ」
最中のことだ。熾弦が呟く。「どうしました?」とファティナが問えば、彼女はクスリと微笑んで。
「ひとまずのお別れの前に、恋人らしいことをしておきます?」
「恋人らしいこと、と言いますと?」
その言葉の返答は。重ねられた唇。柔らかい感触。
「――想いを確かめ合うのには、行動も良いものかと」
体温の間隙に、囁きの台詞。
肩に回される手を感じつつ、頬に額に口付けを浴びるファティナはボッと顔が赤くなる。
「や、優しくお願いします……?」
呟いた言葉。電気が消されるその前に、ファティナが最後に見たのは愛おしそうな青い瞳。
綺麗だな――そう思った。
その目が自分にだけ注がれていることに、優越感のような幸福感。
さらり、こぼれ流れる二人分の銀の髪。それは銀河のように混ざり合い――暗くなった部屋の中、カーテンから差し込む月の光に、きらりきらりと輝いていた。
「ふう」
最後の段ボールをガムテープで閉じ、星杜 焔(ja5378)は息を吐いた。そのまま時計を見やる。もうこんな時間。彼はたった今、明日の引っ越し準備を終えたところであった。
久遠ヶ原島に残る友人には、酒や手製菓子を贈った。
棄棄には家族で作ったあんぱんを贈った。
これで久遠ヶ原学園は卒業――……。
(色んなことがあったなぁ)
窓から夜を見る。幾度も見てきた景色だけれど、なぜか今は特別に見えた。
焔は久遠ヶ原島から離れる。
けれどそれは一年だけ。
というのも、彼の養子である望が来年から幼稚園に通うからだ。アウル適正のある彼が通うのは久遠ヶ原幼稚園が良いだろう。
ゆえに、このマンションの部屋は、島での住居としてこのまま残す予定だ。
とはいえ。住み慣れた場所から離れるのには、やはり寂寥感が否めない。
(これからも、色んなことがあるんだろうなぁ)
人生の節目。これからうんと忙しくなる。
児童養護施設と小料理屋を営むという目標に向けて、専門的な勉強や資格の取得、それから資金集め。幸い、卒業制作発表会で某企業から出資の提案も貰えたが、ノンビリしている暇はないだろう。
そんなことに思いを馳せて。改めて、焔はこの部屋の静けさを思い知る。愛妻は先に、引越し先である彼女の実家に赴き焔達の受け入れ体制を整えている。望と愛犬もふらは、寝室でスヤスヤ眠っている。
(望。おばあちゃん達、君と暮らせるのがとても楽しみだって)
心の中で息子に語りかける。お別れ記念の晩餐を食べた望は夢の中。最後に掃除し尽くしたキッチンがキラリと光る。明日は長旅、たっぷり休もうね。
――激動の未来が待っている。
けれど、それは希望の光に満ちている。
「寝る準備……完了……抱き枕……OK……ヨーソロー……」
ぱちん。消灯。ベアトリーチェ・ヴォルピ(jb9382)はベッドの上。
ふわふわの抱き枕を抱きしめて目を閉じる。温かで柔らかい真っ暗闇。そうすると、忍び寄るまどろみにて、ぐるぐる思考が巡り始める。
――学園を去る者がいる中で、ベアトリーチェは残ることを決めた。
叶えたい夢が、できたから。
「お嫁さんになる」という夢の他に、もう一つ。
アテナ。ベアトリーチェの親友。彼女の、天王の、右腕になること。
その為には経験が必要だ。強くならねばならない。賢くならねばならない。色んなことを知らねばならない。
そして、皆に認められて……胸を張って、アテナの右横に立ちたい。
(それが……私の、ジャスティス……)
抱き枕をギュッと抱き直す。道のりはきっと険しい。それでも進むと、決めたのだ。頑張ろう。そう思って――ふと、脳裏に過ぎるのは外奪の顔。そうだ、次の休み、彼のお墓にも報告をしに行こう。
(お土産……どうしよ……やっぱり、アップルパイ……?)
ああ、アップルパイといえば、サマエル。地球への干渉を永久放棄した大悪魔。彼は今、何をしているんだろうか。
(ベリアルお姉さんに頼んだら……持って行って、くれるかな……今度、聞いてみよう……)
そこまで考えて、ふわ、とあくびが出た。目を閉じている間に這い寄ってきた眠気は、もう抗えない距離にいる。思考が夢と混ざってきた。家庭科室でアップルパイを焼いている外奪が「エプロンと割烹着ってどっちがトレンドなんですか?」とか言っている脳内幻覚が見える。そういうわけで夢の世界に飛び立とう。
……おやすみなさい。
また、ね。
●夜、久遠ヶ原学園02
「こんばんは棄棄先生」
学園中庭。鴉乃宮 歌音(ja0427)は通りかかった棄棄にそう声をかけた。
「よう歌音くん。……何やってんだ?」
足を止めて教師が聞いたのも無理もない。何やら湯気の立ち上るでっかい車の前に、エプロン姿の歌音がいるのだから。
「ああ、依頼が終わったので報告書を作りに来たところでして。ついでに炊事車の整備点検と依頼の打ち上げがてら食事を作ってたところです。ラーメンですがいります?」
「なんかすげーな」
毎度ながら歌音の器用さに圧倒されつつ、どんぶりによそわれたラーメンは受け取るのだ。手近なベンチに腰を下ろす。「袋麺ですがネギ油とニンニク生姜炒めを加えればお店らしくなるんです」と歌音の言葉通りに、香り立つそれはなんとも食欲を刺激する。
「米も炊けばよかったかな?」
「はは、食堂を開けそうだ」
生徒の言葉に教師が笑えば、「そうそう」と歌音がトッピング用のネギを追加で切りつつ言葉を続ける。
「食堂は開きませんが、私も学園で教官をやることになりまして」
「おー、おめでとさん。何の教官?」
「主に実地戦闘訓練の手伝いと野外炊事ですかね。インフィルトレイターの経験は警察や自衛隊、傭兵に大きく勉強になるかと思います。市街地戦ゲリラ戦で物心両面を泣かせ、炊事で食事の美味しさに泣かせるみたいな」
「いいじゃん」
熱いラーメンをすすりつつ、教師は笑った。
「先生、口に合いますか?」
「ほんとおいしいわ、学食は惜しい人材を無くした」
「あはは。引退後は食堂でも開きますかね。……先生は学園に残られるんですよね?」
「おー、そーだな」
「では、今後ともよろしくお願いします」
と、その時だ。
「よ、大将。やってる?」
そんな冗句と共に現れたのは、ミハイル・エッカート(jb0544)だった。
「棄棄先生と話したいことがあってさ」
ラーメンを受け取り、ビール(発泡酒ではないのだ!)の缶を開けて、まずは乾杯。「話したいことって?」と渡されたビールをあおりつつ棄棄が問う。するとミハイルはこう言った。
「先生は三界同盟が永遠に続くと思うか? 俺は思えない」
「ほう?」
「人間界が綻びを見せたら、付けこむ奴はいくらでも出る。外奪のような奴もいる。覚醒者と非覚醒者の溝は今も深く、そこが弱点だ」
もう『恒久の聖女』のような事件は起きて欲しくない。そう溜息を吐く彼の言葉に、教師は夜空を見上げ。
「人間同士でも分かり合うのが難しいのに……ってのは、【双蝕】事件で嫌なほど突き付けられたな」
「ああ」
ラーメンをすする。飲み込んで、ミハイルは言葉を続ける。
「先生は覚醒したのは何歳だった?」
「物心ついた時には、だな」
「俺は二七歳、遅めだ。……だから非覚醒者が覚醒者を恐れる気持ちはわかる。分かるからこそ、溝を埋めたい。
俺はこれからも力を付ける。『正しいことをしたければ偉くなれ』……とある老刑事の言葉だ。人間界を守るため俺は高みに上る。綺麗事では済まない世界だ」
そこまで言って、ミハイルは棄棄へと視線を据えた。
「もし俺がトチ狂ったら、先生が『こいつはダメだ』と思ったら、俺を殴り倒してくれないか。……こんなこと頼める相手、あまりいないんだ」
「おうよ、任せとけ」
拍子抜けするほど二つ返事だった。ニカッと笑われ、けれど、ミハイルはだからこそ、安心した。
「はは。かっこつけたいのにさ、サングラスも曇りまくりだ」
苦笑をこぼす。ラーメンの湯気で曇ってしまったサングラスを外し、ハンカチで拭った。
付け直せばクリアになる視界――そこに、よろめく胡乱な人影あり。
それは若杉 英斗(ja4230)だった。
「まさかの……まさかの留年だったよね……」
棄棄の隣に座り、ラーメンを受け取り、うなだれている英斗。
「もう、先生きいてくださいよこの悲しみをっ。依頼に頑張り過ぎてたら、落第しちゃいましたよっ。……いや元々久遠ヶ原学園には残るつもりだったんですよ? ほら、いきなりたくさん卒業しちゃったら、撃退士の人手が足りなくなるんじゃないかと思ってね。それで、久遠ヶ原残留を選択したんですけど、まさかガチで進級できないとは……いや……うん、逆に、コレで箔が付いたと思うことにしよう……」
そう英斗は立て続けに言葉を続けるも、最終的にはションボリと肩を落としてしまった。「ど、どんまい」と棄棄がかける言葉を迷ったレベルである。
「というわけで、飲まずにはいられないッ!」
途端、英斗は顔を上げてはヤケ買いした酒瓶をポーンと開ける。
「このアルコールで留年の悲しみを吹っ飛ばすッ! だって俺は、ディバインナイトなのだから! 貴方とコンビに!!!」
そのままラッパ飲みである。撃退士でなければ死んでいた。学園随一の防御力を誇る彼も、メンタルにもらった一撃は流石に堪えたようである。ほんとドンマイな……。
「大学部四年は、俺が守るっ! ……うぅぅ」
じょばあ。溢れる涙。
「若ちゃん……そんなお前も……俺は好きだぜ!!」
その背をナデナデする棄棄。「ぜんぜえ゛」と男泣きする英斗。もらったティッシュでチーンと鼻をかんだ。その頭を、棄棄がワシャッと撫でる。
「酒飲んで、美味しいラーメン食って、明日からも頑張ろうぜ……」
「ふぁい……」
「若ちゃんはいつも頑張ってる……先生は知ってる……」
「あざます……」
はぁ、と英斗は幾度目かの溜息を吐いた。そしてもう一回、鼻をチーンとかんだ。
「棄棄先生、お疲れ様です。……なんだか楽しそうですね?」
そこへ新たに顔を覗かせたのは不知火あけび(jc1857)だった。男ばかりの酒の席、美人が来たぞと盛り上がる野郎共。とまあ、例によってラーメンを渡され、未成年ゆえ缶ジュースも渡され、彼女も気が付けばベンチに腰かけていた。
「……先生に聞いて欲しいことがあって」
意気込みというか。そう切り出しつつ、あけびは白柄金鞘の刀をヒヒイロカネより取り出した。
「守護刀『小烏丸』。お師匠様が私に託した刀です。当時、彼に記憶を消されていた私には何も分からず、でも自分に託された刀だと理解できた。誰かを救う刃であれと」
忍の私に、人の心を託したんです。そう語るあけびの眼差しは、まっすぐに小烏丸を見つめている。
「最終決戦で、彼は私を庇い重傷に……結局、私は誰も救えなかった。でも、彼は私に救われたと」
『お前を使徒にしていたら、俺は今頃、ただの駒として共に命を落としていただろう。一介の天使である俺を、師匠に……駒ではない特別にしてくれた』
『お前達と共に生きて行く末を見届けたい』
思い返す言葉。きっと一生忘れられない言葉。あけびは大切そうに、守護刀を抱きかかえる。
「この刀、抜いたことがないんです。お守りにしてたから。……これからは、この刀で誰かを救っていく」
「いい心がけじゃねーの。もう、暴力の時代は終わりなんだ。これからはそういう力が、必要なんだよ」
お食べ、とあけびのラーメンどんぶりにチャーシューを分けてあげながら、棄棄は小さく笑った。「ありがとうございます」と、あけびはチャーシューもりもりのラーメンをすすって。
「先生、何かあれば呼んで下さい。サムライガールは必ず力になります!」
「頼もしいや。九月からもよろしくな!」
さて――ラーメンを食べ終えた棄棄が立ち上がる。
どちらへ? と生徒達が問う。歩き出す教師はこう答えた。
「ちょっと約束があってな」
――旧校舎前。
「よ、センセ」
月夜、降り立つ足音。銀の髪を掻き上げて、ギィネシアヌ(ja5565)は棄棄を見やった。
「ようギィネシアヌ」
「ラーメン美味そうだったな」
屋上から彼女は光景を見下ろしていたのだ。「お前も来たら良かったのに」と教師の言葉には「ガラじゃない」と不敵に笑んで見せる。
「それで、センセ」
「ああ」
演習用のスクールガンを手元でくるくる回しつつ――ずるり。ギィネシアヌの背後に、蛇の頭を持つアウルの尾が八本、幻出する。紅闘技:九龍大系<クリムゾンアーツクーロンモード>。
最後の稽古を付けて欲しい。
それがギィネシアヌの願い。
「教えてくれ、センセ」
少女の足元に、血のようなアウルの薄い膜が広がった。
「もし、どうしても殺さなければならないヤツが、大事な人だったらセンセは殺すかい。それとも誰かの手に委ねる? それとも、その人の為に知らない誰かを犠牲にできるかい」
どろり――無数の紅蛇が湧き上がる。紅蛇世界<グリモワールド>。
「俺は、きっと、この手で終わらせてしまう。それが、苦しいんだ」
囁く少女は赤の中に掻き消える。
教師は、こう答えた。
「皆まるっと笑顔になれるような奇跡(ハッピーエンド)を目指して足搔くかな、俺なら」
襲い来る蛇の群れを、首元のスカーフをシールド代わりに往なしつつ。彼はぬっと手を伸ばし――
「……って思えるようになったのも、お前らが『今』っていう奇跡を掴み取ったからだよ」
わし。ギィネシアヌの頭を無骨に撫でる。
「お前なら大丈夫さ。俺の生徒だ」
アウルの蛇が消えていく。世界は再び夜の色。
ギィネシアヌは顔を上げて教師を見て。
「……、」
言葉は無粋か。くしゃりと少女は笑ってみせた。
(愛してるゼ、センセ)
●夜、海
「夜の浜辺とはいえ、八月に海というのに違和感がありますねー……?」
櫟 諏訪(ja1215)は心底不思議そうに首を傾げ、夜の海を眺めていた。
「いつも、二月だもんな……」
傍ら、砂浜にて携帯闇鍋セットを駆使してバーベキュー台を作り、火を起こしているアスハ・A・R(ja8432)が「シーズンオフ、というやつさ……」などとフッと笑む。
※彼らは特殊な訓練を受けた生徒です。
「夏って、言えば……」
彼方、夜の水平線を眺め、Spica=Virgia=Azlight(ja8786)はほんのり眉尻を下げる。こうして皆と遊ぶ機会もこれで最後かと思うと、少し寂しい気持ちになった。
「学園生活最後の夏……良い思い出を作りましょう!」
快活に言ったのは、いつもの黒猫きぐるみ姿なカーディス=キャットフィールド(ja7927)。浜辺で獲ってきた、カラフルなうみうし、ウニ、辛うじて食べられそうな小魚、毒がなさそうな貝をドサドサと置く。
なんか不穏なブツを用意したのには理由があった。
此度開かれるは、闇鍋ならぬ闇バーベキュー、そして花火大会。
「ねぇもうほんと何で最後まで闇鍋黒ミサ……!?」
矢野 胡桃(ja2617)は顔を覆った。
「学生生活最後つっても何も変わんねえなー」
着々と準備をしつつ月居 愁也(ja6837)が慣れた顔で言う。「なあ」と彼が呼び掛けた先には、折り畳み椅子に置かれたホタテの殻。来られなかったアイツの身代わり。そのまま手にしていた懐中電灯をスッと別方向へ向ければ、夜来野 遥久(ja6843)の顔が下から照らし出された。
「んんん今日もオトコマエな!」
そんな愁也の眉間に、遥久は笑顔でカニ爪をサクッと刺しつつ。
「生ものはある程度、焼いて食べて下さいね」
など、絶叫をBGMに皆へ注意をしていたのだった。そのまま流れるように加倉 一臣(ja5823)を見やり。
「ああ加倉、ここがお前のスペースだ。今なら良く焼けるぞ、さあ」
と。バーベキュー用鉄板の一部を、体育座りできる程度に空けて示す。乗れ。
「……いやいやいや焼き土下座的なセッティングおかしくない? たたき? たたきが食べたいの?」
全力でノーセンキューしつつ、土下座スペースをホタテでそっと埋めていく。
「あいつも食いたかっただろうなぁ……土産に持って帰るか。殻を」
しみじみ。それは華桜りりか(jb6883)も似たような思い。闇バーベキュー用のタコヤキを見、彼女は友人の一人の面影を思い返しては、ちょっと残念な気持ちになるのだ。
(でも、これは詰め込まれる心配がないということなの……)
というわけで。
「焼けば食える。上がれば花火。学生生活最後の宴が今始まる……!!」
開幕宣言はいつものようにアスハの役目。何人か声かけ忘れた気がするが、気のせいに違いない。
「学園最後の宴ってあれですよね? 宴(惨劇)ってやつですよね!?」
カーディスは集まった猛者を見渡した。誰も彼も覚悟を決めた漢の目をしていた。
「さて、焼くか」
アスハもまた漢の一人。平然とした顔で手持ち花火セットを皆に配ってゆく。
「バーナーは? ないのです? あれ? は・な・び……?」
「……アスハさんおかしい。それはおかしい。花火はいけない」
首をひねり冷や汗を流すカーディス。真顔でつっこむ胡桃。あっこれあかんやつや。
「バーナー持ってきたけど花火でいい? そう?」
愁也は何ら疑いを持たない顔で頷いては、花火に火をつけた。他の面々も、次々花火に火をつけてゆく。
「普通に花火で着火すればいいじゃない……? 木材くらいそこら辺にありそうじゃない……?」
若者の深刻なツッコミ離れに、もう何が正しいのか分からなくなる胡桃であった。でも花火に火をつける。
しゅー。
ぱちぱちぱち。
光の色どり。花火の音。
「ところで聞いていい? 俺に線香花火を渡したの誰?」
趣深い線香花火、炙れない肉。一臣が悲しげに微笑む。ちょっと動くとポタッと落ちる。虚無。
「じゃあ代わりにこのアメフラシ炙っておくかーはい加倉さんどうぞ! 美味しいよ!」
そんな一臣に、愁也が花火で炙られたアメフラシを差し出した。ぶっちゃけ半焼けでめっちゃグロイ。
「ナマコは食べてもアメフラシは食べません!」
その一方では、胡桃とりりかはマシュマロを焼いていた。
「ばーべきゅーはご飯になるものだけではないの」
ドヤ顔のりりかは、シイナモンがけのリンゴ、バナナ、クッキー、トッピングに生クリームも用意する女子力の高さだ。
「甘い物は必須なの……です」
神妙に頷くりりか。「おいしい……!」と目を輝かせる胡桃。
「はい胡桃ちゃん」
そんな彼女に、愁也がイチゴを差し出した。ロケット花火が突き刺さっていた。曰く、パフェの飾り的なアレだという。
「しってるか、ろけっと花火は手に持つもの」
遠い目をした胡桃はそれを受け取ると――菩薩の顔でロケット花火を引き抜き、そのまま発射寸前にぶん投げた。一臣へ。
「あぶなっ」
ホタテの殻(お土産用)を回避射撃として容赦なくぶん投げて、ことなきをゲットする一臣。飛び行くロケット花火はそのまま……諏訪が闇バーベキュー用に用意していたカッチカチのカツオブシに命中した。
「ああっ! 一臣さんがー!」
ゴロ……と無残に転がったカツオブシを抱き上げる諏訪。
「そんな! 一臣さんが息をしていない!」
「なんだと……医者は、医者はいないのか!?」
アスハも駆け寄ってくる。すると「医者(アスヴァン)です」と遥久が参上。カツオブシにそっと手を当てるが、
「残念ながら……」
首を横に振る。
「一臣さーーーーーん!!!」
泣き崩れる一同。
「ことなきを 得たと思えば 亡き者に」
一臣、心の一句。
さて、そんな一方で。スピカが炙っているのは国産黒毛和牛の赤身ブロックをワイルドにドーン。ちゃんと野菜もある(女子力)。
「バーベキューって、言えば……やっぱり、これ……」
焼けば食えるの精神でじっくり火を通してゆく。焼くってより炙ってるけど気にしない。腹を壊さなければ問題ない。
「数量限定、なので……お早めに、どうぞ」
「いいですねー、こっちの魚介類とちょっと交換しませんかー?」
そう言う諏訪は、フッツーに薪や炭で海鮮魚介類を焼いていた。どういうことだってばよ。
カーディスもその隣で、風遁・韋駄天斬りで魚やら貝やらを捌き、弱火の火遁・火蛇で焼いている。
「火遁って付くから多分焼けてますよ〜多分」
そんな一同に混ざって、緋打石(jb5225)は闇鍋を焼いていた。闇鍋そのものを焼いていた。
「闇鍋の具材なんて甘っちょろいことなんてするか、鍋そのものを焼くんだ……」
もちろんひっくり返してちゃんと火も通すぞ。自分でも何やってんだかよく分かんなくなってきたけど、裏返して山状になった鍋は、アレだ、ジンギスカン焼くやつみたいな、ああいう感じでスピカの持ってきた肉を焼くには具合がよかった。あと当たり前だけど誰も進んで闇鍋そのものをバリバリ食べようとはしなかったので、結局闇鍋はジンギスカン焼き器的なことになった。ジンギスカンわーい!(※牛肉)
「うん、酒でも飲むぞ!」
飲まずにはいられないッ! 酒を片手に、主に来られなかった面子についての追悼の言葉。犠牲者の捏造。ありもしない過酷な戦いのでっち上げは基本。タコヤキとホタテがそっと花火に照らされていた。
……。
……。
「なんか……」
ふと、アスハが呟いた。
「比較的平和だな」
闇バーベキューなのに食材が割と良心的。というか普通に調理してる面子もいるし。殴り合いも始まらないし。裏切りも起きないし。普通にご飯美味しいし。神の兵士で蘇生した者もいないし今んとこ。
「「「確かに!」」」
これには一同も総同意。
でもよく考えたらこれが普通のバーベキューの姿なんだよなぁ。そう思うと、これまでの学生生活のハチャメチャさを改めて思い知るのだ。
そして今宵が、そんな学生生活最後の夜――とはいえ、遥久に感傷はなかった。いつも通りの面々、他愛もないやり取り。安堵を感じるが、されど幾ばくかの寂寥のようなモノもあり。
いつもの面子でいつもの時間。それで終えられるのはまた一つ良い思い出。
「あ、そうそう」
普通においしく焼けたホタテを頬張りつつ、一臣が言う。
「ちゃんと遊ぶ用の花火も持ってきたよ」
取り出したのはありふれた花火セットだ。この派手なヤツやりたい、と筒状のものに火をつけようとしていると……傍らのアスハが高級マツタケを二本、取り出すではないか。
「一番綺麗に打ちあがったやつに焼きマツタケを進呈しよう!」
その言葉に、りりかが「マツタケ……」と反応しつつも首を傾げる。
「打ちあがる……とは? 人って打ちあがるの、です?」
「打ち上げ花火、下から見るか、お前がなるか――という話だな」
緋打石は得意気だ。打ち上げる側になる気も満々だ。
「マツタケ! 頑張って花火になりますの!」
カーディスは打ち上げられる側になる気満々だ。すげえ。七割が打ち上げたい立候補してるこのクレイジーな世界において凄く貴重な存在。なお諏訪はいつも通りヤる側になるためなら手段と道徳を選ばない男。
「ところで一臣さん、スターマインって花火、綺麗ですよねー? 誰も打ち上げるのが一回とは言ってなかったですねそういえばー……華麗な雄姿、期待してますねー?」
「待って、何でこっち見るの?」
不穏な気配を察知してクリアマインドを発動。このスキルは精神を練磨することで一時的に気配を断つことができるが片手に着火した花火を持っていてはまるで意味がないぞ!
「しってた!!!」
絶望ポーズの一臣。
そこへダンッと踏み込んだのは光纏したスピカだ。Code:HeavyArms展開、少女のアウルが無数の刃となり。
「……顕現せよ、“破壊者”ミョルニル……ッ!」
具現化<マテリアライズ>ミョルニル。
スピカの光纏である光の武器が、多くの人の想いが込められた銀の疑似聖槍――だとオミーがしぬので、ホタテの殻に憑依する。なんとホタテの殻がアウルの雷を纏う巨大な鎚、「破壊者」ミョルニルになるではないか! ホタテすげえ!
「ライトニングホタテ……」
緋打石がボソッと呟いた。
とまあ、ものすごいホタテによるものすごい一撃が一臣を吹っ飛ばしたのは確かだ。まさか一臣もホタテでこんなに吹っ飛ばされることが人生であるなんて思いもしなかったに違いない。打ち上げられた彼は夜空にて、光纏with噴出し花火によって瞬き煌き、思い出に一輪を添えたのであった……。
「ホタテでも、なんとか、なるものですね……」
「食べてよし、打ち上げてよし、ホタテはすごいの、です」
スピカの隣、人柱花火を見上げているりりかは普通に手持ち花火を楽しんでいた。「あ、回復はお任せ下さい、です」とコックリ頷く。この世界において回復は善意だけど善意じゃない場合もあるんだ。それは彼らがこの学生生活で学んだこと。
「すげー」
愁也はタコヤキをもぐもぐしながら打ち上げ花火(?)を眺めていた。
と。その背後に――B級映画の殺人鬼さながら、遥久が得物を振りかぶっていた。
ッパーン。
振りぬかれたのはハリセンの一撃、インパクト。普段よりも力を込めて、相手に一撃を叩き込みます。シンプルな技だ。
「えッ――」
上空へ吹っ飛ばされる愁也。得も言われぬ浮遊感と共に振り返れば、遥久が地上から微笑んでいて。
「打ち上がりたそうにしてたから」
サムズアップ。
「言ってたっけ!?」
こうなりゃヤケだ。愁也はアロハシャツの下に仕掛けていた筒花火(なんで仕掛けてたんだろう。夏のせいかな?)をヒャッハーと点火した、が。
「ん?」
気が付けば自分の周囲に彗星がある。彗星? ハテ? 犯人はすぐに分かった。遥久のコメットだ……。
「愁也、言ってたよな。いつか彗星と夜を飛んでみたいって」
「言ってたっけ!!? あっちょっ待っダメっアーーーーー!!!!」
そして輝く阿修羅様(ウルトラソウル)。
「……美しい散り様ですね。さて次の希望者は」
<○><○>
「……」
自力で打ち上ろうとしていたカーディスはそっと遥久から目をそらした。黒猫の体にはすでに花火がたくさん巻き付けられ、両手にも花火をたくさん持っている。
「じ……迅雷で自力でできますのでっ……!」
冷や汗を滴らせながら苦し紛れに呟いたが、ここで緋打石と諏訪に両サイドから抑え込まれる。
「ヤメロー! シニタクナーイ!」
もがくカーディスに遥久が迫る。
「貴方……言ってましたよね」
「言ってないですの!!!」
言われる前に食い気味に否定。
でもまあ結局ハリセンで吹っ飛ばされました。緋打石と諏訪ごと。なぜって? 夏のせいさ。
「……じゃあ自分、皆さんを盾にするのでよろしくですよー?」
「「外道!」」
「どうせやられるならできるだけ他者に苦痛を押し付けたいじゃないですかー?」
「「外道!!」」
そんなこんなのワチャワチャが夜空でありましたが、ここでカーディスの花火が爆ぜて仲良く3タテされました。めでたしめでたし。
「最後まで通常運転ゴチソウサマデシタ!!」
胡桃はとりあえず合掌しといた。
「なーんか賑やかだと思ったら」
楽しそうじゃん、とそこに現れたのは棄棄だった。「せんせ!」と胡桃が彼に突撃する。
「モモそつぎょーです、よ」
「おう、おめでとさん! 卒業後はどうすんだい?」
「学園を出て、ちょっと岐阜まで」
「いいねえ。俺もどっか旅するかな〜」
「先生も旅に出るです? なら、二月の海には集合しませんか?」
軽い同窓会みたいなものです! と胡桃が笑う。
その言葉に……りりかは今日が最後の日なんだと改めて思い知る。
(この見慣れた皆と……これからは、頻繁に集まることもないの、でしょうか)
そうすると込み上げてくるのは寂しさだ。
最後までワイワイガヤガヤ騒いで過ごす、いつもの面子、いつもの時間。
きっとこれが最後の瞬間――。
でも、祭りの最後に「さよなら」は禁句。スピカがニコリと微笑む。
「またいつか、どこかで集まりましょう」
「じゃあ、次は二月だな」
アスハも肯定の頷きを示す。
「そだね、次は二月に!」
「二月にまた海で会いましょう。それまでどうぞ御元気で」
愁也と遥久も笑顔で口を揃えた。寂しいとは無縁の、最後の夜。
「次の二月辺り海行けそうな気がする……」
カーディスと諏訪に支え支えられ、ヨロヨロ戻ってきた緋打石もそう言った。
棄棄はそんな一同を見渡して。
「おう! 二月と言えば海だからな。来年もよろしく! 約束だ!」
「あっ。卒業してても参加してOKですか!?」
一臣が問う。「もちろんだ!」と教師が笑う。
二月かぁ。
きっと想像できないぐらい寒くって、想像できないぐらい楽しいんだろう。
なんて。思いながら。
生徒達は……海の彼方を眺める。
静かに寄せては返す波。
久遠ヶ原学園の生徒として居られる、最後の瞬間。
進む先はバラバラだけど。
心はいつも、絆でしっかと繋がっている。
過ごした思い出がその証。
幾つも幾つも思い返せる、たくさんの思い出……。
未来は変わっていく。
でも、いつもの面子のいつもの空気はきっといつまでも変わらない。
「最後に写真撮ろうよ」
一臣が提案する。反対意見はもちろんなかった。
寂しくないと言えば嘘になる。
だけど大丈夫。また会える。これは永遠の別れじゃない。
海を背に並ぶ。砂浜に幾つもの足跡。
はい、ちーず。フラッシュがパチリ。
さらば、我らの青春よ。
我らの行く先に幸あれ!
●夜、それぞれの場所
(卒業、か……)
夜の町、街灯の下、イリス・リヴィエール(jb8857)は一人歩いていた。彼女は戦闘任務帰り、被害や負傷者を出すことなく無事に任務を終えて、「お疲れ様」の言葉の後に解散して間もなく。
静かだ。コオロギの声。さっきの仲間達との賑やかさが、天魔と激しく戦った緊張感が、嘘のよう。
そしてその静寂は――イリスが「考えないように」していたことを、次から次へと誘い出すのだ。
任務前の出来事である。
復讐相手から手紙が届いた。
この学園を去り、個人の誓いを果たしに行く。果たし終えたらイリスとの約束を果たしに会いに行く、と――そこには綴られていた。
「Ailes」
愛竜の名前を口にすれば、ポンとヒリュウのエールが彼女の肩に現れる。「キィ」と鳴いて甘えてくるその子の喉を指先であやしつつ、おもむろにイリスは呟いた。
「逃げられた、訳ではないようだけど」
そこまで言って、己の言葉は復讐相手の言い分を素直に信じるものじゃないか、と苦笑する。
「……再会するまでに、もっと強くならなくてはいけない。お前も覚悟をして」
きゅ! と力強く鳴くエール。イリスは深呼吸を一つして、夜の空を見上げた。
彼との約束。
彼が誓いを果たすまで、イリスは彼を殺さない。
誓いが果たされた時はすなわち、イリスの復讐を彼が受け入れるということ。
イリスの復讐劇はまだ終わらない。
この夜の空が果てしないように。
しかし明けぬ夜もまた、ない。
「いつか。……いつか、明けるのかしら、ね」
答える者はいない。
答えを求めてもいなかった。
満ちる時を待つ十日夜の月が、静かにイリスを見つめ返している。
その黄金の輝きは、まるで“彼”の瞳のようで――……。
「きれいなお月様なのだ」
メリッサ・アンゲルス(ja1412)は月を見上げ、それから視線を前に戻した。
とある田舎の自然の中、広い広い一軒家。メリッサが立っているのはその広い庭。手入れが施されているのは――彼女が日中から庭の手入れをしたからだ。
ここはXという悪魔――メリッサの“父”と出会い、過ごした場所。
メリッサにとっての、思い出の場所。
今は誰もいない家だけれど、今日はメリッサが家の掃除や庭の手入れを行った。
「夏休み宿題は、おとーさんの言いつけ通り早々に終わらせたのだぞ!」
得意気な彼女が語る先には、赤いサルビアの花に囲まれたザクロの木。それを父の墓に見立て、娘は笑顔で言葉を続ける。
「明日から我は中等部なのだぞ! まぁハーフに覚醒してから外見はさっぱり変わっとらぬが……だがこの通り制服は変わるのだ! カッコイイであろう!」
くるんと回ってみせるメリッサのいでたちは、おろしたての久遠ヶ原学園中等部女子制服だ。
「まぁ外見が変わらぬのも考え様、おとーさんに貰った服をずっと着られるということだ!」
言葉の直後に風が吹く。『子孫の守護』の樹木言葉を持つザクロが、『家族愛』の花言葉を持つサルビアが、返事のように揺らいだ。それがまるで、父の相槌のような気がして。少女は堂々と、胸を張って言い放つ。
「明日からもたくさん勉強して、いつか天界と魔界の両方に行ってみたいのだ。我は三界の子であるからな! 全てを見て、全てを守るのだ、この先も!」
小さな体に、大きな夢。
優しい葉擦れの音が、メリッサの言葉を肯定していた。
「さて……我はそろそろ寝るのだ。おやすみなさい、おとーさん!」
踵を返す先には“我が家”。メリッサは一歩ずつ、歩いていく――。
●夜、久遠ヶ原学園03
「……あら、先客。こんばんは先生。好い夜ね」
十日夜の月の下。屋上にて。シュルヴィア・エルヴァスティ(jb1002)の視線の先には、見覚えのある背中。
「ようシュルヴィア。卒業おめでとさん」
柵にもたれていた棄棄が振り返る。「月見かしら?」「そんなもんさ」と言葉を交わしつつ、シュルヴィアは彼の隣へ歩を進めた。
「お前も月見か?」
「私? 私は……まぁ、月見かしら。せっかくだし、と思って」
教師のように柵にもたれる。寸の間の静寂。口を開いたのはシュルヴィアで。
「思い出深い場所だしね。先生、覚えてる? ここ、初めて会った場所よ」
クリスティーナのおつかいを見守ったり。お菓子パーティしたり、ビニールプールで遊んだり……。
「覚えてるぜ、全部な」
棄棄は目を細める。
と、その時だ。「そうだ先生」と彼女が口にし、一通の手紙を差し出して。
「はい。……実家の住所。じき帰るから」
「フィンランドだったか」
手紙を受け取り、月に透かし。「ええ」とシュルヴィアは頷く。
「休みが取れたら、顔出しなさいな。案内してあげる。何なら欧州一回りだって付き合ってあげるわ。旅行に、現地ガイドは重要よ?」
そう言って……さて。
シュルヴィアは柵から身を離す。
「ありがと、先生。先生に会えて、本当によかった。……貴方自身と、皆の棄棄先生。どちらも。私は、大好きよ」
「へへ、照れるねそいつぁ。俺も大好きだぜ、シュルヴィアのこと。生徒としても、一人の人間としても」
「そ」
ふわり、笑んで見せる。
「またきっと、会いましょう。……おやすみ、先生」
そう言って、スカートを優雅にひるがえし、踵を返す。
「三月だ」
その背に、棄棄の声。
「三月んなったら、会いに行く」
「なんでまた三月?」
「ナイショ」
「食えない人ね。どこまでが計算で、どこまでが素なのかしら?」
「ちょいとミステリアスな方がカッコイイだろ?」
「……まぁ、いいわ。お疲れ様、先生」
「ほいほい、お前さんもお疲れさん」
……二〇一八年、本当に会いに来る。
●九月一日
九月の寸前。
真緋呂は屋上にて、フルートを手に景色を眺めていた。
それから、おもおむろに。奏で始める旋律の名は――夢<トロイメライ>。
――夢は見ず、叶えて現実にする主義だけど。
最後の夜くらい夢を奏でよう。
まどろみの夜が明ければ、朝日と共に現実が始まる。
夢はいつか醒める。夢は永遠のものじゃない。
それでも人は夢を見るのだろう。
人が、明日という未来を、物語を、歩み続ける限り。
夢の終わりはサヨナラじゃない。
これで終わりなんかじゃない。
夢は、未来は、続いてゆく。
これからも――ずっと。
『了 ……あるいは、いつまでも続く』
(色々なことがあったなぁ)
八月三一日。それは蓮城 真緋呂(jb6120)にとって、久遠ヶ原学園で過ごす最後の日。
(学園に編入したのが、四年前の六月……)
見慣れてしまった景色とも、今日でお別れ……名残惜しさを噛み締めて、真緋呂は夜の学園の散策を始める。
「初めての教室がここ。……何だか必死だったわよね」
最初に訪れたのは高等部校舎の一年生教室。最初に座った座席――机をそっと指先で撫でた。
敵を討つ為に強くならなくては。そんな想いが強くあって、我武者羅に依頼を受け続けたっけ。
「手が届かなかったことも……あった」
羽根を残してくれた黄金の天使に、何もできなかったと涙したことを思い出す。
あれから強くなれただろうか。など、自問してみる。最初の席に、座ってみる。目を閉じれば鮮明に思い返せる、激闘の日々――。
「……ある意味、強者相手に戦い続けた凄い場所よね」
所変わって学食。ここもまた、真緋呂にとっては激闘の場所。顔を覗かせてみれば、厨房で職員達が明日の分の仕込みを行っている。
は、と彼等と目が合った。食欲魔人として名高い真緋呂の出現に「まだ準備中ですよ〜」と先制されるが、彼女は「食べに来たんじゃないんです」と苦笑を浮かべた。
「ご馳走様でした」
手を合わせ、深々とお辞儀。心が折れた時もお腹は空いた。そんな時、いつだって優しく迎えてくれたのがここだった……。
「久遠ヶ原から人が旅立つのは何度も見送ってきたが――今度は俺が旅立つ番、ってな」
今日で小田切ルビィ(ja0841)の学園生活が終わる。
(十年以上厄介になった学園からやっと解放……もとい、新たな一歩、か)
明日からの肩書は『卒業生』。彼は明日、ここから旅立つ。荷造りなどは既に終え、今はちょっとした『野暮用』、だ。手には花束、学園内を歩いて、足を止めたのはとある場所。
「よう」
見上げた先には、供養塔。敵味方問わず、今までの戦いで命を落とした者達の冥福を祈る場所。ルビィはそこに花を供え、線香に火をつける。
「人の血も、魔の血も抱えて――俺は生きるぜ、ゐのり……」
目を閉じれば思い出す、孤独な少女。ルビィと同じ半魔という、血の宿命を持っていた者。京臣ゐのりは、ルビィのありえた可能性……。
(できることなら、あんたを救ってやりたかった……)
立ち上る細い煙の中、手を合わせ。目を閉じて。少女と同じ名前の行為――『いのり』を捧げる。
「棄棄先生、お疲れさま」
職員室の戸が開いて、Robin redbreast(jb2203)が顔を覗かせた。
「パウンドケーキを作ってみたよ。食べてくれたら嬉しいな」
そう言って、棄棄のデスクまで来ると、差し出したのは可愛らしくラッピングされたパウンドケーキだ。書類に向かっていた教師だったが、差し入れに「ありがとさん!」と笑みを向ける。
「ロビンちゃん、宿題は終わったのかい?」
「うん、ばっちり」
ロビンはそう頷くと、次いで差し入れに視線をやった。味の感想が聞きたいな、という意思表示である。
――ロビンは去年から料理教室に通っている。
二年前に受けた、殺人的料理を作成する依頼からの成長は著しい。最近は乙女らしく、休みの日などにお菓子作りにもチャレンジしており、「寮のキッチンは狭いので」と学園の家庭科室を借りては勤しんでいるのである。
ただ、練習で大量に作りすぎてしまうので、こうして夏休みでも学園に来ている教師陣におすそ分けしているのだ。
「はい、めしあがれ」
お皿に盛って、紅茶も淹れて。食器も料理の一つと語らんばかりの行動は、『例の依頼』を受けた少女のものとは思えない。
「いただきます」
手を合わせ、パウンドケーキを頬張る棄棄。ロビンはそんな教師の様子をじーっと見ている。
「美味しい?」
「もちろん!」
「よかった」
にこ。その笑みは、かつてのような『人形的』ではない。少女が笑みたいと思って笑んだ笑顔。そんな表情のまま、ロビンは歌うように声を弾ませる。
「明日から大学生になるんだよ。大学の制服つくってみたんだ」
「作ったって、自作したのか!? そりゃ凄いな」
「明日、着てくるね」
「楽しみにしとくよ。進学、おめでとさん」
「ありがとう」
と、そこへ。
再び職員室の戸が開いて、今度はルビィが現れる。
「こんばんは、棄棄センセー」
「おうルビィくん、お前もパウンドケーキか?」
「へ?」
「ははは。で、どした?」
紅茶片手に教師が問う。実は、とルビィは表情を改めて――告げるのは、明日ここを発つこと。「そうか」と、教師は穏やかに微笑み、それを肯定してくれた。
「そういえば」
ルビィが問う。
「センセーは学園辞めた後はどうすんだ? 俺は世界をこの目で見る為に旅に出るぜ」
「いいねえ、俺もそんな感じの予定さ。じゃ、世界のどっかで会うかもな!」
「それじゃあ、どっかて会ったらよろしくな、センセー」
「こちらこそ」
また会おうぜ。それは男の約束ってやつだ。
●夜、久遠ヶ原島
「早かったような短かったような、学園生活でしたね……」
腰を下ろしたソファー。ファティナ・V・アイゼンブルク(ja0454)はそう呟き、隣の神月 熾弦(ja0358)にそっと身を預けていた。
「そうですね。でも、色んなことがありましたね……」
恋人の体温を感じつつ、熾弦が答える。二人の手は繋がれ、白い指が絡んでいる。
かち、こち、時計の針の音。
ここはファティナが経営する喫茶店「silver faery」の二階、その私室。
二人は沈黙に耳を傾け、長かったような短かったような、学園での日々を思い返していた。
「シヅルさん、話しておかないといけないことがあります」
「私からもですよ、ファティナさん」
おもむろな言葉。
ひとつずつ語る。
ファティナはこの喫茶店を閉め、一度故郷に戻る。
熾弦も同じく学園を離れ、将来のために家に戻る。
つまり、長いお別れになるのだ。
「……料理の勉強をし直したら、またここに必ず戻ってきます」
ファティナが告げる。熾弦はゆったり微笑み、恋人の手を優しく握り直した。
「迷いなく進む道ではありますが、先に待つ困難は男女の恋人とは大きく違います……家族の理解も。それを乗り越えるための期間だと、私は理解しています」
「そうですよね……。家族のこと、特に父とは疎遠でしたが流石に話をしないとですし。お姉様はともかく、お兄様はシスコンで説得が大変そうですし」
苦笑してみせる。顔を上げれば、ファティナを見守る熾弦と視線が合った。赤い瞳と、青い瞳――。
「ふふ」と、笑んだのは熾弦。
「待っていてください、と言うのも変ですね。楽しみにしていてください、と言いましょうか、お互いにそれぞれの道を乗り越えてまた寄り添える日を」
その言葉に、ファティナは笑みと共に頷きを返した。
「遠く離れても、私の一番はずっとシヅルさん。また寄り添える日を心待ちにしております」
性別という世間的な壁はあるけれど。
愛は勝つ、なんて乙女思考が過ぎるかもしれないけれど。
それでも、二人は愛し合っていた。二人の愛は本物で。
長いお別れになる。寂しくないと言えば嘘になる。
でも、二人は互いを信じている。
いつかきっと、また会える――。
「――……」
余分な言葉はもう蛇足だろうか。二人は寄り添い続けている。しばしの別れを惜しむように。一秒でも、恋人の体温を覚えていたいと言わんばかりに。
「あ」
最中のことだ。熾弦が呟く。「どうしました?」とファティナが問えば、彼女はクスリと微笑んで。
「ひとまずのお別れの前に、恋人らしいことをしておきます?」
「恋人らしいこと、と言いますと?」
その言葉の返答は。重ねられた唇。柔らかい感触。
「――想いを確かめ合うのには、行動も良いものかと」
体温の間隙に、囁きの台詞。
肩に回される手を感じつつ、頬に額に口付けを浴びるファティナはボッと顔が赤くなる。
「や、優しくお願いします……?」
呟いた言葉。電気が消されるその前に、ファティナが最後に見たのは愛おしそうな青い瞳。
綺麗だな――そう思った。
その目が自分にだけ注がれていることに、優越感のような幸福感。
さらり、こぼれ流れる二人分の銀の髪。それは銀河のように混ざり合い――暗くなった部屋の中、カーテンから差し込む月の光に、きらりきらりと輝いていた。
「ふう」
最後の段ボールをガムテープで閉じ、星杜 焔(ja5378)は息を吐いた。そのまま時計を見やる。もうこんな時間。彼はたった今、明日の引っ越し準備を終えたところであった。
久遠ヶ原島に残る友人には、酒や手製菓子を贈った。
棄棄には家族で作ったあんぱんを贈った。
これで久遠ヶ原学園は卒業――……。
(色んなことがあったなぁ)
窓から夜を見る。幾度も見てきた景色だけれど、なぜか今は特別に見えた。
焔は久遠ヶ原島から離れる。
けれどそれは一年だけ。
というのも、彼の養子である望が来年から幼稚園に通うからだ。アウル適正のある彼が通うのは久遠ヶ原幼稚園が良いだろう。
ゆえに、このマンションの部屋は、島での住居としてこのまま残す予定だ。
とはいえ。住み慣れた場所から離れるのには、やはり寂寥感が否めない。
(これからも、色んなことがあるんだろうなぁ)
人生の節目。これからうんと忙しくなる。
児童養護施設と小料理屋を営むという目標に向けて、専門的な勉強や資格の取得、それから資金集め。幸い、卒業制作発表会で某企業から出資の提案も貰えたが、ノンビリしている暇はないだろう。
そんなことに思いを馳せて。改めて、焔はこの部屋の静けさを思い知る。愛妻は先に、引越し先である彼女の実家に赴き焔達の受け入れ体制を整えている。望と愛犬もふらは、寝室でスヤスヤ眠っている。
(望。おばあちゃん達、君と暮らせるのがとても楽しみだって)
心の中で息子に語りかける。お別れ記念の晩餐を食べた望は夢の中。最後に掃除し尽くしたキッチンがキラリと光る。明日は長旅、たっぷり休もうね。
――激動の未来が待っている。
けれど、それは希望の光に満ちている。
「寝る準備……完了……抱き枕……OK……ヨーソロー……」
ぱちん。消灯。ベアトリーチェ・ヴォルピ(jb9382)はベッドの上。
ふわふわの抱き枕を抱きしめて目を閉じる。温かで柔らかい真っ暗闇。そうすると、忍び寄るまどろみにて、ぐるぐる思考が巡り始める。
――学園を去る者がいる中で、ベアトリーチェは残ることを決めた。
叶えたい夢が、できたから。
「お嫁さんになる」という夢の他に、もう一つ。
アテナ。ベアトリーチェの親友。彼女の、天王の、右腕になること。
その為には経験が必要だ。強くならねばならない。賢くならねばならない。色んなことを知らねばならない。
そして、皆に認められて……胸を張って、アテナの右横に立ちたい。
(それが……私の、ジャスティス……)
抱き枕をギュッと抱き直す。道のりはきっと険しい。それでも進むと、決めたのだ。頑張ろう。そう思って――ふと、脳裏に過ぎるのは外奪の顔。そうだ、次の休み、彼のお墓にも報告をしに行こう。
(お土産……どうしよ……やっぱり、アップルパイ……?)
ああ、アップルパイといえば、サマエル。地球への干渉を永久放棄した大悪魔。彼は今、何をしているんだろうか。
(ベリアルお姉さんに頼んだら……持って行って、くれるかな……今度、聞いてみよう……)
そこまで考えて、ふわ、とあくびが出た。目を閉じている間に這い寄ってきた眠気は、もう抗えない距離にいる。思考が夢と混ざってきた。家庭科室でアップルパイを焼いている外奪が「エプロンと割烹着ってどっちがトレンドなんですか?」とか言っている脳内幻覚が見える。そういうわけで夢の世界に飛び立とう。
……おやすみなさい。
また、ね。
●夜、久遠ヶ原学園02
「こんばんは棄棄先生」
学園中庭。鴉乃宮 歌音(ja0427)は通りかかった棄棄にそう声をかけた。
「よう歌音くん。……何やってんだ?」
足を止めて教師が聞いたのも無理もない。何やら湯気の立ち上るでっかい車の前に、エプロン姿の歌音がいるのだから。
「ああ、依頼が終わったので報告書を作りに来たところでして。ついでに炊事車の整備点検と依頼の打ち上げがてら食事を作ってたところです。ラーメンですがいります?」
「なんかすげーな」
毎度ながら歌音の器用さに圧倒されつつ、どんぶりによそわれたラーメンは受け取るのだ。手近なベンチに腰を下ろす。「袋麺ですがネギ油とニンニク生姜炒めを加えればお店らしくなるんです」と歌音の言葉通りに、香り立つそれはなんとも食欲を刺激する。
「米も炊けばよかったかな?」
「はは、食堂を開けそうだ」
生徒の言葉に教師が笑えば、「そうそう」と歌音がトッピング用のネギを追加で切りつつ言葉を続ける。
「食堂は開きませんが、私も学園で教官をやることになりまして」
「おー、おめでとさん。何の教官?」
「主に実地戦闘訓練の手伝いと野外炊事ですかね。インフィルトレイターの経験は警察や自衛隊、傭兵に大きく勉強になるかと思います。市街地戦ゲリラ戦で物心両面を泣かせ、炊事で食事の美味しさに泣かせるみたいな」
「いいじゃん」
熱いラーメンをすすりつつ、教師は笑った。
「先生、口に合いますか?」
「ほんとおいしいわ、学食は惜しい人材を無くした」
「あはは。引退後は食堂でも開きますかね。……先生は学園に残られるんですよね?」
「おー、そーだな」
「では、今後ともよろしくお願いします」
と、その時だ。
「よ、大将。やってる?」
そんな冗句と共に現れたのは、ミハイル・エッカート(jb0544)だった。
「棄棄先生と話したいことがあってさ」
ラーメンを受け取り、ビール(発泡酒ではないのだ!)の缶を開けて、まずは乾杯。「話したいことって?」と渡されたビールをあおりつつ棄棄が問う。するとミハイルはこう言った。
「先生は三界同盟が永遠に続くと思うか? 俺は思えない」
「ほう?」
「人間界が綻びを見せたら、付けこむ奴はいくらでも出る。外奪のような奴もいる。覚醒者と非覚醒者の溝は今も深く、そこが弱点だ」
もう『恒久の聖女』のような事件は起きて欲しくない。そう溜息を吐く彼の言葉に、教師は夜空を見上げ。
「人間同士でも分かり合うのが難しいのに……ってのは、【双蝕】事件で嫌なほど突き付けられたな」
「ああ」
ラーメンをすする。飲み込んで、ミハイルは言葉を続ける。
「先生は覚醒したのは何歳だった?」
「物心ついた時には、だな」
「俺は二七歳、遅めだ。……だから非覚醒者が覚醒者を恐れる気持ちはわかる。分かるからこそ、溝を埋めたい。
俺はこれからも力を付ける。『正しいことをしたければ偉くなれ』……とある老刑事の言葉だ。人間界を守るため俺は高みに上る。綺麗事では済まない世界だ」
そこまで言って、ミハイルは棄棄へと視線を据えた。
「もし俺がトチ狂ったら、先生が『こいつはダメだ』と思ったら、俺を殴り倒してくれないか。……こんなこと頼める相手、あまりいないんだ」
「おうよ、任せとけ」
拍子抜けするほど二つ返事だった。ニカッと笑われ、けれど、ミハイルはだからこそ、安心した。
「はは。かっこつけたいのにさ、サングラスも曇りまくりだ」
苦笑をこぼす。ラーメンの湯気で曇ってしまったサングラスを外し、ハンカチで拭った。
付け直せばクリアになる視界――そこに、よろめく胡乱な人影あり。
それは若杉 英斗(ja4230)だった。
「まさかの……まさかの留年だったよね……」
棄棄の隣に座り、ラーメンを受け取り、うなだれている英斗。
「もう、先生きいてくださいよこの悲しみをっ。依頼に頑張り過ぎてたら、落第しちゃいましたよっ。……いや元々久遠ヶ原学園には残るつもりだったんですよ? ほら、いきなりたくさん卒業しちゃったら、撃退士の人手が足りなくなるんじゃないかと思ってね。それで、久遠ヶ原残留を選択したんですけど、まさかガチで進級できないとは……いや……うん、逆に、コレで箔が付いたと思うことにしよう……」
そう英斗は立て続けに言葉を続けるも、最終的にはションボリと肩を落としてしまった。「ど、どんまい」と棄棄がかける言葉を迷ったレベルである。
「というわけで、飲まずにはいられないッ!」
途端、英斗は顔を上げてはヤケ買いした酒瓶をポーンと開ける。
「このアルコールで留年の悲しみを吹っ飛ばすッ! だって俺は、ディバインナイトなのだから! 貴方とコンビに!!!」
そのままラッパ飲みである。撃退士でなければ死んでいた。学園随一の防御力を誇る彼も、メンタルにもらった一撃は流石に堪えたようである。ほんとドンマイな……。
「大学部四年は、俺が守るっ! ……うぅぅ」
じょばあ。溢れる涙。
「若ちゃん……そんなお前も……俺は好きだぜ!!」
その背をナデナデする棄棄。「ぜんぜえ゛」と男泣きする英斗。もらったティッシュでチーンと鼻をかんだ。その頭を、棄棄がワシャッと撫でる。
「酒飲んで、美味しいラーメン食って、明日からも頑張ろうぜ……」
「ふぁい……」
「若ちゃんはいつも頑張ってる……先生は知ってる……」
「あざます……」
はぁ、と英斗は幾度目かの溜息を吐いた。そしてもう一回、鼻をチーンとかんだ。
「棄棄先生、お疲れ様です。……なんだか楽しそうですね?」
そこへ新たに顔を覗かせたのは不知火あけび(jc1857)だった。男ばかりの酒の席、美人が来たぞと盛り上がる野郎共。とまあ、例によってラーメンを渡され、未成年ゆえ缶ジュースも渡され、彼女も気が付けばベンチに腰かけていた。
「……先生に聞いて欲しいことがあって」
意気込みというか。そう切り出しつつ、あけびは白柄金鞘の刀をヒヒイロカネより取り出した。
「守護刀『小烏丸』。お師匠様が私に託した刀です。当時、彼に記憶を消されていた私には何も分からず、でも自分に託された刀だと理解できた。誰かを救う刃であれと」
忍の私に、人の心を託したんです。そう語るあけびの眼差しは、まっすぐに小烏丸を見つめている。
「最終決戦で、彼は私を庇い重傷に……結局、私は誰も救えなかった。でも、彼は私に救われたと」
『お前を使徒にしていたら、俺は今頃、ただの駒として共に命を落としていただろう。一介の天使である俺を、師匠に……駒ではない特別にしてくれた』
『お前達と共に生きて行く末を見届けたい』
思い返す言葉。きっと一生忘れられない言葉。あけびは大切そうに、守護刀を抱きかかえる。
「この刀、抜いたことがないんです。お守りにしてたから。……これからは、この刀で誰かを救っていく」
「いい心がけじゃねーの。もう、暴力の時代は終わりなんだ。これからはそういう力が、必要なんだよ」
お食べ、とあけびのラーメンどんぶりにチャーシューを分けてあげながら、棄棄は小さく笑った。「ありがとうございます」と、あけびはチャーシューもりもりのラーメンをすすって。
「先生、何かあれば呼んで下さい。サムライガールは必ず力になります!」
「頼もしいや。九月からもよろしくな!」
さて――ラーメンを食べ終えた棄棄が立ち上がる。
どちらへ? と生徒達が問う。歩き出す教師はこう答えた。
「ちょっと約束があってな」
――旧校舎前。
「よ、センセ」
月夜、降り立つ足音。銀の髪を掻き上げて、ギィネシアヌ(ja5565)は棄棄を見やった。
「ようギィネシアヌ」
「ラーメン美味そうだったな」
屋上から彼女は光景を見下ろしていたのだ。「お前も来たら良かったのに」と教師の言葉には「ガラじゃない」と不敵に笑んで見せる。
「それで、センセ」
「ああ」
演習用のスクールガンを手元でくるくる回しつつ――ずるり。ギィネシアヌの背後に、蛇の頭を持つアウルの尾が八本、幻出する。紅闘技:九龍大系<クリムゾンアーツクーロンモード>。
最後の稽古を付けて欲しい。
それがギィネシアヌの願い。
「教えてくれ、センセ」
少女の足元に、血のようなアウルの薄い膜が広がった。
「もし、どうしても殺さなければならないヤツが、大事な人だったらセンセは殺すかい。それとも誰かの手に委ねる? それとも、その人の為に知らない誰かを犠牲にできるかい」
どろり――無数の紅蛇が湧き上がる。紅蛇世界<グリモワールド>。
「俺は、きっと、この手で終わらせてしまう。それが、苦しいんだ」
囁く少女は赤の中に掻き消える。
教師は、こう答えた。
「皆まるっと笑顔になれるような奇跡(ハッピーエンド)を目指して足搔くかな、俺なら」
襲い来る蛇の群れを、首元のスカーフをシールド代わりに往なしつつ。彼はぬっと手を伸ばし――
「……って思えるようになったのも、お前らが『今』っていう奇跡を掴み取ったからだよ」
わし。ギィネシアヌの頭を無骨に撫でる。
「お前なら大丈夫さ。俺の生徒だ」
アウルの蛇が消えていく。世界は再び夜の色。
ギィネシアヌは顔を上げて教師を見て。
「……、」
言葉は無粋か。くしゃりと少女は笑ってみせた。
(愛してるゼ、センセ)
●夜、海
「夜の浜辺とはいえ、八月に海というのに違和感がありますねー……?」
櫟 諏訪(ja1215)は心底不思議そうに首を傾げ、夜の海を眺めていた。
「いつも、二月だもんな……」
傍ら、砂浜にて携帯闇鍋セットを駆使してバーベキュー台を作り、火を起こしているアスハ・A・R(ja8432)が「シーズンオフ、というやつさ……」などとフッと笑む。
※彼らは特殊な訓練を受けた生徒です。
「夏って、言えば……」
彼方、夜の水平線を眺め、Spica=Virgia=Azlight(ja8786)はほんのり眉尻を下げる。こうして皆と遊ぶ機会もこれで最後かと思うと、少し寂しい気持ちになった。
「学園生活最後の夏……良い思い出を作りましょう!」
快活に言ったのは、いつもの黒猫きぐるみ姿なカーディス=キャットフィールド(ja7927)。浜辺で獲ってきた、カラフルなうみうし、ウニ、辛うじて食べられそうな小魚、毒がなさそうな貝をドサドサと置く。
なんか不穏なブツを用意したのには理由があった。
此度開かれるは、闇鍋ならぬ闇バーベキュー、そして花火大会。
「ねぇもうほんと何で最後まで闇鍋黒ミサ……!?」
矢野 胡桃(ja2617)は顔を覆った。
「学生生活最後つっても何も変わんねえなー」
着々と準備をしつつ月居 愁也(ja6837)が慣れた顔で言う。「なあ」と彼が呼び掛けた先には、折り畳み椅子に置かれたホタテの殻。来られなかったアイツの身代わり。そのまま手にしていた懐中電灯をスッと別方向へ向ければ、夜来野 遥久(ja6843)の顔が下から照らし出された。
「んんん今日もオトコマエな!」
そんな愁也の眉間に、遥久は笑顔でカニ爪をサクッと刺しつつ。
「生ものはある程度、焼いて食べて下さいね」
など、絶叫をBGMに皆へ注意をしていたのだった。そのまま流れるように加倉 一臣(ja5823)を見やり。
「ああ加倉、ここがお前のスペースだ。今なら良く焼けるぞ、さあ」
と。バーベキュー用鉄板の一部を、体育座りできる程度に空けて示す。乗れ。
「……いやいやいや焼き土下座的なセッティングおかしくない? たたき? たたきが食べたいの?」
全力でノーセンキューしつつ、土下座スペースをホタテでそっと埋めていく。
「あいつも食いたかっただろうなぁ……土産に持って帰るか。殻を」
しみじみ。それは華桜りりか(jb6883)も似たような思い。闇バーベキュー用のタコヤキを見、彼女は友人の一人の面影を思い返しては、ちょっと残念な気持ちになるのだ。
(でも、これは詰め込まれる心配がないということなの……)
というわけで。
「焼けば食える。上がれば花火。学生生活最後の宴が今始まる……!!」
開幕宣言はいつものようにアスハの役目。何人か声かけ忘れた気がするが、気のせいに違いない。
「学園最後の宴ってあれですよね? 宴(惨劇)ってやつですよね!?」
カーディスは集まった猛者を見渡した。誰も彼も覚悟を決めた漢の目をしていた。
「さて、焼くか」
アスハもまた漢の一人。平然とした顔で手持ち花火セットを皆に配ってゆく。
「バーナーは? ないのです? あれ? は・な・び……?」
「……アスハさんおかしい。それはおかしい。花火はいけない」
首をひねり冷や汗を流すカーディス。真顔でつっこむ胡桃。あっこれあかんやつや。
「バーナー持ってきたけど花火でいい? そう?」
愁也は何ら疑いを持たない顔で頷いては、花火に火をつけた。他の面々も、次々花火に火をつけてゆく。
「普通に花火で着火すればいいじゃない……? 木材くらいそこら辺にありそうじゃない……?」
若者の深刻なツッコミ離れに、もう何が正しいのか分からなくなる胡桃であった。でも花火に火をつける。
しゅー。
ぱちぱちぱち。
光の色どり。花火の音。
「ところで聞いていい? 俺に線香花火を渡したの誰?」
趣深い線香花火、炙れない肉。一臣が悲しげに微笑む。ちょっと動くとポタッと落ちる。虚無。
「じゃあ代わりにこのアメフラシ炙っておくかーはい加倉さんどうぞ! 美味しいよ!」
そんな一臣に、愁也が花火で炙られたアメフラシを差し出した。ぶっちゃけ半焼けでめっちゃグロイ。
「ナマコは食べてもアメフラシは食べません!」
その一方では、胡桃とりりかはマシュマロを焼いていた。
「ばーべきゅーはご飯になるものだけではないの」
ドヤ顔のりりかは、シイナモンがけのリンゴ、バナナ、クッキー、トッピングに生クリームも用意する女子力の高さだ。
「甘い物は必須なの……です」
神妙に頷くりりか。「おいしい……!」と目を輝かせる胡桃。
「はい胡桃ちゃん」
そんな彼女に、愁也がイチゴを差し出した。ロケット花火が突き刺さっていた。曰く、パフェの飾り的なアレだという。
「しってるか、ろけっと花火は手に持つもの」
遠い目をした胡桃はそれを受け取ると――菩薩の顔でロケット花火を引き抜き、そのまま発射寸前にぶん投げた。一臣へ。
「あぶなっ」
ホタテの殻(お土産用)を回避射撃として容赦なくぶん投げて、ことなきをゲットする一臣。飛び行くロケット花火はそのまま……諏訪が闇バーベキュー用に用意していたカッチカチのカツオブシに命中した。
「ああっ! 一臣さんがー!」
ゴロ……と無残に転がったカツオブシを抱き上げる諏訪。
「そんな! 一臣さんが息をしていない!」
「なんだと……医者は、医者はいないのか!?」
アスハも駆け寄ってくる。すると「医者(アスヴァン)です」と遥久が参上。カツオブシにそっと手を当てるが、
「残念ながら……」
首を横に振る。
「一臣さーーーーーん!!!」
泣き崩れる一同。
「ことなきを 得たと思えば 亡き者に」
一臣、心の一句。
さて、そんな一方で。スピカが炙っているのは国産黒毛和牛の赤身ブロックをワイルドにドーン。ちゃんと野菜もある(女子力)。
「バーベキューって、言えば……やっぱり、これ……」
焼けば食えるの精神でじっくり火を通してゆく。焼くってより炙ってるけど気にしない。腹を壊さなければ問題ない。
「数量限定、なので……お早めに、どうぞ」
「いいですねー、こっちの魚介類とちょっと交換しませんかー?」
そう言う諏訪は、フッツーに薪や炭で海鮮魚介類を焼いていた。どういうことだってばよ。
カーディスもその隣で、風遁・韋駄天斬りで魚やら貝やらを捌き、弱火の火遁・火蛇で焼いている。
「火遁って付くから多分焼けてますよ〜多分」
そんな一同に混ざって、緋打石(jb5225)は闇鍋を焼いていた。闇鍋そのものを焼いていた。
「闇鍋の具材なんて甘っちょろいことなんてするか、鍋そのものを焼くんだ……」
もちろんひっくり返してちゃんと火も通すぞ。自分でも何やってんだかよく分かんなくなってきたけど、裏返して山状になった鍋は、アレだ、ジンギスカン焼くやつみたいな、ああいう感じでスピカの持ってきた肉を焼くには具合がよかった。あと当たり前だけど誰も進んで闇鍋そのものをバリバリ食べようとはしなかったので、結局闇鍋はジンギスカン焼き器的なことになった。ジンギスカンわーい!(※牛肉)
「うん、酒でも飲むぞ!」
飲まずにはいられないッ! 酒を片手に、主に来られなかった面子についての追悼の言葉。犠牲者の捏造。ありもしない過酷な戦いのでっち上げは基本。タコヤキとホタテがそっと花火に照らされていた。
……。
……。
「なんか……」
ふと、アスハが呟いた。
「比較的平和だな」
闇バーベキューなのに食材が割と良心的。というか普通に調理してる面子もいるし。殴り合いも始まらないし。裏切りも起きないし。普通にご飯美味しいし。神の兵士で蘇生した者もいないし今んとこ。
「「「確かに!」」」
これには一同も総同意。
でもよく考えたらこれが普通のバーベキューの姿なんだよなぁ。そう思うと、これまでの学生生活のハチャメチャさを改めて思い知るのだ。
そして今宵が、そんな学生生活最後の夜――とはいえ、遥久に感傷はなかった。いつも通りの面々、他愛もないやり取り。安堵を感じるが、されど幾ばくかの寂寥のようなモノもあり。
いつもの面子でいつもの時間。それで終えられるのはまた一つ良い思い出。
「あ、そうそう」
普通においしく焼けたホタテを頬張りつつ、一臣が言う。
「ちゃんと遊ぶ用の花火も持ってきたよ」
取り出したのはありふれた花火セットだ。この派手なヤツやりたい、と筒状のものに火をつけようとしていると……傍らのアスハが高級マツタケを二本、取り出すではないか。
「一番綺麗に打ちあがったやつに焼きマツタケを進呈しよう!」
その言葉に、りりかが「マツタケ……」と反応しつつも首を傾げる。
「打ちあがる……とは? 人って打ちあがるの、です?」
「打ち上げ花火、下から見るか、お前がなるか――という話だな」
緋打石は得意気だ。打ち上げる側になる気も満々だ。
「マツタケ! 頑張って花火になりますの!」
カーディスは打ち上げられる側になる気満々だ。すげえ。七割が打ち上げたい立候補してるこのクレイジーな世界において凄く貴重な存在。なお諏訪はいつも通りヤる側になるためなら手段と道徳を選ばない男。
「ところで一臣さん、スターマインって花火、綺麗ですよねー? 誰も打ち上げるのが一回とは言ってなかったですねそういえばー……華麗な雄姿、期待してますねー?」
「待って、何でこっち見るの?」
不穏な気配を察知してクリアマインドを発動。このスキルは精神を練磨することで一時的に気配を断つことができるが片手に着火した花火を持っていてはまるで意味がないぞ!
「しってた!!!」
絶望ポーズの一臣。
そこへダンッと踏み込んだのは光纏したスピカだ。Code:HeavyArms展開、少女のアウルが無数の刃となり。
「……顕現せよ、“破壊者”ミョルニル……ッ!」
具現化<マテリアライズ>ミョルニル。
スピカの光纏である光の武器が、多くの人の想いが込められた銀の疑似聖槍――だとオミーがしぬので、ホタテの殻に憑依する。なんとホタテの殻がアウルの雷を纏う巨大な鎚、「破壊者」ミョルニルになるではないか! ホタテすげえ!
「ライトニングホタテ……」
緋打石がボソッと呟いた。
とまあ、ものすごいホタテによるものすごい一撃が一臣を吹っ飛ばしたのは確かだ。まさか一臣もホタテでこんなに吹っ飛ばされることが人生であるなんて思いもしなかったに違いない。打ち上げられた彼は夜空にて、光纏with噴出し花火によって瞬き煌き、思い出に一輪を添えたのであった……。
「ホタテでも、なんとか、なるものですね……」
「食べてよし、打ち上げてよし、ホタテはすごいの、です」
スピカの隣、人柱花火を見上げているりりかは普通に手持ち花火を楽しんでいた。「あ、回復はお任せ下さい、です」とコックリ頷く。この世界において回復は善意だけど善意じゃない場合もあるんだ。それは彼らがこの学生生活で学んだこと。
「すげー」
愁也はタコヤキをもぐもぐしながら打ち上げ花火(?)を眺めていた。
と。その背後に――B級映画の殺人鬼さながら、遥久が得物を振りかぶっていた。
ッパーン。
振りぬかれたのはハリセンの一撃、インパクト。普段よりも力を込めて、相手に一撃を叩き込みます。シンプルな技だ。
「えッ――」
上空へ吹っ飛ばされる愁也。得も言われぬ浮遊感と共に振り返れば、遥久が地上から微笑んでいて。
「打ち上がりたそうにしてたから」
サムズアップ。
「言ってたっけ!?」
こうなりゃヤケだ。愁也はアロハシャツの下に仕掛けていた筒花火(なんで仕掛けてたんだろう。夏のせいかな?)をヒャッハーと点火した、が。
「ん?」
気が付けば自分の周囲に彗星がある。彗星? ハテ? 犯人はすぐに分かった。遥久のコメットだ……。
「愁也、言ってたよな。いつか彗星と夜を飛んでみたいって」
「言ってたっけ!!? あっちょっ待っダメっアーーーーー!!!!」
そして輝く阿修羅様(ウルトラソウル)。
「……美しい散り様ですね。さて次の希望者は」
<○><○>
「……」
自力で打ち上ろうとしていたカーディスはそっと遥久から目をそらした。黒猫の体にはすでに花火がたくさん巻き付けられ、両手にも花火をたくさん持っている。
「じ……迅雷で自力でできますのでっ……!」
冷や汗を滴らせながら苦し紛れに呟いたが、ここで緋打石と諏訪に両サイドから抑え込まれる。
「ヤメロー! シニタクナーイ!」
もがくカーディスに遥久が迫る。
「貴方……言ってましたよね」
「言ってないですの!!!」
言われる前に食い気味に否定。
でもまあ結局ハリセンで吹っ飛ばされました。緋打石と諏訪ごと。なぜって? 夏のせいさ。
「……じゃあ自分、皆さんを盾にするのでよろしくですよー?」
「「外道!」」
「どうせやられるならできるだけ他者に苦痛を押し付けたいじゃないですかー?」
「「外道!!」」
そんなこんなのワチャワチャが夜空でありましたが、ここでカーディスの花火が爆ぜて仲良く3タテされました。めでたしめでたし。
「最後まで通常運転ゴチソウサマデシタ!!」
胡桃はとりあえず合掌しといた。
「なーんか賑やかだと思ったら」
楽しそうじゃん、とそこに現れたのは棄棄だった。「せんせ!」と胡桃が彼に突撃する。
「モモそつぎょーです、よ」
「おう、おめでとさん! 卒業後はどうすんだい?」
「学園を出て、ちょっと岐阜まで」
「いいねえ。俺もどっか旅するかな〜」
「先生も旅に出るです? なら、二月の海には集合しませんか?」
軽い同窓会みたいなものです! と胡桃が笑う。
その言葉に……りりかは今日が最後の日なんだと改めて思い知る。
(この見慣れた皆と……これからは、頻繁に集まることもないの、でしょうか)
そうすると込み上げてくるのは寂しさだ。
最後までワイワイガヤガヤ騒いで過ごす、いつもの面子、いつもの時間。
きっとこれが最後の瞬間――。
でも、祭りの最後に「さよなら」は禁句。スピカがニコリと微笑む。
「またいつか、どこかで集まりましょう」
「じゃあ、次は二月だな」
アスハも肯定の頷きを示す。
「そだね、次は二月に!」
「二月にまた海で会いましょう。それまでどうぞ御元気で」
愁也と遥久も笑顔で口を揃えた。寂しいとは無縁の、最後の夜。
「次の二月辺り海行けそうな気がする……」
カーディスと諏訪に支え支えられ、ヨロヨロ戻ってきた緋打石もそう言った。
棄棄はそんな一同を見渡して。
「おう! 二月と言えば海だからな。来年もよろしく! 約束だ!」
「あっ。卒業してても参加してOKですか!?」
一臣が問う。「もちろんだ!」と教師が笑う。
二月かぁ。
きっと想像できないぐらい寒くって、想像できないぐらい楽しいんだろう。
なんて。思いながら。
生徒達は……海の彼方を眺める。
静かに寄せては返す波。
久遠ヶ原学園の生徒として居られる、最後の瞬間。
進む先はバラバラだけど。
心はいつも、絆でしっかと繋がっている。
過ごした思い出がその証。
幾つも幾つも思い返せる、たくさんの思い出……。
未来は変わっていく。
でも、いつもの面子のいつもの空気はきっといつまでも変わらない。
「最後に写真撮ろうよ」
一臣が提案する。反対意見はもちろんなかった。
寂しくないと言えば嘘になる。
だけど大丈夫。また会える。これは永遠の別れじゃない。
海を背に並ぶ。砂浜に幾つもの足跡。
はい、ちーず。フラッシュがパチリ。
さらば、我らの青春よ。
我らの行く先に幸あれ!
●夜、それぞれの場所
(卒業、か……)
夜の町、街灯の下、イリス・リヴィエール(jb8857)は一人歩いていた。彼女は戦闘任務帰り、被害や負傷者を出すことなく無事に任務を終えて、「お疲れ様」の言葉の後に解散して間もなく。
静かだ。コオロギの声。さっきの仲間達との賑やかさが、天魔と激しく戦った緊張感が、嘘のよう。
そしてその静寂は――イリスが「考えないように」していたことを、次から次へと誘い出すのだ。
任務前の出来事である。
復讐相手から手紙が届いた。
この学園を去り、個人の誓いを果たしに行く。果たし終えたらイリスとの約束を果たしに会いに行く、と――そこには綴られていた。
「Ailes」
愛竜の名前を口にすれば、ポンとヒリュウのエールが彼女の肩に現れる。「キィ」と鳴いて甘えてくるその子の喉を指先であやしつつ、おもむろにイリスは呟いた。
「逃げられた、訳ではないようだけど」
そこまで言って、己の言葉は復讐相手の言い分を素直に信じるものじゃないか、と苦笑する。
「……再会するまでに、もっと強くならなくてはいけない。お前も覚悟をして」
きゅ! と力強く鳴くエール。イリスは深呼吸を一つして、夜の空を見上げた。
彼との約束。
彼が誓いを果たすまで、イリスは彼を殺さない。
誓いが果たされた時はすなわち、イリスの復讐を彼が受け入れるということ。
イリスの復讐劇はまだ終わらない。
この夜の空が果てしないように。
しかし明けぬ夜もまた、ない。
「いつか。……いつか、明けるのかしら、ね」
答える者はいない。
答えを求めてもいなかった。
満ちる時を待つ十日夜の月が、静かにイリスを見つめ返している。
その黄金の輝きは、まるで“彼”の瞳のようで――……。
「きれいなお月様なのだ」
メリッサ・アンゲルス(ja1412)は月を見上げ、それから視線を前に戻した。
とある田舎の自然の中、広い広い一軒家。メリッサが立っているのはその広い庭。手入れが施されているのは――彼女が日中から庭の手入れをしたからだ。
ここはXという悪魔――メリッサの“父”と出会い、過ごした場所。
メリッサにとっての、思い出の場所。
今は誰もいない家だけれど、今日はメリッサが家の掃除や庭の手入れを行った。
「夏休み宿題は、おとーさんの言いつけ通り早々に終わらせたのだぞ!」
得意気な彼女が語る先には、赤いサルビアの花に囲まれたザクロの木。それを父の墓に見立て、娘は笑顔で言葉を続ける。
「明日から我は中等部なのだぞ! まぁハーフに覚醒してから外見はさっぱり変わっとらぬが……だがこの通り制服は変わるのだ! カッコイイであろう!」
くるんと回ってみせるメリッサのいでたちは、おろしたての久遠ヶ原学園中等部女子制服だ。
「まぁ外見が変わらぬのも考え様、おとーさんに貰った服をずっと着られるということだ!」
言葉の直後に風が吹く。『子孫の守護』の樹木言葉を持つザクロが、『家族愛』の花言葉を持つサルビアが、返事のように揺らいだ。それがまるで、父の相槌のような気がして。少女は堂々と、胸を張って言い放つ。
「明日からもたくさん勉強して、いつか天界と魔界の両方に行ってみたいのだ。我は三界の子であるからな! 全てを見て、全てを守るのだ、この先も!」
小さな体に、大きな夢。
優しい葉擦れの音が、メリッサの言葉を肯定していた。
「さて……我はそろそろ寝るのだ。おやすみなさい、おとーさん!」
踵を返す先には“我が家”。メリッサは一歩ずつ、歩いていく――。
●夜、久遠ヶ原学園03
「……あら、先客。こんばんは先生。好い夜ね」
十日夜の月の下。屋上にて。シュルヴィア・エルヴァスティ(jb1002)の視線の先には、見覚えのある背中。
「ようシュルヴィア。卒業おめでとさん」
柵にもたれていた棄棄が振り返る。「月見かしら?」「そんなもんさ」と言葉を交わしつつ、シュルヴィアは彼の隣へ歩を進めた。
「お前も月見か?」
「私? 私は……まぁ、月見かしら。せっかくだし、と思って」
教師のように柵にもたれる。寸の間の静寂。口を開いたのはシュルヴィアで。
「思い出深い場所だしね。先生、覚えてる? ここ、初めて会った場所よ」
クリスティーナのおつかいを見守ったり。お菓子パーティしたり、ビニールプールで遊んだり……。
「覚えてるぜ、全部な」
棄棄は目を細める。
と、その時だ。「そうだ先生」と彼女が口にし、一通の手紙を差し出して。
「はい。……実家の住所。じき帰るから」
「フィンランドだったか」
手紙を受け取り、月に透かし。「ええ」とシュルヴィアは頷く。
「休みが取れたら、顔出しなさいな。案内してあげる。何なら欧州一回りだって付き合ってあげるわ。旅行に、現地ガイドは重要よ?」
そう言って……さて。
シュルヴィアは柵から身を離す。
「ありがと、先生。先生に会えて、本当によかった。……貴方自身と、皆の棄棄先生。どちらも。私は、大好きよ」
「へへ、照れるねそいつぁ。俺も大好きだぜ、シュルヴィアのこと。生徒としても、一人の人間としても」
「そ」
ふわり、笑んで見せる。
「またきっと、会いましょう。……おやすみ、先生」
そう言って、スカートを優雅にひるがえし、踵を返す。
「三月だ」
その背に、棄棄の声。
「三月んなったら、会いに行く」
「なんでまた三月?」
「ナイショ」
「食えない人ね。どこまでが計算で、どこまでが素なのかしら?」
「ちょいとミステリアスな方がカッコイイだろ?」
「……まぁ、いいわ。お疲れ様、先生」
「ほいほい、お前さんもお疲れさん」
……二〇一八年、本当に会いに来る。
●九月一日
九月の寸前。
真緋呂は屋上にて、フルートを手に景色を眺めていた。
それから、おもおむろに。奏で始める旋律の名は――夢<トロイメライ>。
――夢は見ず、叶えて現実にする主義だけど。
最後の夜くらい夢を奏でよう。
まどろみの夜が明ければ、朝日と共に現実が始まる。
夢はいつか醒める。夢は永遠のものじゃない。
それでも人は夢を見るのだろう。
人が、明日という未来を、物語を、歩み続ける限り。
夢の終わりはサヨナラじゃない。
これで終わりなんかじゃない。
夢は、未来は、続いてゆく。
これからも――ずっと。
『了 ……あるいは、いつまでも続く』
依頼結果
| 依頼成功度:大成功 |
| MVP: − |
| 重体: − |
| 面白かった!:15人 |







