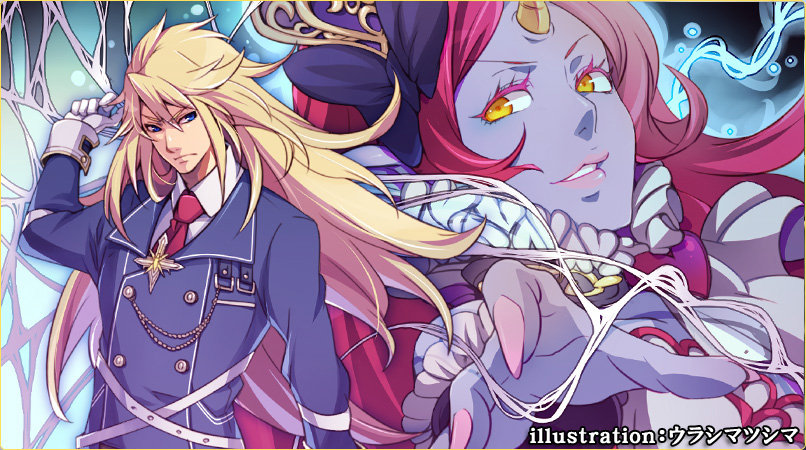
イメージノベル
5月26日更新分
●
2016年、北国の春が盛りとなる頃。初夏に向けて準備を始める頃。
ずっと息を潜めていたレジスタンスが動き始める。
祈りを捧げよ。
蜂起せよ。
旗を掲げ、火柱を立て、彼の地を奪還せよ。
そして、北の楔を穿て。
●
北海道・洞爺湖ゲート。
「おい、リザベル。話がある」
爬虫類のように獰猛な目つきの男が、足早に近づいては女へ呼びかける。
「偵察部隊からの報告について? 捨て置きなさいと言ったでしょう」
東北へ発ったルシフェルの守備を預かる女男爵・リザベルは、眉をひそめて旅団長・ソングレイへ振り向いた。
「あんたが捨て置くなら、俺が軽く見て来てやるって言ってるんだ。万が一、祭器が量産されているならマズイ」
「何がどう、マズイというの? 見え透いた敵の動きに踊らされて拠点を空ける方が危ういわ」
報告とは、ここから東へ離れた街――苫小牧付近にて、旗槍を掲げる撃退士らしき一団が確認されたというものだ。
「ブラフだってなら構わない、手勢でブッ潰して帰るだけだ。ホンモノだった場合は、下手すりゃ喉元に喰いつかれる。それからじゃ遅いって言ってるんだよ」
祭器の威力を体験していないリザベルには、どうにも伝わらない。もどかしさに、ソングレイは歯噛みする。
東北での撤退を、その悔しさを、彼は忘れていない。
そしてまた、こうも思うのだ。『面白くなった』と。
(デカイ力量差のゲームなんて、ハンデを考えるだけ面倒ってなもんだ。どうせ賭けるなら全額――だろう?)
「目が笑ってるのよ」
「……ん?」
指摘され、ソングレイは咳払いをしながら着崩したスーツの襟元を正す。片膝をつき、首を垂れる。
「それじゃあ、こうするか。女男爵(バロネス)・リザベル。ルシフェル様よりゲートを預かりし御方。私に、拠点を離れ撃退士を討つべく東へ出向く勝手をお許し下さいますか」
恭しくもわざとらしい振る舞いに、リザベルは何度目かの深いため息を返した。
●
撃退士を脅威に思うかと問われたなら、リザベルは否と言う。
触れることを許す距離まで接近されたことが無いでもないが、命の危険を感じるところまではいかない。
おまえたちに、この首を落とせるものか。そう思う。
それは彼女の用心深さに裏打ちされた行動にもある。自ら危険域へ飛び込むことはしない。使える手駒を最大限に使う。
その点で、ソングレイとは真逆だ。あれは、嬉々として自ら危険域へ突っ込む。
(さすがに、今回はこれまでとは違うみたいだけれど)
祭器に関する彼の言を信じないわけではない。しかし、全てを信じるわけでもない。
それほど驚異的な武器ならば、なぜ、もっと積極的に出てこないのか。
(鳥海山で、冥魔軍の足止めをすることに専念しているのだとしたら、それまでの能力のはずよ)
このゲートを落とそうというなら、それ以上の『力』が必要だ。
「リザベル様」
ソングレイが東へ発った翌日、下級悪魔がやってきた。札幌方面の偵察へ向かわせていた者だ。
「街の地下から、光……? どういうことかしら」
もたらされた報告に、リザベルは首を傾げる。
このところ、撃退士が札幌界隈に頻出していることは知っている。リザベル自らが捕え、何を企んでいるのか探ろうとしたこともあった。
(何かの調査、それが成ったということ? あの場所で……)
洞爺湖ゲートからも決して遠くはない冥魔の領域で、彼らは何をしようというのか。
城砦があるでもない、将を置いているでもない、あるのは――『糧』だ。
支配領域外から攫ってきた人間たちを大型の建物へ押し込め、吸魂の場としている。市内には、収容所とも呼べるそういった建物がいくつもある。
それは札幌に限らず幾つかの都市部で行っており、そうしてエネルギー源を確保し続けてきたわけだが……
(この期に及んで、人間の奪還を目論んでいる……? まさか)
ゲートを襲うだけの『力』はなくても、囚われの同胞を助けるくらいなら決行するかもしれない。
「――ソングレイ!!」
名を呼んだところで、赤翼の旅団長は既にいない。
(『祭器のブラフ』なんて可愛いものじゃないわ、あれは――……。それじゃあ)
出向くのは自分しかいない。
(ゲートの守りを厚く残せば問題ない。判断だけは、私がしなくては)
謎の発光の正体を突き止め、それが撃退士に依るものならば叩き潰す。それだけだ。
ソングレイが繰り返す『祭器』と同様の脅威を持つというのなら、自分が相手になればいい。
――まさか、とは思うけれど。
●
札幌市内、とある地下。
無尽光研究会によって割り出された、地脈が最も効果的に流れている場所。
そこで、レジスタンスリーダーであるミーナ・ヴァルマは【祭器】の一つである『祈光陣』発動術式を展開していた。
白い水晶のような物質からなる小さな星型の十二面体――『星幽核(アストラル・コア)』が宙に浮き、純白の輝きを放っている。
術式は数時間を超え、少女の額から頬、顎へと汗が伝う。疲労の色も見えるが、ミーナは気丈に呪文詠唱を続けていた。
(……お嬢、もう一息だ……)
息を詰めて見守るのは、彼女の護衛を自負するレジスタンス構成員・天斎。
他地域のメンバーとの連絡役も兼ね、その手には光信機が握られている。物資に事欠くレジスタンスへ、久遠ヶ原から貸与されたものだ。
(陣さえ、無事に完成すれば……あとは)
ミーナは疲労で戦うことはできないだろう、陣の維持のためにも護衛は必要なままだ。
しかし、発動した陣の輝きは良い『囮』となる、敵が大挙して押し寄せるのは想像に易い。
本当の戦いは、そこからだ。
「札幌は今のところ、順調らしい。術式完成まで折り返しも過ぎた」
他方、苫小牧方面。
『千億星の光旗槍(ブライティングペノン・オブ・ジリオンスター)』を掲げ進むレジスタンスサブリーダー・オヤジの隣で、天斎と同じく連絡役を担うレジスタンス構成員・レラが向こうの様子を報告する。
「ふむ。進行状況は良い具合だな」
「あとはオヤジ、あんたがぶっ倒れなければいい」
【祭器】は未だ、光を放っていない。苫小牧市街へ入るまではアウルを通さずに行く手筈だ。
――鳥海山での勢いはどうした?
手痛いダメージを被った戦いを思い出し、レラは苦い顔をする。
(ソングレイは、確実にこの『光旗槍』を意識してるはずだ)
これまで、ずっと存在をひた隠しにしてきた『レジスタンス』。その牙を剥く、一世一代の賭けだった。
戻って、札幌市街。
巡回するディアボロを駆除しながら、撃退士の部隊が進む。
「苫小牧の陽動部隊は、予定通り間もなく市街へ入るそうです。使い魔らしきディアボロも確認したとのこと。あとはソングレイが向こうへ現れてくれれば……」
部隊の一つを率い、光信機で各部隊へ連絡を入れるのは学園生の御影光。年明けの『特殊鉱石』採掘依頼から始まり『祈光陣』試用依頼など、レジスタンスとは別方面から【祭器】に携わり続けていた。
縁は、ここで繋がった。
「『祈光陣』が発動すれば、市内に捕らわれている人々の吸魂は止められます。陽動だなんて思わないで、助けられる命をここで可能な限り救出しましょう……!!」
冥魔が定期的に、支配地外から『糧』となる人間を攫っていることをレジスタンスたちは知っていた。
もちろん、それを止めることも活動の一つではあったが、力及ばぬこともあった。
捕らわれている命は、彼らの悔恨の象徴でもある。
●
人類側の目的が『市民救出』だと思わせ、少ない手勢でリザベルを釣り出す……それは、『光旗槍』をまるごと囮にした大胆な作戦だった。
あの力を知っているソングレイならば、必ずや動くだろう。
対して慎重派のリザベルならば、拠点を優先するはず。
そこへ『祈光陣』の輝きが届けばリザベルが動くしか、無くなる。二重の陽動作戦だ。
洞爺湖にルシフェルがゲートを開いてから、細々と細々と紡がれてきた思い。願い。祈り。
ソングレイとの戦い。リザベルとの邂逅。陣の試用実験。
成功も失敗も結びつき、全てが一つの方向へと向かう。
小さな力が縒り糸のように絡み合い強くなり、札幌の街を今、奪い返す。
(執筆:佐嶋ちよみ)
2016年、北国の春が盛りとなる頃。初夏に向けて準備を始める頃。
ずっと息を潜めていたレジスタンスが動き始める。
祈りを捧げよ。
蜂起せよ。
旗を掲げ、火柱を立て、彼の地を奪還せよ。
そして、北の楔を穿て。
●
北海道・洞爺湖ゲート。
「おい、リザベル。話がある」
爬虫類のように獰猛な目つきの男が、足早に近づいては女へ呼びかける。
「偵察部隊からの報告について? 捨て置きなさいと言ったでしょう」
東北へ発ったルシフェルの守備を預かる女男爵・リザベルは、眉をひそめて旅団長・ソングレイへ振り向いた。
「あんたが捨て置くなら、俺が軽く見て来てやるって言ってるんだ。万が一、祭器が量産されているならマズイ」
「何がどう、マズイというの? 見え透いた敵の動きに踊らされて拠点を空ける方が危ういわ」
報告とは、ここから東へ離れた街――苫小牧付近にて、旗槍を掲げる撃退士らしき一団が確認されたというものだ。
「ブラフだってなら構わない、手勢でブッ潰して帰るだけだ。ホンモノだった場合は、下手すりゃ喉元に喰いつかれる。それからじゃ遅いって言ってるんだよ」
祭器の威力を体験していないリザベルには、どうにも伝わらない。もどかしさに、ソングレイは歯噛みする。
東北での撤退を、その悔しさを、彼は忘れていない。
そしてまた、こうも思うのだ。『面白くなった』と。
(デカイ力量差のゲームなんて、ハンデを考えるだけ面倒ってなもんだ。どうせ賭けるなら全額――だろう?)
「目が笑ってるのよ」
「……ん?」
指摘され、ソングレイは咳払いをしながら着崩したスーツの襟元を正す。片膝をつき、首を垂れる。
「それじゃあ、こうするか。女男爵(バロネス)・リザベル。ルシフェル様よりゲートを預かりし御方。私に、拠点を離れ撃退士を討つべく東へ出向く勝手をお許し下さいますか」
恭しくもわざとらしい振る舞いに、リザベルは何度目かの深いため息を返した。
●
撃退士を脅威に思うかと問われたなら、リザベルは否と言う。
触れることを許す距離まで接近されたことが無いでもないが、命の危険を感じるところまではいかない。
おまえたちに、この首を落とせるものか。そう思う。
それは彼女の用心深さに裏打ちされた行動にもある。自ら危険域へ飛び込むことはしない。使える手駒を最大限に使う。
その点で、ソングレイとは真逆だ。あれは、嬉々として自ら危険域へ突っ込む。
(さすがに、今回はこれまでとは違うみたいだけれど)
祭器に関する彼の言を信じないわけではない。しかし、全てを信じるわけでもない。
それほど驚異的な武器ならば、なぜ、もっと積極的に出てこないのか。
(鳥海山で、冥魔軍の足止めをすることに専念しているのだとしたら、それまでの能力のはずよ)
このゲートを落とそうというなら、それ以上の『力』が必要だ。
「リザベル様」
ソングレイが東へ発った翌日、下級悪魔がやってきた。札幌方面の偵察へ向かわせていた者だ。
「街の地下から、光……? どういうことかしら」
もたらされた報告に、リザベルは首を傾げる。
このところ、撃退士が札幌界隈に頻出していることは知っている。リザベル自らが捕え、何を企んでいるのか探ろうとしたこともあった。
(何かの調査、それが成ったということ? あの場所で……)
洞爺湖ゲートからも決して遠くはない冥魔の領域で、彼らは何をしようというのか。
城砦があるでもない、将を置いているでもない、あるのは――『糧』だ。
支配領域外から攫ってきた人間たちを大型の建物へ押し込め、吸魂の場としている。市内には、収容所とも呼べるそういった建物がいくつもある。
それは札幌に限らず幾つかの都市部で行っており、そうしてエネルギー源を確保し続けてきたわけだが……
(この期に及んで、人間の奪還を目論んでいる……? まさか)
ゲートを襲うだけの『力』はなくても、囚われの同胞を助けるくらいなら決行するかもしれない。
「――ソングレイ!!」
名を呼んだところで、赤翼の旅団長は既にいない。
(『祭器のブラフ』なんて可愛いものじゃないわ、あれは――……。それじゃあ)
出向くのは自分しかいない。
(ゲートの守りを厚く残せば問題ない。判断だけは、私がしなくては)
謎の発光の正体を突き止め、それが撃退士に依るものならば叩き潰す。それだけだ。
ソングレイが繰り返す『祭器』と同様の脅威を持つというのなら、自分が相手になればいい。
――まさか、とは思うけれど。
●
札幌市内、とある地下。
無尽光研究会によって割り出された、地脈が最も効果的に流れている場所。
そこで、レジスタンスリーダーであるミーナ・ヴァルマは【祭器】の一つである『祈光陣』発動術式を展開していた。
白い水晶のような物質からなる小さな星型の十二面体――『星幽核(アストラル・コア)』が宙に浮き、純白の輝きを放っている。
術式は数時間を超え、少女の額から頬、顎へと汗が伝う。疲労の色も見えるが、ミーナは気丈に呪文詠唱を続けていた。
(……お嬢、もう一息だ……)
息を詰めて見守るのは、彼女の護衛を自負するレジスタンス構成員・天斎。
他地域のメンバーとの連絡役も兼ね、その手には光信機が握られている。物資に事欠くレジスタンスへ、久遠ヶ原から貸与されたものだ。
(陣さえ、無事に完成すれば……あとは)
ミーナは疲労で戦うことはできないだろう、陣の維持のためにも護衛は必要なままだ。
しかし、発動した陣の輝きは良い『囮』となる、敵が大挙して押し寄せるのは想像に易い。
本当の戦いは、そこからだ。
「札幌は今のところ、順調らしい。術式完成まで折り返しも過ぎた」
他方、苫小牧方面。
『千億星の光旗槍(ブライティングペノン・オブ・ジリオンスター)』を掲げ進むレジスタンスサブリーダー・オヤジの隣で、天斎と同じく連絡役を担うレジスタンス構成員・レラが向こうの様子を報告する。
「ふむ。進行状況は良い具合だな」
「あとはオヤジ、あんたがぶっ倒れなければいい」
【祭器】は未だ、光を放っていない。苫小牧市街へ入るまではアウルを通さずに行く手筈だ。
――鳥海山での勢いはどうした?
手痛いダメージを被った戦いを思い出し、レラは苦い顔をする。
(ソングレイは、確実にこの『光旗槍』を意識してるはずだ)
これまで、ずっと存在をひた隠しにしてきた『レジスタンス』。その牙を剥く、一世一代の賭けだった。
戻って、札幌市街。
巡回するディアボロを駆除しながら、撃退士の部隊が進む。
「苫小牧の陽動部隊は、予定通り間もなく市街へ入るそうです。使い魔らしきディアボロも確認したとのこと。あとはソングレイが向こうへ現れてくれれば……」
部隊の一つを率い、光信機で各部隊へ連絡を入れるのは学園生の御影光。年明けの『特殊鉱石』採掘依頼から始まり『祈光陣』試用依頼など、レジスタンスとは別方面から【祭器】に携わり続けていた。
縁は、ここで繋がった。
「『祈光陣』が発動すれば、市内に捕らわれている人々の吸魂は止められます。陽動だなんて思わないで、助けられる命をここで可能な限り救出しましょう……!!」
冥魔が定期的に、支配地外から『糧』となる人間を攫っていることをレジスタンスたちは知っていた。
もちろん、それを止めることも活動の一つではあったが、力及ばぬこともあった。
捕らわれている命は、彼らの悔恨の象徴でもある。
●
人類側の目的が『市民救出』だと思わせ、少ない手勢でリザベルを釣り出す……それは、『光旗槍』をまるごと囮にした大胆な作戦だった。
あの力を知っているソングレイならば、必ずや動くだろう。
対して慎重派のリザベルならば、拠点を優先するはず。
そこへ『祈光陣』の輝きが届けばリザベルが動くしか、無くなる。二重の陽動作戦だ。
洞爺湖にルシフェルがゲートを開いてから、細々と細々と紡がれてきた思い。願い。祈り。
ソングレイとの戦い。リザベルとの邂逅。陣の試用実験。
成功も失敗も結びつき、全てが一つの方向へと向かう。
小さな力が縒り糸のように絡み合い強くなり、札幌の街を今、奪い返す。
(執筆:佐嶋ちよみ)
5月19日更新分
●
2016年5月、北国へ短い春が訪れる頃。
北海道・某所。レジスタンスの数あるアジトの一つに、『レジスタンス』数名の構成員と久遠ヶ原からの協力者が集っていた。
「特殊鉱石の採集は順調に進んでいて、『祭器』の強化もほどなく完成するだろうということよ」
レジスタンスリーダーであるミーナ・ヴァルマは、学園からの報告書へ目を通すと仲間たちへ向き直った。
褐色の肌にはめ込まれたライトグリーンの瞳は輝く星のようで、一人一人を力づけるように見つめる。
「こっちも久遠ヶ原の協力のお陰で、札幌周辺の情勢はだいぶ掴めてきた。タイミングを重ね、一斉蜂起だな」
彼女の隣で、虚無僧姿の中年男性――サブリーダーの『オヤジ』が喉の奥で笑い声で続けた。
札幌の奪還。それがレジスタンスの悲願。
「冥魔にエネルギー源として囚われている人々は、支配領域効果を無効化する陣によって解放されるわ。
そのまま札幌を人類側の拠点とすることで敵に対して『楔』としたいけど……冥魔の報復が強力であれば、元の木阿弥になってしまう」
ミーナは言う。
「リザベルとソングレイ……今、北海道に居る強力な二柱を同時に討ってこそ、私たちは存在を認められると思うの」
存在を認める――『脅威』と見なされる。
「これまでは小さな勢力だったから目立つことを避けてきたけれど、今度は違うわ。
力持つ者として向き合うことで、戦いを避けるの。容易に手出しをさせない状態へ運ぶのよ」
「『俺たち』の存在は、今の今まで徹底的にひた隠しにしてきた。独学で習得した技に加え、少しずつ『久遠ヶ原』の知識・技術も吸収し始めている。ソレを、悪魔サンたちは御存知ない。トコトンまで見くびってくれている。勝機はそこだ」
ミーナの言葉を、オヤジが補足する。
「リザベルやソングレイとは直近でも対峙する場面はあったが、幸か不幸か深手を与えるには至ってない。
深手を与えていたなら今回の戦いは楽になったろうし、与えられなかったら向こうはコチラをナメてくる。それはそれで好機だ」
「……それはいいんだがよ」
決戦へ沸きあがる空気の中、部屋の端に居た構成員の一人である青年・レラが眉根を寄せて言葉を挟んだ。
「『祭器』ってのは、誰が扱うんだ? 『広域展開の陣』と『能力上昇の槍』の2つがあるんだろう」
陣は展開までに時間がかかり、光旗槍については相当な熟練者である必要があると聞く。
「『陣』は、私が発動するつもりよ」
「リーダーが? ……危険だ。展開の呪文詠唱中は無防備になると聞いてる」
「私を救ってくれた『レジスタンス』のため……。ここは、頑張らせて?」
案じる仲間へ、ミーナ決意を固めた表情を浮かべた。
堕天使である彼女がレジスタンスに身を寄せ、久遠ヶ原側から表だって存在を認識されていなかったには理由がある……しかしそれはまた、別の話。
「そこまで言うなら……わかった。それじゃあ、『槍』は?」
「愚問だな」
レラの疑問に対し、深編笠の下でオヤジが笑う。
「伊達に古参はしていない。槍の使用条件については、俺が満たしておる」
「はぁああああ?」
「ミーナさんもオヤジさんも、非常に熱心に鍛錬していたんですよ」
二人の間へ、無尽光研究会から派遣されている研究員・千塚が割って入った。
「どちらの祭器も、使用するには無尽光に関する知識・相応の経験が必要です。短期間ながら、お二人はそれぞれを満たされました」
「独学は、私たちの得意分野よ。知識の吸収力に関しては自信があるわ」
千塚へ、ミーナが悪戯っぽく笑う。
「わかった……。リーダーについては承知した。……だがな、オヤジ。あんたは自分の年齢考えろよ、戦場に出るんだぞ!? そんなんで敵に襲われでもしたら――」
「死ぬかも知れんなぁ。……故に、しっかり護れよ?」
「……槍を持ってる間は、気の抜ける尺八も吹けないだろうから丁度いいか……」
「レラったら。でも……そうね。戦いが終わったら、オヤジの尺八の音を聞きたいわ。その為にも、負けられない。
私たちの力は小さなものだけれど、戦うのは私たちだけじゃない。久遠ヶ原学園と協力して、再起を図りましょう!」
●
同刻・鳥海山。
「レミエルさんの研究も順調のようですね」
学園からの定時連絡を受け、天魔各陣営へ睨みを効かせる久遠ヶ原学園生徒会長・神楽坂茜は表情を和らげた。
「それに時期を重ねて、レジスタンスも動くそうだ」
茜の護衛を務める青年、岸崎蔵人――久遠ヶ原学園執行部親衛隊総長――は、他方の文書へ目を通している。
「我々の仕事も、大詰めといったところだな。会長も、早く学園へ戻りたいだろう?」
「戻りたくないと言ったら嘘になりますが、私にしかできないことがあるのなら、全うするまでです」
「会長にしかできないことは、他にもある。関東を放置しておくわけにはいかないはずだ」
蔵人は眼光鋭く、茜を見つめる。
「つくばと横浜のゲートですね。ルシフェルは、どう動くでしょうか」
本拠地・洞爺湖ゲートの喉元とも言える札幌を襲われ。
その間にも、関東へ展開した巨大ゲートは着々と成果を挙げている。
北海道へ戻るか? それとも関東へ後押しの進撃をするか?
「戦略的に考えれば、北海道へ退くのが易いと思う。鳥海山を牽制しながら、安全に戻ることができるからな」
茜の問いへ、蔵人は淡々と答える。
人類と多少の小競り合いはあるだろうが、札幌を奪われたところでゲートが落ちるわけではない。
待ち受ける人類側としては、ルシフェルが北へ戻り本気で再度侵攻したなら札幌を守り切るのは難しいだろう。
そのかわり、関東における冥魔勢力への対応は楽になるはずだ。上手くいけば関東から冥魔を叩き出す時間を作れるかもしれない。
「関東への南下を選んだらどうでしょう」
「向かう際に鳥海山と我々へ背中を見せることになる。移動は難儀だろうが、そこさえ切り抜けたなら厄介だな」
より強大な支配地たる関東でエネルギー搾取へ力を入れられたら――関東が天魔に飲まれれば――、人類は終わりだ。
「つくばゲートの主はルシフェルの妻だそうですが……強大な力を持ち、信頼を置く相手なら、任せたままにしておきそうなものですけど」
危険を冒してまで関東へ向かうだろうか、総大将ともあろうものが。
――否、危険ならすでに冒している。拠点を離れ、総大将自らが鳥海山を攻めるという危険を。
「二人の関係がなんであれ、ルシフェルが背後につくと関東ゲートの攻略は困難を極めるな」
「そうですね……。その分、北が手薄になるということですか」
「ああ。いずれにせよ『北の楔』は有効だ」
「『祭器の量産』こそが天魔への対抗の道だとレミエルさんはお話ししていましたね。……今回の戦いは、試金石となるのでしょう」
札幌での戦いは新たなる道を作り、未来に向けて開拓していくことだろう。
(執筆:佐嶋ちよみ)
2016年5月、北国へ短い春が訪れる頃。
北海道・某所。レジスタンスの数あるアジトの一つに、『レジスタンス』数名の構成員と久遠ヶ原からの協力者が集っていた。
「特殊鉱石の採集は順調に進んでいて、『祭器』の強化もほどなく完成するだろうということよ」
レジスタンスリーダーであるミーナ・ヴァルマは、学園からの報告書へ目を通すと仲間たちへ向き直った。
褐色の肌にはめ込まれたライトグリーンの瞳は輝く星のようで、一人一人を力づけるように見つめる。
「こっちも久遠ヶ原の協力のお陰で、札幌周辺の情勢はだいぶ掴めてきた。タイミングを重ね、一斉蜂起だな」
彼女の隣で、虚無僧姿の中年男性――サブリーダーの『オヤジ』が喉の奥で笑い声で続けた。
札幌の奪還。それがレジスタンスの悲願。
「冥魔にエネルギー源として囚われている人々は、支配領域効果を無効化する陣によって解放されるわ。
そのまま札幌を人類側の拠点とすることで敵に対して『楔』としたいけど……冥魔の報復が強力であれば、元の木阿弥になってしまう」
ミーナは言う。
「リザベルとソングレイ……今、北海道に居る強力な二柱を同時に討ってこそ、私たちは存在を認められると思うの」
存在を認める――『脅威』と見なされる。
「これまでは小さな勢力だったから目立つことを避けてきたけれど、今度は違うわ。
力持つ者として向き合うことで、戦いを避けるの。容易に手出しをさせない状態へ運ぶのよ」
「『俺たち』の存在は、今の今まで徹底的にひた隠しにしてきた。独学で習得した技に加え、少しずつ『久遠ヶ原』の知識・技術も吸収し始めている。ソレを、悪魔サンたちは御存知ない。トコトンまで見くびってくれている。勝機はそこだ」
ミーナの言葉を、オヤジが補足する。
「リザベルやソングレイとは直近でも対峙する場面はあったが、幸か不幸か深手を与えるには至ってない。
深手を与えていたなら今回の戦いは楽になったろうし、与えられなかったら向こうはコチラをナメてくる。それはそれで好機だ」
「……それはいいんだがよ」
決戦へ沸きあがる空気の中、部屋の端に居た構成員の一人である青年・レラが眉根を寄せて言葉を挟んだ。
「『祭器』ってのは、誰が扱うんだ? 『広域展開の陣』と『能力上昇の槍』の2つがあるんだろう」
陣は展開までに時間がかかり、光旗槍については相当な熟練者である必要があると聞く。
「『陣』は、私が発動するつもりよ」
「リーダーが? ……危険だ。展開の呪文詠唱中は無防備になると聞いてる」
「私を救ってくれた『レジスタンス』のため……。ここは、頑張らせて?」
案じる仲間へ、ミーナ決意を固めた表情を浮かべた。
堕天使である彼女がレジスタンスに身を寄せ、久遠ヶ原側から表だって存在を認識されていなかったには理由がある……しかしそれはまた、別の話。
「そこまで言うなら……わかった。それじゃあ、『槍』は?」
「愚問だな」
レラの疑問に対し、深編笠の下でオヤジが笑う。
「伊達に古参はしていない。槍の使用条件については、俺が満たしておる」
「はぁああああ?」
「ミーナさんもオヤジさんも、非常に熱心に鍛錬していたんですよ」
二人の間へ、無尽光研究会から派遣されている研究員・千塚が割って入った。
「どちらの祭器も、使用するには無尽光に関する知識・相応の経験が必要です。短期間ながら、お二人はそれぞれを満たされました」
「独学は、私たちの得意分野よ。知識の吸収力に関しては自信があるわ」
千塚へ、ミーナが悪戯っぽく笑う。
「わかった……。リーダーについては承知した。……だがな、オヤジ。あんたは自分の年齢考えろよ、戦場に出るんだぞ!? そんなんで敵に襲われでもしたら――」
「死ぬかも知れんなぁ。……故に、しっかり護れよ?」
「……槍を持ってる間は、気の抜ける尺八も吹けないだろうから丁度いいか……」
「レラったら。でも……そうね。戦いが終わったら、オヤジの尺八の音を聞きたいわ。その為にも、負けられない。
私たちの力は小さなものだけれど、戦うのは私たちだけじゃない。久遠ヶ原学園と協力して、再起を図りましょう!」
●
同刻・鳥海山。
「レミエルさんの研究も順調のようですね」
学園からの定時連絡を受け、天魔各陣営へ睨みを効かせる久遠ヶ原学園生徒会長・神楽坂茜は表情を和らげた。
「それに時期を重ねて、レジスタンスも動くそうだ」
茜の護衛を務める青年、岸崎蔵人――久遠ヶ原学園執行部親衛隊総長――は、他方の文書へ目を通している。
「我々の仕事も、大詰めといったところだな。会長も、早く学園へ戻りたいだろう?」
「戻りたくないと言ったら嘘になりますが、私にしかできないことがあるのなら、全うするまでです」
「会長にしかできないことは、他にもある。関東を放置しておくわけにはいかないはずだ」
蔵人は眼光鋭く、茜を見つめる。
「つくばと横浜のゲートですね。ルシフェルは、どう動くでしょうか」
本拠地・洞爺湖ゲートの喉元とも言える札幌を襲われ。
その間にも、関東へ展開した巨大ゲートは着々と成果を挙げている。
北海道へ戻るか? それとも関東へ後押しの進撃をするか?
「戦略的に考えれば、北海道へ退くのが易いと思う。鳥海山を牽制しながら、安全に戻ることができるからな」
茜の問いへ、蔵人は淡々と答える。
人類と多少の小競り合いはあるだろうが、札幌を奪われたところでゲートが落ちるわけではない。
待ち受ける人類側としては、ルシフェルが北へ戻り本気で再度侵攻したなら札幌を守り切るのは難しいだろう。
そのかわり、関東における冥魔勢力への対応は楽になるはずだ。上手くいけば関東から冥魔を叩き出す時間を作れるかもしれない。
「関東への南下を選んだらどうでしょう」
「向かう際に鳥海山と我々へ背中を見せることになる。移動は難儀だろうが、そこさえ切り抜けたなら厄介だな」
より強大な支配地たる関東でエネルギー搾取へ力を入れられたら――関東が天魔に飲まれれば――、人類は終わりだ。
「つくばゲートの主はルシフェルの妻だそうですが……強大な力を持ち、信頼を置く相手なら、任せたままにしておきそうなものですけど」
危険を冒してまで関東へ向かうだろうか、総大将ともあろうものが。
――否、危険ならすでに冒している。拠点を離れ、総大将自らが鳥海山を攻めるという危険を。
「二人の関係がなんであれ、ルシフェルが背後につくと関東ゲートの攻略は困難を極めるな」
「そうですね……。その分、北が手薄になるということですか」
「ああ。いずれにせよ『北の楔』は有効だ」
「『祭器の量産』こそが天魔への対抗の道だとレミエルさんはお話ししていましたね。……今回の戦いは、試金石となるのでしょう」
札幌での戦いは新たなる道を作り、未来に向けて開拓していくことだろう。
(執筆:佐嶋ちよみ)
4月6日更新分
2016年4月、東北・鳥海山。
祭器『千億星の光旗槍』の使い手はレミエル・N・ヴァイサリスから久遠ヶ原学園生徒会長・神楽坂茜へ交代したが、事態は相変わらず三つ巴の様相を呈していた。
こちらの考えはさすがに天界にも通じているらしく、冥魔が人類へ攻撃の矛先を向ければ天界からの横槍が入る。
冥魔軍が退こうものなら、天・人が共同でその背後を突いて見せる鋭ささえある。
実際にそうするかは別として、『そう思わせる』ことが脅威だ。
人類にしてみれば天・魔が同様の動きを見せるかもしれず、従って三者はその場に縫い止められている。
「……会長、撃退庁は話を飲むだろうか」
「長月司令たちの協力がなければ、今回の作戦は難しいです。それにこれは、決して分の悪い賭けではないと考えています」
久遠ヶ原学園執行部親衛隊総長・岸崎蔵人の問いに、厳しい表情のまま神楽坂茜は応じた。
分の悪すぎる賭け……京都でのことを思うたび、茜の胸にはじわりとした痛みが広がる。
今はとにかく、出来る限りの最善を尽くし、一つ一つの問題をクリアしていくしかない。そう言い聞かせ続けていた。
「珍しいな、学園代表が二人そろって訪れるとは」
撃退庁東北支部の拠点にて、司令・長月 耀は、神楽坂茜と岸崎蔵人を迎え入れた。
ここしばらくの間、戦線を共にするうちに互いの性格はなんとなく把握している。
この戦場で、人類側の鍵である祭器を唯一扱える茜には疲労の色が見て取れる。蔵人は、彼女にとって一騎当千の護衛といったところだろう。
「この度は、貴重な時間を割いてくださりありがとうございます。……長月司令は、北海道のレジスタンスをご存知ですか?」
会議室へ通された濡れ羽髪の娘は、真っ直ぐな瞳で耀を見上げる。
「北海道か。『自発的に地域住民を守る者が居る』程度なら……。レジスタンス?」
「はい。ルシフェルゲートの脅威から人々を守るために暗躍している、名のない組織です」
冥魔の攻撃対象となることを避けるため、ずっと水面下で活動をしてきたのだと。蔵人が説明を補足する。
「組織内には久遠ヶ原学園関係者も居り、秘密裏に連絡を取ってきました。そして今回、2種の祭器の完成とゲート主であるルシフェルが拠点を離れたことから――」
「…………」
「大都市・札幌の奪還に向けて、具体的に動くべしと意見が一致しました」
「…………ほう」
腹の底から低く低く、男は声を絞り出す。予想通りの結論だ。
「つまり……これからは意図的に『現状維持』をせよ、と?」
『札幌を奪還するまで、ルシフェルを東北に縫い止めておけ』ということだ。
(冗談じゃない)
「簡単に言うがなぁ、生徒会長さんよ」
耀は、後頭部に指を差し入れ掻きむしった。
これまでの1ヶ月でさえ、神経をすり減らす日々だった。
現場の対応以外にもやることはある、自分たちがこの拠点に居る間にも東北各地では大小さまざまな事件が起きている。
それをいうなれば、久遠ヶ原の生徒会長たる茜とて同じではないか。いつまでも学園を離れているわけにもいかないはずだ。
「それぁ一体、どれくらいの期間だ。1週間か。1ヶ月か。1年か。札幌は大都市ったってもはや冥魔の領域、奪還したところで再興に時間はかかるだろうし周辺は変わらず冥魔の領域だ。メリットは?」
ゲートのある洞爺湖と札幌とは、そう遠くない。
本気を出した冥魔軍に襲われたら、せっかく奪還したところで水の泡だ。
そうまでして取り返す、その利を耀は問う。
冗談じゃない、と彼は考える。しかし――確かな『利』があるのなら、あともう少し耐えることもやぶさかではない。
歪めた口元に込められたメッセージを正しく受け取り、茜は再び言葉を紡いだ。
●
同刻。北海道某所。
「札幌の奪還は、決して一時の夢まぼろしではありません」
そう熱弁するのは、無尽光研究会研究員・千塚 華。後方には撃退士である弟の千塚 護が立っている。
華の傍らでにこやかに話を聞いているのは久遠ヶ原学園学園長・宝井正博であった。自分も初耳だと言わんばかりの態度である。如何せん、彼は代表者だが専門家ではない。
学園長は北海道の『レジスタンス』への繋ぎ役にすぎない。
学園側3名――学園長、無尽光研究会研究員、撃退士。彼らが通されたのは、レジスタンスが使用している拠点の一つ、コンクリートで囲まれた廃墟。
古めかしい応接セットの向かい側には、褐色の肌に黒髪ロングウェーブの少女と、屈強な肉体を持つ虚無僧が腰を下ろしていた。
実に珍妙な取り合わせであるが、少女が当団体のリーダーであるミーナ・ヴァルマ。虚無僧は補佐を務めており、『オヤジとでも呼んでくれ』と渋い美声で自己紹介を切り上げた。
「『結界の無効化』と『ゲートの無効化・撃退士の能力上昇』。2つの祭器がこの地に揃えば、敵本拠地の領域内であろうと対等に戦うことができ、対等であると知らしめれば無益な戦いが減ります」
喉笛に喰らいついた上で戦闘力を持続し一定以上の迎撃を見せたなら、以降は均衡状態へ持ち込めるだろう。そう、華は語る。黒髪ショートカットにノンフレームの眼鏡が知的に光る。
「……札幌の奪還は、我等の悲願だ」
虚無僧が言う。無駄な美声が深編笠の下から響く。
「彼の地を取り戻し、巻き込まれた罪なき人々を解放できるのなら我らは力を惜しまない」
「私たちだけでは、できることに限界がある……。協力し合えたなら、心強いわ。学園の撃退士の評判は身内からも聞いているの、充分に信用に足るって。もちろん、私もそう感じたわ」
ミーナが学園生と接したのは、つい先日の事だった。それまでの間にも、幾つも情報が寄せられている。
話に聞くと実際に会うとの双方を満たしたことで、ミーナも確信を深めたようだ。
「ありがとうございます」
素っ気なく礼を告げるのは、撃退士の護。
華と護の姉弟もまた、祭器の試用に際し学園生へ協力を仰ぎ成功の結果を持ち帰った経緯がある。彼らにとって久遠ヶ原の撃退士は、同志であり恩人でもあった。
特に、研究員とはいえ華は一般人なのだ。
専門知識を必要とされる局面が安全な地とは限らない。札幌で祭器が本格的に用いられるならば、彼女はこの地に留まることになるだろう。
撃退士とレジスタンスの信頼関係、互いの能力の認識も、深めていく必要がある。
「堂島教授より届けられた、北海道内における地脈情報について研究会でも精査いたしました。祭器の効果範囲、目的地、目的達成後の展望、それらから計算し――……」
札幌奪還戦に向けての話し合いは、それからしばらく続けられた。
●
再び、鳥海山。冥魔陣営。
「はーー。リザベルが、なぁ」
「応援は無用とのことですが」
札幌にて撃退士との接触があったという。
レヴィアタンからの報告を受け、ルシフェルは緊張感のない声を吐き出す。
「そらぁ、アイツならそう言うだろうよ」
女男爵・リザベルの誇り高さは彼も良く良く知っている。
総大将の留守を預かる以上、鉄壁以上の守りを意識しているはずだ。それ故に、他者へ弱いところを見せない。
慎重派の彼女の事だ、万が一の遅れもないだろうけれど、万が一が起きては拙い。
例えば、現在の自分たちのように。
「『祭器』が簡単に量産できるものでも誰にでも扱えるものでもないと思いたいが、油断すりゃあこの通りだ。そうだな――……ソングレイ!」
手勢を頭の中で整理して、最善と思われる一名を呼びつける。
「お呼びですか、ルシフェル様」
赤翼の悪魔旅団長がフラリと姿を見せた。
「お前、ちょっと北海道へ行ってこい」
「……とは?」
娯楽を好む青年悪魔は、唐突な指示ながら、面白いことの始まりかと表情が変わる。
「予想はしてたが、空き巣狙いが出やがった。お前なら、上手いことリザベルをサポートしてやれるな?」
「なるほど、そういうことでしたら」
レヴィアタンは冥界から派遣されているルシフェルの目付け役だ、ここを離れるわけにはいかない。
武人肌のアラドメネクでは、コミュニケーション面でリザベルと上手く折り合いを付けられるか疑問。
マルコシアスは彼女のプライドを華麗に逆撫でしそうである。
「『膠着状態に飽きてきたんで遊びに戻った』あたりでいいでしょうかね。あながち嘘でもない」
黒スーツの胸元をわざとらしく整える旅団長へ、ルシフェルは明るく笑った。
「ああ。祭器のことも、お前ならわかるだろう。まさか向こうにも用意してるとは思わんが、情報の共有は悪いことじゃない」
「承知。向こうも春が近い、羽を伸ばしてきますよ」
かくして、一柱の悪魔が東北から北海道へ舞い戻った。
長い膠着状態が、北海道をも巻き込んで、少しずつ変わり始めようとしている。
(執筆:佐嶋ちよみ)
祭器『千億星の光旗槍』の使い手はレミエル・N・ヴァイサリスから久遠ヶ原学園生徒会長・神楽坂茜へ交代したが、事態は相変わらず三つ巴の様相を呈していた。
こちらの考えはさすがに天界にも通じているらしく、冥魔が人類へ攻撃の矛先を向ければ天界からの横槍が入る。
冥魔軍が退こうものなら、天・人が共同でその背後を突いて見せる鋭ささえある。
実際にそうするかは別として、『そう思わせる』ことが脅威だ。
人類にしてみれば天・魔が同様の動きを見せるかもしれず、従って三者はその場に縫い止められている。
「……会長、撃退庁は話を飲むだろうか」
「長月司令たちの協力がなければ、今回の作戦は難しいです。それにこれは、決して分の悪い賭けではないと考えています」
久遠ヶ原学園執行部親衛隊総長・岸崎蔵人の問いに、厳しい表情のまま神楽坂茜は応じた。
分の悪すぎる賭け……京都でのことを思うたび、茜の胸にはじわりとした痛みが広がる。
今はとにかく、出来る限りの最善を尽くし、一つ一つの問題をクリアしていくしかない。そう言い聞かせ続けていた。
「珍しいな、学園代表が二人そろって訪れるとは」
撃退庁東北支部の拠点にて、司令・長月 耀は、神楽坂茜と岸崎蔵人を迎え入れた。
ここしばらくの間、戦線を共にするうちに互いの性格はなんとなく把握している。
この戦場で、人類側の鍵である祭器を唯一扱える茜には疲労の色が見て取れる。蔵人は、彼女にとって一騎当千の護衛といったところだろう。
「この度は、貴重な時間を割いてくださりありがとうございます。……長月司令は、北海道のレジスタンスをご存知ですか?」
会議室へ通された濡れ羽髪の娘は、真っ直ぐな瞳で耀を見上げる。
「北海道か。『自発的に地域住民を守る者が居る』程度なら……。レジスタンス?」
「はい。ルシフェルゲートの脅威から人々を守るために暗躍している、名のない組織です」
冥魔の攻撃対象となることを避けるため、ずっと水面下で活動をしてきたのだと。蔵人が説明を補足する。
「組織内には久遠ヶ原学園関係者も居り、秘密裏に連絡を取ってきました。そして今回、2種の祭器の完成とゲート主であるルシフェルが拠点を離れたことから――」
「…………」
「大都市・札幌の奪還に向けて、具体的に動くべしと意見が一致しました」
「…………ほう」
腹の底から低く低く、男は声を絞り出す。予想通りの結論だ。
「つまり……これからは意図的に『現状維持』をせよ、と?」
『札幌を奪還するまで、ルシフェルを東北に縫い止めておけ』ということだ。
(冗談じゃない)
「簡単に言うがなぁ、生徒会長さんよ」
耀は、後頭部に指を差し入れ掻きむしった。
これまでの1ヶ月でさえ、神経をすり減らす日々だった。
現場の対応以外にもやることはある、自分たちがこの拠点に居る間にも東北各地では大小さまざまな事件が起きている。
それをいうなれば、久遠ヶ原の生徒会長たる茜とて同じではないか。いつまでも学園を離れているわけにもいかないはずだ。
「それぁ一体、どれくらいの期間だ。1週間か。1ヶ月か。1年か。札幌は大都市ったってもはや冥魔の領域、奪還したところで再興に時間はかかるだろうし周辺は変わらず冥魔の領域だ。メリットは?」
ゲートのある洞爺湖と札幌とは、そう遠くない。
本気を出した冥魔軍に襲われたら、せっかく奪還したところで水の泡だ。
そうまでして取り返す、その利を耀は問う。
冗談じゃない、と彼は考える。しかし――確かな『利』があるのなら、あともう少し耐えることもやぶさかではない。
歪めた口元に込められたメッセージを正しく受け取り、茜は再び言葉を紡いだ。
●
同刻。北海道某所。
「札幌の奪還は、決して一時の夢まぼろしではありません」
そう熱弁するのは、無尽光研究会研究員・千塚 華。後方には撃退士である弟の千塚 護が立っている。
華の傍らでにこやかに話を聞いているのは久遠ヶ原学園学園長・宝井正博であった。自分も初耳だと言わんばかりの態度である。如何せん、彼は代表者だが専門家ではない。
学園長は北海道の『レジスタンス』への繋ぎ役にすぎない。
学園側3名――学園長、無尽光研究会研究員、撃退士。彼らが通されたのは、レジスタンスが使用している拠点の一つ、コンクリートで囲まれた廃墟。
古めかしい応接セットの向かい側には、褐色の肌に黒髪ロングウェーブの少女と、屈強な肉体を持つ虚無僧が腰を下ろしていた。
実に珍妙な取り合わせであるが、少女が当団体のリーダーであるミーナ・ヴァルマ。虚無僧は補佐を務めており、『オヤジとでも呼んでくれ』と渋い美声で自己紹介を切り上げた。
「『結界の無効化』と『ゲートの無効化・撃退士の能力上昇』。2つの祭器がこの地に揃えば、敵本拠地の領域内であろうと対等に戦うことができ、対等であると知らしめれば無益な戦いが減ります」
喉笛に喰らいついた上で戦闘力を持続し一定以上の迎撃を見せたなら、以降は均衡状態へ持ち込めるだろう。そう、華は語る。黒髪ショートカットにノンフレームの眼鏡が知的に光る。
「……札幌の奪還は、我等の悲願だ」
虚無僧が言う。無駄な美声が深編笠の下から響く。
「彼の地を取り戻し、巻き込まれた罪なき人々を解放できるのなら我らは力を惜しまない」
「私たちだけでは、できることに限界がある……。協力し合えたなら、心強いわ。学園の撃退士の評判は身内からも聞いているの、充分に信用に足るって。もちろん、私もそう感じたわ」
ミーナが学園生と接したのは、つい先日の事だった。それまでの間にも、幾つも情報が寄せられている。
話に聞くと実際に会うとの双方を満たしたことで、ミーナも確信を深めたようだ。
「ありがとうございます」
素っ気なく礼を告げるのは、撃退士の護。
華と護の姉弟もまた、祭器の試用に際し学園生へ協力を仰ぎ成功の結果を持ち帰った経緯がある。彼らにとって久遠ヶ原の撃退士は、同志であり恩人でもあった。
特に、研究員とはいえ華は一般人なのだ。
専門知識を必要とされる局面が安全な地とは限らない。札幌で祭器が本格的に用いられるならば、彼女はこの地に留まることになるだろう。
撃退士とレジスタンスの信頼関係、互いの能力の認識も、深めていく必要がある。
「堂島教授より届けられた、北海道内における地脈情報について研究会でも精査いたしました。祭器の効果範囲、目的地、目的達成後の展望、それらから計算し――……」
札幌奪還戦に向けての話し合いは、それからしばらく続けられた。
●
再び、鳥海山。冥魔陣営。
「はーー。リザベルが、なぁ」
「応援は無用とのことですが」
札幌にて撃退士との接触があったという。
レヴィアタンからの報告を受け、ルシフェルは緊張感のない声を吐き出す。
「そらぁ、アイツならそう言うだろうよ」
女男爵・リザベルの誇り高さは彼も良く良く知っている。
総大将の留守を預かる以上、鉄壁以上の守りを意識しているはずだ。それ故に、他者へ弱いところを見せない。
慎重派の彼女の事だ、万が一の遅れもないだろうけれど、万が一が起きては拙い。
例えば、現在の自分たちのように。
「『祭器』が簡単に量産できるものでも誰にでも扱えるものでもないと思いたいが、油断すりゃあこの通りだ。そうだな――……ソングレイ!」
手勢を頭の中で整理して、最善と思われる一名を呼びつける。
「お呼びですか、ルシフェル様」
赤翼の悪魔旅団長がフラリと姿を見せた。
「お前、ちょっと北海道へ行ってこい」
「……とは?」
娯楽を好む青年悪魔は、唐突な指示ながら、面白いことの始まりかと表情が変わる。
「予想はしてたが、空き巣狙いが出やがった。お前なら、上手いことリザベルをサポートしてやれるな?」
「なるほど、そういうことでしたら」
レヴィアタンは冥界から派遣されているルシフェルの目付け役だ、ここを離れるわけにはいかない。
武人肌のアラドメネクでは、コミュニケーション面でリザベルと上手く折り合いを付けられるか疑問。
マルコシアスは彼女のプライドを華麗に逆撫でしそうである。
「『膠着状態に飽きてきたんで遊びに戻った』あたりでいいでしょうかね。あながち嘘でもない」
黒スーツの胸元をわざとらしく整える旅団長へ、ルシフェルは明るく笑った。
「ああ。祭器のことも、お前ならわかるだろう。まさか向こうにも用意してるとは思わんが、情報の共有は悪いことじゃない」
「承知。向こうも春が近い、羽を伸ばしてきますよ」
かくして、一柱の悪魔が東北から北海道へ舞い戻った。
長い膠着状態が、北海道をも巻き込んで、少しずつ変わり始めようとしている。
(執筆:佐嶋ちよみ)
3月4日更新分
●
冥魔連合・地球方面派遣軍の総大将ルシフェルが、拠点を離れ鳥海山を強襲。
そこへ天界・地球派遣軍司令官メタトロンが救援に駆けつけ、撃退士たちの存在からも三者が距離を置いて睨み合いとなる。
前代未聞の均衡から、数日が経過していた。
2016年3月、鳥海山。
メタトロンは未だ、そこに駐留していた。
睨み合いの相手が、他でもないルシフェルである。一度は撤退を促したものの、そこに安堵してメタトロンが離脱するとあれば、今度こそ鳥海山は冥魔に喰われるであろう。
しかしながら、いつまでも駐留するわけにもいかない。
地球派遣軍に課せられた『資源調達』の任は、言葉で発するより重い。
資源たる原住民……『人間』は脅威ではない。それを守ろうと足掻く撃退士も、それほどでもない。
が、付け入ろうとする冥魔は厄介だ。今回のような睨み合い、あるいはこの先に頻発するであろう奪い合い。これはよろしくない。効率を妨げる。
それにもうひとつ、メタトロンにとって懸念することがある。
地球における、ルシフェルの強襲。
天界における、ベリンガム派の凶行。そしてザインエルの離反。
タイミングを見るに切り離して考えることは難しい。
つまり――どこかで、なんらかの形で『情報は漏れていた』と考えるのが自然だろう。
今ここで内通者を炙りだすことに躍起になってもしかたあるまい、そうとも考える。
獅子身中の虫を飼いながら、今の間は逆手に取ればいい。
「メタトロン様。増援の手配が成りました」
「……そうか。トビト、居るか」
「ここに」
サンダルフォンの隣には、既に鳥海山の主・力天使トビトが控えていた。
「私の手勢を、しばし預ける。鳥海山の情勢が安定するまで、そなたの指揮下にあるよう命じてある。相手はルシフェルだ、防備を重ね不測の事態に備えよ」
「かしこまりました。温情、有り難くお受けいたします」
「うむ。……あやつとて、そう長く拠点を空けることはあるまい。私が帰らねばならぬようにな」
軍の長が拠点を空けるとなれば、留守を狙う輩が必ず出てくる。
メタトロンの拠点は熊本である。もし今この間にも【四国】の冥魔が、ルシフェルの動きに呼応したら? 案の定、メフィストフェレスが不穏な動きを見せているとの報告も入ってきている。
単に牽制の見せ掛けだけかもしれないし、本気だとしても、そう簡単に落ちやしないと自負はあるが、何がどう転がるかわからないのが現在だ。
「しかと頼む」
そう言い残し、メタトロンはサンダルフォンを従えて、拠点へと戻っていった。
「護り護り……、か。今は仕方がないね。ただで喰われるつもりもないけど」
見送った後、顔を上げた少年姿の力天使は小悪魔めいた笑みを浮かべるのであった。
●
撃退庁東北支部からは、大部隊が天・魔両者を睨む位置に拠点をひとつ、築いている。
司令である長月 耀は報告書を纏め上げ、深々と息を吐いた。
「……片倉ぁ」
「お疲れ様です、司令。誤字脱字必要事項の抜け落ちが無いか確認の後、撃退庁本部と久遠ヶ原へ転送します」
「…………」
伝えたいことは確かにそれであるが、何かこう、もっとこう。
副司令・片倉 花燐との付き合いは長い、こういう性格だと解かってはいるが。
「しかしまあ、恐ろしいことになったものだな」
大きく伸びをして、耀は言う。
「駆けつけて数日って距離に、地球における冥魔の総大将と天界の総司令がいるとはな……」
久遠ヶ原所属のレミエルが発動した『祭器』の威力もまた、予想以上だった。あの存在があったから、人類も『脅威の一つ』として牽制の役目を果たしていられる。
一戦の後、レミエルは去ったが強い印象を与えさえできれば、脅威というものは持続する。
「副司令!! ここでしたか。あ、司令官おはようございます」
そこへ、慌ただしく部下が駆けつけた。情報収集に、近辺を回っていた者だ。
「……いいけどな。で、何があった」
信頼度が、副司令官より下な気がするのは気のせいか。さておき、耀は話を促す。
「それが…… 今朝方、メタトロンが鳥海山を後にしたという目撃情報が入りまして」
「なんだって!?」
「その代わり鳥海山には大規模な戦力投入が為され、守りを固めているとのこと」
「なるほどな。……片倉、それの提出は少し待ってくれ。追加して報せる」
かくして鳥海山周辺の状況は、程なくして久遠ヶ原へも伝えられることとなる。
東北における睨み合いは、今暫し続きそうだ。
●
久遠ヶ原学園、無尽光研究委員会。
二つの『祭器』を前に、レミエル・N・ヴァイサリスは腕組みをしていた。
祭器の一つ『千億星の光旗槍』については、先の戦いで実戦確認が取れた。
残るはもう一つ。こちらも、学園生への依頼報告より成果は届けられている。
「『ゲート内ペナルティの無効化と能力上昇』、それに『結界の無効化』……。二つが安定化すれば、人間を搾取しようとする天・魔に抗うことができますね」
「そうだな」
報告書を纏めた補佐の言葉に、レミエルは頷きを返す。
『千億星の光旗槍』に関しては使用者の熟練が必要であり簡単には発動できないが、他方は今後のゲート戦で戦況を有利に運んで行けるはず。
「まずは完成した。量産化も追って必要とされる、忙しくなるぞ」
「はい!」
(執筆:佐嶋ちよみ)
冥魔連合・地球方面派遣軍の総大将ルシフェルが、拠点を離れ鳥海山を強襲。
そこへ天界・地球派遣軍司令官メタトロンが救援に駆けつけ、撃退士たちの存在からも三者が距離を置いて睨み合いとなる。
前代未聞の均衡から、数日が経過していた。
2016年3月、鳥海山。
メタトロンは未だ、そこに駐留していた。
睨み合いの相手が、他でもないルシフェルである。一度は撤退を促したものの、そこに安堵してメタトロンが離脱するとあれば、今度こそ鳥海山は冥魔に喰われるであろう。
しかしながら、いつまでも駐留するわけにもいかない。
地球派遣軍に課せられた『資源調達』の任は、言葉で発するより重い。
資源たる原住民……『人間』は脅威ではない。それを守ろうと足掻く撃退士も、それほどでもない。
が、付け入ろうとする冥魔は厄介だ。今回のような睨み合い、あるいはこの先に頻発するであろう奪い合い。これはよろしくない。効率を妨げる。
それにもうひとつ、メタトロンにとって懸念することがある。
地球における、ルシフェルの強襲。
天界における、ベリンガム派の凶行。そしてザインエルの離反。
タイミングを見るに切り離して考えることは難しい。
つまり――どこかで、なんらかの形で『情報は漏れていた』と考えるのが自然だろう。
今ここで内通者を炙りだすことに躍起になってもしかたあるまい、そうとも考える。
獅子身中の虫を飼いながら、今の間は逆手に取ればいい。
「メタトロン様。増援の手配が成りました」
「……そうか。トビト、居るか」
「ここに」
サンダルフォンの隣には、既に鳥海山の主・力天使トビトが控えていた。
「私の手勢を、しばし預ける。鳥海山の情勢が安定するまで、そなたの指揮下にあるよう命じてある。相手はルシフェルだ、防備を重ね不測の事態に備えよ」
「かしこまりました。温情、有り難くお受けいたします」
「うむ。……あやつとて、そう長く拠点を空けることはあるまい。私が帰らねばならぬようにな」
軍の長が拠点を空けるとなれば、留守を狙う輩が必ず出てくる。
メタトロンの拠点は熊本である。もし今この間にも【四国】の冥魔が、ルシフェルの動きに呼応したら? 案の定、メフィストフェレスが不穏な動きを見せているとの報告も入ってきている。
単に牽制の見せ掛けだけかもしれないし、本気だとしても、そう簡単に落ちやしないと自負はあるが、何がどう転がるかわからないのが現在だ。
「しかと頼む」
そう言い残し、メタトロンはサンダルフォンを従えて、拠点へと戻っていった。
「護り護り……、か。今は仕方がないね。ただで喰われるつもりもないけど」
見送った後、顔を上げた少年姿の力天使は小悪魔めいた笑みを浮かべるのであった。
●
撃退庁東北支部からは、大部隊が天・魔両者を睨む位置に拠点をひとつ、築いている。
司令である長月 耀は報告書を纏め上げ、深々と息を吐いた。
「……片倉ぁ」
「お疲れ様です、司令。誤字脱字必要事項の抜け落ちが無いか確認の後、撃退庁本部と久遠ヶ原へ転送します」
「…………」
伝えたいことは確かにそれであるが、何かこう、もっとこう。
副司令・片倉 花燐との付き合いは長い、こういう性格だと解かってはいるが。
「しかしまあ、恐ろしいことになったものだな」
大きく伸びをして、耀は言う。
「駆けつけて数日って距離に、地球における冥魔の総大将と天界の総司令がいるとはな……」
久遠ヶ原所属のレミエルが発動した『祭器』の威力もまた、予想以上だった。あの存在があったから、人類も『脅威の一つ』として牽制の役目を果たしていられる。
一戦の後、レミエルは去ったが強い印象を与えさえできれば、脅威というものは持続する。
「副司令!! ここでしたか。あ、司令官おはようございます」
そこへ、慌ただしく部下が駆けつけた。情報収集に、近辺を回っていた者だ。
「……いいけどな。で、何があった」
信頼度が、副司令官より下な気がするのは気のせいか。さておき、耀は話を促す。
「それが…… 今朝方、メタトロンが鳥海山を後にしたという目撃情報が入りまして」
「なんだって!?」
「その代わり鳥海山には大規模な戦力投入が為され、守りを固めているとのこと」
「なるほどな。……片倉、それの提出は少し待ってくれ。追加して報せる」
かくして鳥海山周辺の状況は、程なくして久遠ヶ原へも伝えられることとなる。
東北における睨み合いは、今暫し続きそうだ。
●
久遠ヶ原学園、無尽光研究委員会。
二つの『祭器』を前に、レミエル・N・ヴァイサリスは腕組みをしていた。
祭器の一つ『千億星の光旗槍』については、先の戦いで実戦確認が取れた。
残るはもう一つ。こちらも、学園生への依頼報告より成果は届けられている。
「『ゲート内ペナルティの無効化と能力上昇』、それに『結界の無効化』……。二つが安定化すれば、人間を搾取しようとする天・魔に抗うことができますね」
「そうだな」
報告書を纏めた補佐の言葉に、レミエルは頷きを返す。
『千億星の光旗槍』に関しては使用者の熟練が必要であり簡単には発動できないが、他方は今後のゲート戦で戦況を有利に運んで行けるはず。
「まずは完成した。量産化も追って必要とされる、忙しくなるぞ」
「はい!」
(執筆:佐嶋ちよみ)
12月21日更新分
天魔と人間という種の間の実力差は隔絶としたものがある。
いや、堕天使やはぐれ悪魔が増加し混血の発現なども鑑みるなら【天界軍と冥魔界軍に対し地球人類側勢力の戦力は】というのが正確だろうか。
まあ要は、天界冥魔界に所属する天魔は強大強靭であり、対する人間及び人間に味方する者達は非力であり脆い、という事である。
確かに、ここ数年で撃退士達は実力を大きく向上させ、中には中級以上の天魔とも渡り合える剛の者達もちらほらと出現し始めていた。
だが、全体を平均して見れば、そして総戦力を見比べれば、やはり圧倒的な差が存在していた。
地球人類側が今日まで存続しえているのは、天界と冥魔界のパワーバランスと、そして両界が【地球に対して本気になっていない】という事が理由であった。
「これでは駄目だ」
地下室の薄闇の中、一見では何処にでもいそうなスーツ姿の柔和な老人――久遠ヶ原学園の産みの親、国際撃退士養成機構の長官、V兵器確立以前より天魔と戦い続けてきた男、『武聖』長野綱正は静かに呟いた。
「いや……正確に言うならば、これ『だけ』では、駄目だ。天使と悪魔に、その複数の並行世界に跨る大戦力の巨大さと分厚さに……この世界は抗いきれない。空を埋めつくが如き万の天使と悪魔の軍勢に抗するには、百の英雄だけでなく、万のつわもの達が必要なのだ。質だけでなく数が必要なのだ」
それを得られなければ、いずれ地球は天魔いずれかに、あるいは両陣営に分割されて――支配されてしまうだろう、と、長野綱正は呟いた。
「せめて、話になるだけの最低限の実力がなければ……家畜ではなく『人として』の……交渉の席にすら、就けん。私達や私達の子供達は、未来永劫、家畜とされてしまう……良くて奴隷だろう」
歴史を紐解けば、同じ人間同士でさえ、そうであった。
「希望はある」
ブロンド碧眼の長身の男が呟いた。天界への反逆者、武聖の戦友、V兵器の産みの親、無尽光研究委員会の長レミエル・N・ヴァイサリス。
「この二種の【祭器】が完成し、量産化され、配備されるようになれば、人類はゲートの支配を退け、天魔と互角、あるいは、互角以上に渡り合う力を手にするだろう」
そう述べる青年の前には光輝く二つの水晶が浮遊していた。
それは奇しくも、ゲートのコアに、よく似ていた。
「だがまだ未完だ。【祭器】を完成させ量産化するには。必要なものがある」
レミエルは言った。
「我々はそれを、集めなければ、ならない」
●
「――祭器?」
ゲートの最奥、地球に派遣されている天界軍の司令官を務める智天使《ケルビム》メタトロンは訝しげに声をあげた。
「は、報告をまとめますと、背約者レミエル・N・ヴァイサリスを長とする無尽光研究委員会なるものらが、あるいは、不遜ながら、神器にも勝る力を持った兵器を作りあげんとしている、と」
メタトロンの机の上に置かれたカップに霊薬入りの茶を注ぎつつ、副官のサンダルフォンは述べた。
すると、
「ふ……は、は、は!」
このうえなく愉快な冗談を聞いた、とでも言うようにケルビムは声をあげて笑った。
「神器に……神の造形物に勝ると?! あのレミエル如きが作り上げるものが?」
「事実であれば、笑い事ではありませぬ」
「私は天界にいた頃のレミエルという男を知っているが、そんな大それたモノを作れる存在ではない――元は単なる一介のアークエンジェル、さらに堕天して弱体化した者だぞ? 例えその後にいかに研鑽を積んだのだとしても”たか”は知れている。杞憂だ」
メタトロンは優雅にカップに口つけせせら笑った。
元は下級天使の上に背約者である男が生み出すものが、神の造形物に勝るなどという事がありえようか?
否である。
断じて否である。
例え血の滲むような努力を積んだ所で無理なものは無理だ。
『理論的に不可能』なのだ。
メタトロンはそう信じており、そしてそれは一般的に事実であった。
この場合、そんな荒唐無稽な話に警戒しているサンダルフォンの方が一般的な天使としては異常だといえる。
堕天使が『神』に勝る――そんな事がありえる筈がない。
「奴が産み出せるものなど、せいぜいヴァイサリス・ウェポンなどという玩具程度なものよ」
「しかし……近頃はその”玩具”の性能は我々にも無視しえぬレベルになってきております。それに、先の秩父においても地球側の地脈への干渉を成功させたのは奴の産み出した介霊符なる符を用いての事です」
「ふむ…………」
副官の言葉にメタトロンは笑みを収めた。
「御前がそこまで言うか……そこまで言うのならば、杞憂だとは思う、思う、が――」
●
冥魔軍地球方面軍・本拠地・洞爺湖のゲートの最深部。
「――そんなに心配だと言うのなら、暇そうな奴を向かわせておけ! 好きにしろ! 止めはせん、予算は出さんがな! それよりそんなバカげた報告でルシフェル様を煩わせるな!! 殺すぞ!!!!」
黒のゴシックドレスに身を包んだ女が叫んだ。
報告にきた悪魔は悲鳴をあげてほうほうの態で御前より逃げさってゆく。
奇しくも天魔両陣営、その報告に対してくだされた結論は、言葉は違えども、ほぼ同じものであった。
「おいおい、可愛い部下をあんまり脅してやるものではない」
玉座で片胡坐をかき肘をついている着流し姿のブロンド男は苦笑した。冥魔連合地球方面軍の総大将、魔界宰相ルシフェルだ。
「ですが、あまりにも馬鹿げた話を持ってくるんですもの」
黒ドレス姿の女――冥界からの魔界宰相への目付け、その副官を務めているレヴィアタンはルシフェルへと振り向き、口を尖らせた。
「俺は細かい事はあまり良く解らんのだがな――」
「腕っ節だけで伸し上がったかたですものね」
「まぁな」
ルシフェルは笑った。しかし、瞳の奥には微かな緊張があった。
「だから聞くんだが、それは、本当に、馬鹿げた話なのか?」
「馬鹿げてます。どう足掻いても堕天使やはぐれ悪魔や人間ごときがそんな物を作り出せる訳がない。蟻が像に勝てますか? 不可能です。それと同じです」
「ふぅん……そうか」
副官の言葉にルシフェルは納得し、そしてその微かな心配を脳味噌から消した。
彼は結構レヴィアを信頼していたし、元よりそんな心配性な性格ではなかったからだ。
そして何より、
「そんな事よりも、例の『あの情報』に対して我々はどう動くべきでしょうか?」
彼の耳にはもっと巨大な、もっと注意を向けるべき情報が届いていたのである。
「『あの情報』か」
ルシフェルは唸った。
「ありえん話ではないな。俺が奴の立場でもそうする」
「野望バリバリですか、目付けの私の前でそれを言いますか」
「奴と俺とでは立場が違うからな。奴は傀儡だが、俺はそうじゃない。理解があり賢く美人な補佐が傍にいて、結構なところ我が意思で自由気侭にやらせて貰っている。だから俺は奴と同じ行動は取らんよ。それくらい解っているだろう?」
「……ええ」
レヴィアタンはなんといえぬ苦虫をかみ殺したような顔で頷いた。
クッと喉を鳴らしてルシフェルは笑うと、
(さぁてどうしたもんか)
思案に耽った。
『天界』というのは多くの並行世界を支配する巨大な勢力である。
その力はルシフェルが所属する魔界、レヴィアタンが所属する冥界、二つを併せてようやく互角――と言いたいがそれでも実際は上をゆかれている。
旧態依然とした硬直した組織の為に動きが鈍いから、無駄が多いから、優秀な才能が階級差に抑えつけられて殺されているから――報告に聞くギメルやザインエルなどというのは最もたる例だろう。ザインエルは突き抜けた武力で階級をあげたが、ギメル・ツァダイは長き時を冷遇され、燻り続けていた。そして、先の秩父で例の事件を起した。ルシフェルの目には、あの事件は天界の階級システムが産み出した錆であると見えていた――なんとか拮抗しているものの、総戦力的には天界側の方が勝っているのだ。
天界は強大である。
しかし強大ではあったが、必ずしも一枚岩ではなかった。冥魔はさらに一枚岩ではないどころではなかったが、それはこの際おいておく。
穏健派と武闘派という二大派閥の対立と軋轢は地球に派遣されている天界軍でさえも良く見られたし、そもそもに天界の主であるベリンガム、この王が大元からして、まっとうな方法で王になったのではなかった。
元をただせば天界はゼウス、という比較的穏健な王が治めていた。
その下には『長老支族《エルダー・トライブス》』と総称される有力一族が十二あり、諸世界を分割統治してさらに下の者達を治め、王の治世を支えていた。
だが長い時の中で、何かの心変わりがあったのか、彼等は次第にゼウスの穏健統治に対して反発を強め、天界統治下外の世界への侵略・拡大政策を訴えるようになったという。
(まあ徐々に力を増していっていた冥魔の圧力は一因ではあろうな)
とルシフェルとしては思う所ではある。
ゼウス王の世の末、当時、王家の傍流の子女である熾天使ベリンガムは若く、力に溢れ、天界最強と謳われる将軍であった。そして血気盛んな男としても名が知られていた――苛烈な侵略・拡大主義者であると。
「我が率いる天界の軍勢は三千世界を制圧する」
とあの男は謳っていた。
そして、そんなベリンガムとは穏健であったゼウス王は対立し、そして殺され、王冠をベリンガムに奪われた。
ベリンガムが王になった。
天界はベリンガムが統治している。
そして、天界はそれまでの崇拝を集めるような穏やかな統治を捨て、ゲートを用いて精神を搾り取る苛烈な侵略・拡張路線を取るようになった。
それほど昔の話ではない。
およそ数十年程度前の話でしかない。
そうして天界が地球での搾取を強めたから、冥魔軍も天界には負けてはられぬとこの地球にやってきたのだ。
表向きは、そういう話だ。
ベリンガムが天界の主であると――
「ケルビム・メタトロンは生粋のエルダー派だ。というよりも、天界の地球派遣軍の首脳部はエルダー派の集まりで大体ができている。王権派は数が少ない……――この前のギメルってのは声に導かれたと言っていたらしいな?」
ルシフェルの声にレヴィアタンは頷く。
「”奴”がついに動くというのならば――それは、地球にいる俺達にとっては、メタトロン達を相手にしている俺達にとっては、またとない大きな好機だろう。相手の混乱に付け込むのは趣味じゃあないんだがな、拮抗状態で動けないというのにはいい加減飽いた。だから、いつでも動ける準備を整えておけ。時節到来となれば、本気でいくぞ」
「…………はっ!」
悪魔の女はブロンドの総大将に敬礼した。
言葉の通り、久しくなかった、このルシフェル軍本軍が本気で仕掛ける戦が、やってくるのかもしれない。
その予感を覚えていたからである。
そう、だから――彼等は【祭器】のことなど、この時にはもうすっかり忘れ去っていたのだった。
(執筆:望月誠司)
いや、堕天使やはぐれ悪魔が増加し混血の発現なども鑑みるなら【天界軍と冥魔界軍に対し地球人類側勢力の戦力は】というのが正確だろうか。
まあ要は、天界冥魔界に所属する天魔は強大強靭であり、対する人間及び人間に味方する者達は非力であり脆い、という事である。
確かに、ここ数年で撃退士達は実力を大きく向上させ、中には中級以上の天魔とも渡り合える剛の者達もちらほらと出現し始めていた。
だが、全体を平均して見れば、そして総戦力を見比べれば、やはり圧倒的な差が存在していた。
地球人類側が今日まで存続しえているのは、天界と冥魔界のパワーバランスと、そして両界が【地球に対して本気になっていない】という事が理由であった。
「これでは駄目だ」
地下室の薄闇の中、一見では何処にでもいそうなスーツ姿の柔和な老人――久遠ヶ原学園の産みの親、国際撃退士養成機構の長官、V兵器確立以前より天魔と戦い続けてきた男、『武聖』長野綱正は静かに呟いた。
「いや……正確に言うならば、これ『だけ』では、駄目だ。天使と悪魔に、その複数の並行世界に跨る大戦力の巨大さと分厚さに……この世界は抗いきれない。空を埋めつくが如き万の天使と悪魔の軍勢に抗するには、百の英雄だけでなく、万のつわもの達が必要なのだ。質だけでなく数が必要なのだ」
それを得られなければ、いずれ地球は天魔いずれかに、あるいは両陣営に分割されて――支配されてしまうだろう、と、長野綱正は呟いた。
「せめて、話になるだけの最低限の実力がなければ……家畜ではなく『人として』の……交渉の席にすら、就けん。私達や私達の子供達は、未来永劫、家畜とされてしまう……良くて奴隷だろう」
歴史を紐解けば、同じ人間同士でさえ、そうであった。
「希望はある」
ブロンド碧眼の長身の男が呟いた。天界への反逆者、武聖の戦友、V兵器の産みの親、無尽光研究委員会の長レミエル・N・ヴァイサリス。
「この二種の【祭器】が完成し、量産化され、配備されるようになれば、人類はゲートの支配を退け、天魔と互角、あるいは、互角以上に渡り合う力を手にするだろう」
そう述べる青年の前には光輝く二つの水晶が浮遊していた。
それは奇しくも、ゲートのコアに、よく似ていた。
「だがまだ未完だ。【祭器】を完成させ量産化するには。必要なものがある」
レミエルは言った。
「我々はそれを、集めなければ、ならない」
●
「――祭器?」
ゲートの最奥、地球に派遣されている天界軍の司令官を務める智天使《ケルビム》メタトロンは訝しげに声をあげた。
「は、報告をまとめますと、背約者レミエル・N・ヴァイサリスを長とする無尽光研究委員会なるものらが、あるいは、不遜ながら、神器にも勝る力を持った兵器を作りあげんとしている、と」
メタトロンの机の上に置かれたカップに霊薬入りの茶を注ぎつつ、副官のサンダルフォンは述べた。
すると、
「ふ……は、は、は!」
このうえなく愉快な冗談を聞いた、とでも言うようにケルビムは声をあげて笑った。
「神器に……神の造形物に勝ると?! あのレミエル如きが作り上げるものが?」
「事実であれば、笑い事ではありませぬ」
「私は天界にいた頃のレミエルという男を知っているが、そんな大それたモノを作れる存在ではない――元は単なる一介のアークエンジェル、さらに堕天して弱体化した者だぞ? 例えその後にいかに研鑽を積んだのだとしても”たか”は知れている。杞憂だ」
メタトロンは優雅にカップに口つけせせら笑った。
元は下級天使の上に背約者である男が生み出すものが、神の造形物に勝るなどという事がありえようか?
否である。
断じて否である。
例え血の滲むような努力を積んだ所で無理なものは無理だ。
『理論的に不可能』なのだ。
メタトロンはそう信じており、そしてそれは一般的に事実であった。
この場合、そんな荒唐無稽な話に警戒しているサンダルフォンの方が一般的な天使としては異常だといえる。
堕天使が『神』に勝る――そんな事がありえる筈がない。
「奴が産み出せるものなど、せいぜいヴァイサリス・ウェポンなどという玩具程度なものよ」
「しかし……近頃はその”玩具”の性能は我々にも無視しえぬレベルになってきております。それに、先の秩父においても地球側の地脈への干渉を成功させたのは奴の産み出した介霊符なる符を用いての事です」
「ふむ…………」
副官の言葉にメタトロンは笑みを収めた。
「御前がそこまで言うか……そこまで言うのならば、杞憂だとは思う、思う、が――」
●
冥魔軍地球方面軍・本拠地・洞爺湖のゲートの最深部。
「――そんなに心配だと言うのなら、暇そうな奴を向かわせておけ! 好きにしろ! 止めはせん、予算は出さんがな! それよりそんなバカげた報告でルシフェル様を煩わせるな!! 殺すぞ!!!!」
黒のゴシックドレスに身を包んだ女が叫んだ。
報告にきた悪魔は悲鳴をあげてほうほうの態で御前より逃げさってゆく。
奇しくも天魔両陣営、その報告に対してくだされた結論は、言葉は違えども、ほぼ同じものであった。
「おいおい、可愛い部下をあんまり脅してやるものではない」
玉座で片胡坐をかき肘をついている着流し姿のブロンド男は苦笑した。冥魔連合地球方面軍の総大将、魔界宰相ルシフェルだ。
「ですが、あまりにも馬鹿げた話を持ってくるんですもの」
黒ドレス姿の女――冥界からの魔界宰相への目付け、その副官を務めているレヴィアタンはルシフェルへと振り向き、口を尖らせた。
「俺は細かい事はあまり良く解らんのだがな――」
「腕っ節だけで伸し上がったかたですものね」
「まぁな」
ルシフェルは笑った。しかし、瞳の奥には微かな緊張があった。
「だから聞くんだが、それは、本当に、馬鹿げた話なのか?」
「馬鹿げてます。どう足掻いても堕天使やはぐれ悪魔や人間ごときがそんな物を作り出せる訳がない。蟻が像に勝てますか? 不可能です。それと同じです」
「ふぅん……そうか」
副官の言葉にルシフェルは納得し、そしてその微かな心配を脳味噌から消した。
彼は結構レヴィアを信頼していたし、元よりそんな心配性な性格ではなかったからだ。
そして何より、
「そんな事よりも、例の『あの情報』に対して我々はどう動くべきでしょうか?」
彼の耳にはもっと巨大な、もっと注意を向けるべき情報が届いていたのである。
「『あの情報』か」
ルシフェルは唸った。
「ありえん話ではないな。俺が奴の立場でもそうする」
「野望バリバリですか、目付けの私の前でそれを言いますか」
「奴と俺とでは立場が違うからな。奴は傀儡だが、俺はそうじゃない。理解があり賢く美人な補佐が傍にいて、結構なところ我が意思で自由気侭にやらせて貰っている。だから俺は奴と同じ行動は取らんよ。それくらい解っているだろう?」
「……ええ」
レヴィアタンはなんといえぬ苦虫をかみ殺したような顔で頷いた。
クッと喉を鳴らしてルシフェルは笑うと、
(さぁてどうしたもんか)
思案に耽った。
『天界』というのは多くの並行世界を支配する巨大な勢力である。
その力はルシフェルが所属する魔界、レヴィアタンが所属する冥界、二つを併せてようやく互角――と言いたいがそれでも実際は上をゆかれている。
旧態依然とした硬直した組織の為に動きが鈍いから、無駄が多いから、優秀な才能が階級差に抑えつけられて殺されているから――報告に聞くギメルやザインエルなどというのは最もたる例だろう。ザインエルは突き抜けた武力で階級をあげたが、ギメル・ツァダイは長き時を冷遇され、燻り続けていた。そして、先の秩父で例の事件を起した。ルシフェルの目には、あの事件は天界の階級システムが産み出した錆であると見えていた――なんとか拮抗しているものの、総戦力的には天界側の方が勝っているのだ。
天界は強大である。
しかし強大ではあったが、必ずしも一枚岩ではなかった。冥魔はさらに一枚岩ではないどころではなかったが、それはこの際おいておく。
穏健派と武闘派という二大派閥の対立と軋轢は地球に派遣されている天界軍でさえも良く見られたし、そもそもに天界の主であるベリンガム、この王が大元からして、まっとうな方法で王になったのではなかった。
元をただせば天界はゼウス、という比較的穏健な王が治めていた。
その下には『長老支族《エルダー・トライブス》』と総称される有力一族が十二あり、諸世界を分割統治してさらに下の者達を治め、王の治世を支えていた。
だが長い時の中で、何かの心変わりがあったのか、彼等は次第にゼウスの穏健統治に対して反発を強め、天界統治下外の世界への侵略・拡大政策を訴えるようになったという。
(まあ徐々に力を増していっていた冥魔の圧力は一因ではあろうな)
とルシフェルとしては思う所ではある。
ゼウス王の世の末、当時、王家の傍流の子女である熾天使ベリンガムは若く、力に溢れ、天界最強と謳われる将軍であった。そして血気盛んな男としても名が知られていた――苛烈な侵略・拡大主義者であると。
「我が率いる天界の軍勢は三千世界を制圧する」
とあの男は謳っていた。
そして、そんなベリンガムとは穏健であったゼウス王は対立し、そして殺され、王冠をベリンガムに奪われた。
ベリンガムが王になった。
天界はベリンガムが統治している。
そして、天界はそれまでの崇拝を集めるような穏やかな統治を捨て、ゲートを用いて精神を搾り取る苛烈な侵略・拡張路線を取るようになった。
それほど昔の話ではない。
およそ数十年程度前の話でしかない。
そうして天界が地球での搾取を強めたから、冥魔軍も天界には負けてはられぬとこの地球にやってきたのだ。
表向きは、そういう話だ。
ベリンガムが天界の主であると――
「ケルビム・メタトロンは生粋のエルダー派だ。というよりも、天界の地球派遣軍の首脳部はエルダー派の集まりで大体ができている。王権派は数が少ない……――この前のギメルってのは声に導かれたと言っていたらしいな?」
ルシフェルの声にレヴィアタンは頷く。
「”奴”がついに動くというのならば――それは、地球にいる俺達にとっては、メタトロン達を相手にしている俺達にとっては、またとない大きな好機だろう。相手の混乱に付け込むのは趣味じゃあないんだがな、拮抗状態で動けないというのにはいい加減飽いた。だから、いつでも動ける準備を整えておけ。時節到来となれば、本気でいくぞ」
「…………はっ!」
悪魔の女はブロンドの総大将に敬礼した。
言葉の通り、久しくなかった、このルシフェル軍本軍が本気で仕掛ける戦が、やってくるのかもしれない。
その予感を覚えていたからである。
そう、だから――彼等は【祭器】のことなど、この時にはもうすっかり忘れ去っていたのだった。
(執筆:望月誠司)
(※タイトルをクリックすると表示/非表示が変更できます)


