|
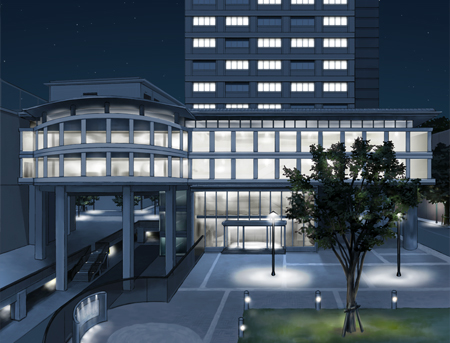 |
みんなの思い出
オープニング
それがディアボロであるなどと、誰が想像できただろう。
雨の日、男が道端で見たのは、『肉の塊』だった。
奇妙という他ないが、他に形容しようがない。微妙にうねうねと蠢き、小動物のような鳴き声さえ出す、白い肉の塊。
見る者が見れば、芋虫のようだ、とも。あるいは動かなければ、変わった形のジャガイモか、とも思うだろう。
『きゅるるる』
両手で抱えられるほどの大きさで、重量にして、おおよそ2kgほどであろうか。成人男性ならば、持ち運びに苦労する荷物ではない。
だが、これを見たとき、一般人としてはどう行動するべきであろうか。警察に一報するか、無視して通り過ぎるのが普通であろう。だが、彼はそんな無難な対応を取ることを許されなかった。
――持って、帰ろう。
そう。これに出会った時点で、他の選択肢はない。
なぜなら、アレはディアボロであるから。一目見た瞬間から、男は肉の塊に魅了されていた。
どうしてか、何ゆえかは全く分からないが、持って帰りたくなる衝動に突き動かされ、男は肉を自宅へと持ち帰る。
男は家で、料理の準備を始めていた。言うまでもなく、拾った肉を調理するためだ。
下ごしらえはしない。ただフライパンを取り出して、焼くだけだ。
――なんて、美味そうな肉なんだろう。
食いたい。貪りたい。そうした衝動に突き動かされている。それでも調理と言う行為をはさむのは、男に一抹の理性が残っているからか。
焼きあがる間も、肉は蠢いていた。時には鳴き声さえ出していたのに、彼にとっては食欲を刺激するものでしかなかった。
そして焼きあがり、皿に盛り付けると、手づかみで丸かじりしたい衝動をこらえながら、フォークを突き刺して食らった。
当然、口に入れて消化して終わり、ということはない。
「う、うぐ……」
肉塊を胃に収めた瞬間、男は胸を押さえて苦しみ出した。
「あが、ががが……ッ」
痛むのは胸だけではない。腹、下半身、そして喉元まで登ってくるような熱い痛みが、彼の身をさいなむ。
「ぐぇろぉぉぉぉぉぉ――ッ!」
吐き出した、のではない。断末魔、である。
正しく、男は死んでいる。死因は肉塊。それも肥大化した白い肉の塊が、男の腹を突き破るほどの勢いで飛び出て、また喉からは顎が外れるほど大きな塊として、排出された。
あまりに、男の体内ではしゃぎすぎたからであろうか。肉塊はばらばらに裂け、分裂していたが、それぞれが意志を持つように動いている。どうにも、この状態でも活動には支障がないらしい。
『きゅるるる』
しかし、バラバラになったとしても、発見当時とは大きさも、重量も、今や比べ物にならぬ。まるで男の体を食って成長したかのようである。
分裂した肉塊は、集結、結合し一体となって、人間大ほどの塊となっていた。
家の壁を、体をうねらせて打ち砕き、外へ出る。そして蛆虫が這い進むように、あるいはムカデがうぞうぞと床をはいずるように、不気味な肉は新たな犠牲者を求めていくのだ。
そして肉は自ら苗床を見出して、操り、体積を増やすのだ。おそらく、限界まで。
――この限界とは、どれほどの大きさを意味するのか? もし際限がないとしたら? まさに、悪魔と言う他ない。
救いといえば、隠密性をまったく考えていないらしいことか。人目を気にせず動いている様子で、無差別に人を襲っていく。これでは秘匿性などないようなものであり、早晩、討伐隊が組織されるであろう。
……被害はすでに出ている。あるいは、これからも出続ける可能性がある。
言うまでもないが、撃退士は、自らが犠牲とならぬよう、心掛けねばならない。もし万が一、この肉に撃退士が食われるようなことがあれば、それはどれほどの成長を促すことか、まったく予測がつかないからだ。
雨の日、男が道端で見たのは、『肉の塊』だった。
奇妙という他ないが、他に形容しようがない。微妙にうねうねと蠢き、小動物のような鳴き声さえ出す、白い肉の塊。
見る者が見れば、芋虫のようだ、とも。あるいは動かなければ、変わった形のジャガイモか、とも思うだろう。
『きゅるるる』
両手で抱えられるほどの大きさで、重量にして、おおよそ2kgほどであろうか。成人男性ならば、持ち運びに苦労する荷物ではない。
だが、これを見たとき、一般人としてはどう行動するべきであろうか。警察に一報するか、無視して通り過ぎるのが普通であろう。だが、彼はそんな無難な対応を取ることを許されなかった。
――持って、帰ろう。
そう。これに出会った時点で、他の選択肢はない。
なぜなら、アレはディアボロであるから。一目見た瞬間から、男は肉の塊に魅了されていた。
どうしてか、何ゆえかは全く分からないが、持って帰りたくなる衝動に突き動かされ、男は肉を自宅へと持ち帰る。
男は家で、料理の準備を始めていた。言うまでもなく、拾った肉を調理するためだ。
下ごしらえはしない。ただフライパンを取り出して、焼くだけだ。
――なんて、美味そうな肉なんだろう。
食いたい。貪りたい。そうした衝動に突き動かされている。それでも調理と言う行為をはさむのは、男に一抹の理性が残っているからか。
焼きあがる間も、肉は蠢いていた。時には鳴き声さえ出していたのに、彼にとっては食欲を刺激するものでしかなかった。
そして焼きあがり、皿に盛り付けると、手づかみで丸かじりしたい衝動をこらえながら、フォークを突き刺して食らった。
当然、口に入れて消化して終わり、ということはない。
「う、うぐ……」
肉塊を胃に収めた瞬間、男は胸を押さえて苦しみ出した。
「あが、ががが……ッ」
痛むのは胸だけではない。腹、下半身、そして喉元まで登ってくるような熱い痛みが、彼の身をさいなむ。
「ぐぇろぉぉぉぉぉぉ――ッ!」
吐き出した、のではない。断末魔、である。
正しく、男は死んでいる。死因は肉塊。それも肥大化した白い肉の塊が、男の腹を突き破るほどの勢いで飛び出て、また喉からは顎が外れるほど大きな塊として、排出された。
あまりに、男の体内ではしゃぎすぎたからであろうか。肉塊はばらばらに裂け、分裂していたが、それぞれが意志を持つように動いている。どうにも、この状態でも活動には支障がないらしい。
『きゅるるる』
しかし、バラバラになったとしても、発見当時とは大きさも、重量も、今や比べ物にならぬ。まるで男の体を食って成長したかのようである。
分裂した肉塊は、集結、結合し一体となって、人間大ほどの塊となっていた。
家の壁を、体をうねらせて打ち砕き、外へ出る。そして蛆虫が這い進むように、あるいはムカデがうぞうぞと床をはいずるように、不気味な肉は新たな犠牲者を求めていくのだ。
そして肉は自ら苗床を見出して、操り、体積を増やすのだ。おそらく、限界まで。
――この限界とは、どれほどの大きさを意味するのか? もし際限がないとしたら? まさに、悪魔と言う他ない。
救いといえば、隠密性をまったく考えていないらしいことか。人目を気にせず動いている様子で、無差別に人を襲っていく。これでは秘匿性などないようなものであり、早晩、討伐隊が組織されるであろう。
……被害はすでに出ている。あるいは、これからも出続ける可能性がある。
言うまでもないが、撃退士は、自らが犠牲とならぬよう、心掛けねばならない。もし万が一、この肉に撃退士が食われるようなことがあれば、それはどれほどの成長を促すことか、まったく予測がつかないからだ。
リプレイ本文
戦場を前にして、もっとも強く緊張しているのは、デニス・トールマン(jb2314)であった。
というのも、彼は大規模戦闘による負傷が癒えないまま、出撃を余儀なくされたからだ。
「痛ててて……クソッ、アラドメネクの野郎め。こんなザマで依頼に参加することになっちまうとは」
緊張の所以は、自らが直接戦闘に関われず、仲間を守ることが出来ない為だ。己の命を惜しんでの事ではない、という辺りが彼らしい。
「だが嘆いてても仕方無ェ、少ねェが出来る事をやるしか無ェな。後はアイツらを信じてやる事か……ヘッ、無事を信じて待つなんて、ガキの頃以来だな」
戦闘地外周に射程が届く範囲で、屋根の上など戦闘地を見渡せる高い場所に陣取る。
実際に支援が行き届くかどうかは、戦況次第であろう。が、他に術はない。
「まるでB級ホラーに出てくるようなヤツだな、こりゃ」
センスが古い、とテト・シュタイナー(ja9202)はうんざりした顔で言った。
ここからでも敵は見える。デニスはすでに離れた位置だが、他の全員は包囲を敷くため、正面から迎え撃つ必要があった。
「これで、少しはマシになるかね?」
鳴き声対策に耳栓をした。これで聴覚からの情報はあてに出来ないが、いくらかは効果が見込めるだろう。
「正気度喪失1D6/1D20、て所か」
鴉乃宮 歌音(ja0427)が、TRPGに例えて言った。神話生物が如きディアボロは、ただの人間を狂気に堕とすには十分。
しかし、ここまで大きいと恐怖より笑いの方が来る、というのが彼の正直な感想だった。
「これ以上、犠牲者を増やさせはしない」
遠石 一千風(jb3845)は、生理的な嫌悪感を堪えながら、敵を見ていた。
彼女も耳栓をしているが、戦闘時の連携に支障をきたさぬよう、仲間との間でハンドサインを決めていた。これで少なくとも、攻撃のパートナーであるテトとは真っ当な連携が出来るだろう。
『宜しくね。私が前で切り裂くわ』という意志を、試しにハンドサインで伝えてみる。テトは『了解』とサインで返した。
「同士討ちだけはしたくないっすね」
虎守 恭飛虎(jb3956)は正直だった。普段は気弱な彼だが、今回は積極的に行動するつもりである。重視すべきは敵の討伐より味方の安否。特に今回は、重傷の仲間がいるのだ。意識せずにはいれらない。
「でかい肉だなァオイ」
御神島 夜羽(jb5977)が気楽に言う。彼に緊張はない。食ったら美味そうだ、などと思える程度には余裕もある。
その余裕を羨ましそうに見ていたのは、鬼一 凰賢(jb5988)。彼の方は、嫌悪感で胸がいっぱいだった。
「これ、気持ち悪い。おー、これ、嫌い」
彼は知略を以て組み伏せる、絡め手の戦術を得意とする。が、今回はそれほど高度な知略は必要なかった。つまり思考に余裕が出来てしまっている。
その余裕で敵を観察すると、どうしても気持ち悪さが込み上げてきてしまうのだ。これを食欲に昇華できる夜羽を羨むのは、当然といえた。
「人食い肉塊、ですか。なんともまぁ、同胞達は何を考えてこんなもの作ったんでしょうね」
突撃の瞬間を目の前にして、百瀬 莉凛(jb6004)は無感動に言い放った。私も人間を食い物にする、という意味では彼女もある種同類と言えるのだが、莉凛は自分の方がよほどエレガントだと思っている。
「ともかく、被害は少なからず出ているようですし、きっちり駆除しないと」
彼女の言葉に、同感だと応える仲間達。そして、敵が戦場の広場に突入、これをもって開戦とする。
デニスを除く、七人による包囲。単に巨大なだけの敵であるなら、充分な包囲網を敷けることだろう。
だが、相手は分裂する可能性を秘めている。泥沼の乱戦になってしまえば、この程度の方位など意味をなさなくなる。
「文字通りに、一片たりとも残さねぇよ。覚悟しやがれ!」
テトはそれを理解していた。一千風の援護を行える位置に付きながら、敵を包囲網の中心に追い込んで逃がさない様に意識する。
耳栓をしている以上、彼女の声は意気込み以上の意味を持たない。だが、高い士気の発露と思えば、これもまた開戦の狼煙としては悪くないだろう。
事前のハンドサインに従って、一千風が切り込んだ。テトがそれを支援するのは当然だが、戦闘は二人だけで行うものではない。他の仲間達も、当然それに続く。
『きゅるるる、きゅるるるる――』
そして確定の流れとして、敵もまたこちらを知覚する。獲物が近づいてくる事を理解した肉塊は、まずはその鳴き声をもってして撃退士の魅了を狙った。
「同士討ちだけは、したくないんすよねぇ」
恭飛虎は、敵が鳴き声による魅了を図った事を理解していた。肉塊に口があって、それを震わせた、と言う訳ではないのだが――。
こちらが接近し、敵が待ち受けると言う態勢になっている以上、それは定石と言ってよい。
「愛の囁きでもしてくれてるのかしら? 貴方みたいな醜い化物からのなんて、どちらにしろお断りだけどね♪」
莉凛は、そうつぶやくほどの余裕まであった。耳栓の効果と言うべきか、ともあれこの時点で魅了された仲間はいない。効果が単体であるということも、有利に働いた。
「すまねェが、あのデカブツは頼んだ。もっとも、そこまで心配はして無ェけどな!」
そしてデニスの堅実防御が支援に入り、攻勢準備は完了した。まず配置についた遠距離支援の者達から、牽制の射撃が入る。そして――。
「胴体は『太い』。一撃だけなら、何とか――」
一千風が近接し、最も太い胴体を剣で削るように切りつける。分裂しなかった事を確認して後、テトの支援射撃が直撃した。
身もだえする肉塊は、そのまま次の射撃の的となり、傷と赤い血にまみれた。なぜ、血が赤いのかなどと、場違いな感想を思いつつ、歌音は『猟兵』による射撃を行う。
敵陣深く入り込み、火力によって敵を滅する兵。歌音の姿は、まさにそれであった。彼は敵が『個体が分裂する』のではなく、『複数が合体している』と捉えており、その認識に則って、射撃も全体にまんべんなくばらまいている。
「ちょいと火力に乏しいっすけど、やるだけやります。トドメはお任せするっすよ」
【忍刀・血霞】を鞘に入れたまま、殴打するように恭飛虎が殴りかかった。痛打である。
これでひるんでくれれば、という思いもむなしく、肉塊は元気にうねり、彼にそのまま跳ね返るように飛んでくる。
「――やッ、ばかった……あ」
避けられたのは僥倖であり、たまたま運が良かっただけだと本人は自覚していた。当たれば、ただでは済まぬ。敵はいまだに一塊であり、重量に不足はなく――その分だけ、攻撃力も高い。
やや動きが鈍重だが、攻撃の瞬発力は侮ると痛い目を見るだろう。恭飛虎は背中に冷や汗が流れるのを自覚した。
「肉は焼くモンだよなァオイ!」
「分裂、させる、ない」
そして敵の攻撃後の隙を狙って、夜羽と凰賢が支援射撃を行う。光と炎が肉を焦がし、また塊が躍動し、うねりよがる。
これを莉凛は興奮するような視線で見ていた。嗜虐嗜好に目覚めた、とは言わぬ。ただ大きな肉の塊が、まるで感情を持つように痛み、苦しむ情景を見て、何かしら扇情的なものを感じたのだろう。
「間近で見ると……やっぱり大きい。これは楽しめそうです♪」
行うことは白夜珠による射撃であり、これもまた敵を分裂させるほどの衝撃は生み出さない。ここまでの巨体に育ったのが祟ったのか、よほど大きな一撃を受けない限り、分裂する可能性は高くない様子である。
もっとも、それは現状に限った話であり、本人が自身の意志で切り離せるなら話は別であろう。ただ、ここまで来てそれをしないということは、まだ必要性を感じていないのかもしれない。
「ん……?」
近接攻撃に専念していた一千風は、どうしてか、自分が熱っぽくなった気がした。まるで風邪でも引いたかのように。
もし、彼女が耳栓をしていなければ、敵の鳴き声を聞いたであろう。そして周囲の仲間も、それを察したであろう。
しかし、現実として彼女は魅了されながら自覚せず、そしてまた仲間もこの瞬間には理解し得なかった。
「うう……おいし、そう?」
耳が良い者ならば、彼女の異様な声にも、即座に反応できたであろう。それもまた、不運といえば不運であった。対策はあくまで軽減程度であり、魅了そのものを無効化することは出来なかったのだ。
『武器を握りしめたまま』ふらふらと肉塊に手を伸ばす。そして衝動的に引き起こされた食欲を満たすために、この魅惑の肉塊を手ごろな大きさにしようと斬り裂く。結果、二つに肉塊は分裂された。
しかし、ハンドサインを準備していたのが、せめてもの僥倖と言うべきか。一千風は事前にそれを決めようと言い出すほどの慎重な人物である。合図なしに敵の分断を行うなど、ありえなかった。
「一千風、おい! ……ええい、鬱陶しい! 食えもしない肉が増えたって、嬉しくはねぇっての!」
彼女の異変に真っ先に気付いたのは、当然ながら彼女のパートナーのテトであった。あってほしくない現実に、顔が青ざめる。
「こんな肉に魅了されても嬉しくはねーだろ? 早く目を覚ませ!」
声をかけるが、それだけで魅了が消えるはずもない。ともあれテトは分裂した肉塊を狙って撃つ。
「切って分裂するってーのならな。その分裂体を速攻で焼き切ればいいだけの話だ!」
融蝕炎珠。圧縮された炎の塊が、高熱を発し肉を焼いた。まるで溶解したかのような焦げ痕を与え、肉塊は血肉を一部焼失した。
「クソッ…! 気付いてくれ!」
次に一千風の異変に気付いたのは、遠くから戦場を睥睨していたデニス。発煙手榴弾を投げて異常を知らせた。
敵は分裂したといえど、手に負えないほど増えた訳ではない。なのにこの時点で投擲されたということは、異変が生じた証拠。全員がそれを感じ、一考の後にテトと同じ結論に至る。
「ハァイ、ステキなおじ様♪ ……なんて、おどけてる暇はないかしら」
莉凛はテトに続いて追撃。焦げ痕の残った肉を『炎焼』にてさらに焼き焦がす。
ことここに至っては、敵も遠くのデニスを気にしている余裕はあるまい。魅了された一千風は気がかりであるが、これは集中攻撃の機会が出来たと言えなくもなかった。
「分裂、させる、ない」
「おっそろしいんで、気をつけていきますよっと」
凰賢が、炎による火力の集中攻撃を行った。前述の効果からも見て、敵に炎が有効なのは明らかである。ここは徹底して敵の弱点をつくべきだった。
そして恭飛虎はサイドステップによる攻撃を行い、流し切るように忍刀で抜き打ち、後に一足で左に跳んだ。ヒットアンドアウェイ、その見本である。
「オイオイ、正気に戻れっての。……頼むぜ」
夜羽は待機して一千風に備えた。また魅了されて妙な動きをするようなら、軽く攻撃して止めるつもりである。彼がその役目を負っている事は誰もが知っていたから、乱れなく攻勢を続けられたのである。
「仲間の腹から肉が飛び出す光景は、流石に見たくねェからなァ」
恐るるべきはそれであった。彼としては、こんな場末の戦場で仲間の死など見たくない。ならばこその、当然の用心だった。
まったく彼にとっても、誰にとっても喜ばしい事に、彼の備えは杞憂に終わる。ここで、一千風が正気に戻ったのだ。
「は。……あ、え?」
正気に戻った瞬間、彼女は飛びさって頭を振る。周囲を見やり、状況を把握した。敵は二つに分裂しているが、一つは息も絶え絶えの瀕死であり、一方はまだ健在なるも、周囲の味方がそれで被害を受けた様子は見られなかった。
安心し、次にテトのハンドサインを確認し、申し訳なく思いつつも素直に感謝した。
「ありがとう、ございます。……ご迷惑を」
『急いで攻撃を続けろ、自分が援護する』……テトはそう言っていた。
その意志をくみ、彼女は気を取り直して攻撃を再開した。不覚は取らぬと、己に言い聞かせて。
一方は炎によって消滅し、残りも攻撃を受け続けたせいか、しぼんできている。戦いの終わりは近い。
「『蠢きたる闇の落とし子、浄化の光を抱いて滅せよ』」
歌音がとどめとばかりに、『修道士』の光を掲げ、打ち出した。闇を払うその一撃を最後に、肉塊は沈黙した。
これで何事もなく敵が消滅してくれれば、万々歳であったものだが――早々たやすくは終わってくれないのが、ディアボロのいやらしさであろうか。
致死の一撃を食らうや否や、まるで風船が割れるかのように肉塊が弾け、戦場にその欠片を散らばらせた。あわよくば、これで一片でも逃し、再起するつもりなのであろう。
ともあれ、本格的な戦闘は終わったと言ってよい。後は戦後処理も同然である。
「どの道、鴉の餌にもならんから消し炭確定なのだが」
歌音は、肉塊が弾けた直後でも冷静に行動した。消滅するまで油断せず火炎放射で焼いていく。事前情報から、僅かでも生き残れば、喰らわせてまた増えるのは確定であったから。
「ったく、食欲が失せる相手だったぜ」
「……耳が痛いです」
テトが黙々と肉片を焼いていく。一千風は、魅了されたとはいえ食欲を見せた以上、何とも言い難い気分である。
「ここで見逃すようなヘマはさらさねぇよ。――せめて、な」
デニスは高所から見下ろす形で、狙撃によって肉片の処理を行う。重傷は負っているが、目まで悪くなった訳ではない。隅々まで捜索し、見落とさぬ心積もりであった。
「食べられたがり、お前、運、いい。炎流蛇、焔の蛇。喰らい飲み込み、焼き溶かす」
「きっちり駆除しないと。反応は悪くありませんでしたけど、貴方、美しくありませんでしたわよ」
凰賢と莉凛が、一番大きな肉片を処理したのを最後に、敵の姿は確認できなくなった。全て滅したと考えてよいだろう。
「最後にもう一度取り残しが無いか確認しますよ、っと」
恭飛虎は、敵の逃走など最初から許さないつもりであるから、改めて徹底して捜索を行った。結果、見落としはなし。……数日の経過を見れば、彼らの仕事が完璧であった事は証明されるはずだ。
「まぁ美味そうではあったなァ♪」
作業を終了した所で、夜羽は気楽にもそう述べた。それを呆れながらも、仕事を果たした事を誇りながら、撃退士たちはその場を去っていった。
そして数日後も肉塊の被害は報告されず、依頼は大成功とみなされた。被害者の冥福を祈りつつ、斡旋所の職員は書類を決裁した。そしてこの事件は過去の物となったのである。
というのも、彼は大規模戦闘による負傷が癒えないまま、出撃を余儀なくされたからだ。
「痛ててて……クソッ、アラドメネクの野郎め。こんなザマで依頼に参加することになっちまうとは」
緊張の所以は、自らが直接戦闘に関われず、仲間を守ることが出来ない為だ。己の命を惜しんでの事ではない、という辺りが彼らしい。
「だが嘆いてても仕方無ェ、少ねェが出来る事をやるしか無ェな。後はアイツらを信じてやる事か……ヘッ、無事を信じて待つなんて、ガキの頃以来だな」
戦闘地外周に射程が届く範囲で、屋根の上など戦闘地を見渡せる高い場所に陣取る。
実際に支援が行き届くかどうかは、戦況次第であろう。が、他に術はない。
「まるでB級ホラーに出てくるようなヤツだな、こりゃ」
センスが古い、とテト・シュタイナー(ja9202)はうんざりした顔で言った。
ここからでも敵は見える。デニスはすでに離れた位置だが、他の全員は包囲を敷くため、正面から迎え撃つ必要があった。
「これで、少しはマシになるかね?」
鳴き声対策に耳栓をした。これで聴覚からの情報はあてに出来ないが、いくらかは効果が見込めるだろう。
「正気度喪失1D6/1D20、て所か」
鴉乃宮 歌音(ja0427)が、TRPGに例えて言った。神話生物が如きディアボロは、ただの人間を狂気に堕とすには十分。
しかし、ここまで大きいと恐怖より笑いの方が来る、というのが彼の正直な感想だった。
「これ以上、犠牲者を増やさせはしない」
遠石 一千風(jb3845)は、生理的な嫌悪感を堪えながら、敵を見ていた。
彼女も耳栓をしているが、戦闘時の連携に支障をきたさぬよう、仲間との間でハンドサインを決めていた。これで少なくとも、攻撃のパートナーであるテトとは真っ当な連携が出来るだろう。
『宜しくね。私が前で切り裂くわ』という意志を、試しにハンドサインで伝えてみる。テトは『了解』とサインで返した。
「同士討ちだけはしたくないっすね」
虎守 恭飛虎(jb3956)は正直だった。普段は気弱な彼だが、今回は積極的に行動するつもりである。重視すべきは敵の討伐より味方の安否。特に今回は、重傷の仲間がいるのだ。意識せずにはいれらない。
「でかい肉だなァオイ」
御神島 夜羽(jb5977)が気楽に言う。彼に緊張はない。食ったら美味そうだ、などと思える程度には余裕もある。
その余裕を羨ましそうに見ていたのは、鬼一 凰賢(jb5988)。彼の方は、嫌悪感で胸がいっぱいだった。
「これ、気持ち悪い。おー、これ、嫌い」
彼は知略を以て組み伏せる、絡め手の戦術を得意とする。が、今回はそれほど高度な知略は必要なかった。つまり思考に余裕が出来てしまっている。
その余裕で敵を観察すると、どうしても気持ち悪さが込み上げてきてしまうのだ。これを食欲に昇華できる夜羽を羨むのは、当然といえた。
「人食い肉塊、ですか。なんともまぁ、同胞達は何を考えてこんなもの作ったんでしょうね」
突撃の瞬間を目の前にして、百瀬 莉凛(jb6004)は無感動に言い放った。私も人間を食い物にする、という意味では彼女もある種同類と言えるのだが、莉凛は自分の方がよほどエレガントだと思っている。
「ともかく、被害は少なからず出ているようですし、きっちり駆除しないと」
彼女の言葉に、同感だと応える仲間達。そして、敵が戦場の広場に突入、これをもって開戦とする。
デニスを除く、七人による包囲。単に巨大なだけの敵であるなら、充分な包囲網を敷けることだろう。
だが、相手は分裂する可能性を秘めている。泥沼の乱戦になってしまえば、この程度の方位など意味をなさなくなる。
「文字通りに、一片たりとも残さねぇよ。覚悟しやがれ!」
テトはそれを理解していた。一千風の援護を行える位置に付きながら、敵を包囲網の中心に追い込んで逃がさない様に意識する。
耳栓をしている以上、彼女の声は意気込み以上の意味を持たない。だが、高い士気の発露と思えば、これもまた開戦の狼煙としては悪くないだろう。
事前のハンドサインに従って、一千風が切り込んだ。テトがそれを支援するのは当然だが、戦闘は二人だけで行うものではない。他の仲間達も、当然それに続く。
『きゅるるる、きゅるるるる――』
そして確定の流れとして、敵もまたこちらを知覚する。獲物が近づいてくる事を理解した肉塊は、まずはその鳴き声をもってして撃退士の魅了を狙った。
「同士討ちだけは、したくないんすよねぇ」
恭飛虎は、敵が鳴き声による魅了を図った事を理解していた。肉塊に口があって、それを震わせた、と言う訳ではないのだが――。
こちらが接近し、敵が待ち受けると言う態勢になっている以上、それは定石と言ってよい。
「愛の囁きでもしてくれてるのかしら? 貴方みたいな醜い化物からのなんて、どちらにしろお断りだけどね♪」
莉凛は、そうつぶやくほどの余裕まであった。耳栓の効果と言うべきか、ともあれこの時点で魅了された仲間はいない。効果が単体であるということも、有利に働いた。
「すまねェが、あのデカブツは頼んだ。もっとも、そこまで心配はして無ェけどな!」
そしてデニスの堅実防御が支援に入り、攻勢準備は完了した。まず配置についた遠距離支援の者達から、牽制の射撃が入る。そして――。
「胴体は『太い』。一撃だけなら、何とか――」
一千風が近接し、最も太い胴体を剣で削るように切りつける。分裂しなかった事を確認して後、テトの支援射撃が直撃した。
身もだえする肉塊は、そのまま次の射撃の的となり、傷と赤い血にまみれた。なぜ、血が赤いのかなどと、場違いな感想を思いつつ、歌音は『猟兵』による射撃を行う。
敵陣深く入り込み、火力によって敵を滅する兵。歌音の姿は、まさにそれであった。彼は敵が『個体が分裂する』のではなく、『複数が合体している』と捉えており、その認識に則って、射撃も全体にまんべんなくばらまいている。
「ちょいと火力に乏しいっすけど、やるだけやります。トドメはお任せするっすよ」
【忍刀・血霞】を鞘に入れたまま、殴打するように恭飛虎が殴りかかった。痛打である。
これでひるんでくれれば、という思いもむなしく、肉塊は元気にうねり、彼にそのまま跳ね返るように飛んでくる。
「――やッ、ばかった……あ」
避けられたのは僥倖であり、たまたま運が良かっただけだと本人は自覚していた。当たれば、ただでは済まぬ。敵はいまだに一塊であり、重量に不足はなく――その分だけ、攻撃力も高い。
やや動きが鈍重だが、攻撃の瞬発力は侮ると痛い目を見るだろう。恭飛虎は背中に冷や汗が流れるのを自覚した。
「肉は焼くモンだよなァオイ!」
「分裂、させる、ない」
そして敵の攻撃後の隙を狙って、夜羽と凰賢が支援射撃を行う。光と炎が肉を焦がし、また塊が躍動し、うねりよがる。
これを莉凛は興奮するような視線で見ていた。嗜虐嗜好に目覚めた、とは言わぬ。ただ大きな肉の塊が、まるで感情を持つように痛み、苦しむ情景を見て、何かしら扇情的なものを感じたのだろう。
「間近で見ると……やっぱり大きい。これは楽しめそうです♪」
行うことは白夜珠による射撃であり、これもまた敵を分裂させるほどの衝撃は生み出さない。ここまでの巨体に育ったのが祟ったのか、よほど大きな一撃を受けない限り、分裂する可能性は高くない様子である。
もっとも、それは現状に限った話であり、本人が自身の意志で切り離せるなら話は別であろう。ただ、ここまで来てそれをしないということは、まだ必要性を感じていないのかもしれない。
「ん……?」
近接攻撃に専念していた一千風は、どうしてか、自分が熱っぽくなった気がした。まるで風邪でも引いたかのように。
もし、彼女が耳栓をしていなければ、敵の鳴き声を聞いたであろう。そして周囲の仲間も、それを察したであろう。
しかし、現実として彼女は魅了されながら自覚せず、そしてまた仲間もこの瞬間には理解し得なかった。
「うう……おいし、そう?」
耳が良い者ならば、彼女の異様な声にも、即座に反応できたであろう。それもまた、不運といえば不運であった。対策はあくまで軽減程度であり、魅了そのものを無効化することは出来なかったのだ。
『武器を握りしめたまま』ふらふらと肉塊に手を伸ばす。そして衝動的に引き起こされた食欲を満たすために、この魅惑の肉塊を手ごろな大きさにしようと斬り裂く。結果、二つに肉塊は分裂された。
しかし、ハンドサインを準備していたのが、せめてもの僥倖と言うべきか。一千風は事前にそれを決めようと言い出すほどの慎重な人物である。合図なしに敵の分断を行うなど、ありえなかった。
「一千風、おい! ……ええい、鬱陶しい! 食えもしない肉が増えたって、嬉しくはねぇっての!」
彼女の異変に真っ先に気付いたのは、当然ながら彼女のパートナーのテトであった。あってほしくない現実に、顔が青ざめる。
「こんな肉に魅了されても嬉しくはねーだろ? 早く目を覚ませ!」
声をかけるが、それだけで魅了が消えるはずもない。ともあれテトは分裂した肉塊を狙って撃つ。
「切って分裂するってーのならな。その分裂体を速攻で焼き切ればいいだけの話だ!」
融蝕炎珠。圧縮された炎の塊が、高熱を発し肉を焼いた。まるで溶解したかのような焦げ痕を与え、肉塊は血肉を一部焼失した。
「クソッ…! 気付いてくれ!」
次に一千風の異変に気付いたのは、遠くから戦場を睥睨していたデニス。発煙手榴弾を投げて異常を知らせた。
敵は分裂したといえど、手に負えないほど増えた訳ではない。なのにこの時点で投擲されたということは、異変が生じた証拠。全員がそれを感じ、一考の後にテトと同じ結論に至る。
「ハァイ、ステキなおじ様♪ ……なんて、おどけてる暇はないかしら」
莉凛はテトに続いて追撃。焦げ痕の残った肉を『炎焼』にてさらに焼き焦がす。
ことここに至っては、敵も遠くのデニスを気にしている余裕はあるまい。魅了された一千風は気がかりであるが、これは集中攻撃の機会が出来たと言えなくもなかった。
「分裂、させる、ない」
「おっそろしいんで、気をつけていきますよっと」
凰賢が、炎による火力の集中攻撃を行った。前述の効果からも見て、敵に炎が有効なのは明らかである。ここは徹底して敵の弱点をつくべきだった。
そして恭飛虎はサイドステップによる攻撃を行い、流し切るように忍刀で抜き打ち、後に一足で左に跳んだ。ヒットアンドアウェイ、その見本である。
「オイオイ、正気に戻れっての。……頼むぜ」
夜羽は待機して一千風に備えた。また魅了されて妙な動きをするようなら、軽く攻撃して止めるつもりである。彼がその役目を負っている事は誰もが知っていたから、乱れなく攻勢を続けられたのである。
「仲間の腹から肉が飛び出す光景は、流石に見たくねェからなァ」
恐るるべきはそれであった。彼としては、こんな場末の戦場で仲間の死など見たくない。ならばこその、当然の用心だった。
まったく彼にとっても、誰にとっても喜ばしい事に、彼の備えは杞憂に終わる。ここで、一千風が正気に戻ったのだ。
「は。……あ、え?」
正気に戻った瞬間、彼女は飛びさって頭を振る。周囲を見やり、状況を把握した。敵は二つに分裂しているが、一つは息も絶え絶えの瀕死であり、一方はまだ健在なるも、周囲の味方がそれで被害を受けた様子は見られなかった。
安心し、次にテトのハンドサインを確認し、申し訳なく思いつつも素直に感謝した。
「ありがとう、ございます。……ご迷惑を」
『急いで攻撃を続けろ、自分が援護する』……テトはそう言っていた。
その意志をくみ、彼女は気を取り直して攻撃を再開した。不覚は取らぬと、己に言い聞かせて。
一方は炎によって消滅し、残りも攻撃を受け続けたせいか、しぼんできている。戦いの終わりは近い。
「『蠢きたる闇の落とし子、浄化の光を抱いて滅せよ』」
歌音がとどめとばかりに、『修道士』の光を掲げ、打ち出した。闇を払うその一撃を最後に、肉塊は沈黙した。
これで何事もなく敵が消滅してくれれば、万々歳であったものだが――早々たやすくは終わってくれないのが、ディアボロのいやらしさであろうか。
致死の一撃を食らうや否や、まるで風船が割れるかのように肉塊が弾け、戦場にその欠片を散らばらせた。あわよくば、これで一片でも逃し、再起するつもりなのであろう。
ともあれ、本格的な戦闘は終わったと言ってよい。後は戦後処理も同然である。
「どの道、鴉の餌にもならんから消し炭確定なのだが」
歌音は、肉塊が弾けた直後でも冷静に行動した。消滅するまで油断せず火炎放射で焼いていく。事前情報から、僅かでも生き残れば、喰らわせてまた増えるのは確定であったから。
「ったく、食欲が失せる相手だったぜ」
「……耳が痛いです」
テトが黙々と肉片を焼いていく。一千風は、魅了されたとはいえ食欲を見せた以上、何とも言い難い気分である。
「ここで見逃すようなヘマはさらさねぇよ。――せめて、な」
デニスは高所から見下ろす形で、狙撃によって肉片の処理を行う。重傷は負っているが、目まで悪くなった訳ではない。隅々まで捜索し、見落とさぬ心積もりであった。
「食べられたがり、お前、運、いい。炎流蛇、焔の蛇。喰らい飲み込み、焼き溶かす」
「きっちり駆除しないと。反応は悪くありませんでしたけど、貴方、美しくありませんでしたわよ」
凰賢と莉凛が、一番大きな肉片を処理したのを最後に、敵の姿は確認できなくなった。全て滅したと考えてよいだろう。
「最後にもう一度取り残しが無いか確認しますよ、っと」
恭飛虎は、敵の逃走など最初から許さないつもりであるから、改めて徹底して捜索を行った。結果、見落としはなし。……数日の経過を見れば、彼らの仕事が完璧であった事は証明されるはずだ。
「まぁ美味そうではあったなァ♪」
作業を終了した所で、夜羽は気楽にもそう述べた。それを呆れながらも、仕事を果たした事を誇りながら、撃退士たちはその場を去っていった。
そして数日後も肉塊の被害は報告されず、依頼は大成功とみなされた。被害者の冥福を祈りつつ、斡旋所の職員は書類を決裁した。そしてこの事件は過去の物となったのである。
依頼結果
| 依頼成功度:大成功 |
| MVP: − |
| 重体: − |
| 面白かった!:5人 |
| ドクタークロウ・ 鴉乃宮 歌音(ja0427) 卒業 男 インフィルトレイター |
爆発は芸術だ!・ テト・シュタイナー(ja9202) 大学部5年18組 女 ダアト |
||
| 紫電を纏いし者・ デニス・トールマン(jb2314) 大学部8年262組 男 ディバインナイト |
絶望を踏み越えしもの・ 遠石 一千風(jb3845) 大学部2年2組 女 阿修羅 |
||
| 怒涛の反駁者・ 虎守 恭飛虎(jb3956) 大学部4年203組 男 阿修羅 |
能力者・ 御神島 夜羽(jb5977) 大学部8年18組 男 アカシックレコーダー:タイプB |
||
| 撃退士・ 鬼一 凰賢(jb5988) 大学部4年91組 男 アカシックレコーダー:タイプB |
V兵器探究者・ 百瀬 莉凛(jb6004) 大学部3年88組 女 アカシックレコーダー:タイプB |
||

