|
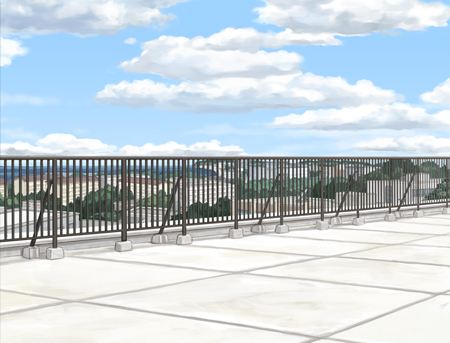 |
みんなの思い出
オープニング
その美術館では、西洋の武具、特に甲冑と刀剣を展示する催しが行われていた。
およそ一ヶ月に渡って展示されるそれら、西洋の武の象徴たちは、当時の文化や闘争に興味を持つ人々によく鑑賞され、評判となっている。
「あれ、動いた?」
「何?」
「――ほら、あれ。あの全身鎧、見て」
入場客の視線の先には、鉄の全身鎧があった。中世の騎士が身にまとうような甲冑で、総重量は相当な重さになるだろう。いわゆる、プレートアーマーと呼ばれる種類のものだが――。
「うん?」
「ほら。……おかしくない?」
鉄の擦れる音と共に、甲冑の手が動いていた。何かを確かめるように、握り、開く動作を繰り返す。
「中に、誰か入っているのかな?」
その動作を見た者たちは、どうにも不可思議に思ったが、それが危険につながるとは考えていなかった。美術館の方に問い合わせが相次いだので、怪しい甲冑の再点検を行ったが、そのときは何も異常は認められず――何かしらの勘違いということになった。
そして、翌日。今度動いたのは、手だけでは済まなかった。
なかに何も入っていないはずの甲冑が動き出し、展示会場を歩き回ったのだ。
「なんかのイベント?」
「でも、様子がおかしいような……?」
阻霊陣を展開していれば、おそらく甲冑の中に潜むものに、気づいていたであろう。だが、昨日の時点で失念していたために、このような奇妙な出来事が起こった。
そして、動き回る甲冑が6体を数えるようになって、ようやく事態の異常さに、美術館側が気づいた。
観客の避難を呼びかける放送が鳴ったのと、甲冑たちが不穏な行動を起こすのは、ほぼ同時であった。
西洋甲冑たちは、思い思いに展示されていた得物(両手剣、斧など)をもぎ取ると、周囲への被害も構わず振り回した。まるで、使い心地を確かめるかのように。
――結果として人的な被害こそ出なかったものの、展示会はこれで続けられなくなった。現在、西洋甲冑たちは、展示会の会場で動き回っている。
奇妙なのは、互いに得物を打ち合い、試合をするような行動を取っていること。それでも型通りの決まった動きをしているような、無味乾燥な動きであるが、奇妙なことに変わりはない。
阻霊陣を展開してみると、どうにも鎧の内部に黒い影が見える。それが甲冑たちを操っているのは間違いない。
今のところ、これらが館外に出る様子はないが、いつ外へ出て人々に危害を加えるかわからない。放置など、到底できるものではなかった。
斡旋所への依頼が受理され、討伐が開始されるまで、この物騒な展示物は互の武を競い合うのだろう。
どれほど物好きな悪魔が、これを仕掛けたのかは知らぬ。目的さえも測れないが――ともかく撃退士たちがすべきことは、甲冑どもを再び、物言わぬ鉄塊にすることである。
およそ一ヶ月に渡って展示されるそれら、西洋の武の象徴たちは、当時の文化や闘争に興味を持つ人々によく鑑賞され、評判となっている。
「あれ、動いた?」
「何?」
「――ほら、あれ。あの全身鎧、見て」
入場客の視線の先には、鉄の全身鎧があった。中世の騎士が身にまとうような甲冑で、総重量は相当な重さになるだろう。いわゆる、プレートアーマーと呼ばれる種類のものだが――。
「うん?」
「ほら。……おかしくない?」
鉄の擦れる音と共に、甲冑の手が動いていた。何かを確かめるように、握り、開く動作を繰り返す。
「中に、誰か入っているのかな?」
その動作を見た者たちは、どうにも不可思議に思ったが、それが危険につながるとは考えていなかった。美術館の方に問い合わせが相次いだので、怪しい甲冑の再点検を行ったが、そのときは何も異常は認められず――何かしらの勘違いということになった。
そして、翌日。今度動いたのは、手だけでは済まなかった。
なかに何も入っていないはずの甲冑が動き出し、展示会場を歩き回ったのだ。
「なんかのイベント?」
「でも、様子がおかしいような……?」
阻霊陣を展開していれば、おそらく甲冑の中に潜むものに、気づいていたであろう。だが、昨日の時点で失念していたために、このような奇妙な出来事が起こった。
そして、動き回る甲冑が6体を数えるようになって、ようやく事態の異常さに、美術館側が気づいた。
観客の避難を呼びかける放送が鳴ったのと、甲冑たちが不穏な行動を起こすのは、ほぼ同時であった。
西洋甲冑たちは、思い思いに展示されていた得物(両手剣、斧など)をもぎ取ると、周囲への被害も構わず振り回した。まるで、使い心地を確かめるかのように。
――結果として人的な被害こそ出なかったものの、展示会はこれで続けられなくなった。現在、西洋甲冑たちは、展示会の会場で動き回っている。
奇妙なのは、互いに得物を打ち合い、試合をするような行動を取っていること。それでも型通りの決まった動きをしているような、無味乾燥な動きであるが、奇妙なことに変わりはない。
阻霊陣を展開してみると、どうにも鎧の内部に黒い影が見える。それが甲冑たちを操っているのは間違いない。
今のところ、これらが館外に出る様子はないが、いつ外へ出て人々に危害を加えるかわからない。放置など、到底できるものではなかった。
斡旋所への依頼が受理され、討伐が開始されるまで、この物騒な展示物は互の武を競い合うのだろう。
どれほど物好きな悪魔が、これを仕掛けたのかは知らぬ。目的さえも測れないが――ともかく撃退士たちがすべきことは、甲冑どもを再び、物言わぬ鉄塊にすることである。
リプレイ本文
戦場に臨むまでに、準備を整えるのは当然のことだ。よって、事前に敵の動きを観察し、行動パターンを探るというのも、当然準備のうちに含まれる。
「入った途端に接敵したのでは、班分けの意味がないですからね。――よく観察して、時期を見定めないと」
封鎖された会場の入口。その隙間から、彩・ギネヴィア・パラダイン(ja0173)は敵を覗いていた。
最初は慎重に伺っていたが、どうも相手は会場内のことしか知覚できないらしい。いくらかバリケードをどけて、しっかりと相手を視認できるほど視覚を広げても、歩き回る西洋甲冑どもは反応しない。
「美術館での戦闘だなんて、本当に面倒臭いわね」
月臣 朔羅(ja0820)は柱や登れそうな展示物を見つけて登り、敵の動きの規則性を把握しようと試みた。
――際どいところであったが、これは成功した。彼女だけであれば失敗したかもしれないが、一人で偵察しているわけではないのだ。敵の動きを見張っていれば、隙を見て移動しながら、敵の反応を伺うこともできる。
戦闘中、どちらかの班が挟撃を受けそうな時は即座に警告――という試みも、己の手数を減らすことを選べるのなら、おそらく可能であろう。
「ばらけている上に、動きには規則性があるみたい。上手く各個撃破しましょ」
「そうだね。多分上手くいく。……常識的に考えて、隙だらけなんだ。何の意味があるんだろう。天魔って、時々訳分からない事するよね。文字通り『人智を超えた』って感じの」
朔羅の言葉に、桐原 雅(ja1822)はそう答えた。意味は分からないが、現れたならそれを速やかに処理するのが、撃退士としての仕事である。
「でも、被害者が出てない事には感謝しなくちゃだね。暴れだしたりする前に、さっさと退治しちゃおう」
「久々の依頼だ、腕がなるぜ! ……館長さんは諦めてるみたいだが、展示品は出来る限り破壊しないように注意したい所だな」
金鞍 馬頭鬼(ja2735)が、戦いを前にして心構えを説いた。
敵を殲滅するのは大前提だが、戦場は元々展示会の会場であったことをかんがみるべきだ。展示品への被害は、少ないに越したことはない。
「展示物を考慮するなら、戦い方も考えないと。まあ、展示物といってもアレらは別だ。美術品と取るなら冒涜的使い方だが、武具と取るなら全うな使い方でもある。まあ所有者から強奪した時点で全うも何もないが」
アイリス・レイバルド(jb1510)は、美術館の地図と監視カメラの映像を見直しながら言った。他の仲間の情報と照らし合わせても、敵の行動に規則性がある事は間違いない。
動き回る西洋甲冑――しかもこれから戦いに臨むとなれば、武具としては本望とも言えるのだろう。だがこういう形で散らせるのは、武具としてはともかく、美術品としては惜しくもある。
ミズカ・カゲツ(jb5543)は無言で準備をしていた。彼女は皆の方針の下に、やるべきことをやるだろう。
「西洋甲冑……かっこいい……」
水無月 ヒロ(jb5185)は、美術品としての武具に興味津々な様子だった。すぐにみとれている己を自覚して頭を振ったが、ああした中世の古美術に憧れを抱くのは、少年としてはごく真っ当な感性である。
「みんな、がんばろーねっ!」
ヒロの元気の良い挨拶に、皆も意気よく応えた。事前の準備というなら、こうした元気の良さで勢いをつけるというのも、一手である。撃退士たちは、十分に準備を整えたと言って良いであろう。
「ま、実際、けったいなやっちゃなぁ。何がしたいんやろか? ――案外、なんも考えとらんかったりしてな」
ゼロ=シュバイツァー(jb7501)の疑問には、誰も確かには答えられなかったが、本人もこの手の疑問に納得など期待していない。
結局、理解しがたいのだ。感性が違い、価値観が違う。自分たちの敵が、そうした手合いなのだと、そういう意味での理解しか、やはり出来ないのだ。
戦いに入る前の準備は入念で、緻密であったと言える。――が、戦闘そのものは単純なものとなった。敵が歩き回るパターンは既に読んでいたし、攻撃を仕掛けるタイミングも、全員の意思が統一されているため、ほぼ最善の形で挟撃できる。
最初の一体目は、好条件が重なったこともあり、二班の連携によって仕留めることになった。初撃で一体倒せれば、後の展開が楽になると踏んでのことだ。
「多少の知能はあっても、知識の蓄積がない。そうした手合いを積ませるのは、容易いものです」
彩は壁走りで敵の背後に回り、正面の味方と連携して攻撃していた。展示物や地形を利用すれば、回り込んで敵を翻弄するのも難しくない。ましてや敵は経験がない。思いもよらぬ戦術を取られれば、対応が遅れるのも当然であろう。
「関節部の装甲が薄いのは定番よね。そうでないと動き難いもの」
朔羅の射撃が、敵を狙い撃つ。回り込んだ相手に敵が対応しようとすると、そのスキを狙って援護射撃が放たれるのだ。
つまり、ここに各個撃破が成り立つ。数が多い分、一体一体を手早く始末するのが定石だが、それを的確にこなすのは言葉で言うほど容易くない。
――で、あるにもかかわらず、順調に行っているのは、敵が悪いのかこちらが巧妙なのか。それは結果が物語るであろう。
「今のところ、そんなに動きは良くないみたいだね。一気に間合いを詰めるよ!」
雅は前衛としての役目を全うしていた。敵を引きつけ、近接戦闘に持ち込み、味方への被害を抑える。
攻撃を身に受けるリスクはあるが、一人で戦っているわけではないのだ。仲間の援護がある限り、彼女が前に出ることを恐ることはない。
そして与えた一撃が、ついに鋼の外装を大きく打ち砕いた。甲冑が大きな被害を受ければ、中身のディアボロの反応が予想されていた。果たしてそれは確かに、ディアボロであったのだろう。
もはや透過させる意味さえ忘れたのか、ディアボロは内部の姿をさらけ出した。
「何かと思えば、ただの化物か。いや、想定外の相手でなかったのは幸運だった」
化物、怪物、と言って良いのだろう。鎧の中にギチギチに収まっていたのは、筋張った肉塊のようでもあり、ある種の遺骸の集合体のようでもあった。
目があり、口があり、空洞がある。そして触手があり、剥き出しになった部分から生えるように伸びていた。ありていに言って醜い悪魔のような造形だが、撃退士にとっては珍しい手合いではない。
鎧がなくなった以上、ダメージはそのまま敵を直撃するだろう。これは撃破の好機でもあった。
「合わせてくれ! この場で倒せれば――」
「被害を抑えられる――な。さあ、その甲冑姿は実に窮屈そうだな。今、楽にしてやろう」
馬頭鬼の声にアイリスが答えた。馬頭鬼の攻撃に合わせて、アイリスの黒死鬼焔晶が放たれる。虹色の光を帯びたフルカスサイスが、胴体を断つ。一瞬遅れて黒い爆炎が肉塊の全身を焼き払い、黒焦げた鉄くずのみが残された。
「次! 近くまで来てるよ、警戒して!」
ヒロの声掛けに全員が反応した。まだ五体残っている。気を抜ける状況ではないのだから、即座に体勢を立て直す必要があった。
彼が警戒していればこそ、攻撃も集中できたと言える。そしてヒロが仕事をこなせた以上、スムーズに事が運ぶのは当然の結果であったろう。
「続けていくで!」
ゼロが先頭に立って、A班が近づいてきた甲冑に仕掛ける。
そしてA班が挟撃を受けないように、B班は背後に当たりそうな別の敵を対処するのだ。
「中身が人間じゃないなら、意外な動きをしてくるかも。――B班! 庇護の翼で出来る部分はカバーリングする!」
雅の言葉に、B班の者たちは頷きながらも、フォローは忘れなかった。撃退士たちは運命共同体であり、協力して目的を達成するもの。
その意識を皆が等しく持っている限り、誰一人として負担を一方的に背負うことなど、ありはしないのだ――。
二班がさらに一体ずつ、甲冑をなぎ倒した。残りは三体。ここまで戦ってきて、わかったことがある。
「事前に偵察していたのが、ここで効いていますね。剣技の型が決まっているなら、動きを先読みできる。結果、形にハメやすい」
「同感、順調だね。最後まで、上手くはまってくれればいいんだけど」
彩がつぶやくと、雅もそれに同意した。ヒロは周囲を警戒しつつ、次の敵を見定めていた。
「次は、アレですね。長剣と短剣の二刀流――たしか、長剣が攻撃用で、短剣が防御用、でしたっけ」
「そう。まあ、どちらにせよ、近接攻撃しかできない相手です。同じように処理してしまえばよろしいかと」
ミズカがぶっきらぼうに答えた。実際、これでうまく回っている以上、やり方を変える必要はないだろう。
彩が展示品の武器をとり、甲冑の前に立って甲冑と同じ型を示して手合わせを求めて注意を引く。すると、相手はこれに答えるように構え、向かってくるのだ。動きを誘導するのも、容易かろうというものである。
もう一方では、ゼロがなぎ倒した甲冑の中身をよく検分していた。まだ敵とは距離があり、待ち構えていられる状況であるから、許されることである。
「さて、鎧の中身はなんじゃろなってか?」
すでに戦闘に際して、中身の様子は伺えているが――実際に間近でいじくりまわしてみると、別のものが見える。
「憑依型やったり、何かしらの自我のある幽鬼型やもしれんと思うとったけど、ホンマにただの肉の塊みたいやな。――合体して面倒なことになるっちゅう結果は、危惧せんでもええかもしれん」
面倒な系統の悪魔ではない。それだけでも朗報であった。もっとも、驚異であるかどうかといえば、そもそも律儀に剣術の型にはまった動きしかしない時点で、恐るべき敵ではないと彼は思っている。
そうして、また新たな敵を迎える。余裕を持って、手招きするような余裕さえ、こちらにはあった。
「儀礼を重んじてたら俺の相手は務まらんよ? 俺、型にはまらん悪魔やねん」
「動きが単調だぞ? そら、私と視線を合わせた、己の迂闊を呪え」
ゼロが不敵な言葉とともに甲冑の攻撃をいなし、アイリスがその隙につけ込んで攻める。
戦いが長引くほど、敵の戦闘スタイルはあらわになり、それを全員が常に情報共有し、行動パターンを把握していくのだ。
撃退士側が難なく敵をあしらっていくのに比べ、敵は経験を蓄積出来るだけの知能がないのか、一定の行動に終始し、それを破られ続けて不利になっていく。
「その鎧を砕けば中身を蒸し焼きに出来るが、鉄の塊と私の一撃ならどちらの方が強いかな?」
「余裕を持つのはいいが、油断だけはしないように。――油断大敵、ですよ」
「……まさに。心しておこう、淑女的にな」
馬頭鬼の諌めを、アイリスは素直に受け入れた。淑女として、常に己を省み、他者の目を意識して優雅に振舞うことを忘れてはならぬ。
馬頭鬼は自身の言葉が届いたことに安堵しつつも、気合を入れて敵に向かう。といっても、単なる力押しではない。忍法「胡蝶」による敵の朦朧を狙う戦術は、確かに味方の役に立っていた。
「足を潰すわ。そこで仕留めて」
「応!」
「任せよ」
「行くでぇ!」
朔羅が甲冑の膝を打ち抜いたのが、合図となり、攻撃が集中。――有効な反撃すら行うこと叶わず、軽微な傷を与えるだけでそのディアボロは沈んだ。
同時期に、B班も一体を倒しており、これで倒した敵は合計五体。残りは一体となった。これまでの動き通りなら、まっすぐこちらに向かってくるはず――だが。
「ん?」
「あれ?」
ゼロがまず違和感に気づき、次にヒロが気づいた。最後の一体は、足を止めて構えを取ったまま、出方を伺っている。これまでに見られない動きであった。
右手に剣を、左手に盾を。それだけならば、他の敵と大きく変わらないが――ここで足を止めるなど、パターンにそっていない。これだけには明確な意志が宿っているのではないかと、つい怪しんだ。
ゼロは敵に知識の共有がないか、常に警戒していたこと。ヒロは自身に課した役割から、攻撃よりも敵の観察と防御に重点を置いていたから気づけたことだった。
「行動パターン変化! ちょい待ち、合流しようや」
「みんな、こっちに合流しよう!」
二人の呼び掛けで、撃退士たちは一箇所に集まり、隊形を組み直した。最後の一体であるから、攻撃を効率的に集中するためにも、この行為は必要なことである。
しかし、それを全く意識していなかったら、惰性のまま敵に向かっていたかもしれず、それは結果として非効率な戦闘に繋がり、展示物への被害に繋がったかもしれない。
とすれば、彼らの働きは最後の詰めとして、良い結果をもたらしたと言えるだろう。
牽制に放った銃弾が盾にはじかれ、半ば展示物を狙うような大振りの剣撃が、最後に撃退士たちの手を焼かせたが――。
順調に勝ちを重ねてきた撃退士たちに、余力は十分ある。よってこれまでの過程に従って、毛色の変わった甲冑悪魔は形にハメられるように、無難にすり潰されたのであった。
全員が、展示物の被害を考えて動いたからだろう。極力戦闘を行う範囲を限定して、フォローも行いつつ戦った。そうしたおかげか、展示物への損害は軽微にとどまった。
美術館の館長と職員から感謝を受けて、撃退士たちも誇らしい気持ちでいっぱいになった。
「展示物への被害は最初から抑えるつもりだったけど、うまくいってよかったね」
雅は本当に喜ばしいようで、終始笑顔であった。自分の怪我がそれで多少増えても、たとえ修復できる程度であっても、やっぱり無事であって欲しいから――という思いが、滲み出ている。
「戦闘終了。では怪我人は前に出ろ、治療の時間だ」
アイリスは味方の傷を癒し、お互いの功を労った。彼女も彼らも痛みで怯むような手合いではないが、ここで治せる傷なら直したほうがいいに違いない。
「確認確認っと。隠れて後で出てくるっちゅうんは、ナシにしといてや」
ゼロは、戦闘終了後も他の展示物に紛れてないか、散らかった現場の掃除も兼ねて入念に確認していた。言葉の調子は軽いが、行動はあくまで慎重そのもの。奇襲を受けぬよう立ち位置を考慮しながら探る。
全て調べ終えるまで、彼は気を張り詰めていた。だから、というわけでもないが。
「ほい、そこ! 遊んどらんで片付けぇや」
「はいぃ! すいません!」
「……ま、気を抜きたくなるのもわかる。でもな、流石にソレはどーなんや自分」
ヒロは展示会場を掃除する傍ら、内緒で西洋甲冑をかぶろうとしていた。出来れば、甲冑で剣を取り闘いたいほどの思いがあるのだろう。
それはロマンだ――と、ゼロは理解してやりたいのだが、勝って甲を緒を締めよとも言う。年長者として、注意せずにはおれなかった。
滞りなく後始末が終わると、様々な思いを残して撃退士たちはこの場を後にした。彷徨い歩く甲冑どもは、もはやない。
あとに残るのは、鉄の残骸だけだった。
依頼結果
| 依頼成功度:大成功 |
| MVP: − |
| 重体: − |
| 面白かった!:5人 |
| 撃退士・ 彩・ギネヴィア・パラダイン(ja0173) 大学部6年319組 女 鬼道忍軍 |
 |
封影百手・ 月臣 朔羅(ja0820) 卒業 女 鬼道忍軍 |
|
 |
戦場を駆けし光翼の戦乙女・ 桐原 雅(ja1822) 大学部3年286組 女 阿修羅 |
 |
撃退士・ 金鞍 馬頭鬼(ja2735) 大学部6年75組 男 アーティスト |
| 深淵を開くもの・ アイリス・レイバルド(jb1510) 大学部4年147組 女 アストラルヴァンガード |
優しき心を胸に、その先へ・ 水無月 ヒロ(jb5185) 大学部3年117組 男 ルインズブレイド |
||
| 銀狐の絆【瑞】・ ミズカ・カゲツ(jb5543) 大学部3年304組 女 阿修羅 |
縛られない風へ・ ゼロ=シュバイツァー(jb7501) 卒業 男 阿修羅 |
||

