|
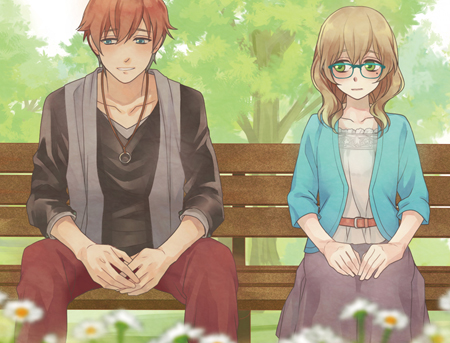 |
みんなの思い出
オープニング
――目を開けると、布団の上に猫。
そして自分と同じ枕に頭を乗せているのが、もう1匹。
すぐ横で人が寝ていた痕跡を示すところに、2匹、潜りこんでいる。
起き上がると、猫達は皆一斉にベッドから降り、ドアの前で「さあ行きましょう、ご主人」と言ってるかのようにニャアと鳴く。
着替えて部屋を出ると、居間に漂う、パンの焦げている匂い――少し焦げた具合が好きな、自分用だろう。
居間のすぐ横に備え付けのキッチンで、エプロン付けて卵を焼いてくれている、猫並、いや猫よりもたぶんきっと愛しい人の後ろ姿。
その後ろ姿に向け、口を開いた――
「おはよう、智恵さん」
……自分の声で、目が覚めた。
なんていうか、あーいう夢を見るのは仕方ないよな……つーか、今のが初夢か。縁起いいと言うべきなんだか、なんなんだか。
それはともかくとして、だ。
夢の続きなのか、それともこのせいで夢でも感じる事が出来たのか、パンが少し焦げた匂いがする。
そういえば昨日、クソったれな悪友・杉田 亮が実家帰らないから暇だーとかで押しかけてきて、そのまま泊まっていったんだったか。
ま、パンくらい焼いてても問題ないけどな――外からのノック音。
「光平、起きたのか?」
「おー」
やはり亮だったか。
ドアを開け、亮が入って――!?
「なんで裸でエプロンつけてんだ!?」
「ばっか、ちゃんとモラルは守ってるっつーの」
見たくはないがその場でクルリと回転して、パンツは履いているのを俺に見せる。
だが、パンツとエプロンしか着てないじゃねぇか。
「新年早々、気色悪いモンみせんじゃねぇ!」
「なにおう。つるつるすべすべぼでーが気色悪いだと?」
クルリクルリと回転するたびにエプロンの裾が、ゆらゆら踊っている。
俺も一応男だから裸エプロンとかそういうのも嫌いじゃないけど、これはないな。
こんなキモイもん見せられるくらいなら、もう少し寝ておけばよかった。
あんな夢を見ていられるなら――
そして自分と同じ枕に頭を乗せているのが、もう1匹。
すぐ横で人が寝ていた痕跡を示すところに、2匹、潜りこんでいる。
起き上がると、猫達は皆一斉にベッドから降り、ドアの前で「さあ行きましょう、ご主人」と言ってるかのようにニャアと鳴く。
着替えて部屋を出ると、居間に漂う、パンの焦げている匂い――少し焦げた具合が好きな、自分用だろう。
居間のすぐ横に備え付けのキッチンで、エプロン付けて卵を焼いてくれている、猫並、いや猫よりもたぶんきっと愛しい人の後ろ姿。
その後ろ姿に向け、口を開いた――
「おはよう、智恵さん」
……自分の声で、目が覚めた。
なんていうか、あーいう夢を見るのは仕方ないよな……つーか、今のが初夢か。縁起いいと言うべきなんだか、なんなんだか。
それはともかくとして、だ。
夢の続きなのか、それともこのせいで夢でも感じる事が出来たのか、パンが少し焦げた匂いがする。
そういえば昨日、クソったれな悪友・杉田 亮が実家帰らないから暇だーとかで押しかけてきて、そのまま泊まっていったんだったか。
ま、パンくらい焼いてても問題ないけどな――外からのノック音。
「光平、起きたのか?」
「おー」
やはり亮だったか。
ドアを開け、亮が入って――!?
「なんで裸でエプロンつけてんだ!?」
「ばっか、ちゃんとモラルは守ってるっつーの」
見たくはないがその場でクルリと回転して、パンツは履いているのを俺に見せる。
だが、パンツとエプロンしか着てないじゃねぇか。
「新年早々、気色悪いモンみせんじゃねぇ!」
「なにおう。つるつるすべすべぼでーが気色悪いだと?」
クルリクルリと回転するたびにエプロンの裾が、ゆらゆら踊っている。
俺も一応男だから裸エプロンとかそういうのも嫌いじゃないけど、これはないな。
こんなキモイもん見せられるくらいなら、もう少し寝ておけばよかった。
あんな夢を見ていられるなら――
リプレイ本文
●夢でなくとも
ヒビキ・ユーヤ(jb9420)が寝ぼけ眼で廊下をふらふら、ふらふら。
――早く、温かいお布団の中に行かなければ。
「……ん、朝」
激化する大戦の最中、幸せ求めて麻生 遊夜達と3人で孤児院兼実家に住んでいて、それもそろそろ落ち着いてきた頃合いの休日の朝……?
何かがおかしい気もするが、おかしい事など無い。
とにかく温もりの足りないベッドから這い出て匂いに誘われると、居間に広がる香ばしい匂い。
「……おはよう……良い匂い」
「おぅ、おはよう。飯できてるぜ?」
ヒビキが目をごしごしとこすっているとナイティがスルリと肩から抜け落ち、かろうじて胸の上で留まるが、新雪のような白い肩が露わになる。
その儚くも眩しい肩に遊夜は目を細めながらナイティを直してやるのだが、自分の顔をまじまじと見ているヒビキと目が合った。
「……ヒビキ? どうしたんだ?」
その問いに答えるでもなく、ヒビキは遊夜の首に腕を回して引き寄せると、キスをかわす。
おはようのキスにしては長く、貪りあうような唇をやっと離して、首をかくりと曲げた。
「ん……ちょっと、昔の夢を、見たの」
「それで、不安になったか?」
首を横に振ると、微笑んだ。
「今は、幸せだなって」
それからお互いに食べさせあったりと、休日の朝食をゆっくり堪能していた。
そして、今日はどうするかという話。
「皆出かけちまったから2人きりだな」
「ん、今日は、私だけの日」
「となればヒビキの好きな事に、今日は付き合うぜ」
その途端、ヒビキの目は熱を帯びたようにやや潤み、立ち上がっては直してもらったばかりの肩を自分からさらけ出した。
今度はさっきよりもきわどく、それを見せつけるように腕を前で組んで強調して魅惑の微笑みを浮かべ、クスクスと笑う。
「なら、一緒に寝よう?」
その誘いに抱き上げる事で答え、腕の中でヒビキは首に腕を回してきつく抱きついて自らを押しつけて、首筋にキスを浴びせたり頬に当たるくすぐったさを愉しんでいた。
「ふふっ、良い匂い……温かい…ユーヤ、大好き」
寝室のベッドで、遊夜の胸の上に顎を乗せて気だるげに見上げる遊夜の優しい顔。
愛おしくて愛おしくて、言葉で足りないその想いは胸を押しつけ、キスの雨で伝えると、その全てを受け入れてくれる。
いつの間にか眠ってしまっていても、目を覚ませば変わらず遊夜の腕の中。
クスクスと笑ってしまった。
「ふふっ……おかーさん達に、怒られる、かな?」
でも今は――今だけは、この幸せに包まれていたい。
腕の中で再び目を閉じて、深く大きく温かい世界へと沈んでいった――
「ユーヤ、大好き……愛してる、愛してる……よ」
その寝言に、何故か深夜荘の廊下で眠っていたヒビキを抱き上げて運んでいた遊夜の頬が、ほころぶ。娘に愛されて喜ぶ父親の顔であった。
「俺も、愛してるよ」
この先もずっと――
と。
感慨にふけって油断していたところに、眠ったままのヒビキが遊夜の頬に口づけをする。
「今のは、不可抗力……ッ」
●幸せだなぁ
大戦が終わって10年の事。
築半世紀以上で立てつけが悪く隙間風の入る窓の木造アパート。
6畳一間のトイレ共用風呂無し(近くに銭湯はある)と、お世辞にも立派とは言い難いそこへの帰路を、なんとか180台にまで成長を果たしたもののまだ幼い面影を残した青年、藍那湊(jc0170)――いや、今は来海湊と改姓した湊は、仕事でくたくたになりながらも、急いでいた。
土木作業員とあまり似つかわしくない仕事をし、その傍ら、かつてアイドル活動で培った知名と笑顔で、人間界にいる天魔やハーフ達が住みやすい世の中になるようボランティア活動をしているので、肉体だけでなく精神的にもだいぶ疲弊していた。
だがそれでも、我が家にさえ帰れば。たとえどんな豪華な家やホテルや旅館よりも、あの少し情けなくはあるおんぼろでも我が家だからこそ、帰りたい。
だってそこには――
「たっだいまー!」
「おっかえりー」
かつてより10cmほど伸びて、可愛いから美人へと成長を果たした(と思っている)胡桃 みるく(ja1252)改め、来海 みるくは、腕の中の赤ん坊の手を取って振りながら出迎えた。
「――ふわぁぁぁぁ!! らく!! 朝より更に可愛くなって……ッ」
湊が大声を上げると、赤ん坊のらくは泣きだしてしまう。
おろおろする湊を前に、みるくは腕の中のらくをあやそうとするも、一向に泣き止む気配がない――と思った矢先、ぴたりと泣き止んだ。
その小さな手でしっかりと、湊のみょんと伸びるアホ毛を掴んだその瞬間にである。
「らくは、お父さんのアホ毛が大好きなのね。
あんなに泣いていたのに、アホ毛を掴んだ途端、泣き止むんだから」
「らくー。お父さんの本体はそっちじゃなくてこっちだよ〜」
自分の頬を突っついてアピールするが、頑としてらくはアホ毛から手を離さない。
諦めて掴まれたまま、アホな体勢からなんとか、娘の顔を懸命に盗み見る。
「このしっかりした眉はきみにそっくりだよね。
髪の色も……きれいで……将来が悪い虫がつかないか、今から心配だよー」
「ホラ、アナタ。らくにもアホ毛が……こうしてみると、湊くんの面影もありますね」
もっとじっくりと我が娘を見ようとしても、アホ毛を掴まれては力が出ない――もとい、アホな体勢から脱する事ができない。
そのうちに諦め、解放されるまでじっと待っていると、ドアからの隙間風に身を震わせ、これがみるくの足元も冷やしているのかと思うと、凄く申し訳ない気がしてきた。
「稼ぎが良ければ、もっといい暮らしができるのだろうけれど……みるくとらくには苦労をかけてしまって、ごめんね。
僕の夢のために、ありがとう」
そんな湊の上唇を、指で抑え込んだ。
「おじいちゃんが言っていたのです。『幸せという字は、±と¥で成り立っている』と。
どんな事象も結局は中立で、幸せの本質は、当人がそれをどちらに捉えるかにあるのです」
顔を、近づける。
「そして幸せという字の土台にあるのは、人の縁なのです。
ボクはアナタとらく、3人で生きられることが、一番の幸せなのですよ?」
最愛の人に目の前でそんな事を言われ微笑まれては、もはや反則である。
2人の唇の距離が縮まり、湊は目を潤ませながら両腕を広げ――らくが泣き出すと、みるくはパッと離れて部屋の真ん中へと行ってしまう。
「あらあら、お腹が空いたのかしら」
すかされて、がっくり肩を落す。
湊はのろのろと靴を脱いで上がりこむと、ちょこんと正座していたのだが、みるくがふと視線に気づき「授乳するんだから、あっち向いててください」と、赤くなりながらも小声で訴え、湊は耳まで真っ赤になって後ろを向く。
何となく気まずいような、気恥ずかしいような沈黙。
腹が、鳴る。
「僕もお腹すいたなー今日の晩御飯はなn……ゴメンナサイ!」
もうそろそろ終わったかと思ってふり返ったのだが、ばっちり継続中。
崩れかけた正座を正して、シャキッと背筋を伸ばす湊だった。
電気を消し、小さなランプに照らされたまま寝静まったみるくとらくを起こさないよう気遣いながら、湊は髪と眉にそっとキスをする。
「不思議だな、眠るのが勿体ないや……
夢の中でも君達に会いたいなあ。おやすみ、らく。みるくちゃん」
出会えた事、自分と一緒になる事を選んでくれた事を、幸せだなぁと噛みしめながら、湊もゆっくり瞼を閉じるのであった。
●え?
(味噌汁の匂い……)
それに気づいて、ゆっくりと目を開ける中本 修平だが、両腕に何かが乗っているらしく、動かせない。
なんなのかと、右を見ると――津崎 海だった。
「!?」
顔を強ばらせながらも左を見れば、吾亦紅 澄音だった。
どちらも布団から覗く肩は、素肌である。
「え、なにこれ?」
「おはよう、修平」
お盆に朝食を持って部屋へと入ってきたアルジェ(jb3603)はこの様子に動じることなく、平然と挨拶してきた。
「あ、うんおはよう……ってこの状況は何?!」
何を言っているのかわからないという風に、アルジェは小首を傾げる。
「いつもの事じゃないか? 一緒に住んでいるんだから」
「いや、それにしたってこれは……」
2人と、ゴスロリ風のエプロンで気づくのが遅れたが、アルジェの格好に気づいてしまった修平は、おろおろとするばかりである。
「修平が皆大事な人だからと、選ばなかったからだろう? それじゃあ全員で一緒になれば解決!
……と言ったのは誰だったか忘れたが、そういうことだ」
「そう言われると……そうだったかも」
「2人を起こすのは忍びないな……ほら、修平。口を開けろ――いや、口移しが良かったか?」
ほぐして箸に乗せていた焼き魚をアルジェは口に含み、問答無用で修平と唇を重ねると、舌で懸命に口の中へと押し込んでいく。
目を覚ました2人が自分も自分もと、唇を奪い合うのであった。
嬉し楽しひどい目にあったなと、風呂場に逃げ込んでシャワーを浴びていた修平だったが――このお話以上に、甘い。
「修平。いつものように身体で洗ってやるぞ」
当たり前のように押しかけるアルジェ。
もちろんこうなってくるとやはり、他の2人も黙っているはずがなく次々に入ってきてシャワーヘッドの取り合いから始まる。
四方八方に、暴れ、飛び散る飛沫――
「熱い――冷たい……?」
目を覚ました修平がむくりと起き上がると、ひんやりとした濡れタオルが額から落ちた。
身体中どっと汗が噴きだしているが、熱い。
そこでようやく、自分が熱を出して寝込んでいたのを思い出したのだが、シートを貼っていたはずの額に何故か濡れタオル。
まあ、それはいい。
「なんであの2人まで出てくるかな……アルジェだけでいい――」
「呼んだか?」
入ってきたアルジェの手には、朝食が。焼き魚もある。
焼き魚をほぐし、箸に乗せて修平へ差し出す。
「ほら、修平。口を開けろ――いや――……」
●夢だ夢だ夢だ!
(いや、夢だろこれ)
城里 千里(jb6410)はそう、分析する。
ついさっきまでこれを夢だと思ってはいなかった。
いつも通り自分の部屋で、音楽を聴いてぼっちを満喫していたはずなのに、なぜか後ろに黒松 理恵がいて、いきなり愛の告白をしてきた。
(いきなりこれは、ない)
理恵は顔を赤くしてこっちを睨んだまま、ネクタイを緩めると、ブラウスのボタンを躊躇いながらも意を決したように、一個一個外していく。
(え、待って。確かに黒松はそんな行動取りそうだけども!)
ブラウスが、床に。
(まてまてこれ俺の望みか? いや自分の事だから理解はしてるが!)
スカートがすとんと、落ちた。
(つか覚めてーはやく覚めてーこれもう理性もたないよー?)
必死にリアル自分に呼びかけるのだが、応答はなく、目の前の理恵はとうとう最後の砦すらも脱ぎ捨ててしまう。
理恵の傷ひとつなく綺麗な肌に、目が離せない千里だが「あれ?」と、何かが足りない様な気がした。
(何だ……?)
何が足りないと自分へ問いただそうにも、目の前の理恵が自分に身を寄せる。
理恵の匂いがする――そんな事を思ってしまったところに、うつむいたまま囁かれてしまえば、もはや理性がどこかへ飛んでいってしまった。
千里の震える腕は理恵を――
すっげー見覚えのある天井が見えた。
むくりと起き上がる――うん、誰もいない。ぼっちだ。
当たり前だ。さっきのは夢だって、知ってた。そう知っていたさ。ビー・クール。
「……ふっ」
余裕の笑み。
次の瞬間、布団に顔を押し付けて「ざっけんなー!!」と叫んでいた。
「この夢、アニエニの仕業か? アニスなら仕方ない。エニスだったら許さん――ああ、そうか」
足りなかったもの、それは海で見てしまった胸の古傷。
秘密にしてと言われ、結局、自分は何も云わなかった。
(自分の都合で、記憶を書き換えるな……自分に、反吐が出る)
先ほどまでの幸福感も、自己嫌悪で完全に上書きされてしまう。
(俺は彼女の必死さ、直向きさを遠くから見ていた。必死になってもいいことなんてない、なんて。
だけど同時に、必死な奴が救われないなんて、嘘だとも思った)
だけど理恵は泣いたり笑ったりしながらも、常に必死だった。
「そうだ。『彼女』は俺の否定した物全て……勝手なイメージだ。
だからこそ憧れた。だからこそ書き換えて汚しちゃいけない」
側頭部を殴りつけ、逃げそうな自分を呼び戻す。
そうだ。好きかどうかなんて、最初から決まってる――
●願わくば――
天魔達との、最終決戦。
様々な痛みに耐え、身も心もボロボロになってしまっても、生きて還ってきた。
「これで……これからは、何にも邪魔されない穏やかな日々が始まるのか――さあ、還ろう。君のいる地へ」
穏やかな地を求めた君田 夢野(ja0561)の足は、自然とそこへ。
そこで時々、旧い友と出会い、あの日の事を皆で語り合った。
そして1年に一度、あの時の仲間と共に『君』の母の眠る地で音楽を捧げる――そんな日々。
春の風に撫ぜられ2人で風の歌を聴き、夏の空を見上げ2人で日差しの情熱に目を細め、秋の花を飾り2人で芳醇な香りを楽しみ、冬の雪に触れ2人で冷たいねと笑いあった。
これを1年、また1年と、飽きもせず繰り返す。
だが穏やかで変わりばえしなくても必ず変化は訪れ、苦しい時は『君』と互いに支え合い、『君』との間に未来への萌芽を1粒残し、永久まで『君』と一緒に幸せを分かち合うことに、飽きるはずがなかった。
いつまでもと願っても、いつかは死が2人を分かつ。
しかも、悲しい事に『君』はいつまでも変わらず輝き続けるのに、自分はどんどん萎み、くすんでいくばかり。
それは決して、揺ぐ事のない事実。
それは決して、逃れられない現実。
それは『君』が半天として生きる事を選んだ時から、覚悟していた――だが『君』は?
「……なぁ、理子さん」
雲の差しかかる月を見上げ、夢野は独白するように隣の矢代 理子へと言葉を投げる。
「俺が君を置いて老いさらばえ、枯れ木のようにしわくちゃになって、君を愛する事の意味すらも分からなくなって――そして時が俺を殺し、君を独りぼっちにしてしまったとしても……」
月が雲に隠れ、辺りは完全に真っ暗となってしまう。
どんな表情をしているのかわからないが、今、自分もどんな表情をしているのかわからないので、見えない事に安堵して続けた。
「それでも君は――」
一呼吸だけ、覚悟の間を貰う。
「――俺と一緒に生きられて幸せだったと、そう言ってくれますか?」
そう、願わくば――君が選んだ選択と俺が先に逝く事を恨まないでほしい。
贅沢で、身勝手な事だとは分かっている。
それでも理子はただ黙って、その小さな手で懸命に、夢野の手を力強く握りしめてくれるのであった――
【初夢】同棲生活(夢だがな) 終
ヒビキ・ユーヤ(jb9420)が寝ぼけ眼で廊下をふらふら、ふらふら。
――早く、温かいお布団の中に行かなければ。
「……ん、朝」
激化する大戦の最中、幸せ求めて麻生 遊夜達と3人で孤児院兼実家に住んでいて、それもそろそろ落ち着いてきた頃合いの休日の朝……?
何かがおかしい気もするが、おかしい事など無い。
とにかく温もりの足りないベッドから這い出て匂いに誘われると、居間に広がる香ばしい匂い。
「……おはよう……良い匂い」
「おぅ、おはよう。飯できてるぜ?」
ヒビキが目をごしごしとこすっているとナイティがスルリと肩から抜け落ち、かろうじて胸の上で留まるが、新雪のような白い肩が露わになる。
その儚くも眩しい肩に遊夜は目を細めながらナイティを直してやるのだが、自分の顔をまじまじと見ているヒビキと目が合った。
「……ヒビキ? どうしたんだ?」
その問いに答えるでもなく、ヒビキは遊夜の首に腕を回して引き寄せると、キスをかわす。
おはようのキスにしては長く、貪りあうような唇をやっと離して、首をかくりと曲げた。
「ん……ちょっと、昔の夢を、見たの」
「それで、不安になったか?」
首を横に振ると、微笑んだ。
「今は、幸せだなって」
それからお互いに食べさせあったりと、休日の朝食をゆっくり堪能していた。
そして、今日はどうするかという話。
「皆出かけちまったから2人きりだな」
「ん、今日は、私だけの日」
「となればヒビキの好きな事に、今日は付き合うぜ」
その途端、ヒビキの目は熱を帯びたようにやや潤み、立ち上がっては直してもらったばかりの肩を自分からさらけ出した。
今度はさっきよりもきわどく、それを見せつけるように腕を前で組んで強調して魅惑の微笑みを浮かべ、クスクスと笑う。
「なら、一緒に寝よう?」
その誘いに抱き上げる事で答え、腕の中でヒビキは首に腕を回してきつく抱きついて自らを押しつけて、首筋にキスを浴びせたり頬に当たるくすぐったさを愉しんでいた。
「ふふっ、良い匂い……温かい…ユーヤ、大好き」
寝室のベッドで、遊夜の胸の上に顎を乗せて気だるげに見上げる遊夜の優しい顔。
愛おしくて愛おしくて、言葉で足りないその想いは胸を押しつけ、キスの雨で伝えると、その全てを受け入れてくれる。
いつの間にか眠ってしまっていても、目を覚ませば変わらず遊夜の腕の中。
クスクスと笑ってしまった。
「ふふっ……おかーさん達に、怒られる、かな?」
でも今は――今だけは、この幸せに包まれていたい。
腕の中で再び目を閉じて、深く大きく温かい世界へと沈んでいった――
「ユーヤ、大好き……愛してる、愛してる……よ」
その寝言に、何故か深夜荘の廊下で眠っていたヒビキを抱き上げて運んでいた遊夜の頬が、ほころぶ。娘に愛されて喜ぶ父親の顔であった。
「俺も、愛してるよ」
この先もずっと――
と。
感慨にふけって油断していたところに、眠ったままのヒビキが遊夜の頬に口づけをする。
「今のは、不可抗力……ッ」
●幸せだなぁ
大戦が終わって10年の事。
築半世紀以上で立てつけが悪く隙間風の入る窓の木造アパート。
6畳一間のトイレ共用風呂無し(近くに銭湯はある)と、お世辞にも立派とは言い難いそこへの帰路を、なんとか180台にまで成長を果たしたもののまだ幼い面影を残した青年、藍那湊(jc0170)――いや、今は来海湊と改姓した湊は、仕事でくたくたになりながらも、急いでいた。
土木作業員とあまり似つかわしくない仕事をし、その傍ら、かつてアイドル活動で培った知名と笑顔で、人間界にいる天魔やハーフ達が住みやすい世の中になるようボランティア活動をしているので、肉体だけでなく精神的にもだいぶ疲弊していた。
だがそれでも、我が家にさえ帰れば。たとえどんな豪華な家やホテルや旅館よりも、あの少し情けなくはあるおんぼろでも我が家だからこそ、帰りたい。
だってそこには――
「たっだいまー!」
「おっかえりー」
かつてより10cmほど伸びて、可愛いから美人へと成長を果たした(と思っている)胡桃 みるく(ja1252)改め、来海 みるくは、腕の中の赤ん坊の手を取って振りながら出迎えた。
「――ふわぁぁぁぁ!! らく!! 朝より更に可愛くなって……ッ」
湊が大声を上げると、赤ん坊のらくは泣きだしてしまう。
おろおろする湊を前に、みるくは腕の中のらくをあやそうとするも、一向に泣き止む気配がない――と思った矢先、ぴたりと泣き止んだ。
その小さな手でしっかりと、湊のみょんと伸びるアホ毛を掴んだその瞬間にである。
「らくは、お父さんのアホ毛が大好きなのね。
あんなに泣いていたのに、アホ毛を掴んだ途端、泣き止むんだから」
「らくー。お父さんの本体はそっちじゃなくてこっちだよ〜」
自分の頬を突っついてアピールするが、頑としてらくはアホ毛から手を離さない。
諦めて掴まれたまま、アホな体勢からなんとか、娘の顔を懸命に盗み見る。
「このしっかりした眉はきみにそっくりだよね。
髪の色も……きれいで……将来が悪い虫がつかないか、今から心配だよー」
「ホラ、アナタ。らくにもアホ毛が……こうしてみると、湊くんの面影もありますね」
もっとじっくりと我が娘を見ようとしても、アホ毛を掴まれては力が出ない――もとい、アホな体勢から脱する事ができない。
そのうちに諦め、解放されるまでじっと待っていると、ドアからの隙間風に身を震わせ、これがみるくの足元も冷やしているのかと思うと、凄く申し訳ない気がしてきた。
「稼ぎが良ければ、もっといい暮らしができるのだろうけれど……みるくとらくには苦労をかけてしまって、ごめんね。
僕の夢のために、ありがとう」
そんな湊の上唇を、指で抑え込んだ。
「おじいちゃんが言っていたのです。『幸せという字は、±と¥で成り立っている』と。
どんな事象も結局は中立で、幸せの本質は、当人がそれをどちらに捉えるかにあるのです」
顔を、近づける。
「そして幸せという字の土台にあるのは、人の縁なのです。
ボクはアナタとらく、3人で生きられることが、一番の幸せなのですよ?」
最愛の人に目の前でそんな事を言われ微笑まれては、もはや反則である。
2人の唇の距離が縮まり、湊は目を潤ませながら両腕を広げ――らくが泣き出すと、みるくはパッと離れて部屋の真ん中へと行ってしまう。
「あらあら、お腹が空いたのかしら」
すかされて、がっくり肩を落す。
湊はのろのろと靴を脱いで上がりこむと、ちょこんと正座していたのだが、みるくがふと視線に気づき「授乳するんだから、あっち向いててください」と、赤くなりながらも小声で訴え、湊は耳まで真っ赤になって後ろを向く。
何となく気まずいような、気恥ずかしいような沈黙。
腹が、鳴る。
「僕もお腹すいたなー今日の晩御飯はなn……ゴメンナサイ!」
もうそろそろ終わったかと思ってふり返ったのだが、ばっちり継続中。
崩れかけた正座を正して、シャキッと背筋を伸ばす湊だった。
電気を消し、小さなランプに照らされたまま寝静まったみるくとらくを起こさないよう気遣いながら、湊は髪と眉にそっとキスをする。
「不思議だな、眠るのが勿体ないや……
夢の中でも君達に会いたいなあ。おやすみ、らく。みるくちゃん」
出会えた事、自分と一緒になる事を選んでくれた事を、幸せだなぁと噛みしめながら、湊もゆっくり瞼を閉じるのであった。
●え?
(味噌汁の匂い……)
それに気づいて、ゆっくりと目を開ける中本 修平だが、両腕に何かが乗っているらしく、動かせない。
なんなのかと、右を見ると――津崎 海だった。
「!?」
顔を強ばらせながらも左を見れば、吾亦紅 澄音だった。
どちらも布団から覗く肩は、素肌である。
「え、なにこれ?」
「おはよう、修平」
お盆に朝食を持って部屋へと入ってきたアルジェ(jb3603)はこの様子に動じることなく、平然と挨拶してきた。
「あ、うんおはよう……ってこの状況は何?!」
何を言っているのかわからないという風に、アルジェは小首を傾げる。
「いつもの事じゃないか? 一緒に住んでいるんだから」
「いや、それにしたってこれは……」
2人と、ゴスロリ風のエプロンで気づくのが遅れたが、アルジェの格好に気づいてしまった修平は、おろおろとするばかりである。
「修平が皆大事な人だからと、選ばなかったからだろう? それじゃあ全員で一緒になれば解決!
……と言ったのは誰だったか忘れたが、そういうことだ」
「そう言われると……そうだったかも」
「2人を起こすのは忍びないな……ほら、修平。口を開けろ――いや、口移しが良かったか?」
ほぐして箸に乗せていた焼き魚をアルジェは口に含み、問答無用で修平と唇を重ねると、舌で懸命に口の中へと押し込んでいく。
目を覚ました2人が自分も自分もと、唇を奪い合うのであった。
嬉し楽しひどい目にあったなと、風呂場に逃げ込んでシャワーを浴びていた修平だったが――このお話以上に、甘い。
「修平。いつものように身体で洗ってやるぞ」
当たり前のように押しかけるアルジェ。
もちろんこうなってくるとやはり、他の2人も黙っているはずがなく次々に入ってきてシャワーヘッドの取り合いから始まる。
四方八方に、暴れ、飛び散る飛沫――
「熱い――冷たい……?」
目を覚ました修平がむくりと起き上がると、ひんやりとした濡れタオルが額から落ちた。
身体中どっと汗が噴きだしているが、熱い。
そこでようやく、自分が熱を出して寝込んでいたのを思い出したのだが、シートを貼っていたはずの額に何故か濡れタオル。
まあ、それはいい。
「なんであの2人まで出てくるかな……アルジェだけでいい――」
「呼んだか?」
入ってきたアルジェの手には、朝食が。焼き魚もある。
焼き魚をほぐし、箸に乗せて修平へ差し出す。
「ほら、修平。口を開けろ――いや――……」
●夢だ夢だ夢だ!
(いや、夢だろこれ)
城里 千里(jb6410)はそう、分析する。
ついさっきまでこれを夢だと思ってはいなかった。
いつも通り自分の部屋で、音楽を聴いてぼっちを満喫していたはずなのに、なぜか後ろに黒松 理恵がいて、いきなり愛の告白をしてきた。
(いきなりこれは、ない)
理恵は顔を赤くしてこっちを睨んだまま、ネクタイを緩めると、ブラウスのボタンを躊躇いながらも意を決したように、一個一個外していく。
(え、待って。確かに黒松はそんな行動取りそうだけども!)
ブラウスが、床に。
(まてまてこれ俺の望みか? いや自分の事だから理解はしてるが!)
スカートがすとんと、落ちた。
(つか覚めてーはやく覚めてーこれもう理性もたないよー?)
必死にリアル自分に呼びかけるのだが、応答はなく、目の前の理恵はとうとう最後の砦すらも脱ぎ捨ててしまう。
理恵の傷ひとつなく綺麗な肌に、目が離せない千里だが「あれ?」と、何かが足りない様な気がした。
(何だ……?)
何が足りないと自分へ問いただそうにも、目の前の理恵が自分に身を寄せる。
理恵の匂いがする――そんな事を思ってしまったところに、うつむいたまま囁かれてしまえば、もはや理性がどこかへ飛んでいってしまった。
千里の震える腕は理恵を――
すっげー見覚えのある天井が見えた。
むくりと起き上がる――うん、誰もいない。ぼっちだ。
当たり前だ。さっきのは夢だって、知ってた。そう知っていたさ。ビー・クール。
「……ふっ」
余裕の笑み。
次の瞬間、布団に顔を押し付けて「ざっけんなー!!」と叫んでいた。
「この夢、アニエニの仕業か? アニスなら仕方ない。エニスだったら許さん――ああ、そうか」
足りなかったもの、それは海で見てしまった胸の古傷。
秘密にしてと言われ、結局、自分は何も云わなかった。
(自分の都合で、記憶を書き換えるな……自分に、反吐が出る)
先ほどまでの幸福感も、自己嫌悪で完全に上書きされてしまう。
(俺は彼女の必死さ、直向きさを遠くから見ていた。必死になってもいいことなんてない、なんて。
だけど同時に、必死な奴が救われないなんて、嘘だとも思った)
だけど理恵は泣いたり笑ったりしながらも、常に必死だった。
「そうだ。『彼女』は俺の否定した物全て……勝手なイメージだ。
だからこそ憧れた。だからこそ書き換えて汚しちゃいけない」
側頭部を殴りつけ、逃げそうな自分を呼び戻す。
そうだ。好きかどうかなんて、最初から決まってる――
●願わくば――
天魔達との、最終決戦。
様々な痛みに耐え、身も心もボロボロになってしまっても、生きて還ってきた。
「これで……これからは、何にも邪魔されない穏やかな日々が始まるのか――さあ、還ろう。君のいる地へ」
穏やかな地を求めた君田 夢野(ja0561)の足は、自然とそこへ。
そこで時々、旧い友と出会い、あの日の事を皆で語り合った。
そして1年に一度、あの時の仲間と共に『君』の母の眠る地で音楽を捧げる――そんな日々。
春の風に撫ぜられ2人で風の歌を聴き、夏の空を見上げ2人で日差しの情熱に目を細め、秋の花を飾り2人で芳醇な香りを楽しみ、冬の雪に触れ2人で冷たいねと笑いあった。
これを1年、また1年と、飽きもせず繰り返す。
だが穏やかで変わりばえしなくても必ず変化は訪れ、苦しい時は『君』と互いに支え合い、『君』との間に未来への萌芽を1粒残し、永久まで『君』と一緒に幸せを分かち合うことに、飽きるはずがなかった。
いつまでもと願っても、いつかは死が2人を分かつ。
しかも、悲しい事に『君』はいつまでも変わらず輝き続けるのに、自分はどんどん萎み、くすんでいくばかり。
それは決して、揺ぐ事のない事実。
それは決して、逃れられない現実。
それは『君』が半天として生きる事を選んだ時から、覚悟していた――だが『君』は?
「……なぁ、理子さん」
雲の差しかかる月を見上げ、夢野は独白するように隣の矢代 理子へと言葉を投げる。
「俺が君を置いて老いさらばえ、枯れ木のようにしわくちゃになって、君を愛する事の意味すらも分からなくなって――そして時が俺を殺し、君を独りぼっちにしてしまったとしても……」
月が雲に隠れ、辺りは完全に真っ暗となってしまう。
どんな表情をしているのかわからないが、今、自分もどんな表情をしているのかわからないので、見えない事に安堵して続けた。
「それでも君は――」
一呼吸だけ、覚悟の間を貰う。
「――俺と一緒に生きられて幸せだったと、そう言ってくれますか?」
そう、願わくば――君が選んだ選択と俺が先に逝く事を恨まないでほしい。
贅沢で、身勝手な事だとは分かっている。
それでも理子はただ黙って、その小さな手で懸命に、夢野の手を力強く握りしめてくれるのであった――
【初夢】同棲生活(夢だがな) 終
依頼結果
| 依頼成功度:大成功 |
| MVP: − |
| 重体: − |
| 面白かった!:4人 |
 |
Blue Sphere Ballad・ 君田 夢野(ja0561) 卒業 男 ルインズブレイド |
 |
撃退士・ 来海 みるく(ja1252) 高等部2年20組 女 陰陽師 |
| その愛は確かなもの・ アルジェ(jb3603) 高等部2年1組 女 ルインズブレイド |
 |
Survived・ 城里 千里(jb6410) 大学部3年2組 男 インフィルトレイター |
|
 |
夜闇の眷属・ ヒビキ・ユーヤ(jb9420) 高等部1年30組 女 阿修羅 |
 |
蒼色の情熱・ 大空 湊(jc0170) 大学部2年5組 男 アカシックレコーダー:タイプA |

