|
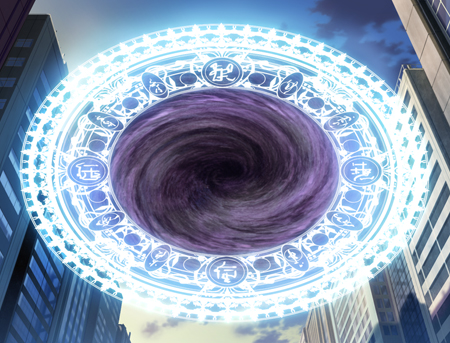 |
みんなの思い出
オープニング
指先が氷のように冷たかった。
冬の寒さは日毎に体を蝕み、寝返りすらうてなくなって数日。病室には機械が運び込まれ、お医者様は一日に何回も部屋に訪れるようになった。
本来素っ気ない風情の部屋の隅には、追いやられた沢山の花とぬいぐるみ。
父から贈られた品物に、看護師も医師も届く度に「よかったね」と言っていた。
けれどその父は、会いに来ない。
少女は小さく咳き込みながら、ぼんやりと天井を見上げた。熱が高くなったのか、白い天井が間近に降りてくるような奇妙な圧迫感を感じる。
(お父さん……お父さん……)
いつも沢山の贈り物を持ってきてくれる父。会社を経営していて、色んな物を持っている父。だけど本当は、贈り物なんて欲しくない。
(お父さん……)
目の前がぼやけて見えない。
その滲んで歪んだ白い視界に、ぬっと黒いものが現れた。
大きな黒い影。大きな緑の目。
嗚呼、夢を見ているんだ。そう思った。でなければ幻だろう。
重くて動かない手に落胆しながら、少女は黒い物体に向かって小さく呟く。
生命の乏しいかすれた声で。
「……ねこちゃん……」
●
郊外の屋敷には、まるで昼間のように煌々と明かりが灯されていた。
「ははは! すごい量だ……! こんなに収集してるとはな!」
燦然と輝く宝飾類の前で男は相好を崩す。
「持っているだろうと思っていたが、想像以上だ! おい、全部金庫に入れろ。……あぁ、向こうの部屋は?」
「毛皮や剥製です」
「まとめて押さえておけ。そのために『落とし』たんだ」
くつくつと笑いながら、男は悠然と屋敷内を歩いた。
ライバルと目されていた会社の倒産。その報告を受けた時はどれほど心が踊っただろう。破産宣告を今か今かと待ち構えていた甘美な日々。差し押さえられた家財一式がこちらに流れてくるのを裏で操りながらずっと待っていた。
「あぁ、君がいけないんだよ、南条君。君が私が欲しがっていたダイヤを落札なんてするから」
ようやく手元に『帰って』来たそれを見つめながら、男は薄笑いを浮かべる。競り勝った相手はすでにこの世界にいない。その妻と子ともども海に沈んだという。
一家心中と人は言う。真実など、知りうる由もなく。
「あぁ……そういえば、先週のオークションでも落札し損ねた……あれも欲しいんだ。あれも手元に収めなくては」
うっそりと笑む男の下で、宝石はどこまでも美しく輝く
緑の瞳が、それをじっと見つめていた。
○
待ち合わせの場所に降り立つと、レックスは丁度来たらしいマッド・ザ・クラウン(jz0145)に声をかけた。
「クラウン、クラウンー」
「おや、レックス。ちょうどいいタイミングでしたね」
クラウンの前にぺたんと座りながら、レックスは「むふー」と笑んだ。
「シルバが四国に来ていたであるー」
「ええ。会いに行ってきたのですか?」
「うむー!」
「おや、おや」
ふと笑んだクラウンに気付かず、レックスはクラウンの前に腹這いになった。
「相変わらず面倒臭そうにだったのであるよ。仕事が無ければのんびり我輩の腹を枕に貸すのであるが、シルバも仕事中……仕事中? なのである。残念なのであるー。なので一日だけ腹枕してきたである」
「ふたりでひなたぼっこしてきたのですか?」
「うむー! 我輩、ひなたぼっこが好きである故」
嬉しげに髭をピンッと張っているレックスに、クラウンは巨大な黒猫の背によじ登りながら微笑んだ。
「ふふふ。楽しそうですね」
「クラウンも会いに行くであるか? 我輩、案内するであるよ」
「ええ。お願いしましょうか」
「任せるである! そうだ、リトルプリンセスも来ているのであるよ。我輩、プリンセスの可愛さにトキメキである。皆で遊べたら楽しいのである!」
「ふふふ。四国も随分と賑やかになってきましたね」
嬉しげに耳をピンッと立てているレックスに、クラウンは頭を掻いてやりながら笑った。
「では、皆で遊ぶためにも、私達もまた楽しむといたしましょうか」
「うむ! 我輩、今度こそクラウンに勝つであるぞ!」
「かかってきなさい。私も負けませんよ」
微笑むクラウンに、レックスは「むふー!」と意気をあげる。
「ところで次の遊びであるが、我輩、気になる人間達を見つけたのであるよ」
「おや。達、なのですか?」
「である!」
どうやらひとりで遊びに行っている間に、興味深い人間を見つけて来たらしい。人の子の世界を楽しんでいるらしい友悪魔に、クラウンは瞳を微笑ませた。
「どんな人間達なのです?」
「むふー。これからクラウンにも見せるのである!」
髭と尻尾をピンと張って、レックスは一路四国の東へと向かっていった。
●
学園の一室で鎹雅は依頼主と対峙していた。
「連れ戻してほしい、と」
「はい」
頷く男はある資産家の親族だ。
「娘が危篤状態になっている時に何をしているのかと、そう、言ってやりたいだけでなく、本当にもう、あの子には時間が残されていないのです。それなのに……」
「ふむ……」
雅は眉をひそめて添付写真を見る。
写真に写っているのは精力的な顔立ちの男だった。いかにも上質なスーツに身を固めた紳士だが、写真でもわかる目のぎらつきがどうにも気にかかる。
「……園部、と言えば色々と曰くのある会社の社長だったと思うが」
「……」
「自身の好む蒐集物を得るためにかなり汚い手も使っていると聞く。今回動いたのも、その類か」
頷き、男はそれを口にした。
「落札し損ねたある宝石が、近々競売にかけられるらしい、と。その招待状を貰ったので行ってくると言われたのですが……」
「……娘が危篤状態なのに、か。それとも父親はそれを知らないのか?」
「いいえ、知っています。……そして、あの男は宝石をとったのです」
「…………」
男は真っ直ぐな眼差しを雅に向けて言う。
「彼を連れ戻していただきたい。欲望にまみれて進むのは本人の勝手かもしれません。ですが、せめて、家族にだけは最後に父親らしい姿をみせてほしい。せめて……せめて、最期の時ぐらいは」
●
子供の頃から不満があった。
あれが欲しい。これが欲しい。それが欲しい。どれも欲しい。
なんでも欲しくて、全部欲しくて、なのに手に入れられる量には限りがあるのが腹立たしかった。父親や母親から諭されても表面だけで頷いて内心では出し抜く方向を考えていた。
自分が持っていなくて誰かが持っているのなら奪えばいい。
誰かが手に入れて自分が手に入れられないのなら、相手を消せばいい。
どうしてそこまでして『欲しい』のかは分からない。ただ再現なく『欲しい』のだ。もっと。もっと。もっともっともっともっともっともっともっともっと……!
(この先に、秘密の集会が……!)
夜。人気のない場所。人目を避けるようにして集まるその集会で、欲しかった品がオークションにかけられる。なら、何をおいても駆けつけずにはいられない。
例え、娘が危篤だと言われても。
永遠に手に残る品が手に入るのは、今しか無いかもしれないのだから。
○
「クラウンは少しだけ離れていて欲しいのであるー」
そう言ってその建物に消えた黒猫を見送ってしばし、クラウンは眼下に現れた車に冷ややかな目を向けた。
仕掛けられた罠。かかった欲深き人間。背負う業。
けれど、そんな車を後から追う影──
「……ほぅ。彼等が来ましたか」
ならば、この先行きは誰にも見通しがつかない。
久遠ヶ原学園の撃退士が来たのだから。
冬の寒さは日毎に体を蝕み、寝返りすらうてなくなって数日。病室には機械が運び込まれ、お医者様は一日に何回も部屋に訪れるようになった。
本来素っ気ない風情の部屋の隅には、追いやられた沢山の花とぬいぐるみ。
父から贈られた品物に、看護師も医師も届く度に「よかったね」と言っていた。
けれどその父は、会いに来ない。
少女は小さく咳き込みながら、ぼんやりと天井を見上げた。熱が高くなったのか、白い天井が間近に降りてくるような奇妙な圧迫感を感じる。
(お父さん……お父さん……)
いつも沢山の贈り物を持ってきてくれる父。会社を経営していて、色んな物を持っている父。だけど本当は、贈り物なんて欲しくない。
(お父さん……)
目の前がぼやけて見えない。
その滲んで歪んだ白い視界に、ぬっと黒いものが現れた。
大きな黒い影。大きな緑の目。
嗚呼、夢を見ているんだ。そう思った。でなければ幻だろう。
重くて動かない手に落胆しながら、少女は黒い物体に向かって小さく呟く。
生命の乏しいかすれた声で。
「……ねこちゃん……」
●
郊外の屋敷には、まるで昼間のように煌々と明かりが灯されていた。
「ははは! すごい量だ……! こんなに収集してるとはな!」
燦然と輝く宝飾類の前で男は相好を崩す。
「持っているだろうと思っていたが、想像以上だ! おい、全部金庫に入れろ。……あぁ、向こうの部屋は?」
「毛皮や剥製です」
「まとめて押さえておけ。そのために『落とし』たんだ」
くつくつと笑いながら、男は悠然と屋敷内を歩いた。
ライバルと目されていた会社の倒産。その報告を受けた時はどれほど心が踊っただろう。破産宣告を今か今かと待ち構えていた甘美な日々。差し押さえられた家財一式がこちらに流れてくるのを裏で操りながらずっと待っていた。
「あぁ、君がいけないんだよ、南条君。君が私が欲しがっていたダイヤを落札なんてするから」
ようやく手元に『帰って』来たそれを見つめながら、男は薄笑いを浮かべる。競り勝った相手はすでにこの世界にいない。その妻と子ともども海に沈んだという。
一家心中と人は言う。真実など、知りうる由もなく。
「あぁ……そういえば、先週のオークションでも落札し損ねた……あれも欲しいんだ。あれも手元に収めなくては」
うっそりと笑む男の下で、宝石はどこまでも美しく輝く
緑の瞳が、それをじっと見つめていた。
○
待ち合わせの場所に降り立つと、レックスは丁度来たらしいマッド・ザ・クラウン(jz0145)に声をかけた。
「クラウン、クラウンー」
「おや、レックス。ちょうどいいタイミングでしたね」
クラウンの前にぺたんと座りながら、レックスは「むふー」と笑んだ。
「シルバが四国に来ていたであるー」
「ええ。会いに行ってきたのですか?」
「うむー!」
「おや、おや」
ふと笑んだクラウンに気付かず、レックスはクラウンの前に腹這いになった。
「相変わらず面倒臭そうにだったのであるよ。仕事が無ければのんびり我輩の腹を枕に貸すのであるが、シルバも仕事中……仕事中? なのである。残念なのであるー。なので一日だけ腹枕してきたである」
「ふたりでひなたぼっこしてきたのですか?」
「うむー! 我輩、ひなたぼっこが好きである故」
嬉しげに髭をピンッと張っているレックスに、クラウンは巨大な黒猫の背によじ登りながら微笑んだ。
「ふふふ。楽しそうですね」
「クラウンも会いに行くであるか? 我輩、案内するであるよ」
「ええ。お願いしましょうか」
「任せるである! そうだ、リトルプリンセスも来ているのであるよ。我輩、プリンセスの可愛さにトキメキである。皆で遊べたら楽しいのである!」
「ふふふ。四国も随分と賑やかになってきましたね」
嬉しげに耳をピンッと立てているレックスに、クラウンは頭を掻いてやりながら笑った。
「では、皆で遊ぶためにも、私達もまた楽しむといたしましょうか」
「うむ! 我輩、今度こそクラウンに勝つであるぞ!」
「かかってきなさい。私も負けませんよ」
微笑むクラウンに、レックスは「むふー!」と意気をあげる。
「ところで次の遊びであるが、我輩、気になる人間達を見つけたのであるよ」
「おや。達、なのですか?」
「である!」
どうやらひとりで遊びに行っている間に、興味深い人間を見つけて来たらしい。人の子の世界を楽しんでいるらしい友悪魔に、クラウンは瞳を微笑ませた。
「どんな人間達なのです?」
「むふー。これからクラウンにも見せるのである!」
髭と尻尾をピンと張って、レックスは一路四国の東へと向かっていった。
●
学園の一室で鎹雅は依頼主と対峙していた。
「連れ戻してほしい、と」
「はい」
頷く男はある資産家の親族だ。
「娘が危篤状態になっている時に何をしているのかと、そう、言ってやりたいだけでなく、本当にもう、あの子には時間が残されていないのです。それなのに……」
「ふむ……」
雅は眉をひそめて添付写真を見る。
写真に写っているのは精力的な顔立ちの男だった。いかにも上質なスーツに身を固めた紳士だが、写真でもわかる目のぎらつきがどうにも気にかかる。
「……園部、と言えば色々と曰くのある会社の社長だったと思うが」
「……」
「自身の好む蒐集物を得るためにかなり汚い手も使っていると聞く。今回動いたのも、その類か」
頷き、男はそれを口にした。
「落札し損ねたある宝石が、近々競売にかけられるらしい、と。その招待状を貰ったので行ってくると言われたのですが……」
「……娘が危篤状態なのに、か。それとも父親はそれを知らないのか?」
「いいえ、知っています。……そして、あの男は宝石をとったのです」
「…………」
男は真っ直ぐな眼差しを雅に向けて言う。
「彼を連れ戻していただきたい。欲望にまみれて進むのは本人の勝手かもしれません。ですが、せめて、家族にだけは最後に父親らしい姿をみせてほしい。せめて……せめて、最期の時ぐらいは」
●
子供の頃から不満があった。
あれが欲しい。これが欲しい。それが欲しい。どれも欲しい。
なんでも欲しくて、全部欲しくて、なのに手に入れられる量には限りがあるのが腹立たしかった。父親や母親から諭されても表面だけで頷いて内心では出し抜く方向を考えていた。
自分が持っていなくて誰かが持っているのなら奪えばいい。
誰かが手に入れて自分が手に入れられないのなら、相手を消せばいい。
どうしてそこまでして『欲しい』のかは分からない。ただ再現なく『欲しい』のだ。もっと。もっと。もっともっともっともっともっともっともっともっと……!
(この先に、秘密の集会が……!)
夜。人気のない場所。人目を避けるようにして集まるその集会で、欲しかった品がオークションにかけられる。なら、何をおいても駆けつけずにはいられない。
例え、娘が危篤だと言われても。
永遠に手に残る品が手に入るのは、今しか無いかもしれないのだから。
○
「クラウンは少しだけ離れていて欲しいのであるー」
そう言ってその建物に消えた黒猫を見送ってしばし、クラウンは眼下に現れた車に冷ややかな目を向けた。
仕掛けられた罠。かかった欲深き人間。背負う業。
けれど、そんな車を後から追う影──
「……ほぅ。彼等が来ましたか」
ならば、この先行きは誰にも見通しがつかない。
久遠ヶ原学園の撃退士が来たのだから。
リプレイ本文
──手に入れれば幸せになれると思っていた。
それは遠い日の幻想。
飢えも虚無も、手に入れられなかった過去すらも癒せるのだと思いこんでいた。
ただがむしゃらに生きて、生きて、生きて、
やっと幸せになれるのだと思ったのだ。
それが幻である事に気付かずに──
●
迫る時と競い合うかのように、八名の撃退士達が地表を走っていた。
(園部源三……欲に塗れた人間は本当に醜くて嫌になるわね)
蒼銀の髪を靡かせ、イシュタル(jb2619)はひたすらに闇を駆け抜ける。
依頼で連れ戻して欲しいと頼まれた相手──園部源三。その欲深き業には眉を顰めるものが多い。
(それに……いや、これ以上は考えても仕方がない……か)
冷ややかに細めた瞳を一度伏せ、イシュタルは軽く首を横に振る。
(何にしろ私は受けた依頼を成功させるだけよ)
「大事なものは人それぞれだけど……でも、それでも」
イシュタルの前を行く氷月はくあ(ja0811)の声が悲しげに風に流れる。
(もし叶うなら、どうか……僅かでも遙ちゃんのことを)
その愛が宝石よりも僅かなものであるとは思いたくないけれど、もし現実が悲しいものであったのなら、せめてその僅かなものでもいいから……
(せめて最期だけでも)
悲しげに瞳を揺らすはくあの隣で、蔵里真由(jb1965)も心を吐露する。
「園部……この手の人にはあまりいい印象がありませんね」
私も人の事を言えませんが、と小さく付け足す声はどこかほろ苦い。
孤児院で生まれ育ち、その出自故に借りや憐憫の眼差しに対して過敏に反応してしまう自分を彼女は冷静に知覚していた。
分かっている。そこには確かに自分達への仄かな愛情があった場面もあるだろうことは。
知っている。自分が基本的に冷たく、打算的であることも。
理解している。自分が人見知りである事も──その反面、人恋しく寂しがり屋だということも。その裏側に、未だ知らぬ決して揺るがぬ繋がりへの渇望を秘めていることも。
(どうして……)
自分が手に入れられなかった宝物を『彼』は持っているのに、どうして無機質な宝石等に目を奪われてしまうのだろうか。
複雑な思いを抱く真由の隣で桐原雅(ja1822)も心の中で独り言つ。
(正直、彼が自身の欲の為に酷い目に遭うのを積極的に助けたいと思う気持ちは、今のボクにはもてないと思う)
けれど、それでも──
(でも遙ちゃんが望むのなら、連れ戻すのに是非も無いよ)
凛と決意を目に宿す雅のすぐ後ろ、機嶋結(ja0725)は眼差しを細める。
(父という人は……もっと温かい人の筈)
その脳裏に浮かぶのは亡くなった実父の姿。唯人の身でそれでも懸命に家族を守ろうと、悪魔の前に立ちはだかったその人の。
(園部は……『彼』は父親じゃない。私が嫌悪する人と同じ人種)
けれど『彼』を待つ娘の為に言葉はかけるだろう。されど耳を貸すものだろうか。
──人の皮を被った悪魔が……
「欲しがることそのものは時に向上心に繋がったり、積極性の源となることもあります。何に価値を重く置くかも人それぞれなのでしょうけれど……」
風に神月熾弦(ja0358)の寂しげな声が攫われる。
「それでも、たった一人の父親を慕う気持ちにぐらいは応えてほしいと、人はそうであってほしいと……」
そう思う。祈るような気持ちで。
親子の絆を願う仲間達の傍らを羽空ユウ(jb0015)は駆ける。
(――血の繋がりなど、些末)
己の身で其れを知っている。其れが全てでは無いことも理解した上で、けれど現実に在るものも決して無視は出来ないから。
(血が繋がっていようとも……私は、あの人達を)
溢れる程の殺意は、彼女の過去に起因するものだ。
(でも)
もし可能なら。
(誰かの、家族は)
せめて、ささやかでも、希望を。
自分には望むべくもなかったから。
「人の欲が今回の敵なら、私は狙い撃つのみです」
父と娘。欲望と切望。
二つの思いへの思考が心の波紋となって少女達の気配に細波をたてる中、石田神楽(ja4485)は静かに声を落とす。
その顔は常に笑顔を浮かべ、その瞳は冷静にそこにある現実を見据え、暴く。
「父娘を会わせる為に、ね」
その悲しき業(カルマ)を打ち破る為に。
○
幼い日。手に入る物などほとんど無かった。
誰もが持っている品ですら自分は持っていなかった。嗤われ、馬鹿にされ、どれほど悔しい思いをしただろうか。
欲しい物は沢山あった。どれもこれも欲しい物ばかりだった。
ウエテイタ
けれど手に入る物は限られていた。
父も母も真っ当な人間だった。真っ当な人間だったから、何も残せないままに冷たくなった。古い薄汚れた集合住宅の片隅で、葬儀すらも執り行えままに──墓すらも無く。
ただ、飢えだけが深まっていった。
手に入れる為なら何でもやった。
ウエスギタママ
手に入れて手に入れて手に入れて、血と泥にまみれ金を積み上げながら、憎悪を積み上げた。
そんな中、一人の女性に出会い、家族を得た。
手に入れたと思った。この飢えを満たす永遠を。
それが儚い幻だと知らないままに。
ウエハマダ イヤサレナイ
●
「は、はは、着いたぞ! ここだ」
車のライトに照らされた建物に、園部源三は生唾を飲み込んだ。
郊外の一角。人里離れたその建物は、闇の中でひっそりと佇んでいる。
入り口にはこちらを誘うかのような外灯の明かり。急ぎ、足をもつれさせるようにして車の外に出た源三の顔は、奇矯な笑みが浮かんでいる。
(ここに、あの宝石が)
永遠に輝きを失わないものが。消えないものが。
(私の)
──妻の瞳と同じ色の。
源三の足は止まらない。長時間の運転によるものか、よろめき、ふらつきながら建物の門をくぐり──
ふいに周囲に漂った腐敗臭に立ち止まった。
「……ぁ?」
饐えた臭いが周囲に満ちる。止まり、見渡す周囲の地面から、生えるようにして蠢き出てくる十体の犬。──半分、腐り溶けた姿の。
「……来たのである……」
建物側で、どこか嘆息をつくような声が聞こえた。
「目標捕捉! 同時に敵影十体捕捉しました!」
間一髪、同時刻に現場へと走り込んだ真由は、建物の外灯にかろうじて照らされた男の姿と周囲の敵の影に鶺鴒を構えた。
「距離測定、戦闘に入ります!」
真由の放ったた矢が最も近い敵影を射抜く。唸り、振り返り、敵としてこちらを認識した腐乱犬の群れに熾弦が斧槍を手に突っ込んだ!
「こんな人気のないところでオークション、というのは……売る側からすれば、参加者がいればいる程良い筈ですのに。気になっていたら、こういう事でしたか」
「効率の悪すぎる競売だとは思いましたが……」
事前に出来る限りの捜査をしていた神楽も低く呟いた。
競売は人が多いほど益が出る。その観点から言えば、今回のこれはあまりにも効率が悪すぎる。だからこそ罠である可能性を疑っていた。
果たして、今在るこの光景こそがその答えだ。
「な、なんだ……何が」
さすがに異常事態を察して狼狽える源三の手前に、熾弦に続いて神気を纏ったイシュタルが走り込んだ。
「手の込んだことね。察するに冥魔勢ってところかしら」
「なっ!?」
明らかに人外の神々しい雰囲気に源三は愕然とした。伝え聞くも直接相対することは無かった天使種族だと、その神気が告げている。
「敵は円陣を組んでいます! 距離は対象から約五メートル、敵はほぼ等間隔配置です!」
夜目により視界を確保したはくあが仲間達におおまかな位置を知らせた。念のために阻霊符を移動前に発動させていた結と、異変に即座に反応したユウの阻霊符により周囲には不透過の結界が敷かれる。
結は憎しみに淀んだ瞳で周囲を見渡す。絶望と怨嗟、そのあらゆる全ての根元たる悪魔共。その眷属──
(……虫酸が走る)
ああその存在全てを死滅さえることが出来れば、この胸の奥にある凝った泥のような憎悪は癒されるかもしれない。話せば分かるなど綺麗事だ。そんなものは、奪われたことのない者だけが口に出来る欺瞞に他ならない。
おぞましいものの全てを味あわされて尚、口に出来るの者が居るのならばともかく。
「なんなんだ、君達は!」
周囲に満ちた戦いの気配と腐敗臭、そして唐突に現れた八人の撃退士に、源三は引きつった声をあげた。この状況下で取り乱す内容がその程度というあたり、ある種肝が据わっているとも言える。
「私達は、撃退士。貴方を、連れ戻してくれるよう頼まれた。故に、保護に来た」
「保護だと!?」
「必要、と思う。今は。違う?」
淡々とユウに言われ、源三は喘ぐように建物と周囲の魔物を交わし見る。
それを横目に、雅は腐乱犬に側面に回り込み掌底を叩き込む。悲鳴を上げて吹き飛んだ個体を冷ややかに見据え、護衛と源三に敵が行かないよう気を引き締めながら言った。
「遙ちゃん、危篤なんじゃないのかい?」
「!?」
「こんな所に居る場合では無いでしょう。最期でも……父親らしい所も見せられないのですか?」
結が極力感情を排した声で雅に続く。円陣の中央に立つ源三を護るのはイシュタルと熾弦。やや遅れて走るはくあの為、神楽が広げた道のをさらに広げるべく銃弾を放つ。
「ギャゥ!」
悲鳴をあげて負傷した腐乱犬が神楽をにらみ据える。敵愾心は群れで連動するわけでは無いらしい。撃退士たちから遠い建物側の敵は未だに源三を狙っていた。
(護衛と敵の間に入る予定でしたが……)
円陣で包囲されているとなると、全方向からの攻撃に対応しなければならなくなる。その危険性は誰もが熟知するところだ。
「「身柄の確保と撤退を!」」
僅かの逡巡もなく雅と真由が声を揃える。
依頼は源三を引き戻すことだ。もはや余命幾ばくもない娘に会わせたいと願うなら、戦闘は本来二の次三の次。必要なのは、彼の身柄と──時間。
「彼の車が使えますね」
放置されている車を示唆し、雅は殿になるべく主に建物側の警戒にあたる。そこへ攻撃対象を絞った腐乱犬が襲いかかってきた!
「射線再確保、行きます」
真由の腕が闇の力を纏い、重なるようにして雅に向かってきた二体を横合いから穿つ。同時に真由に向かって疾走する腐乱犬に向かってユウが魔法で牽制した。
だが、
「じょ、冗談ではない……! なにが起こっている!? 突然現れて……私は、そこの建物に……」
「そんな場合じゃない、って、気づけないのかな?」
未だに事態を把握出来ない源三に雅の眉が跳ね上がった。ユウが油断無く構えながら言葉を重ねる。
「オークション。人間からの情報? 敵に囲まれている、何故?」
「そ、そんなもの、私が知りたい!」
「金、積んでも手に入らない、貴方の命。撃退士、此処にいる敵、怪しいオークション。何らかの作為があると想定、する。どう?」
「なん、だと」
「……このディアボロ達は、貴方が悪魔に罠にかけられた証」
源三に向かって飛びかかる腐乱犬の前に盾となるべく身を晒しつつ、熾弦が声をあげた。
「貴方は、悪魔に『危篤の娘の傍にいてあげる機会』を、奪われようとしているのですよ?」
「ッ」
一瞬、源三の目尻に走った動揺に、こじ開けられた戦場へと踏み込み、源三への攻撃を身を挺して庇いながらはくあが呼びかけた。
「嫌いじゃないんだよね。遙ちゃんのこと」
動揺した。それが証拠。
「な、何故、君達が私の娘の名を知っている!?」
「先に言ったように、依頼を受けたからです」
向かい来る腐乱犬の攻撃を躱し、油断無く逃走ルート確保の為に照準を合わしながら神楽が告げる。
「娘さんを置いて、こんな場所に居る理由は何です。競売? たかが石に釣られて、その挙げ句が命を失いかねない状況ですよ。まだ理解できませんか?」
静かな声、静かな笑み。そこに宿る怒りに何人が気づけただろうか。
「たかが、石、だと!?」
源三は目を見開く。求めていたものがすぐ傍にある。ただの欲深い程度の人間であればディアボロの姿が出た時点で尻尾を巻いて逃げていただろう。『ただの欲深い程度の欲』であれば。
欲が、尽きない。
それを前にしては人も自分も命も心ももはや何もかもどうでもよいほどに価値を失い形を失いまるで掠れ消えかけた風景画のようなものに成り下がる。理由なんて分からない。ずっとずっと分からない。ただ飢えている。欲しくて欲しくて欲しくて欲しくて。ずっとひたすらに飢えているのだ。
「一度手に入れれば失わずに済む、あれほどに永遠に変わらず手元に残る物を、ただの、石と」
「ただの石でしょう。色がついているだけの」
「なにを……ッ」
源三が足を踏み出す。建物側ではなく、車の方にいる神楽へ。戦況が動く。要保護者が移動する。神楽は告げる。彼の、彼すらも知覚しなかった、その根源を。
「貴方が求めているのは宝石でも金銭でも無いでしょう」
○
妻は美しかった。優しかった。暖かかった。
寒々とした白と黒の世界から、鮮やかな世界へと連れ出されたような気がした。
狭く薄汚れた建物から一戸建てへ。死にものぐるいで築き上げた財が彼女との生活を支えた。
やがて妻が身ごもった。
手に入れたと思った。
満たされたと思った。
それが幻に過ぎないと分かったのは、その出産の日。
妻が死んだ。
幼くか弱い、生まれながら欠陥を抱く、儚い命の娘と自分を残して。
ウエガマタ フカマッタ
●
「なに、を」
棒立ちになった源三とその身を庇う熾弦に迫る腐乱犬に、結が光の波を打ち放つ。彼を無事に確保するためにも、移動させないといけない。けれど、だからこそ、今は邪魔をさせてはいけない『時』だ。
「宝石を得て貴方は満たされましたか。欲しいという欲望は止まりましたか」
「……っ」
「止まらなかったでしょう。違う物をどれだけ集めても、貴方の欲望が満たされること等あるはずがない」
それは誰も知らない欲望。
どこにも調書は無く、だから誰も気付かなかった。神楽以外には。
調書に書かれていないからこその違和感。記されていないからこそ把握した『欠如』。
その根源に至る細い糸のような情報。
──彼は僅かな情報からそれをたぐり寄せたのだ。
源三は元より欲深かった。それは幼い頃からだった。
だがその欲の種類は違っていた。けれど源三自身がそれを知覚することは無かった。
欲望は在る。
けれど何が欲しいか分からないから、欲が暴走した。
どれだけ集めても満たされることは無かった。そこに、彼が本当に求めるものは無かったから。
「永遠に残る? 自惚れるな」
告げる神楽に向かう腐乱犬をユウの魔法と真由の炎熱の鉄槌が打ち砕く。言葉を途切れさせない。ここが、全ての正念場。
「人は永遠を求めないから、今を生きていけるのです」
人は永遠には生きられない。その命は決して永久には続かない。
儚いものなのだ。その生は。およそ百年にも満たないほどに。
それは悲しむべきことだろうか。虚しいことだろうか。
否。断じてそうでは無い。
永遠とは求めるべきものでは無いのだ。
有限の者が限られた時間の中で懸命に生きるその全てにこそ、人の生の神秘がある。其れは決して無限のものには生み出すことの出来ない奇跡。
「貴方を求める、遙さんのように」
源三の目が大きく見開かれる。息が止まる。思考が途切れる。頭を占めていた欲望が消えた一瞬だった。
真由はその一瞬を見逃さず声をかける。
「あなたの欲望は娘へは注がれないんですか?」
説得の言葉を邪魔させない為に、はくあが腐乱犬に牽制の一撃を叩き込む。
「この世でもっとも美しいものなのに。愛も涙も永久には続かないけど刹那にしかないからこそ美しいのに」
それは神楽の語るものと同じく、永遠でないからこそかけがえのないものの示唆。
「宝石なんて炎にまかれればくすんでしまうのに?」
形在るものは必ず滅びる。それは世の必定。
「このままだとあなたの宝石には瑕がつきますよ? どんなに美しいものを見ても、亡くしたモノがチラついて愛でられなくなってもいいのです?」
それは源三が既に体験した『現実』。
「自分にとって喪われて取り戻す事が出来ない物、宝石の他にないのか、もう一度思い返してください」
迫り来る一撃を引き受け、熾弦も告げる。その傍らから牙を剥く別の個体をイシュタルの双剣が切り裂いた。
「人間にとって、家族っていうのは、その程度のものなのかしら?」
「渇望……私が、知識を欲する、理由、も、似ている」
問いを、自身をもう一度見直すきっかけを投げかける皆の中で、ユウは彼のもつ衝動の一端を容認する。その全ては無理だけれども、拒絶や否定だけではなく。
「でも、私は、もう少し手段、選ぶ。貴方、随分と敵が多い……その行動が、少しずつ違えば……動く人間、増える」
まるで自分以外の全てを拒絶しているかのような動き。肉親すらも顧みないその在り方。自分が変われば、世界もまた変わるかもしれないのに。
……自分の中にある真実に気付けば。
「宝石がどうだって言うのかな。手に入れる機会は今しかないかも? 違うよね。今しかないのは遙ちゃんの方なんだよ」
淡々とした口調で雅が告げる。その言の葉に僅かに責める雰囲気を滲ませて。
時は戻らない。決して。
そして進む先で失うのは、命を持たぬ石ではなく、か細い命の娘だ。
「今まで散々、自分の欲しいものの為に遙ちゃんを蔑ろにしてきたんだ。なら……最後くらい、遙ちゃんのたった一つの願いを叶えてあげようって。そう思えないのかな……自分の娘でしょ」
放たれた薙ぎ払いが雅の眼前に居た一体に痛恨の一撃を食らわせる。強制的に意識を刈り取られたその一体に、はくあがトドメの一撃を放ち、声を絞り出した。
「もし……どうしても宝石の方が大事だって言うのなら」
せめて、と願いを込めて。零れそうな涙を堪えて。
「だったら……宝石の方が大事でも別に良いから……会ってあげてください」
もう今を逃せば二度と会うことは出来ないかもしれない命に。
娘に。
「私、は……」
源三が呻く。強ばった顔に浮く脂汗が、彼の内心の葛藤を伝えていた。
心が無いわけではない。無いわけでは……無かったのだ。
「貴方の娘は今、貴方『だけ』を求めているのですよ」
円陣を崩し、迫る腐乱犬へと咆吼にも似た音を響かせて弾丸が放たれる。一度に三撃。それを放った銃は神楽の片腕と完全に同化している。腕そのものが禍々しい長銃と化したその技のためか、肩部排出口からは黒いアウルの残滓が流れていた。
源三はその姿を見る。
天魔と戦うべく彼等に与えられた力。その形。人々を護るために在る者の姿と言葉を。
「『欲』ではなく、『想い』からね 」
●
コトリ、と音がした。
残った三体の腐乱犬が退くように撃退士の側から離れる。じりじりと建物と反対側の方に動く犬の視線は建物に。先程響いた音の方へと向いていた。
そして、
「な」
見た。
「猫!?」
大きな頭。大きな目と耳。どこかあどけない表情。明らかに子猫と思しき外見。大きさだけ牝牛並。
そんな相手が外灯の下で二本足で立っていれば誰でも驚くだろう。さしもの結と神楽も絶句している。
無論、かといって戦況を忘れ続ける彼等では無い。驚愕をわずか一瞬で押さえつけ、即座に警戒へと切り替えたのは流石の一言だろう。
そして、こんな場に唐突に現れる相手を見抜けない彼女達でも無い。
「悪魔」
ユウと結の声に猫悪魔は髭をそよがせる。軽く首を傾げるような姿は、どこか大きなぬいぐるみにも似ていた。
「……我輩、また負けたであるか……?」
しょんぼりとした声が流れた。悪魔から。
見れば大きな耳もぺたんと垂れて、長い尻尾は足元にくるりと回っている。
「……我輩、今度こそと思ったである……きっと勝てると思ったであるぞー」
くるりと足元に回した尻尾の先を大きな肉球のついた前脚でいじりながら、大きな大きな子猫がいじけたように言う。
なんだろうか、この不思議の国は。巨大猫が青いジェストコールを着込んでいることからして、なにか喜劇の一場面に招かれてしまったかのような錯覚を受ける。
「まさか、直接、悪魔が出てくるとはね」
イシュタルはこめかみを伝う汗を知覚しながら呟いた。
ファンシーな外見とは裏腹に、悪魔の立ち姿には隙がない。隙しかないような気がするのに、何か奇妙に『攻め込ませない』形となっているのだ。
「彼を病院へ!」
熾弦の声にはくあが源三の手を引き、駆ける。反射的に追った腐乱犬をユウと神楽が同時に撃ち抜いた。
あと二匹。
「きみが全ての元凶?」
雅の声に猫悪魔は首を傾げる。子供のような仕草で。
「我輩?」
「こんな所に居るってことは、あの人間を誘き寄せたのはあなたってことよね?」
イシュタルも言葉を重ねる。源三が逃げ切るまでの時間を稼ぐためにも。
「何が目的だったの?」
「目的、であるか」
猫悪魔は反対側に首を傾げる。そうして頷いた。
「我輩は知りたかったのである」
素直に。
「人は欲望に負ける生き物であるか? 打ち克つ生き物であるか? 七つの大罪とやらは、人間達が勝てぬ欲であるか? 我輩、知りたいである」
「その為に……?」
「我輩、嘘はついておらぬであるぞ」
黒い猫悪魔は胸を張る。その首元、スカーフの所にある青い宝石。
「こちらに来たれば、我輩、ちゃんとこの宝石を渡すつもりであった。勿論、その後食べるであるが」
競争相手のいない競売。代価は命。
魂を売り渡すかのような所行に対する罰のように。
「されど、おぬしらが邪魔をしたのである。途中までは我輩が勝っていたのに」
源三を乗せた車が出発する。護衛を兼ねて乗り込んだのははくあと、寸前で癒しの風を解き放った熾弦。このまま脱出をしてくれれば。注意深く悪魔を観察する神楽の視界が、その時黒に染まった。
否。
「我輩、ここは抗議するべきところであるな?」
恐ろしく目の前に悪魔が居た。
「ッ?」
まるで瞬間移動のようにすら思えた長距離移動。自分達が行う全力疾走ですらない。まさか、これが、
(素の、移動力……!)
構えるのと衝撃が全身を叩くのが同時だった。
「なッ」
そのあまりの速度にイシュタルが声をあげる。肉球で吹っ飛ばされた神楽に愕然となっているうちに、残像のように黒い巨体が背後に現れた。
「我輩、無念である!」
鞭のようにしなった滑らかな毛触りの尻尾がイシュタルと雅の体を吹き飛ばす。そこへ大剣を構えた結が走り込んだ!
「悪魔というものは……本当に、勝手気ままなものなのですね」
「ふむん?」
猫悪魔は髭をそよがせる。そうして渾身の一撃を躱すと同時、
「ふむぅ、複雑な匂いがするであるー」
なんと、少女の匂いをふんふん嗅いだ。
「な……ッ」
「焦点が絞れておらぬ憎しみは成長の妨げとなるであるか……?」
「なにを……」
大きく剣を振りかぶったその体が、もっふ、と絶妙な角度で相手の頬の毛に埋まる。そのまま吹っ飛ばされて結は絶句した。
「狭き視野は盲目に同じである。心配であるぞ? あっ、おぬしらが強くなっては困る故、忘れていいであるぞっ」
「ね、猫さんもふもふ‥‥いえ、今は仕事中。我慢我慢」
そのあまりのもふっぷりを目にして思わず心の声が漏れた真由、ぬん、と現れた猫のドアップにぎょっとなった。
「そぉれー」
「い゛!?」
頭突きが来た。斜め下から体を掬い上げるような一撃に、ぽーんと体が跳ね上げられる。ユウが身構えながら言葉を放った。
「強者が、敗者を淘汰する。人間も天魔も、変わらない」
「ふむ?」
「貴方、に、渇望するもの。は、ある?」
彼等の遊戯的なものに怒りは無い。それは無邪気な邪悪さを内包しつつも、人も同じものを抱えているが故に。
「――私には、ある。だから、まだ、死ねない」
「……」
「……哀しい、ね」
ふむ、と黒猫は呟く。何かを考える表情で。
「智を欲する者であるか。人の子も。ふむ。ふむー」
長い尻尾がぴたんと地面を叩く。ピンッと髭がそよいだ。
「面白いであるぞ。先の男の回答も面白かった。うむ。我輩、負けてしまったが、別のものを手に入れたである!」
ピピンッと耳と尻尾も立つ。
「人は弱いである。欲にも弱いである。であるが、撃退士がそこに入る時、事態は覆るである」
「!」
「ならば、決めたである」
トン、と軽い音がする。同時、巨大な黒猫の体が闇夜に消えた。否、おそらくその異常な脚力を使って移動したのだろう。次に聞こえた声は遙か遠かった。
「次の遊戯も決めたである。さらばである!」
隙を狙われることを警戒して見張っていた腐乱犬も同時に姿を消す。身を起こし警戒にあたっていた神楽は小さく呼気を吐いた。
「……退いた、みたいですね」
まるで新しい玩具を見つけた子供のように無邪気に。あっさりと。
「あれが、悪魔」
今までとは妙に毛色の違う、奇妙な悪魔。
「……悪魔の、くせに……」
体が埋もれたふわふわの毛の温もりを思いだし、結が拳を握る。心配、だと? 何も知らないくせに。悪魔のくせに。その毛触りと温もりが柔らかく優しいだなんて、嘘だ。
「それよりも、遙ちゃんだよ!」
思わぬ珍妙な悪魔に意識を奪われかけ、雅が慌てて声を上げた。ハッとなった一同が即座に全力疾走を開始する。間に合うのか。間に合わぬのか。それを見届けるべく六人は駆ける。
人の持つ可能性に願いを込めながら。
●
「……そうか……」
電話で告げられた言葉に、鎹は目を伏せた。
少女は逝った。念願の父親との対面を果たして。
欲深き業を負った父親は、その後、自ら警察へと出頭したという。その身に蓄えたほとんどの財を慈善団体へと寄付して。
手に残ったのは小さな青と黄色の宝石が一つずつ。
不思議なのは、娘が危篤状態に近づく直前に長かった髪が短く切られていたことと、源三の元に残った宝石のうち、黄色い宝石が何処から出てきたのか分からないことだと依頼主は語る。
娘の死後、いつの間にか源三の元に届けられていたという黄色い金剛石。
「炭素……髪……金剛石」
そういった技術があるのは知っている。だが、誰が?
誰かが誰かの願いを叶えたのだろうか。それは少女の願いだろうか? 源三や親族以外の誰かが?
鎹は伏せていた目をあげる。
謎は残る。疑問は解けない。けれど、世界とはすべからくそういったものに満ちている。
(もし、源三があのまま生き様を改めなければ)
そう遠くない未来で悲惨な結末を迎えていたことだろう。瓦解した心と底なしの欲望を抱えて。
生徒達はそれをも防ぎきったのだ。
「あの子達は我々の誇りだ」
強さと優しさを兼ね備え持つ学園の生徒達。自分達が届かなかった高みへも、きっと何時の日かたどり着くだろう。
永遠なんてあり得ない。
止まらぬ歩みが続く限りはいつか。
「……いつの日にか」
○
葬儀は晴れ渡った空の下で行われた。
ひっそりと執り行われる人間の葬儀を離れた場所で巨大な猫と小柄な幼子の影が見つめている。
「……また負けたである」
「そうですね」
「我輩、めっきり勝ててないのであるぞ」
しょぼんと髭をそよがせているレックスに、クラウンは苦笑を浮かべ、ややあって彼が見ている方向に視線を戻した。
煙が空へと上がる。その、細い細い天の道。
「宝石の作成……ですか。そんな技を持つ、というか……そんなことに技を使うのは貴方ぐらいなものでしょうね、レックス」
「ぬー」
クラウンの声に、レックスが気の抜けた返答を返した。
抽出・精製・熱・圧力・研磨……工程に必要な一連の技能をレックスは有している。実際には宝石を作るための技では無いのだが。
(レックスは食べられないものには興味は持たない質ですが……)
されど往々にして世界とはそういうものなのかもしれない。欲する者の所には無く、欲さない者の所に在る、何かの悪戯のような何か。
「あの人の子と、何か会話でも?」
「……会話と呼べるものは無かったである。独り言を聞いたぐらいであるー」
レックスは髭をそよがせながら答える。静かな眼差しと声のままで。
そう、会話など交わさなかった。ただ訪れたその時に、死を間近にした子供が、熱にうなされるようにしてぽつぽつと語っていたのを横で聞いていただけだ。
ただひとり。
言葉など、交えずに。
──その思いを受けただけ。
「ねこちゃん」
そう人の子は呼んだ。動かない体で、声を出すのすら辛そうな体で。
「あたし、死ぬのかな。お母さんと同じように消えちゃうのかな」
「……」
「そしたらお父さん、ひとりぼっちになっちゃうのかな」
「……」
「お父さん、お母さんの瞳だよ、って言って宝石だけ残していなくなっちゃうの。お母さんの目、綺麗な青色なんだって宝石で知ったの。あたしも、死んだら、宝石になるのかな」
母のような青い色では無いけれど。
「宝石になったら、お父さん、見てくれるかな」
実際にはずっと長い時間をかけて、途切れ途切れにそう語った人の子の娘。人が死んで鉱物になるなど本来あり得るはずもない。そんな夢物語を本気で語っていた。その理由をレックスは知らない。
「お父さんの、傍にいられる……かな」
その思いの名を彼は知りたかった。
愛という名の切願(ねがい)を。
「人間は……謎なのである」
「おや」
レックスは立ち上る煙を見上げて髭をそよがせる。見送るように。空を見上げて。
「貴方の疑問はなかなか解けませんね」
「うむ。疑問は尽きぬのであるぞ」
「では、新たな疑問を解きに行きますか」
「行くであるー!」
レックスは踵を返す。その背の向こうに一筋の煙。
天に還る命の軌跡。
永遠に存在しないのに、永久に胸中に在り続けるもの。
それは決して形在る物ではなく、触れられる物では無く、けれどそこに確かに在って人を癒し包み込むもの。
目には見えない刹那にも似た愛しい久遠の欠片。
そのものの名を──愛と云う。
撃退士八人は、それを護り示したのだ。
依頼結果
| 依頼成功度:大成功 |
| MVP: 黒の微笑・石田 神楽(ja4485) |
| 重体: − |
| 面白かった!:15人 |
 |
撃退士・ 神月 熾弦(ja0358) 大学部4年134組 女 アストラルヴァンガード |
秋霜烈日・ 機嶋 結(ja0725) 高等部2年17組 女 ディバインナイト |
|
 |
ヴァニタスも三舎を避ける・ 氷月 はくあ(ja0811) 大学部2年2組 女 インフィルトレイター |
 |
戦場を駆けし光翼の戦乙女・ 桐原 雅(ja1822) 大学部3年286組 女 阿修羅 |
| 黒の微笑・ 石田 神楽(ja4485) 卒業 男 インフィルトレイター |
運命の詠み手・ 羽空 ユウ(jb0015) 大学部4年167組 女 ダアト |
||
| 高コスト体質・ 蔵里 真由(jb1965) 大学部3年194組 女 ナイトウォーカー |
 |
誓いの槍・ イシュタル(jb2619) 大学部4年275組 女 陰陽師 |
|

