|
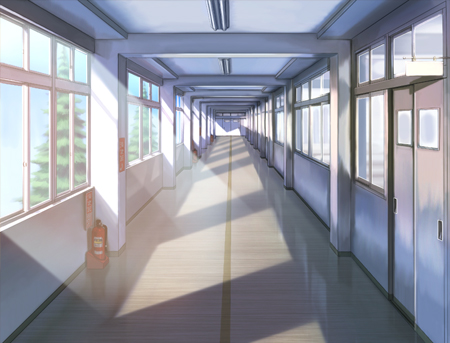 |
みんなの思い出
オープニング
●
大江芙紗子は、何をするにも他者からの視線を避けては生きられない少女であった。
最大の理由は彼女の「体」である。
芙紗子は体が大きい。
何しろ彼女が小学校に入学した時、すでにクラスの男性担任よりも背が高かったのだ。芙紗子のクラス内におけるポジションは、入学初日にして早くも決まってしまっていた。
健康診断の時などは、憂鬱で仕方がなかった。たまに転校生が来ると聞いた時は、どうか背の高い人でありますようにと毎回祈った。あいにく今日に至るまで、その祈りが神様のもとに届いた事は一度もない。
高学年になり、芙紗子より背の高い者が学校に一人もいなくなる頃には、「力」の方もぐんぐんと成長していった。
6年生のある日、同級生の男子から身長を笑われた芙紗子は、軽い反撃のつもりで彼の背中を叩いた。
そうしたら、その男子は吹き飛んだ。
比喩や例えではない。彼の体は本当にマンガのように吹き飛び、教室の黒板に激突したのだ。
打撲で済んだのは奇跡と言うほかなかった。
当然ながらそれ以来、彼女をからかうクラスメイトは一人もいなくなった。
毎日が針のむしろだった。
●
大江芙紗子とは、そんな少女である。
だから少し前に実家に帰って自分達が悪魔の一族だと両親から告げられた時も、驚きは全く感じなかった。
自分の血筋についても、飼い猫の悪源太が父のヴァニタスである事も、色々あって家に戻る前には知っていたし、むしろ、どうしてもっと早く教えてくれなかったのかと両親を恨む気持ちのほうが強かったくらいだ。
両親は両親なりに自分がショックを受けないよう配慮をしてきたつもりだったのだろうが、芙紗子にはそれが煩わしく感じられて仕方がなかった。
いい機会と思い、芙紗子は両親の橘之助と紀美子に、アク――悪源太の事を尋ねた。
「パパ。ひょっとして私のこと、ずっとアクに見張らせてたわけ?」
「……そうよ」
首肯する紀美子を見て、喉まで出かかった怒りの言葉を芙紗子は必死に飲み込んだ。
「だったら、私が撃退士になりたいと思ってることも知ってるんだよね」
しばしの沈黙の後、橘之助は口を開いた。
「ひとつだけ言っておく、芙紗子。お前を学園には絶対に入れんぞ」
「どうして?」
「どうしても、だ。――この話をこれ以上続ける気はない」
父親に話を打ち切られ、その時は結局それ以上、話を続けることは出来なかった。
芙紗子は落胆に肩を落として帰宅したのだった。
●
それから数ヵ月後。
話の舞台は京都府、某市内の公立中学校へと飛ぶ。
●
「えー、大江さん。どうぞ」
男性の教師が教室のドアから顔を出して、廊下にいた芙紗子と橘之助を呼んだ。
「本日は三者面談にお越しいただき、ありがとうございます。担任の中島です、どうぞよろしく」
入口のドアをくぐるようにして教室に入ったふたりに椅子を勧めると、眼鏡をかけた中年の男が自己紹介をした。
学校で一番背の高い芙紗子の父親と聞いて、どんな巨人がやって来るのだろうと中島は内心冷や冷やしていたが、以外にも橘之助の体格は芙紗子と大して変わらない。
内心で安堵の溜息をつくと、さっそく中島は本題を切り出した。芙紗子の卒業後の進路についてである。
「さて、大江さんの進路ですが。彼女は成績の方も良く、生活態度も真面目で……」
成績表を机に広げ、あれこれと説明をする担任の話に、橘之助は満足げに頷きながら聞き入っていた。
「それで、大江さん。希望する学校の事ですが――」
「私は、久遠ヶ原学園への入学を希望します」
担任の中島の言葉を継いで、芙紗子がはっきりと宣言するように言った。
それを聞いた中島が、眼鏡を押し戻して芙紗子に問いかける。
「ふむ。なぜ久遠ヶ原への入学を?」
「はい。それは――」
いい機会と思い、芙紗子は父親と担任に自分の思いを打ち明けることにした。
無論、自分と父親が悪魔であるという事は言わずに、である。
毎日のように、自分が友達を傷つける恐怖に苦しんでいたこと。
このまま皆と一緒に暮らしていたら、きっとまた誰かを傷つける事になる、そんな風に考えていること。
芙紗子は育ち盛りの年頃である。これから体が更に大きくなって、力も更に強くなることだろう。
そんな自分が皆と一緒に生活して、何かの拍子に人を傷つけてしまったら?
考えたくはなかった。だが、考えることをやめたら普通の人と同じ体になるわけではない。
芙紗子は自分の生まれ育った土地を愛していた。叶うならば、ずっとこの街で生きていきたい。しかし……
「私、怖いんです。このままアウルをコントロール出来ずにいたら、また人を傷つけてしまうんじゃないかって。それも恐らくは、取り返しのつかない形で……」
大きな深呼吸の後、芙紗子は言葉を継いだ。
「でも、撃退士になってアウルの制御の仕方を学べれば、私が人を傷つけることもなくなると思うんです。それに、『力』の事で相談できる相手が欲しいという気持ちもあります。学校の友達や、家族には話せない事も出てくると思うから……」
芙紗子が自らの気持ちを余すことなく伝えると、教室に沈黙が流れた。
担任の中島は、真剣なまなざしで何度か小さく頷いた。彼女が本気であること、彼女が目指す将来がどのようなものであるかを理解してくれたのであろう。
「お父さん、如何ですか? 彼女はああ言っています。担任としては、応援したいというのが正直なところですが」
「パパ、先生。私を学園に行かせて」
両親から目をそらさずに芙紗子が言った。本気だった。
だが、父である橘之助の答えは残酷だった。
「駄目だ」
「どうして?」
芙紗子が即座に問い返した。
その顔にはいつもと同じ笑顔を浮かべているが、よく見ると背後の景色が陽炎のようにゆらめいている。
「久遠ヶ原学園は信用できんからだ」
「まあまあ、ふたりともちょっと落ち着――」
「学園のどこが信用できないの? 悪い天魔から、私たちを守ってくれてるのに」
「お前が知る必要はない。入学は諦めろ」
「そんなので納得できるわけないじゃない。ダメだっていうなら、理由くらい教えてくれてもいいでしょ」
教室内に一触即発の空気が流れる。
その光景を窓の外から、どこからか入り込んだ一匹の黒猫が心配そうに眺めていた。
「駄目だ」
「だから、どうして!」
「駄目なものは駄目だからだ」
その時、担任の中島は確かに見た。芙紗子の頭に、二本の角が生えるのを。
「ふざけんなこのバカ親父!」
●
「緊急の依頼が入りました。京都府内の中学校で、アウルを駆使する親子と思しき二人が喧嘩をしているとの事です。直ちに現地に急行し、喧嘩を止めてください」
斡旋所の職員は、事の経緯を手短に説明した。
つい先ほど、「悪源太」と名乗る男性から、学校で親子が暴れているから止めてほしい、という要請があったというのだ。
その男性の話では、暴れている親子は共に悪魔であり、一歩間違えば周囲に甚大な被害を及ぼしかねないという。
「なお、依頼主からの要望で、この親子が悪魔であることを学校の生徒と関係者には絶対に知られないようにして欲しいと言うことですので、この点は厳守を願います。――それでは、受諾を希望される方は窓口にて手続きをお願いします」
大江芙紗子は、何をするにも他者からの視線を避けては生きられない少女であった。
最大の理由は彼女の「体」である。
芙紗子は体が大きい。
何しろ彼女が小学校に入学した時、すでにクラスの男性担任よりも背が高かったのだ。芙紗子のクラス内におけるポジションは、入学初日にして早くも決まってしまっていた。
健康診断の時などは、憂鬱で仕方がなかった。たまに転校生が来ると聞いた時は、どうか背の高い人でありますようにと毎回祈った。あいにく今日に至るまで、その祈りが神様のもとに届いた事は一度もない。
高学年になり、芙紗子より背の高い者が学校に一人もいなくなる頃には、「力」の方もぐんぐんと成長していった。
6年生のある日、同級生の男子から身長を笑われた芙紗子は、軽い反撃のつもりで彼の背中を叩いた。
そうしたら、その男子は吹き飛んだ。
比喩や例えではない。彼の体は本当にマンガのように吹き飛び、教室の黒板に激突したのだ。
打撲で済んだのは奇跡と言うほかなかった。
当然ながらそれ以来、彼女をからかうクラスメイトは一人もいなくなった。
毎日が針のむしろだった。
●
大江芙紗子とは、そんな少女である。
だから少し前に実家に帰って自分達が悪魔の一族だと両親から告げられた時も、驚きは全く感じなかった。
自分の血筋についても、飼い猫の悪源太が父のヴァニタスである事も、色々あって家に戻る前には知っていたし、むしろ、どうしてもっと早く教えてくれなかったのかと両親を恨む気持ちのほうが強かったくらいだ。
両親は両親なりに自分がショックを受けないよう配慮をしてきたつもりだったのだろうが、芙紗子にはそれが煩わしく感じられて仕方がなかった。
いい機会と思い、芙紗子は両親の橘之助と紀美子に、アク――悪源太の事を尋ねた。
「パパ。ひょっとして私のこと、ずっとアクに見張らせてたわけ?」
「……そうよ」
首肯する紀美子を見て、喉まで出かかった怒りの言葉を芙紗子は必死に飲み込んだ。
「だったら、私が撃退士になりたいと思ってることも知ってるんだよね」
しばしの沈黙の後、橘之助は口を開いた。
「ひとつだけ言っておく、芙紗子。お前を学園には絶対に入れんぞ」
「どうして?」
「どうしても、だ。――この話をこれ以上続ける気はない」
父親に話を打ち切られ、その時は結局それ以上、話を続けることは出来なかった。
芙紗子は落胆に肩を落として帰宅したのだった。
●
それから数ヵ月後。
話の舞台は京都府、某市内の公立中学校へと飛ぶ。
●
「えー、大江さん。どうぞ」
男性の教師が教室のドアから顔を出して、廊下にいた芙紗子と橘之助を呼んだ。
「本日は三者面談にお越しいただき、ありがとうございます。担任の中島です、どうぞよろしく」
入口のドアをくぐるようにして教室に入ったふたりに椅子を勧めると、眼鏡をかけた中年の男が自己紹介をした。
学校で一番背の高い芙紗子の父親と聞いて、どんな巨人がやって来るのだろうと中島は内心冷や冷やしていたが、以外にも橘之助の体格は芙紗子と大して変わらない。
内心で安堵の溜息をつくと、さっそく中島は本題を切り出した。芙紗子の卒業後の進路についてである。
「さて、大江さんの進路ですが。彼女は成績の方も良く、生活態度も真面目で……」
成績表を机に広げ、あれこれと説明をする担任の話に、橘之助は満足げに頷きながら聞き入っていた。
「それで、大江さん。希望する学校の事ですが――」
「私は、久遠ヶ原学園への入学を希望します」
担任の中島の言葉を継いで、芙紗子がはっきりと宣言するように言った。
それを聞いた中島が、眼鏡を押し戻して芙紗子に問いかける。
「ふむ。なぜ久遠ヶ原への入学を?」
「はい。それは――」
いい機会と思い、芙紗子は父親と担任に自分の思いを打ち明けることにした。
無論、自分と父親が悪魔であるという事は言わずに、である。
毎日のように、自分が友達を傷つける恐怖に苦しんでいたこと。
このまま皆と一緒に暮らしていたら、きっとまた誰かを傷つける事になる、そんな風に考えていること。
芙紗子は育ち盛りの年頃である。これから体が更に大きくなって、力も更に強くなることだろう。
そんな自分が皆と一緒に生活して、何かの拍子に人を傷つけてしまったら?
考えたくはなかった。だが、考えることをやめたら普通の人と同じ体になるわけではない。
芙紗子は自分の生まれ育った土地を愛していた。叶うならば、ずっとこの街で生きていきたい。しかし……
「私、怖いんです。このままアウルをコントロール出来ずにいたら、また人を傷つけてしまうんじゃないかって。それも恐らくは、取り返しのつかない形で……」
大きな深呼吸の後、芙紗子は言葉を継いだ。
「でも、撃退士になってアウルの制御の仕方を学べれば、私が人を傷つけることもなくなると思うんです。それに、『力』の事で相談できる相手が欲しいという気持ちもあります。学校の友達や、家族には話せない事も出てくると思うから……」
芙紗子が自らの気持ちを余すことなく伝えると、教室に沈黙が流れた。
担任の中島は、真剣なまなざしで何度か小さく頷いた。彼女が本気であること、彼女が目指す将来がどのようなものであるかを理解してくれたのであろう。
「お父さん、如何ですか? 彼女はああ言っています。担任としては、応援したいというのが正直なところですが」
「パパ、先生。私を学園に行かせて」
両親から目をそらさずに芙紗子が言った。本気だった。
だが、父である橘之助の答えは残酷だった。
「駄目だ」
「どうして?」
芙紗子が即座に問い返した。
その顔にはいつもと同じ笑顔を浮かべているが、よく見ると背後の景色が陽炎のようにゆらめいている。
「久遠ヶ原学園は信用できんからだ」
「まあまあ、ふたりともちょっと落ち着――」
「学園のどこが信用できないの? 悪い天魔から、私たちを守ってくれてるのに」
「お前が知る必要はない。入学は諦めろ」
「そんなので納得できるわけないじゃない。ダメだっていうなら、理由くらい教えてくれてもいいでしょ」
教室内に一触即発の空気が流れる。
その光景を窓の外から、どこからか入り込んだ一匹の黒猫が心配そうに眺めていた。
「駄目だ」
「だから、どうして!」
「駄目なものは駄目だからだ」
その時、担任の中島は確かに見た。芙紗子の頭に、二本の角が生えるのを。
「ふざけんなこのバカ親父!」
●
「緊急の依頼が入りました。京都府内の中学校で、アウルを駆使する親子と思しき二人が喧嘩をしているとの事です。直ちに現地に急行し、喧嘩を止めてください」
斡旋所の職員は、事の経緯を手短に説明した。
つい先ほど、「悪源太」と名乗る男性から、学校で親子が暴れているから止めてほしい、という要請があったというのだ。
その男性の話では、暴れている親子は共に悪魔であり、一歩間違えば周囲に甚大な被害を及ぼしかねないという。
「なお、依頼主からの要望で、この親子が悪魔であることを学校の生徒と関係者には絶対に知られないようにして欲しいと言うことですので、この点は厳守を願います。――それでは、受諾を希望される方は窓口にて手続きをお願いします」
リプレイ本文
●
6人の撃退士が学校のグラウンドに駆け付けると、そこでは芙紗子と橘之助の二人が大声で言い争っていた。
校舎の窓からは、その光景を一目見ようと野次馬達が好機の視線を注いでいる。
「これはまた派手な喧嘩ですね〜」
華子=マーヴェリック(jc0898)がおっとりとした口調で呟くと、
「まったくです。親子喧嘩なら人様に迷惑が掛からない所でやって欲しいですね」
呆れ顔の雫(ja1894)も、ため息と共に頷いた。
「パパはいつもそうなんだから! 自分の都合を黙って私に押し付けて!」
「お前はまだ子供だ。いずれ大きくなれば、私の言葉の意味が……」
雫が見たところ、熱くなっているのは芙紗子の方らしい。父親は幾分冷静なようだ。
(まずは父親の橘之助氏と話をつけよう)
雫はグラウンドの中央へと走ってゆき、橘之助に声をかけた。念のため、挑発で相手の目を引くのも忘れない。
「失礼、久遠ヶ原の者です。喧嘩の理由は分かりませんが、周囲に迷惑が掛かっているので場所を――」
「久遠ヶ原だと!」
橘之助の意識が向いたのもつかの間、雫が言葉を終える前に、なぜか今度は彼の顔まで怒気に染まった。
どうやら彼は、学園に良い感情を持っていないらしい。
「さてはあの教師め、学園に連絡を取りおったか! 帰れ! 貴様等に話す事などない!」
「ええ、ですからひとまず落ち着いて下さい」
背丈が二倍はあろうかという相手に向かって怯まず物を言う雫に、キアラ・アリギエーリ(jc1131)が加勢した。
「喧嘩はダメなんです!いったん落ち着いてください!」
「これが落ち着いていられるか! 学園め、芙紗子までさらって行く気か!」
「パパ! ちゃんと私の質問に答えて!」
「こういう時ほど、冷静になるべきなんです。深呼吸です。吸ってー、吐いてー、です。すっすっはーです」
ほんわかとした空気をまとったキアラが橘之助に話しかけるも、彼の怒りは収まる気配がない。
(このままでは埒があきませんね)
雫がちらりと脇に目をやると、先程まで一緒にいた華子の姿が見えなくなっている。依頼主の悪源太を探しに行ったのだろう。他の仲間達も「ある準備」のために到着が遅れている。かといって、今のこの状況を放置していては、騒ぎは大きくなるばかりだ。
(仕方ない。お二方には、納得してもらいましょう。……体で)
ふいに雫の白銀の髪が、意思を持った生物のように蠢きはじめた。
忍法「髪芝居」である。
「……!」
「……!!」
芙紗子と橘之助が髪芝居に心を絡め取られ、グラウンドの喧騒が沈黙へと取って代わられた。
「ふう。すごい大声だったのです」
額の汗を拭って溜息をつくキアラ。これでひとまず、騒ぎは収まった。しかし――
「雫さん。何だかさっきから、すっごく人の視線を感じるのです」
「まあ……これだけ騒げば、そうなるでしょうね」
単なる民間人の喧嘩に撃退士が出てくるという事は、普通はありえない事だ。このまま雫達が何の説明もなしに帰ってしまっては、橘之助や芙紗子の正体を疑う者が出てこないとも限らない。
この場をどう収めたものかと雫が頭をひねっていると、絶妙のタイミングで助け舟がやってきた。
カメラを手にしたRehni Nam(ja5283)、三脚を担いだ鷹司 律(jb0791)、そして澄空 蒼(jb3338)である。
「あれっ、もう始めちゃってます! 」
「そのようですね。……設置を急ぎましょう」
「仲良しなケンカに水を差すのです♪」
蒼は早速、橘之助と芙紗子に意思疎通を飛ばした。髪芝居に拘束され、声が出せずにいる今がチャンスだ。
『落ち着くのですよ。ケンカ続けられる状況かどうか周りを見るのです』
蒼が説得を行っている間に、律はギャラリーの生徒達に騒ぎの「事情」を説明した。
「皆さん、大変お騒がせして申し訳ありません。我々は、学園の撃退士です。いま、自主制作の映画撮影の依頼で、あのお二方――大江芙紗子さんと橘之助氏にご協力をいただいているところなのです」
カメラを装着した三脚をセットし、芙紗子と橘之助に向かってレンズを向けると、背後の校舎で自分達を見物している生徒達に向かって、律は再度声をかけた。
「これより本番の撮影を開始します。見物される方は、安全の為近づかない様お願いします」
――これは映画の撮影であり、更に言えば任務である。
律がそう告げたことで、次第にギャラリーの興味の視線が自分達撃退士へと移り始めたことをRehniは感じ取った。派手なシーンを演出すれば、彼らの興味は更に撃退士達へと向くことだろう。
ギャラリーの興味が再び芙紗子と橘之助に移ってしまう前に、律はRehniに呼びかけた。
「では、シーン46いきましょう。準備お願いします」
「はい」
律は光纏を終えたRehniにカメラを向けた。学園から格安でレンタルした年代物の中古品だが、問題は特にない。必要なのは、グラウンドの光景が撮影であるとギャラリーに思わせることだ。
パルテノンを手に、背中に光の翼を生やしたRehniがスレイプニルの「金狐」を召喚すると、ギャラリーの視線は完全にそちらの方へと釘付けになった。
「おおっ、すげー!」
「狐さんかわいい」
「あの尻尾に抱かれて眠りたい!」
「では、本番いきます。3、2、1、……」
律のカウントと同時に、ギャラリーが水をうったように静まり返った。
Rehniの跨る金狐が空を駆け、校庭の上空に金色の軌跡を描く。アウルの翼を広げて金狐を駆る天使のような神々しい彼女の姿に、ギャラリーはすっかり見惚れていた。もはや誰一人、これを撮影と信じて疑う者はいないようだ。
(頃合ですね)
空を舞うRehniが、蒼に視線で合図を送る。
(二人を連れてここから離れてください。今のうちに)
(了解なのです)
蒼はRehniの合図に頷くと、橘之助に意思疎通を送った。
『お互い言い分があるのは分かるのですよ。でも、他の人の迷惑は良くないのです』
諭すような口調で、蒼は続ける。
『私も同じはぐれ悪魔ですよ。よそに迷惑をかけないなら、何もしません。ですから少し落ち着いてください』
その言葉に警戒を解いたのか、橘之助が観念した声で雫と蒼に意思疎通を送った。
『……分かった。言う通りにするから、芙紗子を離してくれ』
雫が術を解くと、芙紗子も先ほどの怒りはどこへやら、すっかり大人しくなっていた。
「少しは頭が冷えましたか? 話し合うならまずは冷静になって下さい」
「はい。……すみませんでした」
雫の言葉に謝る芙紗子。
頭を上げると、グラウンドの向こう側から悪源太を抱きかかえた華子が走って来るのが見えた。
●
撃退士達の行動の結果、グラウンドの騒ぎは「自主映画の撮影」という事で何とか事なきを得た。
これで芙紗子が悪魔とばれる最悪の事態は回避できたといっていいだろう。
だが、任務はこれで終わりではない。撃退士には、まだすべき事が幾つか残っていた。
●
数刻後、校舎内の教室にて。
「撃退士の華子=マーヴェリックです。撮影の件、ご迷惑をおかけしました」
芙紗子の担任の中島に、華子は頭を下げた。そんな彼女に、中島は恐縮した表情で首を横に振る。
「とんでもない。こちらこそ、本当にありがとうございました。ところで、その……」
「はい?」
伺うような表情の中島に、華子が首を傾げる。
「お二人は、あれから……?」
「ああ、それなら大丈夫です。さっき鷹司さん……私達の仲間達と、職員室に行きましたから」
――もう少し、話し合いが必要なようです。出来れば他者の目に触れない部屋をお貸し願いたいのですが。
律の要請に学校側は直ちに応じ、専用の相談室を貸してくれた。一行はいま、そこで話の続きをしているようだ。
華子の言葉に、中島は胸を撫で下ろした。撃退士が同行していれば、さすがにこれ以上騒ぎは起こらないだろう。
緊張が解けたせいか、ふと中島の脳裏に、気絶する直前に見た芙紗子の顔がフラッシュバックした。
額の両端から生えた、小さな筍めいた二本の角。あれはまるで――
そんな中島の思いを察したかのように、彼の肩を叩く者がいた。Rehniである。
「貴方は何も見ていない。イイネ?」
「は……はい分かりました」
笑顔を浮かべるRehniの言葉に、中島は思わず頷いた。
撃退士が「見ていない」と言ったからには、これ以上詮索しない方が良い。
「さて。これでひとまず、一件落着になりそうですね」
「そうですね。本当に良かったのです」
Rehniの言葉に、キアラが頷く。
「私、実を言うと、あの二人がうらやましいです。こうやって……ちょっと乱暴ですけど、本音を言えるだなんて」
自分の過去を思い出し、キアラは窓の内側から空を見つめた。天界の父や叔父は、今頃どうしているだろうか。
「私、芙紗子さんも自分の力を、誰かを助けるために使えればいいなって思います」
と、そこまで言って、ふいにキアラの表情が曇った。
「でも……ひとつ、気になることがあるのです」
キアラの呟きに、悪源太を抱えた華子が怪訝そうな顔をした。
「気になる? 何がです?」
「さっき橘之助さん、芙紗子『まで』さらって行く気か、って言ってたのです」
「……『まで』?」
「はい。ひょっとして橘之助さん、学園と何かあったのでしょうか?」
「ううん。ちょっと気になりますね」
そう言って首をひねる華子にも、ひとつ気にかかる事があった。話の続きはお二人の家でやりましょうと話を持ちかけた時、橘之輔がそれを強く拒否したのだ。その時の彼の顔に浮かんだ警戒の色に、華子は軽い違和感を覚えた。
(なんだかまるで、何かを見られるのが嫌みたいな……考えすぎでしょうか)
そんな二人の様子を見て、悪源太は華子の腕の中で小さく俯いた。
――旦那……あれは、芙久子様がご自分から申し出た事なのに。
黒猫の薄緑の瞳に、悔恨の光が宿った。
●
その頃、相談室では。
「さて。事情は大体わかりました」
父と娘の向かいに座る雫が、静かに言った。
「芙紗子さんは学園で力の制御を学びたい。それを橘之助さんが反対して、理由を聞いても教えてくれない」
二人は同時に頷いた。
雫は、芙紗子の言い分自体はもっともであり、橘之助が事情を話さない限り、根本的な解決は難しいと思った。
ふたりの感情がすれ違ったままでいる限り、今後も似たトラブルが二度三度と起こる可能性は高い。その度に周囲が振り回され、撃退士が駆り出されるような事態は避けたかった。
あまり他人の家庭の事情に踏み込む事はしたくありませんが、と前置きをして雫は言った。
「橘之助さん。質問があります」
「……何だ」
橘之助が仏頂面で言う。
「入学を認めない理由です。何故それを芙紗子さんに話さないのですか? あるいは、ひょっとして……話さないのではなく『話せない』のですか?」
雫が「話せない」と言った瞬間、橘之助の眉がぴくりと動いた。どうやら彼は、隠し事が苦手らしい。
「芙紗子は私の娘だ。娘の将来を考えているからこそ、入学は認めんと言っている」
「となると、橘之助さん。話せないなら話せない理由があると芙紗子さんに伝えるべきかと思います。私達を信用出来ないというのは結構ですが、理由を話さなければ彼女は納得しないでしょう」
もし我々がいてはまずいならば席を外します、と雫は付け加えた。
「その必要はない。これは娘とも君達とも関わりのない事だ」
「またそうやって!」
「まあまあ。まあまあ、落ち着いて」
律が芙紗子を宥めた。
「芙紗子さん。力の制御を学ぶのでしたら、ご両親から学ぶのでは駄目なのですか? お二方とも、これまで人間の社会に溶け込んで生きてこられたのでしょう?」
「それは私も考えました。でも……」
芙紗子ちらりと橘之助を見て言った。
「パパ、力の制御は上手じゃないんです。男の人で体格もこんなですから、たまに力が入っても結構ごまかしが効いちゃうらしくって。普通の人と一緒に日常生活を何年も、っていうのは無理だと思います」
私も男の子に生まれてたら良かったのに、と芙紗子は自嘲気味に笑った。
「ふむ……お母様は?」
「ママは魔法とかそっち系が専門の、えーと……一族? なんだよね」
芙紗子の問いに、橘之助が頷いた。
「だから物理的な力は普通の人と大差ないらしくって。制御自体、学んでないんです」
頭を抱え込む律の隣で、雫が再び質問を投げた。
「……よく分かりました。では話を戻しましょう。橘之助さん、あなたは先ほど言い争いのときに、芙紗子『まで』さらっていく気か、と仰いましたね。学園を信用できず理由も話せないというのは、もしかしてそこに理由が?」
「私の口から……それを話すことはできん」
橘之助の眦が引きつるのを見て、雫は確信した。
(やはり、間違いない。彼と学園の間で、過去に「何か」があった。そのせいで彼は学園に不信感を抱いている)
そんな橘之助を見て、蒼が決意を秘めた表情で言った。
「これは同じはぐれ悪魔として、いささか放っておけないのですよ」
蒼の言葉に、雫も頷く。
「私も少し事情を探ってみる事にします。理由も分からず学園が信用できないと言われるのは本意ではありません」
それを聞いて、橘之助が皮肉めいた笑みを浮かべる。
「まったく……学園も随分と危険な生徒達を抱えているものだ」
「それは違います。私は学園に恩義は感じていますが、狗になり下がった覚えはありません」
雫の言葉を継いだ蒼が、橘之助の顔を正面から見据えた。
「だから、橘之助さんも約束してほしいのです。もし学園の事をもう一度信じてもいいって思ってくれた時は、芙紗子さんに本当の事を伝えて、もう一度話し合って欲しいのです」
「パパ……」
懇願する顔で芙紗子が橘之助を見つめた。
どのくらい時間が経っただろうか? 張り詰めた空気が流れるなか、橘之助はゆっくりと頭を縦に振った。
「――分かった。約束しよう」
こうして、任務は一応の解決をみたのである。
●
「パパは先生達にお詫びをしてから来るそうです。……本当にありがとうございました」
学校の校門で、悪源太を連れた芙紗子が礼を言った。
「迷惑かけちゃってすみませんでした。パパにはパパの理由があったのに、私、自分の事しか考えてなくて。でも……」
でもそうしたら、私はどうすればいいんだろう。そんな思いが、芙紗子の顔に浮かぶのを見て、雫は言った。
「恐らく、ですが。貴方の入学反対と話せない理由は何処かで繋がっているのでしょう」
芙紗子が学園に入るか否か。それは芙紗子と家族の問題だ。撃退士が立ち入る領分ではない。しかし――
何故、橘之助は芙紗子の入学に反対するのか?
過去、橘之助と学園の間で何があったのか?
これらが明らかにされない限り、問題が真の解決を見ることはないだろう。そして今の時点では、撃退士達の手には何ひとつ手掛かりがないに等しいのだ。
こうして、拭いきれない疑念を胸に一同は学校を後にした。
芙紗子と悪源太に見送られながら――
6人の撃退士が学校のグラウンドに駆け付けると、そこでは芙紗子と橘之助の二人が大声で言い争っていた。
校舎の窓からは、その光景を一目見ようと野次馬達が好機の視線を注いでいる。
「これはまた派手な喧嘩ですね〜」
華子=マーヴェリック(jc0898)がおっとりとした口調で呟くと、
「まったくです。親子喧嘩なら人様に迷惑が掛からない所でやって欲しいですね」
呆れ顔の雫(ja1894)も、ため息と共に頷いた。
「パパはいつもそうなんだから! 自分の都合を黙って私に押し付けて!」
「お前はまだ子供だ。いずれ大きくなれば、私の言葉の意味が……」
雫が見たところ、熱くなっているのは芙紗子の方らしい。父親は幾分冷静なようだ。
(まずは父親の橘之助氏と話をつけよう)
雫はグラウンドの中央へと走ってゆき、橘之助に声をかけた。念のため、挑発で相手の目を引くのも忘れない。
「失礼、久遠ヶ原の者です。喧嘩の理由は分かりませんが、周囲に迷惑が掛かっているので場所を――」
「久遠ヶ原だと!」
橘之助の意識が向いたのもつかの間、雫が言葉を終える前に、なぜか今度は彼の顔まで怒気に染まった。
どうやら彼は、学園に良い感情を持っていないらしい。
「さてはあの教師め、学園に連絡を取りおったか! 帰れ! 貴様等に話す事などない!」
「ええ、ですからひとまず落ち着いて下さい」
背丈が二倍はあろうかという相手に向かって怯まず物を言う雫に、キアラ・アリギエーリ(jc1131)が加勢した。
「喧嘩はダメなんです!いったん落ち着いてください!」
「これが落ち着いていられるか! 学園め、芙紗子までさらって行く気か!」
「パパ! ちゃんと私の質問に答えて!」
「こういう時ほど、冷静になるべきなんです。深呼吸です。吸ってー、吐いてー、です。すっすっはーです」
ほんわかとした空気をまとったキアラが橘之助に話しかけるも、彼の怒りは収まる気配がない。
(このままでは埒があきませんね)
雫がちらりと脇に目をやると、先程まで一緒にいた華子の姿が見えなくなっている。依頼主の悪源太を探しに行ったのだろう。他の仲間達も「ある準備」のために到着が遅れている。かといって、今のこの状況を放置していては、騒ぎは大きくなるばかりだ。
(仕方ない。お二方には、納得してもらいましょう。……体で)
ふいに雫の白銀の髪が、意思を持った生物のように蠢きはじめた。
忍法「髪芝居」である。
「……!」
「……!!」
芙紗子と橘之助が髪芝居に心を絡め取られ、グラウンドの喧騒が沈黙へと取って代わられた。
「ふう。すごい大声だったのです」
額の汗を拭って溜息をつくキアラ。これでひとまず、騒ぎは収まった。しかし――
「雫さん。何だかさっきから、すっごく人の視線を感じるのです」
「まあ……これだけ騒げば、そうなるでしょうね」
単なる民間人の喧嘩に撃退士が出てくるという事は、普通はありえない事だ。このまま雫達が何の説明もなしに帰ってしまっては、橘之助や芙紗子の正体を疑う者が出てこないとも限らない。
この場をどう収めたものかと雫が頭をひねっていると、絶妙のタイミングで助け舟がやってきた。
カメラを手にしたRehni Nam(ja5283)、三脚を担いだ鷹司 律(jb0791)、そして澄空 蒼(jb3338)である。
「あれっ、もう始めちゃってます! 」
「そのようですね。……設置を急ぎましょう」
「仲良しなケンカに水を差すのです♪」
蒼は早速、橘之助と芙紗子に意思疎通を飛ばした。髪芝居に拘束され、声が出せずにいる今がチャンスだ。
『落ち着くのですよ。ケンカ続けられる状況かどうか周りを見るのです』
蒼が説得を行っている間に、律はギャラリーの生徒達に騒ぎの「事情」を説明した。
「皆さん、大変お騒がせして申し訳ありません。我々は、学園の撃退士です。いま、自主制作の映画撮影の依頼で、あのお二方――大江芙紗子さんと橘之助氏にご協力をいただいているところなのです」
カメラを装着した三脚をセットし、芙紗子と橘之助に向かってレンズを向けると、背後の校舎で自分達を見物している生徒達に向かって、律は再度声をかけた。
「これより本番の撮影を開始します。見物される方は、安全の為近づかない様お願いします」
――これは映画の撮影であり、更に言えば任務である。
律がそう告げたことで、次第にギャラリーの興味の視線が自分達撃退士へと移り始めたことをRehniは感じ取った。派手なシーンを演出すれば、彼らの興味は更に撃退士達へと向くことだろう。
ギャラリーの興味が再び芙紗子と橘之助に移ってしまう前に、律はRehniに呼びかけた。
「では、シーン46いきましょう。準備お願いします」
「はい」
律は光纏を終えたRehniにカメラを向けた。学園から格安でレンタルした年代物の中古品だが、問題は特にない。必要なのは、グラウンドの光景が撮影であるとギャラリーに思わせることだ。
パルテノンを手に、背中に光の翼を生やしたRehniがスレイプニルの「金狐」を召喚すると、ギャラリーの視線は完全にそちらの方へと釘付けになった。
「おおっ、すげー!」
「狐さんかわいい」
「あの尻尾に抱かれて眠りたい!」
「では、本番いきます。3、2、1、……」
律のカウントと同時に、ギャラリーが水をうったように静まり返った。
Rehniの跨る金狐が空を駆け、校庭の上空に金色の軌跡を描く。アウルの翼を広げて金狐を駆る天使のような神々しい彼女の姿に、ギャラリーはすっかり見惚れていた。もはや誰一人、これを撮影と信じて疑う者はいないようだ。
(頃合ですね)
空を舞うRehniが、蒼に視線で合図を送る。
(二人を連れてここから離れてください。今のうちに)
(了解なのです)
蒼はRehniの合図に頷くと、橘之助に意思疎通を送った。
『お互い言い分があるのは分かるのですよ。でも、他の人の迷惑は良くないのです』
諭すような口調で、蒼は続ける。
『私も同じはぐれ悪魔ですよ。よそに迷惑をかけないなら、何もしません。ですから少し落ち着いてください』
その言葉に警戒を解いたのか、橘之助が観念した声で雫と蒼に意思疎通を送った。
『……分かった。言う通りにするから、芙紗子を離してくれ』
雫が術を解くと、芙紗子も先ほどの怒りはどこへやら、すっかり大人しくなっていた。
「少しは頭が冷えましたか? 話し合うならまずは冷静になって下さい」
「はい。……すみませんでした」
雫の言葉に謝る芙紗子。
頭を上げると、グラウンドの向こう側から悪源太を抱きかかえた華子が走って来るのが見えた。
●
撃退士達の行動の結果、グラウンドの騒ぎは「自主映画の撮影」という事で何とか事なきを得た。
これで芙紗子が悪魔とばれる最悪の事態は回避できたといっていいだろう。
だが、任務はこれで終わりではない。撃退士には、まだすべき事が幾つか残っていた。
●
数刻後、校舎内の教室にて。
「撃退士の華子=マーヴェリックです。撮影の件、ご迷惑をおかけしました」
芙紗子の担任の中島に、華子は頭を下げた。そんな彼女に、中島は恐縮した表情で首を横に振る。
「とんでもない。こちらこそ、本当にありがとうございました。ところで、その……」
「はい?」
伺うような表情の中島に、華子が首を傾げる。
「お二人は、あれから……?」
「ああ、それなら大丈夫です。さっき鷹司さん……私達の仲間達と、職員室に行きましたから」
――もう少し、話し合いが必要なようです。出来れば他者の目に触れない部屋をお貸し願いたいのですが。
律の要請に学校側は直ちに応じ、専用の相談室を貸してくれた。一行はいま、そこで話の続きをしているようだ。
華子の言葉に、中島は胸を撫で下ろした。撃退士が同行していれば、さすがにこれ以上騒ぎは起こらないだろう。
緊張が解けたせいか、ふと中島の脳裏に、気絶する直前に見た芙紗子の顔がフラッシュバックした。
額の両端から生えた、小さな筍めいた二本の角。あれはまるで――
そんな中島の思いを察したかのように、彼の肩を叩く者がいた。Rehniである。
「貴方は何も見ていない。イイネ?」
「は……はい分かりました」
笑顔を浮かべるRehniの言葉に、中島は思わず頷いた。
撃退士が「見ていない」と言ったからには、これ以上詮索しない方が良い。
「さて。これでひとまず、一件落着になりそうですね」
「そうですね。本当に良かったのです」
Rehniの言葉に、キアラが頷く。
「私、実を言うと、あの二人がうらやましいです。こうやって……ちょっと乱暴ですけど、本音を言えるだなんて」
自分の過去を思い出し、キアラは窓の内側から空を見つめた。天界の父や叔父は、今頃どうしているだろうか。
「私、芙紗子さんも自分の力を、誰かを助けるために使えればいいなって思います」
と、そこまで言って、ふいにキアラの表情が曇った。
「でも……ひとつ、気になることがあるのです」
キアラの呟きに、悪源太を抱えた華子が怪訝そうな顔をした。
「気になる? 何がです?」
「さっき橘之助さん、芙紗子『まで』さらって行く気か、って言ってたのです」
「……『まで』?」
「はい。ひょっとして橘之助さん、学園と何かあったのでしょうか?」
「ううん。ちょっと気になりますね」
そう言って首をひねる華子にも、ひとつ気にかかる事があった。話の続きはお二人の家でやりましょうと話を持ちかけた時、橘之輔がそれを強く拒否したのだ。その時の彼の顔に浮かんだ警戒の色に、華子は軽い違和感を覚えた。
(なんだかまるで、何かを見られるのが嫌みたいな……考えすぎでしょうか)
そんな二人の様子を見て、悪源太は華子の腕の中で小さく俯いた。
――旦那……あれは、芙久子様がご自分から申し出た事なのに。
黒猫の薄緑の瞳に、悔恨の光が宿った。
●
その頃、相談室では。
「さて。事情は大体わかりました」
父と娘の向かいに座る雫が、静かに言った。
「芙紗子さんは学園で力の制御を学びたい。それを橘之助さんが反対して、理由を聞いても教えてくれない」
二人は同時に頷いた。
雫は、芙紗子の言い分自体はもっともであり、橘之助が事情を話さない限り、根本的な解決は難しいと思った。
ふたりの感情がすれ違ったままでいる限り、今後も似たトラブルが二度三度と起こる可能性は高い。その度に周囲が振り回され、撃退士が駆り出されるような事態は避けたかった。
あまり他人の家庭の事情に踏み込む事はしたくありませんが、と前置きをして雫は言った。
「橘之助さん。質問があります」
「……何だ」
橘之助が仏頂面で言う。
「入学を認めない理由です。何故それを芙紗子さんに話さないのですか? あるいは、ひょっとして……話さないのではなく『話せない』のですか?」
雫が「話せない」と言った瞬間、橘之助の眉がぴくりと動いた。どうやら彼は、隠し事が苦手らしい。
「芙紗子は私の娘だ。娘の将来を考えているからこそ、入学は認めんと言っている」
「となると、橘之助さん。話せないなら話せない理由があると芙紗子さんに伝えるべきかと思います。私達を信用出来ないというのは結構ですが、理由を話さなければ彼女は納得しないでしょう」
もし我々がいてはまずいならば席を外します、と雫は付け加えた。
「その必要はない。これは娘とも君達とも関わりのない事だ」
「またそうやって!」
「まあまあ。まあまあ、落ち着いて」
律が芙紗子を宥めた。
「芙紗子さん。力の制御を学ぶのでしたら、ご両親から学ぶのでは駄目なのですか? お二方とも、これまで人間の社会に溶け込んで生きてこられたのでしょう?」
「それは私も考えました。でも……」
芙紗子ちらりと橘之助を見て言った。
「パパ、力の制御は上手じゃないんです。男の人で体格もこんなですから、たまに力が入っても結構ごまかしが効いちゃうらしくって。普通の人と一緒に日常生活を何年も、っていうのは無理だと思います」
私も男の子に生まれてたら良かったのに、と芙紗子は自嘲気味に笑った。
「ふむ……お母様は?」
「ママは魔法とかそっち系が専門の、えーと……一族? なんだよね」
芙紗子の問いに、橘之助が頷いた。
「だから物理的な力は普通の人と大差ないらしくって。制御自体、学んでないんです」
頭を抱え込む律の隣で、雫が再び質問を投げた。
「……よく分かりました。では話を戻しましょう。橘之助さん、あなたは先ほど言い争いのときに、芙紗子『まで』さらっていく気か、と仰いましたね。学園を信用できず理由も話せないというのは、もしかしてそこに理由が?」
「私の口から……それを話すことはできん」
橘之助の眦が引きつるのを見て、雫は確信した。
(やはり、間違いない。彼と学園の間で、過去に「何か」があった。そのせいで彼は学園に不信感を抱いている)
そんな橘之助を見て、蒼が決意を秘めた表情で言った。
「これは同じはぐれ悪魔として、いささか放っておけないのですよ」
蒼の言葉に、雫も頷く。
「私も少し事情を探ってみる事にします。理由も分からず学園が信用できないと言われるのは本意ではありません」
それを聞いて、橘之助が皮肉めいた笑みを浮かべる。
「まったく……学園も随分と危険な生徒達を抱えているものだ」
「それは違います。私は学園に恩義は感じていますが、狗になり下がった覚えはありません」
雫の言葉を継いだ蒼が、橘之助の顔を正面から見据えた。
「だから、橘之助さんも約束してほしいのです。もし学園の事をもう一度信じてもいいって思ってくれた時は、芙紗子さんに本当の事を伝えて、もう一度話し合って欲しいのです」
「パパ……」
懇願する顔で芙紗子が橘之助を見つめた。
どのくらい時間が経っただろうか? 張り詰めた空気が流れるなか、橘之助はゆっくりと頭を縦に振った。
「――分かった。約束しよう」
こうして、任務は一応の解決をみたのである。
●
「パパは先生達にお詫びをしてから来るそうです。……本当にありがとうございました」
学校の校門で、悪源太を連れた芙紗子が礼を言った。
「迷惑かけちゃってすみませんでした。パパにはパパの理由があったのに、私、自分の事しか考えてなくて。でも……」
でもそうしたら、私はどうすればいいんだろう。そんな思いが、芙紗子の顔に浮かぶのを見て、雫は言った。
「恐らく、ですが。貴方の入学反対と話せない理由は何処かで繋がっているのでしょう」
芙紗子が学園に入るか否か。それは芙紗子と家族の問題だ。撃退士が立ち入る領分ではない。しかし――
何故、橘之助は芙紗子の入学に反対するのか?
過去、橘之助と学園の間で何があったのか?
これらが明らかにされない限り、問題が真の解決を見ることはないだろう。そして今の時点では、撃退士達の手には何ひとつ手掛かりがないに等しいのだ。
こうして、拭いきれない疑念を胸に一同は学校を後にした。
芙紗子と悪源太に見送られながら――
依頼結果
| 依頼成功度:成功 |
| MVP: − |
| 重体: − |
| 面白かった!:5人 |
| 歴戦の戦姫・ 不破 雫(ja1894) 中等部2年1組 女 阿修羅 |
 |
前を向いて、未来へ・ Rehni Nam(ja5283) 卒業 女 アストラルヴァンガード |
|
| 七福神の加護・ 鷹司 律(jb0791) 卒業 男 ナイトウォーカー |
チョコバーが繋ぐ絆・ 澄空 蒼(jb3338) 中等部3年4組 女 陰陽師 |
||
| その愛は確かなもの・ 華子=マーヴェリック(jc0898) 卒業 女 アストラルヴァンガード |
堕天使保安官・ キアラ・アリギエーリ(jc1131) 大学部1年289組 女 アストラルヴァンガード |
||

